・2000年代

◆松本次郎 ウェンディ(太田出版)2000
〈ピーターパン物語の現代版〉…と言ってしまうと身もフタもないのだが、普通の女子高生であるウェンディ(愛美)の所に、夜な夜なゴーグル・マスクを付けて「ひゃははは」と笑う不良少年ピーターが現れるユニークにしてシュールな物語。(ただし、まったく「童話」的なメルヘンではなく、冒頭は主人公の処女喪失だし、どこかドラッグ臭のする生々しくも悪夢のような世界なので、その手のモノに抗体のない人は入って来られないかも)。
その後、現実世界から逃れてネバーランドへ行き、そこで海賊フックや時計ワニやティンカーベルやタイガーリリーなどおなじみの登場人物たちと出会うのだが、そのアナーキーで雑然としたわけの分からない設定が凄い。
全編暗いトーンと見事なパースペクティヴ(遠近&透視画法)による圧倒的な(しかし上手いんだか下手なんだか分からない不思議な)筆致で描かれていて、壮大なファンタジーとも単なる(悩める青少年の)現実逃避の夢とも取れる奇妙な世界を、「構造」的に見せてしまう。ただし、お子様向けではないので、念のため。

◆駕籠真太郎 パラノイア・ストリート(メディアファクトリー)2000
駕籠真太郎という漫画家と出くわしたのは「駅前喜劇」という過激な本から。これはもう、良い子には絶対見せられないような想像を絶する世界で、現実世界で起こったら残虐非道・虐殺殺戮・狂気異常きわまりないことが、モーツァルト的天真爛漫な世界であっけらかんと展開してゆく天国的宇宙。
例えば、最大の問題作「輝け!大東亜共栄圏」では、女性を巨大化させて解体・再構築した戦車や潜水艦とか、糞便を打ち出す機関銃とか、さまざまな異様な武器(でも全部なせか女性のパーツで出来ている)で戦う異次元世界での大東亜戦争を描いていて、良識ある大人や女性なら卒倒必至。「一体どういう頭の構造しているのだろう?」と笑って(怒って?)しまうほどの見事で異常なイマジネーション…なのだが、あまりに過激(かつマニアック)で人サマにはお勧めできないのがつらいところ。
唯一「一般向け(?)」のこの「パラノイア・ストリート」は、「何でも測らずにはいられない街」とか「何もかも逆さの街」などなど奇妙きてれつな街を巡る探偵と助手の一話読み切り短編集。駕籠ワールド入門はまずここから。

◆あずまきよひこ あずまんが大王(メディアワークス)2000-02
女子高生の高校生活を描いた4コマまんが。あまりにもアニメ&女のコ風の表紙と変なタイトル(コミック「電撃大王」という雑誌に連載されていたから「あずまんが大王」なのらしい)のため手に取るのが遅れた「遅れてきた傑作」(?)。
確かに、単に可愛い女の子を描きたいだけの他愛のないマンガのような気もするが(笑)、その独特な空間の余白と、とぼけたセリフ、ボケる時の間のほのぼの度は、漫才というより俳句や生け花の世界すら思わせる(…と言ったら褒めすぎか?)。
たいしたギャグがあるわけでもないのに何となくその世界に浸ってしまい、けっこう繰り返し読むのに耐えるので、仕事の合間とか就寝前とかにパラパラと数編を読むとストレス解消に最適。永遠の小学校3年生である某ちび●る子譚と違って、高校の3年間を時間軸に添って(夏休みや運動会などを)描いているので、3年(全4巻)で卒業して終わってしまったのはちょっと残念。

◆黒田硫黄 セクシーボイス アンド ロボ 1-2 2001/3
黒田硫黄(いおう)は、墨の筆あるいはマジックのペンのような荒い(何と言うか棟方志功みたいな)タッチで、不思議なパースペクティヴとデフォルメに満ちた(前衛映画みたいなアングルの)空間を描き出す鬼才。一見殴り書きマンガみたいに見えるのだが、その奥で結構リアルな描写や斬新なショットあるいは哲学的なセリフが浮遊するので、なかなか油断がならない。その感覚は、スピード感のあるモノクロの映画を見ている感じだ。
この「セクシーボイス・アンド・ロボ」は、七色の声を使い分ける女子中学生(自称セクシーボイス)と、その相棒の青年(ロボ)との奇妙でリアルな現代東京絵図。タイトルからしてSFかと思っていたら大間違い。現代っ子の生態やテレクラやヤクザなど裏風俗の描写に交って、サッカーチームや水族館、理髪店やサーカスなどの妙にリアルで不思議な世界も描いていて、これは体験なのか取材なのか、その間口の広さにも感心てしまう。主人公の女の子の破天荒な行動力とバイタリティは、私の世代としてはその昔のちばてつやの主人公を思い出す。

◆カサハラテツロー 空想科学エジソン(ソニー・マガジンズ)2001-02
宮崎駿の「風の谷のナウシカ」や「天空の城ラピュタ」あたりを思わせるタッチの空想科学漫画。万能工具バルカンを操って色々なメカを作ってしまう女主人公ミロが、エジソンという不思議な球体に導かれて旅をし、最後は世界(地球)創世のナゾに触れるという壮大な物語(全3巻)で、エジソンシュタイン、学者ホーキン、助手ガリレー、都市ニュートンキン、アイザック教典などという命名にも思わずニヤリ。
絵はマンガチック(ディズニーっぽい?)だし、メカはいずれも歯車だらけの古風なものだが、さずがにCG世代。その3D感やメカのリアルなタッチは秀逸。(それにしても、男というのは「とにかく可愛い女の子と、かっこいいメカを描きたい!」という一念で絵が上手くなるのだなあ。そういう意味でも、これは正しい少年マンガと言えそう)。

◆五十嵐大介 そらトびタマシイ 2002
最近のお気に入り。繊細な線で、いかにも手仕事風の描き込みがほどこされた作品たちは、昔の古本マンガを思い出してどこか懐かしい。
偶然ヒナ鳥を踏みつぶしてしまった少女が親フクロウに憑依される話、熊を殺した少年太郎がいけにえにされる少女を助けようとする民話風の物語、体から砂がこぼれ出す体質の女性と家出した少女との奇妙な交流の話、親に捨てられて捨て猫を飼う女の子とパン屋の青年とが都会の片隅で出会う話...。いずれも、大きな目ときゃしゃな手足の主人公が、悲しいような冷めたような視線で静かに世界を見つめるのが、不思議ないとおしさを醸し出す。
朝の食事やアパートの一室や町並みなどがリアルに描かれる一方で、「飼い犬に憑依されて半分獣になっている女性」とか「湖の底一面に漂う瓶詰めのいけにえたち」とか「少女の瞳の中の宇宙におりてゆく青年」などという奇妙で不可思議な絵柄が(どこか絵本のようなパースペクティヴで)描かれているのだが、技術におぼれず奇をてらわず淡々とした透明なスタンスなのがいい。

◆鶴田謙二 Forget-me-not 2003
鶴田謙二は漫画家というより絵師。ストーリーよりもなによりも、絵の佇まいとその宇宙に浸っているのがひたすら心地よい。ぱらぱらと物語を追って読むなどということは(もったいなくて)とても出来なくて、座右に置いて一コマ一コマの滞空時間の長さを楽しむといった感じ。
今回の主人公は、ヴェネチアに住む日系の少女マリエル。亡くなったイタリア人の祖父が有名な探偵で大富豪で、宿敵の泥棒ヴェッキオに盗まれた「Forget-me-not」という絵を「取り戻すこと」という遺言が残されているため、その捜索をかねて私立探偵(らしきもの)をやっている・・・という物語らしきものはあるのだが、結局のところヴェネチアの町をバックに近所の人のいい住人たちから「探偵さん」と呼ばれている女の子の(退屈そうで楽しそうな)日常が描かれるだけ。でも、読んでいると、なんだかヴェネチアに行きたくなってしまう。

◆二ノ宮知子 のだめカンタービレ 2002〜
21世紀初頭の日本に疾風のごときクラシック音楽ブームをもたらした「日本クラシック音楽史」?に残る問題作。
ずぼらなピアニスト「のだめ」と、彼女に翻弄される指揮者「千秋」というコンビ設定がまず面白い。昔から星飛雄馬・花形満(巨人の星)にしろ、矢吹ジョー・力石徹(あしたのジョー)にしろ、岡ひろみ・竜崎麗香(エースをねらえ)にしろ、対照的な二者の対峙は芸道精進モノの基本なのです。
と、その点ではスポコン(スポーツ根性モノ)の伝統に則している(笑)と言えなくもないけれど、「なぜそこまでして頑張るのか?」というレーゾン・デートル(存在理由)に関してだけは「ぎゃぼー」なんて言ってる場合じゃないはず。音楽大学内に限定されたラヴ・コメディならともかく、こんな可愛い情熱じゃ魑魅魍魎がうごめくプロの音楽界ではやっていけません(たぶん)。でも、クラシックやオーケストラ業界の裏事情や専門ネタをよく拾っているし、なによりも「クラシック=マジメで堅苦しい芸術」という既成概念を笑い飛ばして、等身大の「聴いて感じる音楽」にしてみせた手腕には拍手。
分別じみた大人としては「所詮マンガ」と軽くいなしがちだけれど、若い人たちが「ああ、こういう世界があるんだ。わたしもやってみたい(聴いてみたい)」と思うきっかけになることは確か。だから、当面のクラシック・ブームとやらより、ここを入口にしてクラシック音楽界に入ってくる10年後20年後の近未来の「巨匠」たちや筋金入りの「音楽愛好家」たちの出現こそが今から楽しみ。

◆もりもと崇 難波鉦異本(なにわどら・いほん)2001〜
江戸「吉原」京都「島原」に対する大阪「新町」を舞台にした遊女のお話…なのだが、視点は遊女「和泉」姐さん付きの禿(かむろ)「ささら」という少女。この童女から見た姐さんは、金の亡者で奔放で男を手玉に取るヘビ女のようなキャラながら、一方で三味線の名手にして武芸の隠れ達人で井原西鶴だの竹本義太夫などから一目置かれている不思議な女性。
よく描き込まれた当時の遊廓の背景や道具や衣類にしろ、「性」と「金」と「情」が交錯する絶妙な駆け引きの面白さにしろ、コミカルさと残酷さとのどかさが混交する不思議な世界観にしろ実に魅力的。コミックス界というのは時に不思議な人材(鬼才)を輩出するものだなあと、しみじみ感心してしまう。亡き杉浦日向子女史の後を継ぐ江戸本作者の登場に拍手。
ちなみに元ネタとなった「色道諸分・難波鉦(難波・どら)・遊女評判記」(岩波文庫)は、江戸時代初期(1680年刊)大阪難波のどら息子が遊里に出かけてなじみの遊女に遊びの指南を受ける、という形をとった当時のHow
To 本。
「よふ思うてみさんせ。はじめて逢ふとても〈よふござりました〉〈寝さしやりませ〉〈起きさしやりませ〉などという言葉。二十三十あいましても此ことばでござんす。床(とこ)のうちでも〈いとおしい〉ということば、なじみての後でもかわる事かや…などと延々続くリズミカルな言葉の響きがなかなか魅力的で、読んでいるとなんだか室内オペラでも聴いている気分になる。例えて言うなら「ペレアスとメリザンド」か・・・(笑)

◆浦沢直樹「PLUTO」2004〜
この作品、「鉄腕アトム」の中のエピソード「地上最大のロボット」を現代風に翻案したもの。まず、そのアイデアに「やられた!」と思ったのがひとつ。物語は、100万馬力で地上最強を誇るロボット〈プルートウ〉が、最強と賞される世界のロボット7人を次々と倒して行くロボット・バトルとして当時の子供たち(私の世代)の人気を博した名作。それを、ロボットの連続殺人(破壊)犯を追うロボット刑事(表紙がそのゲジヒト刑事)のドラマとして、リアルな(そのまま映像化できそうな、SF臭皆無の!)筆致で描いているのだが、きわめて情緒的かつミステリー仕立てな作りの中に、隠し絵のように手塚治虫へのオマージュがちりばめられていて、実はひそかに「アトム・オペラ」など構想していた私としては「なるほど、この手があったか!」とちょっと総毛立つと共に、思わず嫉妬に燃えてしまった(笑)
。
マンガのアトムは、髪の毛がとんがって真っ赤なブーツ履いてパンツ一丁で空を飛んでるけれど、鼻が顔より大きいお茶の水博士と同様、それは「現実」の絵柄としてはあり得ない。天馬博士が作ったのは「人間の子供と変わらない外見をした愛らしい少年」としての人型ロボットであり、となると、この作品の第1巻最後に出てくるレインコート着た普通の小学生である「アトムくん」は、まさにかくあるべき姿なのだ。うーん、なるほど。これは、シェイクスピアのロミオとジュリエットが「ウエストサイド物語」のトニーとマリアに翻案されたようなものかな。
いや、お見事!
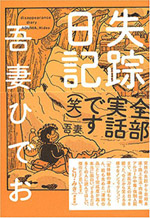
◆吾妻ひでお 失踪日記 2005
1970年代に一世を風靡しながら、90年代に入ると姿を消してしまった天才〈あじましでお〉が久々に放った衝撃の書。…早い話が、この巨匠、80年代末に仕事をほっぽり捨てて失踪し、自殺を図ったりホームレスになったり配管工をやったりアル中で更生施設に入ったりしていたのだそうで、その間の生活を赤裸々に、しかし天国的にマンガで描いたのがこの著作。まさに、ドストエフスキーに匹敵する現代日本の黙示録的作品である(……とまで言ったら言い過ぎか)。