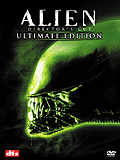 エイリアン(1979年 監督:リドリー・スコット)
エイリアン(1979年 監督:リドリー・スコット)
エイリアン(Alien)と言うと、現在ではE.Tと並んで「異星人」を意味する単語として有名だが、そもそもは異なる国の人間「外国人」ということらしい。だから例えばアメリカの空港などでは入国審査のゲートは「US
Citizen(米国市民)」と「Alien(外国人)」に別れている。
それをSFの世界に当てはめてみれば、宇宙空港には当然「地球人」と「宇宙人」という2つのゲートがあるわけで(あるいは「ロボット」というゲートも?)、「エイリアン」すなわち「地球人でない人間=異星人」となる理屈である。なるほど。
◆SFとホラーの接点
なにしろ子供の頃から、SFが好きで、ホラーが好きだった。SFの方は、もちろん50-60年代の名作SF小説(ブラッドベリの「火星年代記」、ハインラインの「夏の扉」、アーサー.C.クラークの「地球幼年期の終わり」、ゴドウィンの「冷たい方程式」などなどなど)に惹かれたからだけれど、60年代というのはそもそも「科学の進歩によって明るい理想的な未来が来る」と素直に信じられた最後の時代だったから、少年向けの読み物にもSF(宇宙探検や地底探検などから異星人モノ、あるいはタイムマシンや電送装置などの発明モノなどなど)が満ちていた。
少年マンガでは「鉄腕アトム」「鉄人28号」「8マン」「サイボーグ009」など、外国製のTV番組では「宇宙家族ロビンソン」「原子力潜水艦シービュー号」「サンダーバード」「スタートレック(宇宙大作戦)」「インベーダー」などなどSFテイストのオンパレード。SF好き少年としてはわくわくしながらTVにかじり付いていたわけである。
もっとも、実を言うとその手の単なる健康的SFアドベンチャーより100倍も面白かったのが、「アウターリミッツ」とか「トワイライトゾーン」とかいう類いの「怖いSF」。そもそも日本製のSF映画だって、「ゴジラ」(1954)に始まって、「透明人間」(1954)、「美女と液体人間」(1958)、「ガス人間第一号」(1960)、「マタンゴ」(1963)などなど、サスペンス&ホラー・タッチのものが多かったから、SFとホラーというのは表裏一体なのだろう。
考えてみれば基本的にSFとは、発明や宇宙探検によって立ち現れた未知の異界や異物への「遭遇」と「恐怖」、そしてそれを排除撃退する「戦い」と「勝利」が骨子。それは科学的な未来図の中で起こる出来事であるにも関わらず、実は人間なら誰でも持っている「夜(未知のもの)」に対する「興味」の発露であり、人間の原初的な「本能」に根ざす寓話であり童話であるわけなのだ。
ただ、科学が進んだ「未来」を描くのがSFのはずなのに、その世界が「明るく楽しい理想世界」であることは究めて稀で、けっこう恐怖と不条理に満ちていたのは興味深い。なにしろ「メトロポリス」ではロボットが反逆するし、「タイムマシン」は人間が退化した原始人に襲われるし、「キングコング」や「ゴジラ」は怪獣が街を壊し、「宇宙戦争」では火星人が「トリフィドの日」では植物が「遊星からの物体X」や「盗まれた街(ボディ・スナッチャー)」では形状不明の未知の生命体が人類を滅ぼしかけ、「禁断の惑星」ではイドの怪物が人間を襲う。「1984年」や「華氏451度」は自由のない恐怖政治下の未来だし、「ソイレント・グリーン」は人口爆発でスラム化する未来、「猿の惑星」は進化した猿に人間が奴隷にされている未来。友好的な宇宙人と明るい未来が登場する話など、ほとんどないのである!そして、この60年代SFの流れは1968年の「2001年宇宙の旅(2001
: Space Odyssey)」という傑作で頂点を究める。
ちなみに、この時代は、音楽で言うと「前衛音楽」の全盛期。「2001年」ではリゲティのトーンクラスターが響き渡っていたし、50年代の名作「禁断の惑星」では全編に電子音楽が使われていた。SFとは未来の物語なのだから、音楽も未来の音楽、それはイコール前衛音楽や電子音楽、という構図が(一応)あったのだろう。少なくとも21世紀になっても生身の音楽家とかハーモニーなどというものがあろうとは、想像もしなかったわけなのだ・・・(笑)
しかし、その「前衛」の時代も1970年代後半ともなると終わりを告げる。クラシック界ではマーラーがリバイバルを遂げ、ネオ・ロマンティシズムなどという「調性回帰」の風潮さえ現れるようになる。現実世界でも、まず「科学は果てしなく進歩を遂げ、科学で解明出来ないことはなくなる」という信仰に大きなクエスチョン・マークがともり、それに伴って「(科学の進歩によって)人類が皆ひとつになった平和な社会が生まれる」という「大いなる物語」は根底から揺らぎ始める。
そんな時代に登場したのが1977年の「スターウォーズ」であり、1979年の「エイリアン」なのである。
この二作は「陰」と「陽」のようにペアになっているが、もちろん一般の映画ファンに熱狂的に受け入れられ、現在でも続編が作られ続けるほどの人気を博しているのは、健康的で能天気な「スターウォーズ」の方。でも、正直言って「スターウォーズ」の方はどうでもいい(笑)。
あれはただ単に「ローマ帝国の興亡」や「アーサー王の伝説」舞台を宇宙に変えただけで、特に面白いと思ったことはない。ただ唯一驚いたのは、そのSF世界がぜんぜん未来っぽくない能天気なオーケストラのマーチ(J.ウィリアムスによる有名なあの「スターウォーズのテーマ」)に乗って登場したことだけだ。
 ◆エイリアンの時代
◆エイリアンの時代
で、「エイリアン」である。
この映画が公開された1979年(25年も前!)というのは、DVDどころか家庭用ビデオすら充分に普及していない時代(カセットのWalkManが初めて登場した年だ)だったから、映画は映画館で観るもの、と決まっていた。だからこの映画も(確か、夜に現代モノのコンサートがある日、夕方までの時間潰しに)新宿の映画館に見に行ったと記憶している。
もう既に話題作だったから、映画雑誌などでエイリアンの造形も話のあらすじも大体知っていたし、「初めて見たショック」というのはさほど大きかったとは思わない。それでも、その日2度繰り返して見た揚げ句、日を改めてまた数回見に行った。同じ映画を何回も観るなどと言うのは初めての体験だった。
何がそんなに面白かったかと言うと、それはもう一にも二にもこのエイリアンのデザインである。SF映画の異星人というのは(「シンドバッド」シリーズや「アルゴ探検隊の冒険」などで知られる天才ハリーハウゼンの驚異のモデルアニメの名作を除けば)グロテスクで不気味な一方、はてしなくチープで不細工。こけおどしだけで動きの鈍い着ぐるみ、というのが王道だったのに、この異星人は不気味でグロテスクで恐ろしい形状なのに見事なまでに「斬新」かつ「美しい」のである!一発で魅せられてしまった。(しかも、映画ではこれがチラリズムで登場し、ほとんど全身を見せないのだ!)
これがH.R.ギーガーという(当時まだ39歳の)スイスの幻想画家のデザインによるものだと知って、居ても立ってもいられず美術書の輸入書店に予約注文して「ネクロノミコン」という最初の画集を手に入れた。それは、生物(バイオニクス)と機械(メカニクス)の合体した世界であり、骨や死体や性器…という生物の要素と、歯車やパイプや把手…といった機械の要素が、悪夢のような暗い空間で融合した、究めてユニークなものだった。
作品自体は、ピラミッドや古墳に描かれた壁画のような二次元世界のものがほとんどで、まさにH.P.ラブクラフト(アメリカの恐怖小説作家。ネクロノミコンは彼の想像した古代神話の中で死者を蘇らせる秘法が書いてあるという書物)のおどろおどろしい宇宙が現実に「形」になったような印象。色彩はなく、すべて黒か濃い茶系の世界で、「錆びて腐った鉄の表面」とか「腐敗した動物の死体」などと並んで「性器」がモチーフの源泉になっていることが明らかで、良く言えば「エロティック」人によっては「悪趣味」と目を背けたくなるようなイメージの奔流である。
その「醜悪」さと「美しさ」がぎりぎりのところで融合したイメージも強烈だったが、もう一つ、まだCG(コンピュータ・グラフィック) などというのが存在しない時代だったから、この怪物の絵の異様な立体感や光沢(表面のぬめり感)にも驚いた。「どうやったら、こういう絵が描けるんだ?」という疑問は、私の中で眠っていた美術少年(?)の血をたぎらせた。それが〈エアブラシ〉という道具による技術だと知って、あわてて買い込んだほどだ。(もっとも、この頃は既に「美術の方に進もう」という気は100%なかったし、使いこなせるほどには至らなかったのだが…)
つまり(話を無理やり音楽に結びつけるなら)、当時の「現代音楽」が、「聴いたことのない新しいサウンド」をジタバタ追い求めていたにも関わらず単なる雑音と騒音の羅列に堕し始めていたのに対して、「SF映画」という奇妙なジャンルから「見たこともない新しいヴィジュアル」が登場し、それが実は本能的なまでに原初的なイメージに根ざすものだということに発奮させられた…とでも言えばいいだろうか。
難解で無機的な「前衛」だけが新しい文化の方向ではない。原初的な本能や肉体的な感性に基づく(大衆的な)・それでいてまったく新しい文化だって充分可能なのだと、このブキミなエイリアンは教えてくれた(?)のである!(…って、そこまで言うと褒め過ぎか?)
ここで簡単に話のあらすじを解説しておこう。(ネタばらしの部分もあるので、まだ見ていない人は飛ばし読みを!)
◆あらすじ
時は近未来。場所は宇宙空間。舞台は、地球に向かう宇宙貨物船ノストロモ号。乗組員は7人(とネコ一匹)。
どこかで任務を終えて地球に帰還する途中なのか、全員コールド・スリープ(冷凍睡眠)中。ところが、不思議な信号を受信した船のコンピュータ(マザー)が乗員のみんなを起こし、「電波の出所をチェックし、異星人か否かを確認しろ」という(会社の運行規則か何かの)マニュアルを告げる。
そこで、乗務員たちはぶつぶつ文句を言いながらも小惑星に降り、うち3人が宇宙服を着て外を探検してみると、一目で地球のものではないと分かる異星人の遭難宇宙船を発見。おまけに、その中には腹を食い破られて死んでいる巨大な象のようなエイリアンのミイラがある。(この宇宙船と異星人のデザインも凄い。台本では「一目で地球のものではないと分かる」というト書きなのだろうが、それをここまで実際の「形」にした例は(CG以前では)希有だ。
このあたりの展開は、いわゆる「ゴシック・ホラー」そのものである。森で道に迷った主人公たちが、嵐の中で古びた洋館を見つける。で、雨宿りさせて下さいと入ってゆくと、そこには不気味な家主がいて……、という物語。吸血鬼ドラキュラを始めとする無数の恐怖物語の基本中の基本だし、日本でも能の「黒塚(いわゆる「安達が原の鬼婆」)」など多くの古典的名作がある。
そして、一人が宇宙船の地下に降りてゆくと、不思議なタマゴのようなものがびっしり並んでいるのを見つける。人が来たのを察知してか、そのうちの一つがパカッと口を開ける。「何だ?」と覗き込む乗務員。その瞬間、タマゴの中から飛び出した「何か」が宇宙服の顔面に食らいつく。これが有名な〈フェイスハガー〉。
人類が初めて「地球外生物」に出会った記念すべき一瞬なのだが、なんとこのエイリアン、別の生物に食らいついて体内に寄生し、幼生に育つと腹を食い破って外に飛び出し、人間を食って大きくなる、というおぞましい代物。ちなみに、この幼虫は〈チェストバスター〉と呼ばれる。
顔に食らいついて管を口の中に 差し込んで寄生する…という第一段階でも充分気持ち悪いのに、第二段階では生きたまま胸を食い破って出てくるのである!(このシーンは、この映画の最大のショック・シーンで、何も知らないで見に来た世界中の観客が絶叫し卒倒し吐いたらしい。最近はCGでもっとグロなショックシーンが氾濫しているから、今これを見て驚く人はウブな部類だろう。でも、生理的な「気色の悪さ」は不変だ…)
この後、宇宙船という閉鎖空間の中で、この人食いエイリアンを駆除するために乗務員が一致団結するのだが、貨物宇宙船なので武器はせいぜい手製の火炎放射器くらい。これを動体検知器なるものを手に右往左往し、結局一人ひとり殺されてゆく。しかも、その乗務員のうちの一人である科学主任がアンドロイドで、「異星生物を見つけたら、乗務員の命などどうでもいいから地球に持ち帰ること」という会社の密名を受けて動いていることが発覚する。このあたりの二転三転する展開も見事で、飽きさせない。
かくして残り3人となり、宇宙船をエイリアンごと爆破して救難艇で逃げる…という最後の手段に出るが、うち2人もあえなく殺されてしまい、とうとう女性航海士リプリーとネコだけになってしまう。そして、宇宙船自爆のタイムリミットぎりぎりに救難艇で無事脱出。やれやれ、とホッとして穏やかにエンドマークが出るかと思ったら、その救助艇の中にエイリアンが…!
…という怖いお話。
◆エイリアンはゴキブリか?
公開当時だれかが「これはゴキブリ退治だね」と言ったのが言い得て妙。確かに、あれは台所の隅にゴキブリが逃げ込んで、殺虫剤で追いつめるのに似ている。あの黒いテカテカ具合や、かさかさ走るスピード感。家具の奥や狭いすき間に潜り込み、追いつめられると突然、逆襲して顔に飛びついたりするおぞましさ。
考えて見れば、別にゴキブリは人に危害を加えるわけではない。それなのにあの黒くてテカテカ光る代物がカサカサ走るのを見ると、とにかく叩き潰したくなる。何か人類のDNAの記憶の底に仕込まれているのだろうか? 太古の昔、我らが人類とゴキブリ属の間に何か遺恨を残す出来事があったとか…(笑)
ただ、この映画のエイリアンへの対処は、(ゴキブリだと指摘されて改めて思ったのだが)きわめて「女性的な反応」のような気がする。なにしろ「とにかく殺す。火炎放射器で殺す。それでもだめなら宇宙船もろとも爆破させてでも殺す!」という反応は、相手がいかにおぞましい形状をしているからと言って、理性的な対処法とは思えない。しかも、これだけパニックになっているにもかかわらず、主人公である女航海士リプリーは、いなくなったネコを「爆破5分前!」と言ってるのに探しに行くのだ!
映画の公開当時、その場面で「ネコなんかほっとけ〜!」という悲鳴が観衆からはあがったそうだが、絶対それは男性。どこかの映画研究会だかで「この状況でネコ一匹を助けに行くのは妥当かどうか?」という質問をしたら、男性は全員「ノー」、女性は全員「イエス」という反応だったんだとか。(うーん、でも最近の女性はどうかな?)
でも、そのあたりの演出は縁日のお化け屋敷でお客をビックリさせる手練手管と言えなくもない。早く逃げなきゃならないのに車のエンジンがなかなかかからない…とか、暗闇で振り向くといきなり何かが飛び出してくる…とか、なんだネコかと安心させておいて後ろから怪物が襲いかかる…とか、光の点滅やスモークや不協和音の音楽で不安をかき立てる…とか、それはもう山ほどあるハリウッド製ホラー映画の常套手段。安易に多用すると「またか!」と顰蹙を買うのは必至である。
この映画でも、その手のチープなビックリ仕掛けをけっこう多用していて、公開当時はまだホラー映画などと言うジャンルもなかった頃だったから観客はいちいち素直にイスから飛び上がってビックリしていたが、DVDなどで家庭で鑑賞出来る今となっては、あざといだけで品位を損ないかねない。これだけ見事な「恐怖」の造形があるのに、低予算のビックリ箱映画のような編集をする必要があるのか?と首をかしげたくもなる。
そのあたりを考慮したのか、最近(2003年)あらためて作られたディレクターズ・カット(監督本人による新しい編集版)では、単に「ワッ!」と驚かせる類いのチープなカットはいくぶん整理されている。(ついでに、物語途中でエイリアンに殺されてしまったと思っていた船長が、幼虫の苗床として巣の中で生かされていたという衝撃のシーンも追加されている!)
それにしても、何だか分からない気色悪いものが出てきたら宇宙船を爆破してでも殺してしまう…というのは、実にアメリカンな思想(ハリウッド映画風思想…とでも言おうか)だなあ。「スター・ウォーズ」だって敵のダークスターごと爆破してしまうし、続編の「エイリアン2」でも工場施設ごと核爆破してしまうし。ちょっと考えて見ても、ハリウッド映画というのは、敵の基地だろうが古代の遺跡だろうが生物の生息地だろうが、主人公一人が生き残るために(映画の最後では)みんな破壊しぶっ壊してしまう。大虐殺、大量破壊のオンパレードである。
おかげで、このエイリアンにしても、どこから発生してどういう生態なのか、タマゴはどうやって産み付けられどうやって増殖するのか、どの程度の知性とどの程度の本能があるのか、などなど謎だらけのまま、ただ「気持ち悪い」「人襲う」という理由だけで駆除されてしまう。これがアメリカンな思想だというのは、昨今のイラク戦争を見ても分かるけれど、その原点が「女性的反応」だなどと言ったら女性に悪いので、やめておこう。
ちなみに、「男性的反応」というのがあるとしたら、この物語の中では科学主任(実はアンドロイド)アッシュの視点だ。彼は、このエイリアンが「貨物宇宙船の乗組員の生命」などより遥かに貴重だと断定し、寄生し殺し成長することを(人道的などという甘い視点は完全に抜きにして)「完璧なメカニズム」と称える。
人道的見地から見れば非難されるべき意見だとは思うけれど、公平に考えて見れば(つまり、殺される乗務員の側に立たなければ)、必ずしも100%無視すべき意見ではないとような気がするのだが、どうだろうか…。(そう言えば、「ゴジラ」でも、古生物学の山根博士が「あれ(ゴジラ)は貴重な生物なのだからなんとか殺さずに…」とブツブツ言うが、まわりから一蹴されてしまう)
一方で、エイリアン駆除のために狭いダクトに飛び込んでゆくダラス船長も「男性的」には違いないけれど、これは奥さんに「あなた!ゴキブリ殺してよ!」と言われてへっぴり腰で台所に入ってゆく亭主の役にすぎない(笑)。それよりは、事態を分析した結果「だれも助からない」とさっさと結論に達するアッシュ科学主任は(アンドロイドだからとは言え)頼もしいほど「理性的」であると言えるだろう。
もっとも、この役、イアン・ホルムという役者の怪演もあって、「理性的」というより「ブキミ」と化しているのはちょっと…(笑)。逆上した乗務員たちに壊されて首だけになりながらも、残された人間たちに向かって最期に「君たちは助からない。同情するよ」と言ってニヤリと笑うあたりは実に名場面で、好きなのだけど。(首の模型がチャチなのが玉にキズだが…)
◆蛇足
ちなみに、最初の「エイリアン」のヒットで、「エイリアン2(1986年。監督:J.キャメロン)、「エイリアン3(1992年。監督:D.フィンチャー)、「エイリアン4(1997年。監督:J.P.ジュネ)」という続編が作られた。それぞれよく出来た作品で、その点は「ゴジラ」が50年にわたって膨大なシリーズ作を残しながら第一作の足下にも及ばない駄作ぞろいなのとは対照的である。ただ、時代に打ち込んだくさびのような「歴史的傑作」としての第一作には及ぶべくもない。
面白いのは、すべての作が「眠りから覚めると」で始まり、閉鎖空間で仲間が一人ひとり殺されて行った揚げ句、最後に舞台をぜんぶ爆破して逃げ出し、生き残ったと思ったら「最後に一匹生き残っていて」ドンデン返しが…というパターンなこと。これはもうソナタ形式なみにエイリアン形式とでも呼びたいほどだ(笑)
ただ、正当なる続編と言うなら、エイリアンが地球にやって来て…という展開を見たいのが人情なのに、続く3作ともそれは見事に外して舞台を宇宙の閉鎖空間に限定しているのが不満と言えば不満。(もし「エイリアン5」があれば、舞台は地球かも知れないけれど…)
監督のR.スコットによれば、第1作の最後のシーンは「エイリアンが救助艇の中で最後の生存者であるリプリーを殺し、操縦席に座り(人間の声を真似して)地球と交信する」…というものだったそうだが、その方が面白かったかも。
この歴史的な第1作について、私などが「CGがない時代によくぞここまで!」と力説しても、CG当たり前の世代には説得力がないだろうから、あまり大きな声では言わないけれど、個人的には「キングコング」や「ゴジラ」と並ぶ立派な〈クラシック〉だと思っている。ロマンチックな恋愛映画や芸術的な文芸作品がお好きな方にはいまいちお奨め出来ない怪しい映画だけれど、ベータのビデオ〜VHSのビデオ〜LD〜DVD〜DVD-BOX…とメディアが変わるたびに買い替え、今でも座右に置いて(作曲しながら)繰り返し繰り返し見ている〈愛読書〉?のひとつである。
◆蛇足の蛇足
そう言えば、私の初のオーケストラ作「ドーリアン」がこの作品と同じ1979年の作なのだが、「エイリアン」というタイトルを意識したのかどうかは…… 記憶が定かでない(笑)
2004.05.13 記