音夢メモ
赤旗 2003年01月〜02月掲載
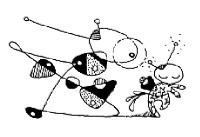 音楽は「夢」に似ている。
音楽は「夢」に似ている。
共に、触れることの出来ない(時には透明でとりとめのない)架空世界であるにもかかわらず、妙に生々しく(時には現実世界より鮮やかに)感情を実感できるからだろうか。
不思議なことに、そこには密かな予感や淡い回想が、様々な種類の快感や不安と共に静かに広がっている。そして、なぜか分からない懐かしさ、どうしようもない悲しさ、何とも言えない恐ろしさ、言葉では説明出来ない優しさ、そんな色々な感情が、心の襞に直接ひたひたと触れて来る。「不思議だ」と、いつも思う。
だから、人は夢(音楽)に心奪われ、夢(音楽)に惹かれる。心地よいだけが夢(音楽)だとは限らないのに、そして、悲しさや苦しさに満ちた夢(音楽)もあるというのに。
そのせいだろうか、音楽が終わった時、人は夢から醒めたような顔になる。
しかし、実を言うと、もうかれこれ三十年ほど作曲家をやっているけれど、「音楽とは何か?」と聞かれてもよく分からない。音楽に何を求め、音楽をなぜ続けているのか。それもよく分からない。そのことについて後ろめたさを感じる時もあるけれど、音楽を夢と思えば、それも納得出来る。人は生まれてからずっと(たぶん夜毎に)夢を見続けているけれど、「夢とは何か?」と聞かれてもよく分からないし、なぜ夢を見、夢に何を求め、夢をなぜ見続けるのか分からないのだから。
そう言えば、蝶になった夢から醒めて、蝶になったのが私の見た夢なのか、それとも今の私が蝶の見ている夢なのか、と悩むのが荘周の「胡蝶の夢」。まさにそれと同じように、「音楽家」などと言って音楽を作っている気になっていても、実は音楽に作られているのかも知れない、と時々思うことがある。
つまり、大気に浮遊している「夢」が、「音」という形で現世に生まれ落ちたいために、音楽家という名の「出口」を利用する。そのために都合のいい形をした出口を持っている人間が、音楽家になるというわけだ。
だから、「音楽の才能」などと言っても、それはただ「音」が出やすい形の「穴」がどこかに付いているという、ただそれだけのことなのかも知れない。夢の世界から音が漏れこぼれてくる「穴」、それが音楽家というわけだ。そう思うと、ちょっと奇妙な気分になるけれど。
かくして人は、音楽を聴き続ける。そう。夢見るように…。
外れた音で下手な歌を歌うと、昔は「ヌカミソが腐る」などと言われたものだが、今は何と言うのだろう?
確かに、人はある種の音程で歌われると「心地よい」と感じ、その音を外されると「気持ち悪い」と感じる(ヌカミソがそれを感じるかどうかは定かでないが…)。ピッタリと「合った」音はそれこそ天にも昇るほど美しく気持ちいいが、それがわずかに「外れる」と、時には耳を押さえて身もだえするほどの気持ち悪さを感じることもある。だから、プロの歌い手ともなるとそれを逆手にとって、微妙に「居心地が悪い」音をわざと出し、その後に出す「心地よい」音の気持ち良さをアップさせる、などという高等テクニックを使ったりするほどだ。
そして、音の持つ「心地よさ」と「居心地の悪さ」を、ひとつの歌として横に並べて組み合わせてゆくのが〈メロディ〉であり、それを縦に並べて2声や3声の音程の組み合わせの変化として聴かせてゆくのが〈ハーモニー〉。つまり、メロディにしろハーモニーにしろ、人間の耳が「あ、その音はけっこう気持ちいい」とか「おっと、その音はなんだか気持ち悪い」と感じる音を縦や横に微妙に組み合わせて、人間の感情や心に触れてゆく「ちょっと不思議な仕掛け」なのである。
特に、西洋の教会音楽の中で培われたハーモニーのシステムは、コーラスのサウンドの中に神や天使や悪魔のイメージを感じさせたり、アンサンブルの響きの中に「悲しい」とか「楽しい」とか「心苦しい」とか「愛らしい」などの感情を織り込むことが出来るまでに発達した。西洋のクラシック音楽史は、この微妙なハーモニー感覚をコーラスやオーケストラやアンサンブルを使って極限まで拡大し、〈音楽〉による表現の限界に挑んできた歴史と言ってもいいかも知れない。
それに対して日本人は、旋律や声色の微妙なニュアンスに「こめられた心」を聴くのが伝統。音の響き方や震えや揺れに「せつない」とか「やるせない」とか「物憂い」などの感情を聴き取る。原点はどちらも同じで、そもそもは音の持つ「心地よさ」と「居心地の悪さ」の探求から始まっているのだが、東西では違った方向に展開してゆくあたりがちょっと面白い。
「音楽は世界共通の言葉だ」とはよく言われることだけれど、民族や文化圏や時代によってその文法が異なるというのもまた事実。それを聴き取るのもまた、音楽を聴く楽しみの一つと言うべきだろう。
 音楽の要素としてメロディやハーモニーと共に重要なのが「リズム」。
音楽の要素としてメロディやハーモニーと共に重要なのが「リズム」。
これは、そもそも心臓の鼓動から生まれたもの。だから、人は早いテンポのリズムを聴くとなんとなく興奮し、ゆっくりしたリズムを聴くとなんとなく落ち着く。
例えば、一拍が一秒(メトロノームのテンポで「60」)くらいだとアンダンテ。これは、ゆっくり歩く早さの平常心のテンポ。そして、これ以下の遅いテンポがいわゆるアダージョ。座ってじっとしていたり眠っている時の心臓の早さなので、人はこれ(例えば子守歌など)を聴くと安心して眠くなる。逆に、倍の「120」くらいの早さになるとアレグロ。急いで走ったり興奮してドキドキしている時の心臓の早さなので、人はこのビートを聴くとなぜか踊り出したくなる。このあたりは、何だか人間の体に組み込まれたヒミツの仕掛けのようで、ちょっと面白い。
とは言え、世にはびこるリズムのほとんどは(心臓そのもののリズムとはちょっと違って)2拍子か4拍子。これは、どうやら人間の手足の数から来ているらしい。歩けば1、2。踊れば1、2、3、4。つまり、リズムはいつだって人間の形をしているのである。ということは、虫の音楽なら6拍子、タコの音楽なら8拍子。では、ムカデの音楽は?
ちなみに、西洋音楽でやたらと4拍子が多いのは、馬に乗る歴史から来たものなのだとか。パカパカパカパカ…と馬の足に合わせて4拍子。早足なら、パカパッ・パカパッと、これも4拍子。ただし、人間が歩く行進曲(マーチ)は、当然ながら2拍子になる。では、ワルツの3拍子は?
これは一説には、くるくると円運動をする踊りなので、円周率の3.14から来ているのだとか。そう言えば、ウィンナ・ワルツなどは正確に聴くと1、2、3の拍子が均等でなく、2拍めが少し長い。なるほど、3拍分を足すと「3」ではなく「3.14…」になるのか、と妙に納得したくなる。
そう言えば、同じ4拍子でも、たんたんたんたん…と正確にリズムを刻むとなんだかぎこちなく聞こえ、たんたかすたたか…というようにちょっと崩して刻むとなんだか軽妙に聞こえるのも不思議だ。強弱(アクセント)の付け方次第で、たった4つの拍子の中に人は無限のニュアンスを盛り込むことが出来るということらしい。
「リズム」とは、人の体をくすぐり、手足をくすぐり、心をくすぐる「神様からもらった不思議な仕掛け」なのである。
子供の頃、音楽というのは(例えば花や夢のような)ひたすらきれいで心地よい「音」の連鎖だった。それが、思春期あたりになると、異性へのあこがれや青春の焦燥をメロディやリズムに乗せて語る不思議な「言葉」に変化していったような気がする。
それでも、その頃は、西洋クラシック音楽の交響曲とか弦楽四重奏曲のような(歌もビートもなく、ひどく長いだけの)音楽は、ただ退屈で理解不可能な音の連続にしか聞こえなかった。実際、中学生の頃までは、「運命」も「未完成」も「第9」も、まともに聴いたことは一度だってなかったほどなのだ。
ところが、高校に上がる頃に何の気なしに手にした「スコア(総譜)」という奇妙なものにより、音楽への認識は一変した。それは、オーケストラが曲を演奏するための大きな楽譜で、いわば曲の設計図のようなもの。どこか電気機器の配線図や電車の時刻表あるいは数式や化学式などに似ていて、知らない人が見ても目がチカチカするだけの代物ではあったのだが。
しかし、それを見て心底驚いたのは、今まで単なる「音」として聴いていたオーケストラの響きの奥に、様々なメロディの線を織物のように組み合わせてゆく「対位法」や、複雑な心情の変化を音の組み合わせで描いてゆく「和声法」、世界の色々な現象や人間の多彩な感覚をサウンドとして構築してゆく「管弦楽法」などなど、厖大な仕掛けが施されているということだった。
それらは、いわば文法のようなものだから、知らない人の耳には単なる「音の響き」にしか聞こえない。ところが、それを言語として理解する人の耳が聞くと、そこには「物語」や「ドラマ」や「思想」が満ち満ちているのだ。例えば、日本語を全く知らない人にとっては、「源氏物語」だろうが「吾輩は猫である」だろうが「雪国」だろうが、単なる「音(あるいは記号)の連鎖」にしか聞こえないが、言葉を勉強すれば、その響きの向こうに豊かな想像力と不思議な体験に満ちた世界が広がっているのを体感することが出来る。それに似ている。
音は確かにただの空気の振動なのだが、人はそこに感性と知性のすべてを投入して、「音楽」という人間独自の豊饒なる文化を作り上げた。それは言葉より深く、人の心の奥に染み入る。音楽とは、まさに人間そのものの形をした「夢」なのである。