傑作選
絶対安全音感日記
あんさんぶる1999年8月号〜2001年1月号連載
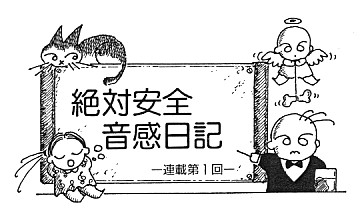
第1回 音楽の才能って・・・
音楽とは「好き」でやるものなのだが、人はある時期、これをプロとして一生の仕事とするか、アマチュアとして純粋な楽しみでやるか、の選択の岐路に立たされる。私ももちろん作曲家になるにあたって体験済みだが、これが結構きつい。
好きでやっている分には気付かないのだが、この分かれ道に立つと最初に考えざるをえないのが、「自分に才能はあるんだろうか?ないんだろうか?」ということ。これは実を言うと恐ろしい問いであって、神ならぬ身に答えなど出せるわけもない。星占いを見て「吉」と出て喜んでいると、おみくじを引けばこちらは「凶」と出たりして落ち込んだりする。お手上げである。
悶々としながら眠ると、夢の中に天使が出てきて「キミに才能がないわけないよ!」と微笑みながら私を音楽の世界へいざなうのだが、入口の受付に座ったミューズの女神は「あんたにそんなものあるわけないでしょ!」と無愛想に言い放って私を中に入れてくれない。どうすりゃいいんだ、と頭かかえたところで目が覚める。そんな繰り返しである。
友人に相談すれば「才能があろうがなかろうが、好きならやればいいじゃん!」と無責任に言われるし、親に相談すれば「音楽なんかにウツツを抜かしてないでちゃんと勉強しなさい!」と説教される。社会人をやってるタカ派の先輩は「甘い、甘い。音楽なんかで妻子が養えるもんか。やめちまえよ!」と言い、その横でハト派の先輩は「いいなあ、夢があって。食えなくてもいいじゃない。やれば?」とけしかける。音楽の先生は「よく考えてあなたの思う通りになさい」と言うが、それは裏返せば「あたしは責任はとりませんからね」という意味だし、泥沼である。
*
この人生の岐路は、だいたい十七歳あたりで「大学進学」という形をとって具体的にドーンと目の前に現れる。もちろん早い人はそれ以前に海外への留学とかプロの音楽家への私淑とかいう形の選択を迫られるし、音楽大学を選択し卒業しても、その後さらなる様々な究極の選択が待っている。
ごくたまに、全然悩まずに小さいころからトントン拍子にコンクール入賞だの海外留学だのをこなして気が付いたらプロをやっている、というような人もいないではないが、普通はみんな悩みに悩むものだ。
で、ある先生はこう言う。
…「プロになりたいんですけど」と若い人に言われたら、「やめなさい」と言うに限ります。本当に才能があるなら「やめなさい」と言われてもやめるわけがありませんし、「やめなさい」と言われてやめられるようならプロになどなれるわけがないからです。
この説には確かに一理ある。私も十七歳の時に「作曲家になりたいんですけど」と相談に行ったプロの音楽家にそう言われた。それでも全然「じゃあ、やめよう」と思わなかったのだから、この説、当たってはいる。
でも、プロとして一線で音楽家をやっている人は必ず「あの時、あの先生(あの人)に出会って音楽を一生やる決心をした」という決定的な出会いがあるものだと言うから、そこで「やめなさい」と言ってしまっては何も育たない。愛されて育てられてこそ、人は愛される音楽家になるのである。
で、もう一人の先生はこう言う。
…人は音楽家として生まれるのではありません。音楽家になるのです。
どこかで聴いたことのあるようなセリフだが、これは説得力がある。もし天下御免の最強の「音楽の才能」があるとしたら、平和な時代に音楽が出来る家に生まれ、知能指数が高くて絶対音感があり手先が器用で記憶力がよく、両親が音楽好きでその知人にプロの音楽家がおり、高価な楽器や先生や留学を選択することが可能な財力があり、人に好かれ舞台で栄える容姿を持っていて、 おまけにコンクールや賞や師匠やパトロンに恵まれる「運」があること。これが「音楽の才能」である。
しかし、そんなもの「音楽が好きッ!」というコケの一念の前には無力極まりない。かく言う私も、自慢じゃないがこの「才能の条件」のうち満たしているのは「両親が音楽好き」ということくらい。後は「それがどうした!」というくらい何もない。むしろ、自分の音楽を自分の手でつかみ取るには「才能」や「運」などはむしろ邪魔なんじゃないかとすら思っている。
と言うわけで最後に一言。
才能のあるものたちは幸いである。
才能は彼らのものだからだ。
しかし、
才能のないものたちこそ幸いである。
音楽はあなたたちのものだからだ。
第2回 作曲家になってしまったら・・・
今でこそなぜか作曲家などというのをやっているが、子供のころ特に音楽が好きだったという記憶はない。
小学生くらいの頃やっていた事というと、プラモデルで第二次世界大戦中の飛行機だの戦艦だの空母だのを作り集めたり、近所の空き地で忍者の手裏剣だの中世の石弓だのを見様見まねで制作したり、川で捕まえたイモリの飼育に明け暮れたり、マンガを書きまくっていたり、縁日で買ったヒヨコが大きくなってニワトリになってしまったのを猫みたいに家の中で飼っていたり、子供向けの科学雑誌やSF読本を読みあさったりしていたことだろうか。
うーん、今になってこうやって羅列してみると、確かにそのころから「一人で何かをやる」ということに異様に執念を燃やし、「みんなと一緒に何かをする」という協調性が欠如していた、と気付くなあ。
それでも家には祖父が買った古いアップライトのピアノがあって、父がフルートを吹いたりピアノを弾いたりしていた。工芸家をやっていた母も、ミッション系の女学校出のせいか賛美歌を歌ったり弾いたりしていた。
そのうち2歳下の妹がピアノを習い始め、私も力づくの見様見まねで「エリーゼのために」なんかを弾いていたのだが、やがて、お約束通りに「ピアノのおけいこ」に巻き込まれることになった。9歳(小学校4年生)頃の話になる。
若くてきれいな女の先生(実は今イギリスで一緒に仕事をしている指揮者の親友のお母さんであることが後に判明!)ではあったのだが、特に上達が早いわけでもなく、作曲の才能を発揮したわけでもなく、「このお子さんは音楽の才能がありますわッ!」と言われたこともなく、毎日毎日ハノンだのブルグミュラーだのの練習曲を弾かされるのは、すぐに苦行になってしまった。
その時に思い知ったのは、「自由にやっていると音楽というのはとても楽しいものなのだが、レッスンとか練習とか勉強とかになるとなんと嫌なものになるのだろう!」ということだった。三つ子の魂百までと言うが、この時の印象から、私は以後いっさい独学を押し通し、音楽学校に行こうとか誰かに習おうとか思ったことがない。
しかし、このあたりは性格によって個人差があるらしく、演奏家として大成した人はここで「練習がイヤ」とは思わないものなのらしい。ギタリストの山下和仁氏などは(昔当人から聴いた話では)練習が好きで好きでたまらず、朝学校へ行く直前の玄関までギターを弾いていて、帰るとランドセルを置いてそのままギターを弾いていたのだとか。
ただ、多くの場合、女の子の方が協調性と順応性に優れていて、先生の言う通りにレッスンをこなしてグングン上達してゆく。どうもそのあたりは男の子というのは分が悪くて、どこか壊れているような気がする。私の場合も、妹や従姉妹がどんどん上手くなってゆくのを横目で見ながら、2年ほどで結局やめてしまった。
そして、中学生になると同時に、ギターを弾きだした。クラシックのではない。当時流行りだしていたフォークやポップスあるいはロックのギターである。
そのころはビートルズやヴェンチャーズに始まったエレキ・バンドのブームの真っ最中で、和製のグループ・サウンズなどがもてはやされている一方でピーター・ポール&マリーやジョーン・バエズのようなフォーク・ソングのブームがあった。男の子としてはギターをかき鳴らして歌の一つも歌えるというのは、紳士のたしなみだったのだ。
と、そんな風にフツーの中学生をやっていた私に当時クラシック音楽がどうなっていたかの記憶はまったくない。
これがどうしてクラシックの作曲家なんかになるかなあ…と、考えれば考えるほど不思議だが、人生というのは分からない。
高校受験を控えた十四の冬、十二月も押し迫った追い込みの時期に、「受験に音楽なんてないんだから、自習にすればいいのに」とボヤきながら受けた音楽の授業で聴いた「交響曲」という言葉になぜかふと魅せられてしまった。これがまず第一の不覚。
続いて、その授業で聴いた「運命・未完成」のレコードをついうっかりクリスマスに買ってもらってしまった。これが第二の不覚。
そして、その2曲の楽譜を父親が持っていて「これがスコアだけど、見る?」と言われて、見てしまった。それが第三の不覚。
そして、その夜、交響曲というものが人間の最高の英知を結集したものであることをガーンという擬音とともに感じてしまい、「俺は作曲家になるッ!」と決めてしまった。これが最後の不覚。
そして、ここから悪夢が始まるのである。
良い子の皆さんは真似しちゃダメよ。
第3回 音楽家の頭の構造って・・・
交響曲などのオーケストラ曲を作曲していると、「一体どういう頭の構造になっているんですか?」と時々聞かれる。
で、「えーと、頭の中に交響曲のタネが3Dみたいにポワンと浮かびましてね、それに毎日水をやってるとだんだん分裂増殖して育っていくんですよ。ちょうど胎児みたいなもんで、大きくなるのに十月十日(とつきとおか)ほどかかりますが…」などと答えると、ポカンとした顔をされる。
確かに、四十段ほどあるオーケストラのスコア(総譜)にビッシリ音符が書いてあるのを見ると、普通の人は謎の暗号で書かれた魔術書のように思えるらしい。高校生の頃そんなスコアをセッセと書いていたり読んでいたら、のぞき込んだ女の子に「わぁ、宇宙人みた〜い!」と言われたことさえある。
うーん、確かに何か変な能力だけは普通の人より優れているのかも知れない。でも、そのほかの能力はサッパリだから、頭の構造自体が優れているというわけではないらしい。その証拠に、私はピアノでデタラメ弾いて曲をでっち上げることは出来るのだが、どんなやさしい小品でも、人が書いたものを楽譜通りに弾くという簡単なことが出来ない。
しかも、お金の計算とか損得勘定とか社会常識とかいうのは完全欠如しているし(だからこそ、交響曲なんて言う代物が書けるのだろうが)、人の顔とか名前とかを憶える記憶力に至ってはゼロに等しい。
以前、私のコンサートに来ていた若いきれいな女性に「初めまして」と言ったら、「お会いするの3回目ですが、毎回そうおっしゃいますね」とにらまれたことがある。その時はまたまずいことに「すみません、ネコなら一度会えば顔を憶えられるんですが」と言ったところ(そのころは本当に人よりネコづきあいの方が多かったのでまぎれもない事実だったのだが)、怒って帰ってしまった。
どうも「記憶する」より「書き留める」傾向が強いせいか、楽譜に音符を書いたりコンピュータを扱ってデータ管理したりするのは得意なのだが、身一つで暗記する能力は日々どんどん衰えてきているような気がする。
そんなわけだから、俳優とか役者のように台本に書かれているセリフを空で暗記して舞台やスクリーン上で演じる仕事というのも、私にはまったく神業にしか思えない。特に舞台などで一晩出づっぱりでセリフをしゃべりまくる俳優さんなどを目の当たりにすると、「一体どういう頭の構造になっているんですか?」と聞きたくなるほどだ。
もちろん、セリフを憶えるというのは才能以上に努力の結果ではあるのだろうが、手帳で調べた電話番号をプッシュボタンを押す前に忘却してしまう私としては、俳優の記憶力というのは驚異でしかない。
ただ、この記憶力は天分によるものが大なのらしく、ピアニストの田部京子さんに以前「コンチェルトやソナタみたいな長い曲は一体どうやって暗譜するんですか?」と尋ねたところ、「耳で聞けば、大体全部憶えられるんです」と言うので驚嘆したことがある。しかも、「子供の頃は一度聞いた曲は大体すぐピアノで弾けましたから楽譜なんかいらなくて、楽譜ってなんであるんだろう?って思ってました」と言うあたりになると、これはもう超能力の域に達している。
俳優やピアニストがセリフや音楽を頭の中でどうやって記憶しているかと言うのは人それぞれらしいが、大きく分けると「体に感覚として覚え込ませる」タイプと、「頭の中に映像として焼き付ける」タイプとがあるのらしい。
前者は、時間をかけてじっくり口や手に覚え込ませるタイプで、記憶についてはこれが基本中の基本だが、時間がかかることと、どんなに完ぺきを期しても本番中いきなり頭の中が真っ白になる恐怖からは逃れられないのが難点だそうだ。
一方後者はプロ仕様。どんな大曲でもすべて目をつむって指揮することで有名だったカラヤン翁は、頭の中で記憶したスコアをめくれたと言うし、かのアルゲリッチ女史は楽譜を見るだけで写真を撮るように頭の中に曲を記憶でき、いきなり暗譜で弾けたと言う。
音楽の能力というと「絶対音感」ばかりが有名だが、演奏家にとっての「音楽を把握する能力」としては、この「記憶力」の方が上かも知れない。ただし、これも生まれつきあったほうが良いのか、努力で身に付けたほうが良いのかは分からないのだが。
と言うわけで、最後に問題です。次の二人のうち、音楽の才能が本当にあるのはどちらの人でしょう?
一、「私、暗譜は苦手です。二回や三回弾いただけじゃ憶えられなくて」という人。
二、「暗譜? もうバッチリですよ。百回も繰り返せば憶えちゃいます」という人。
第4回 ピアノって・・・
作曲家を二十年ほどやっているが、実を言うとグランド・ピアノというものをまだ持ったことがない。
三畳一間の自分の部屋で作曲を始めたころは、六十鍵しかない安いアップライト型電子ピアノ。夜中に仕事をするので音が出ないようにヘッドホンで作業できるようにと言えば聞こえはいいが、早い話がお金がなかったので、楽器店の隅に置いてあった中古の荷崩れ品を格安で買ったのだった。
チェレスタのような軽やかな音がして、それはそれでけっこう気に入ってはいたのだが、なにしろ一日中それこそ十何時間と酷使するものだから、プラスチックの鍵盤がポキポキよく折れた。折れてしまうと音が出なくなってしまうから、その鍵盤を外して最高音とか最低音などの使う回数が少ない部分の鍵盤と取り換え、だましだまし使っていた。
しかし、あんまりポキポキ折れるので、そのうち高音も低音も十コずつほど音が出なくなり、最後は鳴るのは四十鍵3オクターヴ半くらいになってしまった。
これで「朱鷺によせる哀歌」からギター協奏曲「天馬効果」あたりまで書いていたのだが、さすがに「曲がりなりにもプロの作曲家やってるんだから、早くちゃんとしたピアノを買えい!」というまわりからの非難の声で、少なくとも八十八鍵あるフル・サイズのピアノを買わねば…とは思いたったのである。
しかし、ピアノなどという大きくて重くて音のデカい代物、どう考えても日本の住宅事情には合いません。例の中古電子ピアノでさえ、買ったはいいものの二階の部屋に自力で引き上げようとしたら(中古の格安品ですので、設置まではやってくれませんでした)階段の曲がり角でつかえてしまって動かなくなり、そのまま二日ほど岩のように階段を塞いでいたほどなのですから。
もっとも最近は、十何階のマンションでもクレーンで吊るして窓から入れられるらしいので、その点の心配は無用らしい。ただ、あんな何百キロもある鋼鉄の固まりが中に入った楽器を、上下左右に人が住んでいる狭い部屋で鳴らすということ自体がどうしても信じられない。入れたとしても、とてもフォルテ全開で弾きまくるなんてことは出来っこないし、夜中に音を出せないのでは作曲の仕事になど使えないではないか。
そこで「そうか、そもそもグランド・ピアノを手に入れるというのは、グランド・ピアノを入れられる部屋と家をまず手に入れなければならない、ということなのだな」とその時納得。戦車が欲しいからと言ってアパートの自分の部屋に本物のレオパルド戦車を置く人がいないように、日本のウサギ小屋に住む貧乏作曲家としてはそうそう自分の部屋にグランド・ピアノを入れるわけにはいかないのである。嗚呼。
と言うわけで結局、八十八鍵のフル・サイズはまたしてもアップライト型の電気ピアノになってしまい、その後、コンピュータを使うようになってからMIDIで鳴らせるデジタル・ピアノに買い替え、さらに最近アクション部分だけがグランド・ピアノと同じという新型に買い替えて、今に至っている。
まあ、作曲家というのはオーケストラを持っていなくてもオーケストラの曲を書く仕事なわけだから、別にグランド・ピアノなんか持っていなくとも想像力さえあれば大丈夫。(とは言え、ピアニストでピアノを持っていないという人がいたら、さすがに驚くが…)
それに、作曲家というのは仕事柄、右手にシャープペン、左手に消しゴムを持ちながらピアノを弾くという特技(?)があり、おかげでピアノの鍵盤は消しゴムのカスだらけ。まともなピアノなら泣いてしまうのだ。
某先輩作曲家などは、まったく調律をしていないボロボロのアップライト・ピアノで作曲していたっけ。「だいじょうぶ。合ってる音を想像すればいいんだから」と言うのだが、これまた消しゴムのカスが一面にこびりついて化石の丘のようになっている壮絶なピアノだったりする。
その先生は、いくら電気ピアノを勧めても「私は電気と名のつくものは、電気イスも電気ウナギも嫌いです」と頑固なのだが、私は日本の住宅事情に優しいこの電気ピアノ、けっこう気に入っている。
唯一の問題点は、ずっとヘッドホンを付けて仕事していると、電話が鳴っても玄関のチャイムが鳴ってもまったく気付かない、というところくらいだろうか。
と言うわけで、何度ベルを鳴らしても私が全然電話に出ない時は、出かけているのでも居留守を使っているのでも遊びに行っているのでもなく、ピアノを弾いているのです。
たぶん。
…きっと。
いや、おそらく…。
第5回 師と弟子って・・・
私のようなあやしげな独学の作曲家でも、この商売を二十年もやっていると「弟子にして下さい」と言う若者がたまにいる。
しかし、残念ながらすべて丁重にお断りしている。「どうしてですか?」と聞かれた場合は、「〈これ以上、作曲家を増やすな〉というのが祖父の遺言でね」などと適当なことを言うと大体は笑ってあきらめてくれる。
それでもまだ「どうしてですか?どうしてですか?」と食い下がられた場合は、こう言うことにしている。「才能のない弟子に教えると時間のムダになる。そして、才能のある弟子に教えると商売がたきになる。どっちもヤバい。だから弟子はとらない」
これで大体が「そんなムチャクチャな!」とあきれながらも退散してくれるが、そのうちマクベスみたいに「才能がないわけでもあるわけでもないもの」がやって来て、バーナムの森を動かす日が来るのかも知れない。
*
などと言ってはいるが、実は私も十九歳の若き日のころ、とある作曲の先生の家を訪ねて行ったことがある。
ただ、「弟子になろう」とか「何かを教わろう」などという殊勝な気持ちで行ったのではない。クラシック系音楽の場合、おもだった作曲家は当然ながらみんな死んでしまっているので、とにもかくにも「生きている作曲家を見たい」と思ったわけなのだ。
だから、コンサートがある時にリハーサルに付いていったり、楽譜を写すのを手伝ったりということは喜々として手伝ったが、いざ先生が「何かを教えてやろう」というモードになると途端に逃げてしまうという、可愛くない弟子だった。
しかし、そもそも初歩の初歩の「お稽古」ならともかく、芸を究めるレベルで師匠が弟子に優しく手取り足取り教えるなんてあり得ないのだ。修業とは「師の身近にいて芸を見る」ということ。それだけでつながっているのが真の師弟関係なのだ。
そして、師は言う。
芸は教わるもののではなく、
盗むものだ…と。
*
もっとも、本当にそう思って教えないのか、ただ面倒臭くて教える気がないだけのか、それは誰にも分からない。だから、そう偉そうに言っておいてペロッと舌を出す人の悪い師匠もいそうな気がする。
そう言えば、ある津軽三味線の名手の話でこんなのがあった。その人が若いころ付いていた師匠は、住み込みの弟子として彼が家に上がって以来数年、教えらしい教えはただ一言。「とにかく外へ行って弾け!」だけだったそうな。
で、彼は「なるほど、家の中で閉じこもって弾いていては小さな音楽になるばかりだ。外へ出て大自然と向かい合い、それに負けない大きな音楽をつかみ取れ、と言うことなのだな」と一念発起し、雨が降っても雪が降っても、毎日毎日外に出て行って海や滝や風に向かって三味線を弾き、修業したと言う。
やがて、彼はその世界で押しも押されもせぬ名手となり、「これも、大自然と向かい合って弾け、とお教えくださった師のおかげです」と言うと、師はこう答えたそうだ。
「そんなことは言っとらん。ただ、家ん中で弾かれるとやかましくてたまらんから、外へ出て弾け、と言っただけなんだナ」
*
好きだなあ、この話。
もうひとつ、獅子が我が子を千尋の谷に突き落とし、這い上って来た子だけを跡継ぎにする、という有名な故事の裏話もそうだ。
あれも実は父獅子は、大きくなったら自分より強くなりそうな子を「こいつはヤバい!」と突き落としちゃうだけ。普通はそれで死んでしまうのだが、あるとき頑丈な子がいて「何するんだ、このオヤジ!」と怒って這い上ってきた。しかも、すごい剣幕だ。
父獅子はさすがに「これはマズい」と思って、「よくやった。それでこそ我が子! お父さんはお前のことを思って泣く泣く突き落としたのだよ」と口からでまかせを言って抱きしめた。すると、世間知らずの子獅子は、「そうか。そうだったのか。お父さんありがとう!」と感動の涙。かくしてあの故事が出来上がった、と言うわけだ。
これを「師」と「弟子」の関係にあてはめてみると、この話にはなかなか奥深いものがあるような気がする。もしかしたら私も、若者たちをがけから突き落としているだけのように見えて、実は弟子を育てているのかも知れない。(…んなわけないか…)
ちなみに、中国にはこの故事のいわれになった獅子の谷というのがあって、そこには突き落とされた獅子の子の屍が沢山あり、「死屍(獅子)累々」というのはそこから来たというのだが、真偽のほどは明らかではない。
第6回 外国語って・・・
数年前からイギリスのシャンドス(CHANDOS)というCD会社と専属作曲家(コンポーザー・イン・レジデンス)の契約をかわしていて、向こうのオーケストラを使って年にほぼ1枚ほどのペースで作品集を録音している。
…そう言うと、必ず聞かれるのが「じゃあ一年の半分以上は向こうに行っているんですか?」とか「さぞかし英語はペラペラなんでしょうね?」という問い。
うーん。実は二ケ月ほど前にもイギリスに行ったのだが、滞在はわずか3日間だけ。その間しゃべった英語は、スタジオでの二言三言くらいだろうか。
なにしろ、最近ではロンドンまでジェット機でわずか十二時間ほどだし、安い便なら往復十万円もしない。新幹線のグリーン車で大阪に行ってホテルに数泊するのと大差ないのだ。だからと言うわけではないが、別に大阪弁をしゃべれなくても大阪で仕事ができないわけではないように、英語をしゃべれなくても英国で仕事ができないわけではないような気がする。
実際、今年の夏に行った時も、東京でピアニスト嬢と対談の仕事を済ませてから、そのまま成田行き。荷物と言ったら小さなバッグ一つで、「それでイギリス行くんですか? なんか名古屋あたりにフラッと行くような感じですね」と笑われてしまったほど。
確かに、演奏家ならドレスとか着替えとか色々荷物があるのだろうが、録音に出かける作曲家は楽譜と下着の替えだけあれば何も要らない。別にステージに乗るわけでもパーティに出るわけでもなく、ただスタジオで普段着のまま座っていればいいのだから、とりたてて持ち物はないのである。
それに一人旅では、飛行機や電車を乗り換えるのにも切符を買うのにもトイレに行くのにも荷物を全部手元に持っていなければならないから、大きな荷物を持ち歩くのは不可能。身軽に越したことはないのである。
と言うわけで、手荷物一つで成田からロンドンに飛んでヒースロー空港で国内線に乗り換えてマンチェスターという街で降り、着いたその夜はリハーサル。翌日からそこの放送局のスタジオで2日間の録音セッション。終わった次の朝には飛行機に乗って東京に帰ってしまったという次第。
向こうの会社との細かい打ち合わせや連絡はほとんどがFAXと電子メールだし、文書の翻訳はマネージメントを通すものの、指揮者とは日本と英国とでも直接携帯電話で話せる。楽譜やテープなどは航空便で送るが、コンピュータ打ち込みのスコアや音源ならインターネットでMIDIファイルとして送れば即時に向こうに着く。特に現場に長逗留しなければならない理由が見当たらないのだ。
しかし、実を言うとこの「専属」の「イン・レジデンス」というのは、「そこに居住して専属に仕事をする」というのが本来の意味。(マンションで「なんとかレジデンス」というのがあるように、「住居」というような意味らしい)。本当なら、その会社と同じ町に住んで作曲しなければいけないはずなのだが、年に3日しか滞在しないのだからひどい「レジデンス」もあったものだ。
いや、最初の頃はロンドンに何週間か滞在して、あこがれのベーカー街に行ったりミュージカル見まくったりしてはいたのだ。でも、3日もいると、カウンターで刺身をつまみに日本酒すする居酒屋が懐かしくなってたまらなくなる。パブで飲むビールもうまいけれど、やっぱり日本人の血はどうしようもないから、東京でワインがぶ飲みしている外国かぶれの連中の気がしれないわけなのだ。
と言うわけで、「英語ペラペラ」というのも無理な話。イギリスに年1〜2回必ず行くのだから「まあ、そのうちだんだん話せるようになるだろう」と思っていたのだが、どうも逆で、どんどん話せなくなってゆく。困ったものである。
でも、作曲家はあんまりペラペラしゃべらないほうが偉そうに見えるみたいだ。演奏がうまくいけば「グッド」、ちょっと問題ありなら「ノー・グッド」、どうでしたかと演奏家に聞かれたら「グレート!」とか「アイム・ハッピー!」とか言えばいい。たまに気に入らなくて「ノー!」と言うとスタジオ中がピリピリするから面白い。(おっと、面白がっちゃいけないか…)
それより、最近は日本での人付き合いがなくなってきて、気がつくと三日も四日も人と言葉を交わしていないなんてザラ。全然日本語を話さないから、英語どころか「日本語」をどんどん忘れてゆく。
そのうち「少しは日本にいらっしゃるんですか?」とか「日本語も話せるんですか?」と聞かれる日も遠くないのかも知れない。
でも、本当に日本語を忘れたら、この連載どうしよう?
第7回 評論家って一体・・・
この世の中には色々とわけの分からない職業があるものだが、「評論家」というのは、その最たるもののひとつに違いない。
中でも特に、日本における「クラシックの音楽評論家」というのは、そのわけの分からなさで群を抜いている。なにしろ彼らの仕事は、現代の日本人でありながら主に十八・九世紀の西洋音楽を日本人向けに日本語で批評すること。当然ながらそこには最初からかなりの無理があるわけで、読んでいて頭がクラクラするものが多い。
例えば、「ピアニストXXのリサイタルにおけるベートーヴェンは、いまいちドイツ的な構築性に欠ける演奏であった」とか、「△△合奏団のチェンバロにおける通奏低音の処理はバロックの様式から逸脱しているきらいがある」とか、あるいは「歌手XXのドビュッシーはフランス語の発音に難があり、そのソフィスティケートされた世界を再現しているとは言い難い」などなど。
書かれた音楽家としては、さぞや「ちょっと待て、日本人であるおまえが、どうしてドイツ的構築性やバロックの様式やフランス語の発音にツッ込む事が出来るんだ?」と反論したくなるだろうなあ。
最近も、某批評家が日本人ピアニストの弾くショパンの演奏に「ポーランドの魂がない!」などと批判する場面に出くわし、「ちょっと待て。二十一世紀を迎えようとする現代日本に生まれたピアニストにショパンと同じ十九世紀ポーランドの魂なんかがあったら、そっちの方が異常ってもんじゃない?」と思わず突っかかってしまった。
考えても見て欲しい、「どこから見てもポーランド人」なんて言われるのが理想の日本人なんていると思います? まるで十九世紀のドイツ人みたいにベートーヴェンを弾くのがクラシックの極致なんかじゃない。ベートーヴェンを新しい音楽体験として現代に響かせるということこそが現代の日本に生きる音楽家の仕事なのでしょうが!
そんな作曲や演奏に「様式の希求がいまいち」とか「構成感に欠ける」などとツッ込み批判する権利があるなら、自分が垂れ流した批評についてツッ込み批判される義務だって負って欲しい。
例えば「XXの批評は、コンサートに来る前に夫婦げんかでもして不機嫌なまま口を滑らせたかのような文章で、ちょっと笑える」とか、「△△の批評は、旧態依然とした古くも狭いドイツ観から一歩も抜け出ない偏見で書かれていて、残念ながら的外れ」…とかね。
*
などと言っておいて何だが、私も実は作曲家の余技に「音楽評論」をやっている。と言うわけで、人のことをあまり悪くは言えないのだが、でも、ご存知だろうか。音楽批評というのを専門に始めたのは作曲家ロベルト・シューマン先生なのだと言うことを。
しかも、この人、自分で作った音楽雑誌に自分ひとりでいくつものペンネームを使って批評文を書いていたというのだからふるっている。
例えば、Aというペンネームで「XXの新作はひどい。聴けたもんじゃない」と書いておいて、今度はBというペンネームで「いや、そんなことはない。あれはこういう聴き方をすればいいのだ」と反論し、さらにCというペンネームで「いや、私はちょっと意見が違うのだが…」と書く。ひとりでボケとツッコミとウナヅキをこなしながら真理を突いてゆくのである。
そんな筆致の中で、若きショパンを「諸君、脱帽したまえ。天才だ!」と音楽界に紹介し、死後忘れられていたシューベルト晩年の名作を発掘し、無名の若きブラームスをドイツ音楽界の新しい星と見抜いたのは有名な話。この人、批評家としても一級の耳と思想とを持っていたのである。
そう、「音楽批評」とは単に〈音楽を聴く耳〉を持つというだけではなく、どういう〈視点〉どういう〈志向〉のもとで批評し紹介するかという「思想」を必要とする仕事なのである。
*
もっとも、別に文章などを持ち出すまでもなく、演奏すること自体が最大の「批評」である、と言えなくもない。
例えば「先人たちによってやり続けられてきたことを、無キズのまま後世に伝える」ことに徹する演奏。逆に「なにかしら自分の思考をプラスさせて前進する」演奏。
あるいは「作曲家の書いた楽譜を媒体にして、自分を聴かせる」ことが最優先の演奏、そして「とにかく新しく、だれも聴いたことのない音楽を聴かせる」演奏。
それらすべては、言葉の何倍もの威力を持って音楽史を切り開いてゆく真の「批評」となる。
*
というわけで、最後に〈評論家たちに捧げる賛歌〉というのをひとつ。
耳の形をして顔の横に着いているのは
本当に耳ですか?
頭の形をして肩の上に乗っているのは
本当に頭ですか?
そうだったら、…いいですね
そうだったら、…どんなにいいか。
第8回 お稽古と練習って・・・
お隣の国中国では今、子供にピアノを習わせるのがブームなのだそうだ。西欧化が進んできたこと、生活水準が上がってきたこと、少子化政策で子供の教育に情熱を傾ける親が増えてきたこと、などなどが要因らしい。
そう言えば、日本も戦後の経済成長期には空前のピアノ・ブームがあったっけ。親はクラシック音楽など聴きもしないのに、子供にはアップライト・ピアノを買い与え、洗濯機・冷蔵庫・カラーテレビ(これを「三種の神器」なんて言っていた)などと一緒に狭いアパートの部屋に押し込んでいた。
でも、そうやって「情操教育」などと称して子供の頃からピアノを習ったところで、職業として食べていけるレベルになるのはごくわずか。さらにプロの音楽家として成功するとなると、まさに宝クジ並みの確率。なんだか、カニが何千何万とタマゴを産んで海にバラ巻いても、その中の数匹がようやく親に育つだけという話を思い出してしまう。
かくして、膨大に産まれたカニのタマゴたちの一部は魚に食われるかわりにどこかでピアノの先生になり、せっせと子供にピアノを教えて次の世代のカニタマ予備軍を育て上げるという趣向。これを「食物連鎖」と、…言わないか。
と言うわけで、なんとなく恐ろしい構造を秘めながらも底の浅いブームではあったが、少なくとも日本人の勤勉さ(この時代にはまだわが日本人にはこの「勤勉さ」があったのだ!)のせいでかなり土壌の広がりを見せ、西洋クラシック音楽は日本文化の〈個人層〉には、かなり深部まで食い込んだような気がする。もしかしたら現在一線で活躍している日本の音楽家たちは、多かれ少なかれこの時期のピアノ・ブームの落とし子なんじゃないだろうか?
私も、ハイカラ好きの祖父が昭和の初期に買ったという古いアップライト・ピアノが家に置いてあったことから音楽を始めたから、父の代からの.カニタマの末裔。どうやら昭和初期にも同じようなブームがあったらしい。西欧化・生活水準向上・少子化…は、音楽教育の原点のようだ。
*
それにしても、日本や中国で「西洋音楽の才能」を発揮するというのは、ちょっと不思議な話と言えなくもない。
例えば、田舎の小さな村でいきなり音楽の才能がある子供が出現することがある。クラシック音楽の素養などない両親をはじめ、まわりの大人もビックリの中、「村に一台しかないピアノ」なんていうのでショパンだのリストだのプロコフィエフだのをバリバリ弾いてしまう。神童である。
こういう才能の発生は、一体どういう仕掛けになっているのだろう? 本来は音楽の才能のある家系にも係わらず、それに出会うことのない風土に生きていたものが、突然「それ」に出会ったということだろうか。
確かに、ホロヴィッツ級のピアノを弾く才能があっても、戦国時代の日本なんかに生まれてしまった日にはお手上げだし、逆に織田信長クラスの軍略の才能があっても現代の日本に生まれてピアノなんか習わされた日には、落ちこぼれになるしかないような気もする。このあたりは、時代や素材と出会う才能とでも言うべきか。
ただ、ピアノを達者に弾くからと言って「音楽の才能がある」と思ってしまうのはきわめて危険ではある。「知能の高さ」や「記憶力」、あるいは「指の運動神経」や「真似する能力」などが、単なる一つの通過点としてピアノを弾かせることもあるからだ。
そもそも、「ピアノを弾く」ということと「音楽をやる」というのはあまり関係がない。「ワープロを叩く」ということと「文学をやる」ということがあまり関係ないように。
問題は、「ずらりと並んだキイを間違いなく順番通り叩ける」という、それだけではワープロ検定か知能テストの課題にしかならないような行為を、どう「音楽」という目的に結びつけるか、なのだ。すべては、そこから始まる。
*
だから、バリバリと音を立てて「鍵盤を早く正確に叩く」ことに終始している「神童」たちを見ると、可哀想になる。曲芸を仕込まれた子猿のように見えてくるからだろうか。
ねえ、キミ。ピアノは「モグラ叩きゲーム」じゃないんだから、早く正確に叩きゃいいってもんじゃないんだよ。
ピアノの鍵盤を叩くことで「音楽を聴く」ことが目的なんであって、「叩くこと」自体が目的じゃあないんだ。
目的は、自分だけの新しいモグラを探し出すこと。今キミがピアノを弾くのは、その日ための通過儀礼にすぎない。
新しいモグラを自分で探す旅。
それが「音楽」なんだ。
第9回 楽譜っていうのは・・・
作曲家が演奏家に対して「楽譜通り弾いて欲しい」と注文するのは、まあ当然だが、同時に、「楽譜通り弾いて欲しくない」と注文したくなる時もある、と言ったらちょっと不思議だろうか?
以前も、新作カルテットのロマンスの楽章でプレイヤーたちが楽譜通り「きれいに」演奏してくれたのだが、どうも違う。現代風にちょっと歪んだ妖しいロマンスなのに、シンプルな楽譜のそのままをストレートに演奏すると、きれいすぎてまるで清純な恋人たちの青臭いラブ・シーンみたいなのだ。
で、「ラブ・シーンなんだけど、これが実はホモのカップルで、片一方の奥さんが留守の間に不倫してる。で、ふたりが濃厚なキスをやってるのを、奥さんが秘かに隣の部屋から壁ごしに盗聴してる。っていうそんな感じで弾いて欲しい」と説明したら、大笑いで思う通りの演奏に仕上がった。でもそんなこと楽譜に書くわけにはいかない。
イギリスで交響曲を録音したときも、似たようなことがあった。スタジオ録音ゆえの丁寧さで「楽譜通り、音ミスなし、バランスよし」というテイクは録れたのだが、安全運転すぎて曲の異様な熱気が伝わってこず、作曲家から「NO」を出したのだ。
でも、「楽譜通り、音ミスなし、バランスよし、という以上に何をやればいいんだ?」とオーケストラも指揮者も頭を抱えてしまったことは事実。そこで、「最後の最後にもう一回、これで泣いても笑ってもおしまい、キレまくって騒ぎまくって、終わったらバンザイと楽器を空に投げ捨てて帰ってしまう、そんな演奏をしてくれ!」と言ったら、大笑いしつつ応じてくれ、一発OK。なかなか凄まじい演奏が録れた。
*
確かにバッハでもベートーヴェンでも、楽譜に「ファ」と書いてあったら「ファ」であって、「ファ#」でも「ミ」でもないのは当たり前。「メゾ・フォルテ」と書いてあったら、「フォルテ」でも「ピアノ」でもなく「メゾ・フォルテ」である。ジャズならともかく、クラシック音楽の場合は、それらをハズすことは許されない。だから、演奏家の意識は、まず楽譜を間違いなく完璧に弾くということに注がれる。
でも、「楽譜通り間違いなく弾きました」ということほど、音楽から遠いものはないし、作曲家の意向から遠いものはない。(もちろんバッハ先生やベートーヴェン先生は何も言ってくれないから、確かめようがないが)
ここらあたりが、音楽を書き留める「五線譜」というシステムの限界なのだろうなあ。なにしろ、楽譜に「音楽」は書き込めないんだから。
などと書くと、「じゃあ、楽譜に書いてあるのは何なの?」と聞かれそうだが、答えは簡単。それは「音楽を構成する音のデータだけ」なのである。
データは音楽ではない。データが人間ではないように。
例えば、生年月日、出身地、生まれた星座、血液型、学歴、賞罰、両親の名前、買ってるネコの名前などなど、そんなデータをいくら膨大に並べても、「人間」にはならない。
でも、名前すら知らなくても人として愛することは可能。音楽も同じなのだ。
*
それに、音楽というのは実に不思議なもので、楽譜に書いてある一音がわずかに違っても死んでしまうこともあれば、書いてあることをほとんど無視しても音楽として成り立ってしまうことがある。
例えばバッハは、ピアノで弾いてもチェンバロで弾いてもシンセで弾いてもバッハだが、対位法の旋律の一音を弾き間違えたらそれでおしまい。ベートーヴェンは逆に少しくらい音をハズしてあらっぽく弾いてみせても大丈夫だが、パッションが失せたらその瞬間死んでしまう。
その神秘的な微妙さは、どこか「生命」に似ている。水の中だろうと空だろうと陸地だろうと手足がゼロだろうと八本だろうと生命は生命。しかし、酸素を断っただけで死んでしまう。人間だって、手を失っても足がなくても別に人であることに変わりはないのに、たった何グラムかの銃弾や毒物が体内に入っただけで死んでしまう。
音楽とはつまるところ「生命」なのだ。きわめて厳密なシステムで出来ていながら、きわめていい加減な構造で出来てもいて、進化し退化し増殖し衰退し、を繰り返している。
そこで私も、演奏家にはいつも「そんなに楽譜通り弾いちゃダメ。もっと自由に頼みますよ〜」というセリフと「ちゃんと楽譜に書いてある通り弾かなくちゃダメ。もっと厳密に頼みますよ〜」というセリフを交互にぶつけ続けているわけなのである。
第10回 コンピュータって・・・
作曲にコンピュータを使っている。
と言うと、いまだにピコピコ音のコンピュータ音楽を想像する人がいて困ってしまうのだが、別にワープロを使って原稿書いているからと言ってコンピュータやロボットが出て来るSF小説ばかり書いているとはもはや誰も思わないはず。いまや時代小説だろうと俳句だろうと、別にワープロで書いてなんの不思議もないのである。
それに、考えてみれば、作曲家の仕事道具の定番であるピアノは「キイボード」を使うという点でコンピュータと同じ仲間。中にハンマーだの鋼鉄のフレームだの金属線だのが入っている重量級の巨大メカであるピアノより、せいぜいノート大の最近のコンピュータの方が、道具として可愛いと思うのだが、どうだろうか。
*
と言うわけで、緑一色のモニターで英字とカタカナしか打てなかったNECのPC8001という初代パソコン時代から数えるともうかれこれ二十年のお付き合いになる。音楽関係に強いということで十数年前から愛用しているアップルのマッキントッシュというパソコンも、昨年暮れに買ったパワーブックG3でもう5台目である。
以前は、数字(音の高さ・長さ・強さ)をキイボードで打ち込んでシンセサイザーで音を鳴らす〈パフォーマー〉という演奏ソフトを主に使っていたのだが、数年前からまさしく「楽譜ワープロ」そのものの〈フィナーレ〉というソフトに切り替えた。
使い方の基本は簡単。モニター画面の中のパレットに並んでいる四分音符だの十六音符だのを、マウスを使って五線譜の上に貼り付けてゆくのだ。ピアノ用の二段譜からオーケストラ用の数十段のスコアも可。もちろんpとかfとかの強弱記号からクレッシェンドやアクセントなどの表情記号も書き込める。
ありがたいのは、ワープロと同じくカット&ペーストが自在なこと。間違ったら何度でも書き直せるし、同じフレーズを繰り返したければコピー&ペースト、音符でも小節でも簡単に削除したり挿入したりできる。おまけに移調や転調も、その場所を選んで「X度上に移調」をクリックするだけなのだ。
そして、最大の利点は、何と言っても書いた楽譜をすぐ「音」にして鳴らしてみられること。よほどのピアノの達人でも、作曲した直後の込み入った楽譜やオーケストラのスコアを音にして弾いてみるのは不可能だが、彼にはそれが出来る。おかげで、#や♭が落ちている凡ミスや、不協和音が紛れ込んでいるパートや、和音のまずい連結などを「耳」で確かめることが出来るようになった。
さらに音源モジュールをつなげば、オーケストラ・サウンドもシミュレイション出来る(今、使っているのは六十四パートで百二十八音出るマシン。フル・オーケストラも楽々鳴らせる)し、「MM120」とか「MM96」とか厳密な速度指定ができるので、耳で聴いて確かめたテンポ設定ができる。おまけにスコアを書き上げたら、そのままパート譜も作成してくれるのだから凄い。有能な助手が数人いる気分である。
*
それでも、使いこなすのはそれなりに熟練がいるのも確かで、今日買ってすぐスコアを書けるかというと、そうはいかない。
ピアノだって、手に入れてすぐ出来るのは指一本でポツンポツンと音を出すくらい。ワープロだってコンピュータだって、キイボードを見ずにタイプ出来るようになるまでにならないと仕事には使えないし、それにはちょっと時間がかかる。
私の場合も、最初の一年くらいは使い物にならなくて、「こんなもの買っちゃって、どうしよう!」と後悔したのだが、全4楽章百六十ページほどのスコアからなる交響曲を無理矢理これで作曲してみてようやく使えるようになった。
そうなると今度は、ピアノなしでの作曲が考えられないように、コンピュータなしでの仕事は考えられない。なにしろ彼は、楽譜を書く作業のほかに、ワープロで原稿を書く仕事もこなすし、レイアウトやデザインだってやってくれ、インターネットであちこちに繋がっているうえに、過去の仕事すべてのデータからスケジュール、さらに辞書や住所録から家計簿まで全部記憶しているのだから。
おかげで、今の仕事場はピアノとコンピュータ2台と机とがそれぞれ東西南北を占めるという、まるで飛行機の操縦室のコックピットみたいな有り様。
それでも、別に機械に使われているとは感じたことはないし、そもそも彼を機械だなどと思ったことはない。
彼は私にとって、有能な秘書であり、可愛い助手なのである。
第11回 音感とは一体・・・
日本人というのは、ワビ・サビなどという次元では物凄く音に対して鋭敏ということになっている。なにしろ万葉の時代から、竹やぶを吹き抜ける風の音や、秋の夜長を鳴き通す虫の声を愛で、軒先に風鈴を吊るして涼風を聴き、鐘の音や水のせせらぎや鹿威し(シシオドシ)に風情を聞いてきたのだから。
でも今や、音に対する繊細さを現代日本人の特徴に挙げる人など、いるとは思えない。それどころか、これほど音に対して無神経で鈍感な民族もないものだ。
昔からペラペラの紙や木で出来た家に住んでいたので、音に関するプライバシーなどという感覚がなかったのは仕方ないが、それでも紙や木の家で出る生活騒音など高が知れていたから問題にもならなかった。しかし、村社会の中での「気配り」とか「遠慮」で食い止まっていたノイズは、近代の都市型生活様式になってからその歯止めを失ってしまう。
特に、現代都市トウキョウに住んでいると、朝から深夜まで様々なノイズがシャワーのように全身に降り注ぐ。なにしろ自動車やビルに仕込まれたさまざまなエンジンやモーターが大小を問わない膨大な騒音と震動とをまき散らし、何万何億という量で増殖してゆくのだからたまらない。
いや、騒音だけではなく、音楽もひどい。日本に来た世界の音楽家すべてが頭を抱える町中にあふれる垂れ流しBGM、TVから切れ目なく吐き出される十五秒のコマギレ音楽、駅のホームで電車の発着ごとに流れる拷問のようなメロディ、若者が耳栓がわりに常用しているウォークマンから耳に直接注入されるドラッグ化した音楽、商店街やビルや乗り物などの空間でただ匂い消しのように使われている膨大な音楽。
そして最近ではこれに携帯電話の着信メロディというおバカな騒音が加わって、東京は耳のある人間にとっては音の地獄と化していると言っても過言ではない。
*
で、これだけ音に対して無神経になってしまった現代日本人と、音に対する繊細な文化を持っていた旧日本人とは、さて一体同じ民族なのだろうか?…とずっと考えていたのだが、最近「日本人は音に対して繊細でも無神経でもなく、ただ音に対して受け身なだけなのだ」…ということにハタと思い至った。
日本人にとって、音は「聴く」のではなく「聞こえる」のだ。そして、音は「出す」のではなく「出る」のだ。そこにはロジカルな意味も意志も存在しない。
西欧的な耳や音楽家の耳には、どんな自然音も音楽も騒音も意味を持つ記号として聞こえるから、聴く意志に反して音を聴かされることは思考を阻害され異様なストレスを感じる。でも、音に意味も意志も感じなければそんなストレスはない。それこそ馬耳東風。馬の耳になんとやらである。
だから、風や水や動物や人々が出す様々な音にただ耳を傾け、受け止める。それを是とも否とも思わない。その自然体で極めて受動的な姿勢が、古きよき時代には音に対する繊細さに見えていたわけだ。
ところが一転して、近代都市文明になってから、自然音の何倍何百倍もの破壊力を持った人工音が発生する時代になった。エンジンやモーターなどから出る新しいノイズが世界中に満ちあふれ、音楽すら録音メディアによる異常繁殖によってノイズの仲間入りだ。
しかし、それでもわが愛すべき日本の同胞たちは、それらをただ自然体で極めて受動的な姿勢で受け止める。それを是とも否とも思わない。すると今度はそれが逆に音に対する無神経さになるという仕掛けだ。
つまり、このまったく逆の志向に見える神経、実はルーツは同じ。そこには、全然「耳」の構造など関係ない。日本人の極めて日本人的な性格がそこにあるだけなのだ。
かくして、自然音に鋭敏で、人工音に鈍感な日本人が、ここに存在することになったわけだ。ふんふん、なるほどね。
*
などと納得したところで、騒音に満ちあふれ音楽が垂れ流されている現状は改善する気配もない。困ったものだ。
そんなわけで、今一番欲しいのが「無音オーディオ」。とは言っても、音の出ないオーディオ…ではない。コンピュータでまわりの雑音を解析し、それを相殺する音波を出すことによって雑音のすべてを中和し、ある範囲内の空間をシーンと無音にする、そんなオーディオだ。
ヒーリング・ミュージックだのリラクゼーションだのと言って自然音や静かな音楽が流れるCDは巷にあふれているけど、現代人が本当に欲しいのは「静かさ」そのもののはず。
だれか開発してくれないかなあ。
待ってますよお。
第12回 忙しいって・・・
忙しいのは嫌いである。
音楽家の中には、年がら年中世界中を飛び回り、今日はトウキョウ、明日はパリ、来週はニューヨークなどという超多忙な生活を送っている人もいて、まあ、確かにそれは「世界が私を呼んでいる」という状態だから、自慢すべきことなのかも知れないが、私などは「そんなのは人間の生活じゃないぞ〜」とつい思ってしまう。
演奏家ほどではないが、作曲家でも年中コンサートだの録音スタジオだの講演会だのに駆け回り、コンクールの審査員だの大学の教授だの芸術財団の顧問だのホールの音楽監督だのを兼任し、作曲や原稿書きなどは移動の飛行機や新幹線の中でやってしまうという「お忙し派」がいる。
むかし、それこそモーツァルトなどは、新作のスコアを手紙で催促され、「今出来たところなので、これから持ってゆく」と言っておいて、馬車の中でチャッチャッと作曲してしまったことがあるらしいから、これは「お忙し派」作曲家の伝統なのだろうか。
現代でも、電話で催促されて、「もう出来てますから、これからタクシーで届けます」と言っておき、車の中でおもむろに原稿を書きだした(実はその時点ではまだ一文字も書いていなかった!)という作家さんもいたらしいけれど、最近はファックスや電子メールがあるので、さすがにこの手は使えなくなっただろうなあ。
それでも、日頃は怠けていて、〆切直前になると突然嵐のように忙しくなるという「急性お忙し派」は、不摂生をしていると突然訪れるギックリ腰のようにやって来るから、こればっかりは仕方ない。誰だって子供の頃、夏休み中遊び呆けていて八月後半ギリギリになってあわてふためいて宿題を始めるという経験があるように…ね。
でも、年中忙しがっていて、忙しくないと不安になる「慢性お忙し派」というのは、立派にビューキのような気がする。とにかくスケジュール帳がビッシリ埋まってないと落ち着かない人、「忙しい、忙しい」と呪文のようにつぶやくのを楽しんでいる人、一日でもオフがあると何もすることがなくて死にそうになる人、などなど。忙しがってないとダメなんて、まるでサメみたい(サメは常に泳いでないと溺れてしまうらしい)である。
そういう人は、それこそバブルの頃にはよく見かけたものだが、いくらそれでたくさん収入があったとしても、なんだか哀れだ。それに「忙しバブル」は必ずはじけるというのは、もう宇宙の法則のようなものだし。
*
とは言っても、現代でクラシック系の作曲家などやっていると、別に「忙しくなりたくない」などと思わなくても、充分全然忙しくない。特に作曲家になりたての若いころなどは、仕事など全くないから、ヒマだけは佃煮にして売るほどあった。
今は、少しは仕事があるから忙しいといえば忙しいが、晴れていればブラリと散歩に出られるという程度の仕事しかしないことにしているし、お祭りの季節にテケテンテンなんて囃子が聞こえてこようものなら、〆切なんざ放っておいて出かけてしまう(先日も、〆切があるのに、しっかり浅草の三社祭に行ってしまった。てけてんてん)。
そんなわけで、一時は「三時のソバ屋」なんていうのにも凝っていた。堅気の人や普通の勤め人には絶対不可能な、午後三時頃という昼でも夜でもない時間に、ソバ屋に行ってお酒一杯飲んでソバをたぐるのである。
かつて下町の粋なソバ屋さんでは、よくそういう人を見かけたものだ。絵になるのは、壮年の男性のみ。これが一人静かに(これは絶対、男が一人でやるに限るのだ)「天ヌキで冷や」などと注文して黙々と酒を飲む。(注:天ヌキとは、温かい天ぷらソバからソバを抜いたもの。汁に浸ったエビ天をツマミに、温かい汁をすすりながら冷たい酒を飲む。これが絶品なのである)。
これこそ自由人の特権。お金はかからないが、これぞ最高級のぜいたくと言わずして何であろう!
*
そこで結論。
仕事というのは、
お天道さまが上がったらボチボチ始め、
しばらく汗水たらして働いたら、
午後早々には切り上げて、
ソバ屋でキュッと一杯ひっかけて、
街をひやかし歩き、
そして、日が沈んだら
居酒屋で一人静かに酒を飲む、
そのためにやるもんだ。
でも、みんながそんなだったら、日本は滅びる…って?
そりゃ、そうだ。
第13回 いい音楽って・・・
先日、大学に入学したばかりというお嬢さんから「こんなこと言うと笑われるかも知れませんけど、わたし、ベートーヴェンの交響曲ってちゃんと聴いたことがないんですゥ」と告白された。
「運命」とか「合唱」とか、名前だけは風のうわさには聴いたことがあるが、どれもまともに聴いたことはないと言う。
「例えばベートーヴェンだと、どの曲を誰のどんなCDで聴けばいいですかァ? お店に行っても、たくさんありすぎて、どれがいいのか全然分かんないですしィ…」
と、ここまで聞いて頭が一瞬クラッときたのは、「大学生にもなってベートーヴェンも聴いたことがないの?」と呆れたからではない。逆に、「なんてうらやましいんだろう。この子は私がベートーヴェンを生まれて始めて聴いたときのあの感動を、これから体験できるんだ!」という感慨に襲われたせいだった。
そう言えば、作曲家ショスタコーヴィチも若いころのある日のことを回想して、そんな話を書いている。
彼は学生の頃、師であるグラズノフの前で友人と二人してブラームスの交響曲を初見でピアノ連弾したのだが、うまく演奏できなかった。そこで「すみません。実はこの曲、まだ聴いたことがなくて…」と白状したところ、先生はこう言ったそうだ。
「なんて幸せなんだろう。きみたちはこれから、たくさん美しいものに出会えるのだから。私ときたら、もう何もかも知っている。本当につまらないよ」
*
私も、今でこそクラシック界で作曲家などというのをやっているが、中学生までは彼女と同じでベートーヴェンやシューベルトなどは音楽教室の壁に貼ってある知らないオジサンという認識しかなく、「運命」も「未完成」も風のうわさくらいにしか聞いたことがなかった。本当に全曲ちゃんと聴いたのは高校生になってからだ。
ジャズの名盤と称するものだって、聴き始めたのは二十歳すぎてから。それまではマイルス・デイヴィスの名前すら聴いたことなかったし、ビル・エヴァンスもギル・エヴァンスも区別がつかなくて、ジャズ・マニアの大学の先輩に力いっぱい軽蔑の眼を向けられたっけ。
でも、初めてビートルズのアルバムを手に入れて心躍らせた夕方のこと、初めてLPでベートーヴェンの交響曲を聴いて音楽を志した夜のこと、ビル・エヴァンスの世にも美しいピアノに出会って生きる実感を感じた明け方のこと、ピンク・フロイドを初めてFMで聴いて鳥肌が立った瞬間のこと、ピアソラのアルバムに初めて針を降ろして涙した瞬間のこと、みんなはっきり覚えている。
しかし、音楽を専門に始めてからは、新しい音楽との出会いも大量消費型になってきて、今では、クラシック関係のCDだけで月に百枚近い分量を試聴しなければならない、という嬉しくも悩ましい状況下にある。
昔のようにたった一枚のLPにぞくぞくしながら針を降ろすということはなくなってしまい、何十枚という新譜CDの山を次から次へとプレイヤーに投げ込んでは聴いてゆくという色気のない聴き方ではあるが、それでも月に数枚程度の出会いがある。
ただ、現代で音楽を聴くのは大変だ。「常識的に知っていなければならない音楽」が信じられないほど膨大だからだ。
ベートーヴェンとかシューベルトからマーラーあるいはシェーンベルクあたりまでを一応聴いて知っているのがクラシックの常識なら、マイルス・ディヴィスからビル・エヴァンスやキース・ジャレットあたりまでを知っているのがジャズの常識。一方でビートルズからクイーンやオアシスあたりまで聞き知っているのがロックの常識。
それにポップスや歌謡曲の常識から、テクノ・ヒップポップ・ソウル・ラテン・ブラックコンテンポラリー・ヘビメタ・インディーズなどなどから、民族音楽・純邦楽・映画音楽・前衛音楽・古代音楽などなどの常識までを「一応」頭の中に入れようものなら、もう、考えただけで頭がパンクしそうだ。
*
というわけで、冒頭のコにはクライバー盤のベートーヴェン第5と第7、それにビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビー」を推薦。お返しに椎名林檎と浜崎あゆみを推薦されたが、おじさん、それくらいは知ってるよ。
それにしても、
お互い、いい音楽に出会いたいね。
何十年も経ってから、
聴いた瞬間の感動を思い出せるような、
そんな音楽にね。
第14回 音楽家を育てるのは・・・
いつだったか、海外の功成り名を遂げた人がインタビューで「あなたを育てたものは何ですか?」と質問されて、「失望」と答えていたのが、それはひどく印象的だった。
その真意はインタビューアには伝わっていないようだったけれど、私も同じ質問をされたら同じように答えるような気がする。
だって、少なくとも、私を育てたのは「希望」ではないのだから。でも、だからと言って「絶望」していたわけでもないから、これはやはり「失望」としか言い様がないのだろうなあ。
社会に対する失望、音楽界に対する失望、現代音楽に対する失望、コンクールに対する失望、賞というものに対する失望、オーケストラに対する失望、評論家に対する失望、そして自分に対する失望…。
結局、人間を突き動かすのは、希望とか愛とか肯定とかの正のエネルギーなんかじゃなくて、絶望とか恨みとか否定とかの負のエネルギーなんじゃないか…と思っているほどだ。
そのことをインテリ知人に話したら「あ、ルサンチマンね」とひとこと。
自分が人より劣っているとか社会的に下位にあると感じたとき、それを恥じて謙虚になるのが普通。逆に開き直って「人より劣ってて何が悪い」と傲慢かつ攻撃的になるのを哲学用語でルサンチマン…と言うんだそうだが、それって、つまらない解析だなあ。
*
そもそも世の中には、愛されることで育つ人間がいれば、愛されないことで育つ人間もいるのだ。
音楽で言えば、子供の頃から「この子は才能がある!」と言われ、ちゃんとした師に出会い、コンクールに入賞し色々な賞をもらい、批評で好意的に受け入れられ、才能ある音楽家として容認されてスクスクと育ってゆくのが前者。
しかし逆に、子供の頃から「変な子!」とつまはじきされ、先生には「音楽なんかやめなさい」と言われ、コンクールは落選し賞には無視され、批評にも相手にされず、異端と指さされ、それゆえ力ずくで自己の音楽と地盤を固めてゆき一人で育ってゆくのが後者。
私は後者だから、後者の〈負のタイプ〉の音楽家についてはよく分かるが、前者の〈正のタイプ〉の音楽家については、よく分からない。
それでも、日本人はどちらかと言うと昔から〈負のタイプ〉で、芸事でもスポーツでも必ず「そんなんじゃダメだ!」とか「全然なってない!」とか「まだまだだ!」とかいう罵倒で弟子を育ててゆく。
逆にアメリカなどは典型的な〈正のタイプ〉で、「おまえは最高だ!」とか「そうそう、それでいいんだ。出来るじゃないか!」とか「愛してるよ!」とかを連発してブタを木に登らせる。
さて、どっちがいいのか、簡単に結論は出せそうにないが、徹底して叩くのも徹底して抱擁するのも、それはそれで師(親)の哲学が一貫していれば問題ない。
一番まずいのは中途半端。愛されて育ってきた輩は、突然だれかにちょっとケナされるとアッという間に壊れてしまう。逆に、他人を呪いながら育ってきた輩は、だれかにちょっとホメられるとアッという間に凋落してしまう。どちらの純粋培養も脆いのである。それを楽しみにホメたりケナしたりする人の悪い輩もいるので、若者よ、注意せよ。(それはアンタだ…という声も?)
まあ、音楽家も子供と同じで、金持ちの家に生まれて両親の愛と金に包まれて健康にスクスク育つ子もいれば、貧乏家庭に生まれて親や社会やビンボーを呪いながら「いつか大物になってやる!」と大望をもって育つ子もいるということなのだろう。
ただ、人間、愛されて育つに越したことはないわけで、愛されて育たなかった子供は、愛に飢えているものの、他人の愛し方を知らないものだ。同じように、ちゃんと愛されて育てられなかった音楽家は、自己の音楽については貪欲だが、新しい才能の愛し方も育て方も分からない。それは確かだ。
子供だって弟子だって愛されて育てられた方がいいに決まっているし、愛に飢えさせる育て方というのは、そもそも制御不可能だし効率最低なうえ危険だから、とても教育とは言えない。
にもかかわらず、強靱な才能というのは意外にも後者から育つことが多いのだから困ってしまう。そのあたりに教育の難しさがあるのだろうなあ。
*
そう言えば、言い忘れたけれどただひとつ、私はずっと色々なものに失望してきたけれど、音楽にだけは失望したことはない。
それが、いまだに音楽をやり続けている唯一の理由だ。
第15回 現代音楽って一体・・・
現代音楽について書いておこう。
今ではずいぶん矛先が鈍ってきたものの、かつては耳障りで難解で不可解な「鬼っ子」音楽として知らないものはないほど有名で、聴衆には不人気きわまりない代物だった。
にもかかわらず、音楽の未来はここにあると信じた作曲家たちが、こぞってガリガリ・ギイギイ・ゴオゴオと不快な音を並べて「新しい音楽」と言い張っていた。もしかしたら世界大戦とか原爆とかファシズムとかダイオキシンなどと並んで二十世紀最大の悪夢の一つかも知れない。
でも、あれはあれで、ひどく正しい進化の形態だったのだ…なんて、信じてもらえるだろうか?
*
つまり、作曲家は二十世紀に入ったとき考えたのだ。
十九世紀までの世界は伝統とか因習とか迷信に縛られていて、王様とか貴族とか大帝国とかが、一般の庶民や弱小国を搾取する差別と不平等が横行していた。それを、「知性」と「科学」によって「個人の自由」や「権利」を第一に考える平等な世界に変革すること。それが、二十世紀の新しい思想だった。
だとすれば音楽も同じ。十九世紀までの音楽は伝統と因習にとらわれていて、ドミソという王様の下にドファラとかシレソとかいう貴族がいて、ファの#とかラの♭などという音は不協和音だの言われて虐げられていた。これを「知性」によって解放し、全ての音が同等の権利を持つ自由・平等な世界に変革すること。それが、二十世紀の新しい音楽のはずだ…と。
で、ハーモニーを壊して「無調」の音楽を作り始めた。それは、聴き手にとってはわけの分からない音の羅列にしか聞こえなかったにしても、作曲家にとっては「音を古い呪縛から解き放った新しい時代の音楽」だったのだ。ちょうど、王様や貴族に年貢を取り立てられ搾取されていた民衆を革命で解放したように。
でもそのうち、解放された民衆全部が「平等」というのもやりにくいので、持ち回りで「今月は君が議長」「貴女が委員」というように十二の音に順列を付け始めた。それが「十二音技法」というわけだ。
そして遂には、ドレミの代わりに音に数字を付けて、自在自在に扱うようになった(と思ったのだ)。強弱も長短も自在。すべては「数字」なのだから。これを「ミュージック・セリエル」と言う。なんて「知的」なんだろう!
こうして音楽はハーモニーからもリズムからもメロディからも解放されたのである。
それに、音楽史的に見ても、この進化は実に正しかった。なにしろ、大昔はド・レとかド・レ・ミ程度の2つ3つの音だけで単純な童歌や賛美歌などを歌うだけだったのが、民謡などでは5音になり、さらにドレミファ全部の7つの音を使うようになって表現力はアップ。長調や短調を駆使して人間の心理やドラマなど無限の表現を得ることになった。
それなら、さらに半音を含めた十二の音を全部使えば、さらにさらに表現力を倍々にアップすることが出来る理屈ではないか!
音楽の正しい進化とはまさにこのこと。ああ、なんと素晴らしい未来だろう!
*
でも、惜しいことに、たった一つだけ、問題があった。
人間の耳はその進化に付いて行けなかったのである。
それでも作曲家たちは、聴いているうちに人間の耳も無調の表現に慣れてくると信じていた。自分たちの書いた曲が「分からない」のは聴衆の耳が五十年ほど遅れているからだと思っていたのだ。
実際、「五十年も経てば、豆腐屋の小僧だって十二音でラッパを吹くようになる」(当時はトーフーとラッパを吹いて豆腐を売っていたのである。念のため)などと豪語した作曲家もいて、「そんなもんかなあ」と思っていたのだが、さて、五十年経ってみて、ようやく分かった。
だれも十二音でラッパなんか吹いてはいないではないか!
そう。現代音楽の理想は「残念でした、大ハズレ」だったのである。
*
理屈は正しかった。悪意もなかった。でも、気がついてみたら二十世紀(一九二十年代以降)のクラシック系音楽に、メロディとハーモニーとリズムはかき消えていた。
うーん。これは、怒るべきなのか、悲しむべきなのか、呆れるべきなのか…。
で、教訓は、こうだ。
人間の「知性」というのは、
時として「馬鹿」の極致を
演じることがある。
第16回 師について・・・
フィンランドのオウルンサロという小さな町での音楽祭に行ってきた。
ピアニストの舘野泉さんのプロデュースで3年前から始まったこの町の音楽祭、今年は私の作品も一夜〈個展〉としてやるというので、飛行機嫌いをおして出向くことになったのである。
実を言うと、生まれて初めて行った外国がフィンランドだった。今回は実にそれから二十年ぶりに踏むフィンランドの土と言うことで、感慨もひとしお。どこまでも広がる青い空と白い雲、そして森と湖を、たっぷり堪能することになった。
*
さて、北極圏に近い北欧の国〈フィンランド〉の名を聞いて、あなたがまず最初に思い出すのは何? ムーミン? それともサンタクロース?
最新のテクノロジーに詳しい人なら携帯電話業界におけるヨーロッパ最大の大手〈ノキア〉を思い出す人もいるかも知れない。あるいは〈サウナ風呂〉や〈ログ・ハウス〉…?
でも、音楽好きなら、作曲家〈ジャン・シベリウス〉の名がまっ先に出て欲しいなあ。フィンランドと言ったらシベリウス、シベリウスと言ったらフィンランドでしょ?
特に私のように、シベリウスの交響曲を聴いて作曲家を志すことになった者にとっては、彼が晩年を過ごした町ヤルヴェンパーなどは、もう、キリスト教徒におけるイェルサレムのような聖地なのである。
そう、そもそも私が交響曲作家を志したきっかけというのは、高校1年の冬にシベリウスの交響曲を聴いたこと…だったのだ。まあ、変わった高校生である。それは認める。
とは言っても、別にクラシック一辺倒の音楽マニアだったわけではなく、ロックだのポップスだのも聴いていたし、ギター片手にフォーク・ソング歌ったり、ピアノでジャズ弾いたり、バンドでビートルズやヴェンチャーズなんかも弾いていたのだ。
でも、どうもロックとかポップスとかいう「誰でもやって」いて「露出度が高く」て「お金がもうかる」音楽には抵抗があった。まあ、要するに、ひねくれていたのである。それも認める。
そこで、「誰もやってなく」て「露出度が低く」て「お金がもうかりそうもない」クラシック音楽を目指したのだが、ここでも演奏家とか指揮者とか言う「誰でもやって」いて「露出度が高く」て「お金がもうかる」業種には抵抗があった。
で、作曲家を選んだ。これなら「誰もやってなく」て「露出度が低く」て「お金がもうかりそうもない」。これだ、と思った。
その上、ドイツ音楽とかフランス音楽とか言う王道にも抵抗があった。なんか「偉そう」で、「露出度が高く」て、「お金をもうけていそう」ではないか。(おいおい)
そこで、ヨーロッパの中央楽壇から見れば見事な辺境国であるフィンランドで、孤高を貫き、7つの交響曲という透明なる銀河を紡いだ大作曲家シベリウスに惹かれた次第である。はるか極東の日本という国でクラシック音楽をやるのに、指針とすべきは彼の音楽しかないッ!…と、そう思ったのである。
というわけで、ただ「シベリウスの墓に詣でたい」という、コケの一念だけでフィンランドに行った。その時、貧乏旅行の末にシベリウス師の墓にたどり着いたのが(忘れもしない)一九七九年の六月二十一日。そして、私のオーケストラ曲が初めて演奏されて作曲家としてデビューしたのが、それからピッタリ一年後の六月二十一日。
私はこの偶然の符合を、師からの天啓だと信じて疑わない。
*
以来、シベリウスは私の「師」であり続けている。一度も会ったことがないが、一番深い「魂の師」だ。そんな師弟関係もあるのである。
と言うわけで、今回のフィンランド訪問は、それから二十年後の「お礼参り」の旅となった。オウルンサロでの音楽祭が終わってから首都ヘルシンキに出て、そこからいそいそと電車で三十分ほどのヤルヴェンパーへ行き、奥さんの名前を付けた〈アイノラ〉という山荘へ。
そこに師は眠っている。すぐ横の花壇には花が咲き乱れ、小さな森が覆っている。早速、墓に出向いて手を合わせる。
先生、また来ました。
おう。キミか…。
お元気そうで。
ああ、元気に死んどるよ。
…などと墓に話しかけている妙な日本人を、観光客が不思議そうな顔をして横目で見ながら通り過ぎる。
そして、その上に広がるのは二十年前と同じ、どこまでも青い空と白い雲だ。
第17回 音楽の心って・・・
人が音楽を聴いて感じる感情には、いくつかの「お約束ごと」がある。
例えば、長調だったら「楽しい」、短調だったら「悲しい」。早いテンポのアレグロだと「元気」で、遅いテンポのアダージョだと「穏やか」。不協和音だと「不安」で、全音和音だと「神秘的」。
…と、このあたりまでは、人間という生物の生理に関わっていることなので、ほぼ万国共通・全世代共通と言って良いのだが、ここから先となると、人種・国籍・性別・世代などなどによって微妙に変わってくるようだ。
*
例えば、西欧では「低音の男声」というのは「神」をイメージするのか、威厳があり正しいことを言っている感じがするのらしい。テレビのCMなどで最後に商品名や会社名を言うのは低音男声だし、受難曲などに登場する「神」の声はバリトンかバスだ。
ところが、アジア、特に中国あたりになると、儒教思想からだろうか、高音こそが正しいことの象徴。正義とか善というのは天に近い精神なのだから「高い」のだ。ゆえに、高音が「善」で低音はと言うと「悪」。
だからテレビやラジオではアナウンサーは甲高い声で正しいことを話し、京劇などでは正義の味方は甲高い音の鳴り物をバックに登場して甲高い声で歌い、悪役は低音にまみれて登場する。
そう言えば、中国で初めてクラシック音楽が演奏された時、ベートーヴェンやブラームスの交響曲での「重厚」な低音弦のテーマに、聴衆が「あ、悪人が出てきた!」と言ったという笑い話があったっけ。ベートーヴェンの第9なども、バリトンが「友よ!」と歌い上げると、「悪人登場!」のイメージなのだそうだ。
こういう「感じ方の違い」は、楽器の音色になるとさらに複雑多彩になる。
例えば、私の上の世代の日本人にとっては、クラリネットやサクソフォンという楽器の音を聴くとどうしてもチンドン屋(これも今の若い世代は知らないか)を思い出し、場末っぽい哀愁を感じるのだそうだ。ところが、アメリカではクラリネットにサクソフォンといったら南北戦争以来の軍楽隊の楽器。同じ懐かしさの記憶でもイメージは正反対だ。
そういう私も、長いこと、ピアノの音やモーツァルトの音楽を聴くと「ピアノのおけいこ」の思い出しかイメージできず、どうしても受け付けなかった記憶がある。
同じように、戦争を経験した世代なら、トランペットと小太鼓の音は戦争を思い出させる強烈なアイテム。ところが、同じ楽器にサーカスや見せ物小屋での哀愁漂うジンタを思い出す世代もいる。
また、日本人はフルートという楽器に尺八とか横笛の情緒の影を聴いてしまうが、西欧ではむしろ宮廷の優美さ華麗さを感じさせる管楽器で、暗さを感じろと言う方が無理。そのイメージにはかなりズレがある。
*
こういう「感じ方のズレ」を、私のような作曲家は逆に利用して曲を書くわけだが、時には不安になることもある。
例えば、私の世代などはハーモニカやオルゴールの音楽を聴いて「懐かしい」というノスタルジーを感じる。それは多分、子供のころハーモニカやオルゴールを聴いた記憶があるからだ。
でも、今の若い世代は、ゲーム機のビュンビュンとかピポパポいう電子音や、携帯電話のピロリロ・レロラロいう着信メロディなどなどを子供のころから耳にして育っている。と言うことは、彼らは大人になってからああいう音を聴いて「ああ、懐かしい」と思うんだろうか?
それって、ちょっとイヤだなあ。
そして、そういう世代が大人になっても、ピアノやオーケストラの音楽の中の「懐かしさ」や「悲しさ」や「楽しさ」を、感じられるのだろうか? もしかしたら、それらの感情を喚起する音のパターンそのものが世代によってまったく変わってしまう、なんてこともあるんだろうか?
それは、ちょっと不安だなあ…。
でも、子供の頃はカレーだハンバーグだと洋食一辺倒で育った人が、ある年齢になるとなぜか〈おふくろの味〉とか〈和食〉に回帰したり、若いころはギンギンのロックばかり聴いていた人が、三十越えて突然「やっぱり演歌がいいねえ」とか「ストリングスが身にしみるよ」などと言い出すこともある。
ここは、人間の脳の奥に遺伝子レベルで組み込まれている記憶に期待しておこう。
国や時代や世代によって
顔が変わってゆくのが音楽。
でも、
国や時代や世代が変わっても
音楽の心は変わらない。
第18回(最終回) 音楽の未来は一体・・・
私の仕事場の机の上に、鉄腕アトムの時計がある。ただし、この時計、時間を刻んでいるのではなく、日にちをカウントダウンしている。今の数字は八百日ほどだ。
実はこれ、アトムが誕生する日までのカウントダウン。鉄腕アトムは二○○三年四月七日生まれ(らしい)。で、その日まで「あと何日」と時を刻んでいるのである。
もちろん、役に立たないといえばこれほど役に立たない時計もないものだが、「生まれる日までのカウントダウン」というのがなんだかあまりにも愛おしくて思わず買って帰ってきてしまったのだ。
このマンガとしての「鉄腕アトム」が生まれたのは一九五○年代。そのころの〈電気計算機〉はまだ不細工で巨大な真空管のオバケだったから、それが人工知能に進化して人型のロボットになるなどということは当時としては荒唐無稽な空想でしかなかった。
でも、八○年代にはコンピュータが小型化高速化して一般家庭にまで普及し始め、二○○○年代を迎えた現在では人工知能付きのイヌ型ロボットが商品化されているほど。
そんな現状を見ていると、アトム型ロボットの登場もまんざら夢物語ではないような気がしてくる。
*
それにしても二十世紀というのはあわただしい時代だった。なんでもかんでも爆発的に生まれ爆発的に増えていった。人間も科学技術も戦争も…。
おかげで、音楽もその恩恵と弊害とを両方被ることになった。なにしろ昔は好きなとき好きなだけ音楽を聴く…などということは貴族階級の特権でしかなかったのに、現代ではCDラジカセひとつあれば、どんな庶民でもいとも簡単に出来てしまうのだから。
例えば、むかし王様が楽師たちに向かって「ちょっと今すぐ静かな曲、弾いてみて」とか「私が歌うから適当に伴奏して」とか「寝るまで演奏してて、朝になったら音楽で起こして」などと命令していたような贅沢きわまりないことだって、今ではボタンひとつ押すだけ。
しかも、豪華なオペラだろうがアイドルの歌うヒット曲だろうが遥か異国の民族音楽だろうが、音楽がすべてCDという小さな円盤一枚にパックされて同じ値段で売られているのだから、聴き手にとっては天国だ。
まあ、そのこと自体は確かに、聴き手としては巨大な恩恵に違いない。でも、そのせいで「少数のエリートが莫大な金を投じて花開かせる教養文化」としての音楽はほぼ壊滅状態となり、それに代わって「膨大な数の庶民たちが少しのお金で非日常を束の間味わうための嗜好品」としての音楽ばかりが世界を席巻することになった、ということについては、恩恵ばかりとも言っていられない。
なにしろ、巨大なクジラと小さな熱帯魚たちとを、同じ一匹に数えて同じエサを与えていたら、クジラの方は餓死してしまう。また、恐竜のタマゴ一個と何千何万個が塊になっているタラコの一粒とを、同じタマゴとして同じ一ヶと数えていたら、そりゃあ恐竜の方は絶滅してしまうに決まってるではないか。
そうでなくとも、大昔は「神と交感し、大地を讚える聖なる行為」だった音楽は、今や「ちょっと気持ち良くなる」だけのドラッグにまで落ちぶれてしまっているのだ。で、一度に数個しかタマゴを生まない大型鳥のようなタイプの音楽は落ちぶれ、カニのように何千何万と大量産卵するタイプの音楽ばかりが異常繁殖することになったわけだ。
というわけで人間の世界でも、ある種の音楽はこれ以上ないほどに増殖し、ある種の音楽は落ち目になりつつ、二十世紀を終えたわけだが、この構図は二十一世紀にはどうなるのだろう?
アッと驚く大逆転が起こっているのか、あるいはトンでもない音楽が世界中に蔓延しているのか。未来はちょっぴり怖くもあり、楽しみでもある。
もしかしたら、コンピュータや新しいテクノロジイの展開によって全く新しいタイプの音楽が台頭しているかも知れないし、逆に、音楽はドンづまりを迎えてこれ以上まったく進化も変化も見せないのかも知れないし。
あるいは、人類の生命エネルギーの衰退と共に大量生産のメジャーなポップスやダンス・ビートが受けなくなり、逆にマイナーな古い民族音楽やクラ シックや前衛音楽が意外な健闘を見せている可能性だってゼロじゃないような気もするし。(うーん、それはそれでちょっと気色悪い気がするけど…)
*
そうして、
もうすぐアトムの時代が来る。
そのときアトムは音楽を夢見るだろうか?
そして、そのとき人は
まだ音楽に愛されているだろうか?
(1999年6月〜2000年12月 吉松隆)