11月の階段への巨人の歩み
ノヴェンバー・ステップスへのジャイアント・ステップス
武満徹/追悼小論
◆序
困ったことに、いまだに「〈芸術音楽〉と〈娯楽音楽〉は違う」などと言い張る前世紀の恐竜のような思考のクラシック音楽関係者に出くわすことがある。
〈芸術音楽〉に娯楽性はなく〈娯楽音楽〉に芸術性はない…というシンプルな二元論。それを言うなら「世界には〈食べる人間〉と〈食べられる人間〉がいる」というくらい面白いことを言ってほしいね、とツッコみたくなるような幼稚な頑迷さを持った音楽観。いつも聴かされるたびに旧日本陸軍時代の憲兵の亡霊でも見るような軽い眩暈にも似た虚脱感と失望感とがよぎる。
まあ確かに、「芸術音楽は純粋に知的な音の構築物であって、すべての音楽の上に君臨する価値がある」などという思想は、全然ウケていない三流音楽家がゴマメのハギシリとして言った場合には聴き手の苦笑くらい誘えるかも知れない。マーラーが「今に私の時代が来る!」と言ったのは決して勝者の宣言ではなく、「今は私の時代ではない!」という敗者のため息だったように。
その起源は、(古い話になるが)力んで書いている自分の音楽がだんだん世間にウケなくなって替わりにロッシーニなどの軽い音楽がウケているのを横目で見ていたベートーヴェンが精一杯の自嘲と皮肉とをこめてつぶやいた…というあたりなのだろう、たぶん。
でも、ベートーヴェン先生だって重々分かっていたのだ。娯楽こそが芸術であり、芸術は神聖なる娯楽であるということを。
*
 ◆タケミツ風ポピュラリティ考
◆タケミツ風ポピュラリティ考
にもかかわらず、「現代音楽」というのはシェーンベルク先生の十二音主義以後、どうも娯楽からほど遠いところに軌跡を描いてきたような気がする。
そもそも常識的な意味での「音楽」ではなく耳に心地よくないのだから、「これは娯楽として聴くものではない」という言い訳の理論武装をしてからでないと、ブーイングに耐えられないということもあったのだろう。そのうちに言い訳が独り歩きを始め、聴衆が不快感を表明すればするほど芸術度が高いのだという妄想に凝り固まって鉄面皮になっていったのは困ったものだった。
しかし、実を言うと現代音楽がまがりなりにも社会での存在を許されていたのは、矛盾するかも知れないが、ある種の娯楽性があったからなのだ。ジョン・ケージの音楽の(例えば4分33秒のような)うさんくささは、難解な芸術的思想というよりはスキャンダラスなジョークのような一面があるし(今でも一般市民に「現代音楽」のことを話す時、枕話の軽いジョークとして極めて有効だ)、ペンデレツキやリゲティのトーン・クラスター語法はSF映画やホラー映画のサウンドにうってつけ(実際、スタンリー・キューブリック監督はSF映画「2001年宇宙の旅」やホラー映画「シャイニング」で彼等の音楽を実に効果的に使っていた)だった。
そこまでのポピュラー性はないにしても、シュトックハウゼンやクセナキスなどの前衛最右翼のサウンドもある意味では究極の効果音として見事なリアリティを持っていたし(「バキィ!」とか「グワッシャーン!」とか「ズゴゴゴゴォ!」などというマンガの擬音を見ているとシュトックハウゼンの影響か?と思うことがある)、そのアナーキーで一種暴力的な破壊衝動を秘めたサウンドはストレス解消用アイテムとしても享受できた。前衛音楽もあれはあれでサブ・カルチャー文化の極北を担っていたのである。
そして、武満さんの音楽にもまごうことなきそんなポピュラリティがあった。例えば、琵琶と尺八を使った「ノヴェンバー・ステップス」がオバケ屋敷や怪談映画あるいはカンフー映画でどれほど重宝されたことか(決して否定的な意味でなく!)。あるいは、「アステリズム」の強烈なクラスターのクレッシェンドが前述の映画「2001年宇宙の旅」の異次元シーンと並ぶ「トリップ感」を得られる音楽ドラッグとしてマニアの間で有名だったことを挙げてもいい。
いや、皮肉っぽい言い方はよそう。武満さんの音楽のもつポピュラリティを「サウンド」だけで語るのは皮相に過ぎることは誰もが重々承知している。彼の音楽にはまごうことなき「音楽」の部分でのポピュラリティがあったのだ。
それは、例えば初期の名作「テクスチュアズ」の最後のコーダで浮遊する一瞬の官能的メロディから、「ノヴェンバー・ステップス」の感動的に仕組まれた尺八と琵琶の長大なカデンツァ、晩年の作品群の微温にまみれた生暖かいハーモニーに至るまで、独特のハーモニー感とサウンドのセンス、そしてなによりも聴き手の退屈を感知する鋭敏な構成感(クラシックの作品の大多数がいかにこの聴き手の退屈を無視した長さを持っていることか!)などが、凡百のポピュラー音楽作家を凌駕する見事な才能を示していることが証明している。
実際、武満さんはクラシック系の作曲家には珍しい「ポップス」への理解(それは、普通の耳を持って20世紀に生まれた者なら誰でも持っているはずの、当たり前すぎるほど当たり前のことなのだが)を持っていた。少年時代最初に感動した音楽がシャンソンのジョセフィン・ベイカーだったという告白に始まって、アメリカ留学の話を打診された時に師としてジャズ界の大御所デューク・エリントンを指名したり(結局かなわなかったようだが)、作曲のメソッドとして同じくジャズ界の鬼才ジョージ・ラッセルのモード技法(リディアン・クロマティック)を勉強したという話からは、クラシックの勉強にヨーロッパの音楽大学に留学したりする平凡な秀才タイプの人間には見られない真の「音楽好き人間」の姿が見えてくる。
あるいは、ニューヨークで「ノヴェンバー・ステップス」を初演している前後にビートルズの当時の最新アルバム「サージェント・ペパーズ」にリアルタイムで感銘を受け、初来日のころからアストル・ピアソラに注目していたあたりの慧眼もいい例かも知れない。そう言えばフォーク界の井上陽水や小室等との親交は有名だし、キース・ジャレットらの新しいジャズへの注目も早かった。
好きな作曲家としてポール・マッカートニーを挙げ、ガーシュインのような作曲家になりたかったと公言する現代音楽の作曲家としてはきわめて異例なその音楽の嗜好は、逆に言えばまごうことなき「現代の音楽愛好家」のバランスを持っていたというべきだろう。とは言え、時代に敏感でミーハー的なその感性は、芸術家というより万年少年のものだったのかも知れない。自己の思想に基づく批判や議論を外部に向かってすることはなく、前衛と保守あるいは芸術派と娯楽派の間に陣取って妙に八方美人的な立場を取り続けたのも、きわめて「現代的ないい子」のスタンスだ。
もっとも、「現代に生きていてロックにもポップスにも興味を示さないような人間の作る音楽のどこが〈現代の音楽〉なんだ?」…というのは通常の感覚を持った現代の一般聴衆すべての疑問点。普通の食事は食べずにゴキブリの佃煮や鉄サビのスープなどを食べているという人間の料理を誰が食べたがるだろうか?。「新しい味覚の追究」は味覚の壊れた人間には出来ない。通常の味覚を持ちつつ鋭敏な感性を持った者だけに可能なのだ。
武満さんは、戦後の日本という場でそんな「普通の耳」と「鋭敏な感性」を持って登場した希有な音楽家だった。そして、それゆえに彼の生み出す音楽は「現代音楽」という怪しげな魑魅魍魎たちをだますだけの「芸術性」と、ポップス・ファンにもあるところで「カッコいい!」と思わせる「娯楽性」を確かに持っていたのである。
*
 ◆タケミツ風アマチュアリズム考
◆タケミツ風アマチュアリズム考
もう一つ、武満さんの音楽に感じるアマチュアっぽさについて語ろう。あの精密に構成された高濃度な感性に満ちたサウンドと、知性の分解能を極限まで追求したような緻密に編まれたスコア。ある意味では職人中の職人、プロ中のプロの手腕なのだが、その奥になぜか不思議な素人臭さが漂う。それが武満さんの音楽の魅力の強力な部分のような気がする
。
作曲と言う行為は、「感性」と「知性」とのキャッチボールで進められる。「感性」がキャッチしたアナログ的な音のイメージを「知性」が実際のサウンドや楽譜というデジタル的な情報へ変換し、それをふたたび「感性」がチェックし、さらに「知性」が追認する。
なにしろ、「感動的」あるいは「官能的」な音楽イメージが浮かんでも、それを実際に楽譜上あるいは音響上の情報として定着しなければ「作曲」にはならない。いかに宇宙的で全人類的な音楽が頭の中でイメージとして鳴っていても、作曲家の作業は「ヴァイオリンの始めの音がドのシャープなのかミのフラットなのか」あるいは「57小節目の和音の導音はバスーンにするかトロンボーンにするか」といったような瑣末の処理に終始する…と言えばお分かりいただけるだろうか。
それゆえに、この「感性」と「知性」のバランス感覚において、作曲家には二種類あるような気がするのだ。
ひとつはモーツァルトに代表されるような、音楽的天分に満ちあふれた「アポロ的」な作曲家。生まれながらにして「感性」と「知性」が直結していて、音楽の才能100%。どんなメロディも一度聴けばスラスラと楽譜に書け、どんな和音もたちどころに聞き取り、それこそバッハ風でもブラームス風でもモダンジャズ風でも自由自在。話すのと同じくらいのレベルで音符を操ることが可能だが、その反面、世間的常識や言語を知らない。彼にとっては音楽は「空間認識」なので、言語や思想とは直接結びつかない。いわば「無知なるプロフェッショナル」とでも言うべきタイプである。
一方で、ベートーヴェンを代表とする「ディオニソス的」作曲家がいる。こちらは「感性」と「知性」が相互に独立していて、生まれながらにして自己の音楽言語を持っているわけではない。音楽を感じるセンスは抜群ながら音符を言語以上に操るような真似は出来ないので、他者の音楽を雑多に吸収することで自分の座標を徐々に固めてゆく。そのあたりは一般人と同じ音楽的レベルなのだが、いったん自分の音楽語法を身に付けると、音楽を客観的に解析し把握できる分なまじ音楽的才能を生来持っている音楽家より強靱な個性を発揮する。彼にとっては音楽は「言語」でもあるので、言葉によるイマジネーションや思考と結びつくことが多い。これは「博学なるアマチュア」というべきタイプである。
クラシック音楽史を紐解いていると、確かにバロック期からバッハ・ハイドン・モーツァルト・ロッシーニあたりまでは前者が全盛なのだが、ベートーヴェンを境にして後者が圧倒的なシェアを誇り始める。医学生のなりそこないのベルリオーズや詐欺師あがりのワーグナーなどは明らかに後者のタイプの「天才」だし、どう見ても生まれながらの音楽的才能とは別の力学で作曲をデッチあげたとしか思えないブルックナーやマーラー、あるいは法科学生くずれのチャイコフスキーやシベリウスあるいはストラヴィンスキーなども典型的な後者としか言い様がない。
しかし彼らは、なまじの素人ではない。プロフェッショナルを凌駕するアマチュア。言ってみれば「偉大なるアマチュア」なのである。そして、武満さんも確実にこの偉大なるアマチュアの一人なのだ。
例えば、武満さんのサウンドには7thあるいは9thといった和音への偏執がある。短二度をぶつけて喜んでいる膨大な現代音楽たちの間で、全音(長二度)で組み上げたモード(旋法)をべースにしたクラスター(和音の房)から官能的なサウンドを醸し出す指向。それは、ドビュッシー風のフランス近代風ハーモニーでもありメシアンなどの特殊な旋法も思わせ、同時にモダン・ジャズ風のテイストとロックなどのポップスのハーモニー感覚にも通じる。その起源は、彼が青年時代にアメリカ進駐軍のキャンプで聴いたジャズの「バーバー・ショップ・コーラス」風のハーモニー(と、武満さん自身がどこかで書いていた)なのらしいが、とにかくこのハーモニーへの趣味がデビュー作「弦楽レクイエム」から最晩年のオーケストラ作品群まで一貫しているのである。
あるいは、ストリングスや木管のロング・トーン冒頭をハープなどの撥弦音で装飾する趣味、音のアタックを決して小節冒頭に置かずに一瞬の間合いというべきタイム・ラグを生じさせる書式、絶え間なく繊細な音色の変化を仕込むオーケストレイション、弦における無意味にさえ感じられるような細かなディヴィジ、にもかかわらず内声に常に聞こえる緩やかなメロディ・ライン、そして数分からせいぜい10数分という時空を一歩も出ない作品の構造。それらも見事に一貫しているのだ。
それゆえに私たちは、彼のどんな作品を聴いても一瞬にして「あ、これはタケミツだ!」と思うのだが、それは裏返して言えば見事なアマチュアっぽさでありマンネリズムでもある。前述のアポロ的作曲家なら「膨大にあるハーモニーの中のたった数種にすぎない狭い領域の表現」あるいは「無限にあるサウンドの可能性の中のほんのわずかな嗜好」への固執しているのだから。
しかし、さらにまたそれを裏返して言うなら、それこそがまごうことなき「個性」なのだ。ここから導きだされる結論は不思議なものになる。つまり「音楽の才能を100%持つことが音楽家の才能ではない」ということだ。
この異様な結論を私は個人的に気に入っている。べートーヴェンもベルリオーズもワーグナーも武満徹も、音楽的才能がなかったゆえに音楽史上に残る才能となったのだ…という想像はなんとも楽しいではないか。
本来マイナス的要素であるはずの「素人臭さ(アマチュアリズム)」や「惰性(マンネリズム)」といったものが、反転して「個性」として昇華する一瞬。それこそが第一級の音楽が誕生する瞬間なのである。
*
◆タケミツ風タイトル考
ところで、「武満さんの作品について感心するのは、その音楽本体ではなくタイトルだ」…と言うのは暴論だろうか?。実を言うと、私が十代のころ初めて彼の音楽を聴いてまず感心したのは、音楽ではなくてそのタイトルにおける抜群のセンスだった。
「アステリズム」「グリーン」「地平線のドーリア」「弦楽レクイエム」あるいは「ピアノ・ディスタンス」「リング」「スタンザ」などの60年代の作品に付けられたタイトルは、実に新鮮な「カッコよさ」を発散していて当時高校生だった私をわくわくさせた。それはきわめてシンプルながら色彩豊かなイマジネーションを持ち、しかもモダンで新しさを感じさせるタイトルだった。もし「ノヴェンバー・ステップス」が、「尺八と琵琶のための11の協奏的断章」とか「アステリズム」が「ピアノと管弦楽のための幻想的ラプソディ」などと名付けられていたら、そもそも聴いてみようなどと思わなかったに違いない。
そして、このタイトルのセンスは70年代になって幾分ルーティンさを漂わせるようになるものの継続している。たとえば「クロッシング」「ユーカリプス」「カシオペア」「ジェモー」「カトレーン」「マージナリア」あるいは「ディスタンス」「フォリオス」「ガーデン・レイン」「ウォーター・ウェイズ」。英単語ひとつで空間的イマジネーションを換気するその選び方の潔癖さと見事さ、そしてその単語の響き自体が作品のサウンドにも共鳴しているかのような繊細さ。それは、まさに俳句のような切り詰められた語感を持ち、一語に込められた想像力の深さを感じさせる。これほどの名タイトル群を持つ作家がクラシック音楽界に出た例を私は知らない。
しかし、このタイトルのセンスはなぜか80年代に急変する。その転機は77年の「鳥は星形の庭に降りる」であり、その後79年の「秋庭歌」、80年の「遠い呼び声の彼方へ!」を経て、「海へ」「夢の時」「雨の樹」「オリオンとプレアデス」「虹に向かって、パルマ」「ストリング・アラウンド・オータム」「ファンタズマ/カントス」と続いてゆく。そこには、60〜70年代の鋭敏な言葉のセンスはもうない。あるのは妙に生ぬるく文学的な説明だ。そして作風自体も、ドビュッシーとベルクを足しただけのような妙な微温の世界(それはそれで美しいのだが)に変質・収斂してゆく。
60年代なら「テクスチュアズ」あるいは「アステリズム」と一語で切り込んで多層的なイメージを換気させていたものが、80年代のものでは「鳥の群れ(フロック)と星(スター)」あるいは「遠さ(ディスタンス)と声(ヴォイス)」「糸(ストリング)と秋(オータム)」など、二つの単語の間から引き出されるあいまいなイメージに変質している。
このことについて長いこと不思議に思っていたが、年表を見ているうちに謎がとけた。この転回点にあるのは1979年の滝口修造の死なのだ。1951年に「実験工房」で出会って以来決定的な影響を受けてきたこの希代の詩人であり美術家である彼に、もしかしたら武満さんはタイトルにおける多大な助言を受けていたのかも知れない。いわゆるブレインである。
つまり、60〜70年代の武満さんの見事なまでに切り詰められた鮮烈なタイトルのセンスはとりもなおさず滝口修造のセンスだったのであり、その死後のあいまいで三流文学青年的なセンスこそが武満さん自身の本来持っているセンスだったのだ。そう考えないと、79年の滝口修造の死の以前のタイトルとその後のタイトルとの落差を説明できない。そのタイトルにおいて、武満徹における滝口修造はビートルズにおけるジョージ・マーティンだったのである。
*
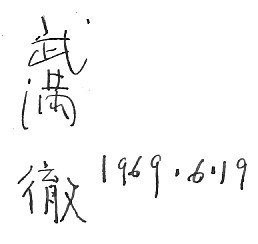 ◆最後に私信風タケミツ・ステップ考
◆最後に私信風タケミツ・ステップ考
武満さん、あなたは私の父親の世代にあたる。奇妙な近代化の時代に少年時代を過ごし、戦争で青春時代を翻弄され、戦後の復興期に壮年時代を迎えた世代です。そこには平和な現代では想像を絶するような様々な人生があった。もう二度と経験することがないような、経験することがあっては困る時代を生きてきたわけです。
そんな時代の中であなたは、戦後の焼け跡の中から前衛の大望を抱いて飛び出し、日本の復興と世界への進出をバックにその作品を海外に輸出するという奇跡を成し遂げた。そして、金満日本のジャパン・マネーを現代音楽界にも放出した揚げ句、バブルが弾けて現代音楽自体も落ち目になるとほぼ同時に鬼籍に入る…という見事なまでの生涯を全うされた。もう後の世代にはそんなことが出来る音楽家は二度と出現しないでしょう(もっとも、したいとも思わないでしょうけれど)。
自身の中にあるメロディへの希求を押さえ込んで、前衛の時代の機運に乗ったのは本意でしたか?。かつて夏の草津でお話しする機会があった時に「メロディを捨てた現代音楽は、もう音楽ではないと思う」とつぶやいた一言は忘れません。晩年に「オペラを書きたい」…という意志を漏らされた時、実は本当に書きたいのは「ミュージカル」なんじゃないか?と私は思いました。冒頭で書いた「芸術」と「娯楽」を分離したがるモンタギュー家とキャピュレット家に、あなたは不本意ながらやはり最後まで縛られていたのでしょうか。それとも、少しは解放されることがあったのでしょうか。
武満さん、あなたがその生涯で描いた見事なまでに戦後日本的なステップは、20世紀後半の日本の音楽家の理想的姿と言えるのかも知れません。よくも悪くも戦後日本的な文化の担い手。そう、もう一人、私が最も敬愛する巨匠「手塚治虫」もそうでした。文化的土壌ゼロの焼け跡から巨大な一歩を踏み出した創始者。そこには黎明期の巨大な苦労と共に、前人のいない気楽さと素人でものし上がれる胡散臭さが表裏一体になっている。
そして、その後の日本の異様な繁栄と共に意外と早い絶頂期と多忙がやってきた。実を言うと、黛敏郎氏のような鮮やかでスマートかつ外向的な才能に比して、武満さんの繊細で内向的な才能は時代が時代なら世間の無理解に終わって死後発掘された可能性だってあったはずです。でも、ニューヨーク・フィルの委嘱で尺八と琵琶をオーケストラとからませるという一世一代のジャイアント・ステップが流れを変えた。以後は、望むと望まざるとにかかわらず日本音楽界の顔として前面に押し出されるハメになってしまった。あまり外交的でなく目立ちたがり屋でもなく権威にも地位にも無頓着なあなたにとっては、あれはかなり不本意だったのではありませんか?
しかし、この「黎明期の苦労」と、その後に訪れる「絶頂期の多忙」、最後に「死後の神格化」、この3つが芸術家を完成させる。ただし、最初の2つは本人が作るものですが、最後の一つは作られるのです。
つまり、芸術家は亡くなってから新たなステップが始まる。死んだ後で、奇妙な作家論がキャラクターを決定したり(最近ではショスタコーヴィチがそうでした)、プライベートな手紙やらラブレターやらが全部公開されたり、作品に仕掛けた女性に宛てた秘密の暗号を読み取られてしまったり(可哀想なベルク!)、性生活まで研究されてしまったり(マーラー先生、ご愁傷さまです!)する。なにしろドイツ語も読めない私が、モーツァルトの結婚のいきさつや独身のブラームス先生が秘かに思っていた女性の名前やブルックナーが求婚してフラれた娘さんのことを知っているんですから、なにをか言わんやです。
武満さん、芸術家は死んでもなお娯楽を供給し続けなければ生き残れない。その証拠に、あなたの亡くなった後でさまざまな文章や書物やCDが、あなたが生きていた時にはありえなかったような未知の部分へスポットを当て始めている。作家の研究といえば聞こえはいいですけど、いわば検死のための解剖のようなものですものね。あなたを知っている人も知らない人も、分かっている人も分からない人も分かろうともしない人も同次元で言葉を膨大に紡いでゆく。もっとも日本ではヨーロッパほどの極端なプライバシー解体はまだないでしょうけれど。
そして、あなたが反論や解説を出来ない時空で、あなたが昔「ばからしい」と言った渋谷の忠犬ハチ公像のような、あなたの新しいイメージが作られてゆく。一人の音楽愛好家としては興味津々ですが、同じ作曲家としては楽しみなような怖いような、そんな奇妙な気分です。それでも、あなたのようになりたいと思うことで作曲家になり、あなたのようになりたくないと思うことで作曲家を続けている私にとって、あなたの生涯と作品は敬愛しつつも恐ろしい指針の一つであり続けると思います。
ですから、あなたの作品の持つポピュラリティとアマチュアリズムとマンネリズムを称えつつ、今でも私はよくあなたの作品を聴きます(ポピュラリティはともかく、アマチュアリズムとマンネリズムについては私も人後に落ちませんので…)。
そして、それは芸術でも娯楽でもなくまぎれもない「音楽」として聴こえます。
(1997.7.31 「武満徹:音の河のゆくえ」に掲載)
11月のカナリアは歌を歌いたかったのか?
武満さんの訃報を聞いた時、彼がしきりに「好きな作曲家はポール・マッカートニーだ」とか「ガーシュインみたいな作曲家になりたかった」とか言っていたということを思い出していた。
最後のCDが石川セリの歌うポップ・ソング風のアルバムだったのも象徴的だったが、20世紀を代表する超一流の大作曲家「トオル・タケミツ」も残念ながらメロディ・メイカーとしては一流ではなかったということを最後に証明する結果になったのは少し悲しかった。
武満さんは、そもそも音楽に目覚めたのは防空壕で聴いたジョセフィン・ベイカーの歌だというし、戦後はアメリカ進駐軍のキャンプでのアルバイトでジャズを身に染み込ませ、その種のバーバー・ショップ・コーラスが彼のハーモニーの原点になったという話を聞いている。若いころアメリカ留学の機会があった時「デューク・エリントンについて学びたい」と本気で言ったそうだし、ジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック」による作曲理論をかなり研究していたそうだから、確かに、武満さんは日本のガーシュインあるいは日本のポール・マッカートニーになる可能性は充分あったのだ。
なにしろ平気で無調の音楽を聴き続けられる「特殊な耳」を持っている現代音楽作曲家たちの中で、武満さんの耳は「普通の音楽を聴く耳」を持っていた。その証拠にデビュー作「弦楽レクイエム」では、その「歌」への指向がまだギリギリと軋みながらも残っている。彼は歌いたかったのだ。それなのに歌わなかった。歌わない時代が到来していたからだ。それが彼の生きた「前衛の時代」だった。
そう。あのころは日本列島全体が「開発」と称する国土破壊や「産業」と称する大気汚染に明け暮れていた。新しさを得るために国土から大気まで破壊する時代なのだから、音楽の美しさを破壊するくらいなんでもなかったのだ。そして、戦後日本の外国コンプレックスをそのまま直輸入するかのように「前衛音楽」が入ってきた。「あと10年したら豆腐屋の小僧も12音でラッパを吹いて豆腐を売りに来るようになる」と本気で信じている作曲家がいた、そんな時代だったのだ。
私が最初にタケミツ・サウンドを聴いたのは、まさにそんな時代の真っ只中の1964年の「テクスチュアズ」という作品だった。しかし、あの美しく混沌としたトーン・クラスターのクレッシェンドの最後にフワッと「メロディ」の断片が浮遊した時、私は武満さんの悲しげな「固定観念(イデー・フィクス)」を聴いたような気がした(それは後に、私自身の作品「朱鷺によせる哀歌」にエコーすることになる)。あれはあの暗黒時代には、隠れキリシタンが仏像の中にマリア像を隠しているような禁断の響きだったのかも知れないけれど。
それはちょっと考えれば誰でもすぐ分かることだったのだ。もし「普通の音楽を聴く耳」を持っているのに現代音楽の作曲家などになってしまったら、「音楽が聞こえなくなる耳」を持ったベートーヴェンのように苦悩するに決まっているのだということは。
そもそも「音楽」は人間という生物の「音に反応する感覚」の上に成り立った行為なのだから、感性を切り離して知性で作る音たちは「音群」ではあっても「音楽」ではない。「音楽」の領域を極めるための実験として「音群」を知性で制御してみようと試みるのは勝手だが、それは「音への試み」ではあっても「音楽」ではないのだ。
ところが、この一般社会から遊離した実験行為がその「芸術」性を振りかざして逸脱し、大衆の支持を得られないのを逆手にとって一般の音楽を大衆音楽とか娯楽音楽と呼んで低いものと見なし始めると、この弱小集団は「現代音楽」という名のファッショのカルト教団化してゆく。(この思考が生みだした最近のおぞましい例を私たちは知っている)。
武満さんが、現代音楽のこのファッショ・カルト化に反感を持ちながらも結局は終生「現代音楽教」の大幹部であり続けたのは、ソヴィエト政府に反感を持ちながらも結局は終生国家権力サイドの御用作曲家の地位にあり続けたショスタコーヴィチを思い起こさせて、作曲家もまた人間であるということを悲しく思い知らされる。
そのあたりのことについて、私は物分かりよさそうな顔をして理解したいとは思わない。いくら知性がたわ言を思い付いても感性はごまかせないはずだし、人一倍音については鋭敏で繊細な感性の持ち主だったはずだ。それなのに彼は「現代音楽」の一線で活躍し続け、ご丁寧にも海外の「現代音楽」を紹介する任まで買って出て、「先鋭的な音楽芸術を社会に認知させるべく働く知性的な文化人」を演じ続けた。その矛盾に耐えた偉大なる精神力には驚嘆するしかない。その苦悩は、たぶん耳が聞こえなくなったベートーヴェンの苦悩に匹敵するに違いない。私はそう思う。
そんな武満さんの作品が80年代を境に甘く退嬰的なサウンド指向に片寄っていったのは、彼自身が本来求めていた「音楽」をそういったストレスを振りきって書こうとし始めた証だった。それは60年代の名作「テクスチュアズ」で既に「歌」を憧れとして秘めていた武満さんにとっては当然の帰結だったのだ。
しかし、60年代70年代と作曲家の一番脂の乗りきった時期にメロディを書かなかったツケは厳しい。甘いサウンドは書けるようになったが、その「核」となるメロディだけはどうしても書けなかったのだ。(訃報を聞いて以後、彼の残した多くの作品を聴き直したうえでそう断定せざるを得ないことは、彼を敬愛し畏敬しながら作曲家を志した私にとっては悲しくつらい)。
確かに、若いころから書き続けてきた映画の音楽や劇音楽のジャンルで、彼はいくつかの「メロディ」を書いている。その中の幾つかは「現代音楽の作曲家」としては異例の美しい旋律の瞬間を聴かせる(歌では「死んだ男の残したものは」、映像では「未来への遺産」が印象的だ)が、ほぼ同世代のこのジャンルの名手たち例えば冨田勲や宇野誠一郎などの天才的メロディ・メイカーたちとは比べるべくもなく、團伊玖磨や芥川也寸志が童謡で聴かせたシンプルさや、現代音楽界の同僚である松村禎三や林光あるいは湯浅譲二が映画やTVの音楽で見せた見事なメロディ作法にも残念ながら達していない。
昔から口ずさんできたポップ・ソングをギターにアレンジした「12の歌」などはその前後の作だが、彼はどんな気持ちでこれらの楽譜を書いたのだろう。ジャズへの憧れ、ポップスの甘い響き、ノスタルジックに心を震わすメロディ。完ぺきなサウンド・コントロールによる見事な自己愛を聴かせる美しいアレンジだが、たったひとつ、「メロディ」だけが彼のものではないのだ。
武満さんの死後、FMの番組でその中の一つの「オーバー・ザ・レインボウ」を若いギタリストが弾いたCDをかける機会があった。その時、その小さな一曲が武満さんの心を象徴しているような気がして、なぜか涙が出てきて仕方なかった。
蛇足になるかも知れないが、昨年イギリスで私の交響曲を録音した時、指揮者である若い世代の藤岡幸夫氏とポップスの話ばかりをしていたのを思い出す。ビートルズ世代以後の私たちにとっては、交響曲もロックンロールもジャズもエスニック音楽も、「音楽である」という点で同義なのだ。そこには、音楽を差別化するファッショも限定されるストレスもない。
武満さんもそういう時代のそういう世界で音と戯れて欲しかった。そうしたらカナリアはきっと歌ったに違いない。「11月の階梯の歌」や「ドーリア旋法の地平線の歌」や「星型の庭に降りた鳥の歌」を...。
(レコード芸術1996年8月号「武満徹・追悼特集」に掲載)