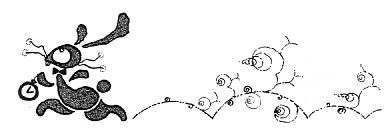■音楽・世界・人間
■タイトルにおける世界観
♪吉松さんが作品に付けるタイトルは、いずれもなかなかユニークですよね。「プレイアデス舞曲集」「忘れっぽい天使」「天馬効果」「一角獣回路」「オリオン・マシーン」「メモ・フローラ」「ケンタウルス・ユニット」などなど。どれもこれも不思議なイマジネーションを持ってます。これは、どういう所から生まれたものですか?
私の場合、音楽というのは音だけで存在するものというより、言葉のイメージを核にして収斂してくる結晶のような感じなんです。ですから、作曲をしてからそれにタイトルを付けるんじゃなくて、音楽を呼び覚ます魅力的なタイトルを思い付くとそこに音が集まってくる…ということが多いですね。
それで、作曲家を志した高校生の頃、音楽を呼び覚ますための言葉のネタ帳みたいなものを作って、言葉を収集し始めたんです。例えば、「シリウス」や「プレイアデス」や「オリオン」のような星の名前、「ペガサス」や「ユニコーン」や「ケンタウルス」など神話の動物の名前。それから「組曲」とか「変奏曲」とか「ソナタ」みたいな音楽用語や、なんとか「効果」なんとか「回路」のような科学用語、さらには「もゆら」とか「なばり」などの古語、「チカプ」や「カムイ」などのアイヌ語などなど。イマジネーションを刺激するような単語を見付けると何でもかんでもノートに片っ端から書き留めて、それをストックするわけですね。
♪なるほど、まさしくネタ帳ですね。
そうやって言葉を蒐集していくうち、17歳くらいの時なんですが、音楽について進化の樹みたいなものの構成が固まってきたんです。自分の音楽が形を成してゆく、成長して行く過程みたいなものと言うか。それが、〈星〉〈天使〉〈鳥〉〈神話の動物〉〈人間〉〈大地(地球)〉〈神〉という7つのステップ。要するに、まだ形を成していない音楽の光るかけらが、空の彼方から徐々に降りてきて大地に着地するまでの「進化」の7つの段階なんです。
♪〈星〉〈天使〉〈鳥〉〈動物〉〈人間〉〈大地〉〈神〉…ですか。
まず最初に、空の彼方にあって光るだけの原初的な存在。それが〈星〉の状態。続いて、それが透明ながらも何かの形を成してくると、それが〈天使〉。そして、それが実体化して羽毛が生えて歌を歌い出す。これが〈鳥〉。さらに、それが天空を疾走し始めるのが〈神話の動物〉のレベル。それが、手足を持つと平凡ながらも普通の〈人間〉となり、ようやく地面に着地すると〈大地〉に至る。そして、そこから先でまだ余裕があれば〈神〉あるいはふたたび星…(笑)。♪地面から空へ高い方に進化して行くんじゃなくて、空から地上へ降りてくるんですね。
そうなんです。「それって逆じゃないの?」と、時々指摘されるんですが、大気に浮遊して拡散しているものを自分の中へと収斂させて行く過程こそが「進化」のイメージだったんですよね。だから、自分の音楽のレベルについても、デビュー前の海のものとも山のものとも付かない〈星の時代〉、それが透明ながら姿を現わす〈天使の時代〉、さらに現実の身体を持って空を飛翔する〈鳥の時代〉…というふうに進化して行こうという、そういう構想だったんです。♪面白い進化論ですね。それはどこから発想したものなんですか? 天使の階級のようでもあり、曼荼羅のようでもあり…。
作風の「何とかの時代」というのは、もちろんピカソの「青の時代」のパクリなんですが(笑)、基本的には何の影響だったんでしょうね。特にニーチェの永劫回帰とかベルグソンの創造的進化とかに心酔した覚えはないし。マーラーの第3番も、花、動物、人間、天使、愛(神)みたいな進化論が構成としてありますけど、それを知ったのはずっと後ですし。メシアンも、鳥や天使が出てきますけど、後になって天使や鳥のシリーズを聴いた人から「メシアンも鳥ですよね」と言われるまで特に気がつかなかったし(笑)。♪作曲を志した17歳の時に、自分の音楽をそういう過程で進化させてゆきたいと考えたわけですか。
そうです。現実の人生設計はゼロのくせに、そういうところだけ綿密に予定を立てているんです(笑)。それで、「27-8歳で世に出る」とか「7つのレベルで進化する」とか「37-8歳でのたれ死ぬ」とか予言していた(笑)。
■進化の樹
◇・・・ 星
♪その進化を順にお聞かせ願えますか。まず最初の〈星〉ですが、確かに〈星のシリーズ〉とでもいうべき作品群がありますね。これが進化の出発点ということになりますか。
op.1が〈シリウスの伴星によせる〉ですし、演奏はされていませんが〈シリウス賛歌〉op.2というのが、作品番号を付けた最初のオーケストラ曲ですしね。第一歩は〈星〉なんです。その後も〈レグルス回路〉〈プレイアデス舞曲集〉、ピアノ四重奏曲〈アルリシャ〉と星の名前ですし、最初の著書は「魚座の音楽論」(笑)。〈ペガサス(天馬効果〉〈ユニコーン(一角獣回路)〉〈オリオン〉は星座の名前ですし、最近書いた〈アルビレオ・モード〉でまた星に戻っている。本当は、夜空の星ぜんぶに音楽を書きたいと思ってたほどなんです(笑)。
♪天文学的あるいは占星術的な意味合いもあるのでしょうか?
いや、作曲…という行為に向かい合った時、最初に思い至った存在が〈星〉だったんです。真っ暗闇の宇宙の中で、ぎりぎりの孤独と対峙して「ただ光っている」というのが、なんと言うか…身につまされて(笑)。例えば、シリウスという星は、全天でもっとも明るい一等星ですから文字通り「スター」ですが、あれは8.6光年の彼方にありますよね。と言うことは、今私たちが見ているのは8年以上前に彼が放った光だということになります。つまり8年間ものタイムラグのあるコミュニケイションですよね。
作曲家もそれに似ていると思うんです。シューベルトが150年以上も前に書いたソナタや、シベリウスが70年以上も前に書いた交響曲に、現代に生きる私が感動する。光を放った当の星は、その光が相手に届いたのかどうか知る由もない。そして、届いた頃に自分はもうこの世にいないかも知れない。その、絶望的なのか理想的なのか分からないコミュニケイション。その象徴が、私にとっては〈星〉だったんです。♪感動的であるとともに、なかなか怖いヴィジョンでもありますね。
もうひとつ宮沢賢治の影響も大きいですね。これはもう母の影響で子供のころから「銀河鉄道の夜」とか「よだかの星」とかさんざん読んでいたもので、その宇宙の中の詩的な存在としての〈星〉が刷り込まれていたと言うか。そうでなくても、星というのはどこか〈魂〉を思わせますよね。「死んで星になる」みたいな。だから、天空で「ただ光るもの」としての存在というのは、孤高の絶対的存在のようでもあり、同時に寂しく悲しい孤独の極致のようでもあり。そういう「ただ存在するもの」という透明感に惹かれたということなんでしょうね。♪それは曲の形にも現われていますよね。プレイアデス舞曲集が7曲から出来ているみたいな。
星というのは、どこか音符に似ているんですよ。星がいくつか組み合わさると星座になる、というのは、どこかメロディの生成に似ているし。例えば、プレイアデス星団は、ギリシャ神話の7人姉妹の名前が付けられていながら実際に見えるのは6つで、日本では六連星(むつらぼし)などと呼ばれてますが、7つあるのに主に聴こえるのは6つ…なんて、旋法と同じですよね。ドレミファソラシ…と7音あるけど、実際は6音か5音がメインになって楽曲は作られている。実際、「プレイアデス舞曲集」のアイデアはそこから来ていますし。
作品番号を付けた最初の〈シリウスの伴星によせる〉と〈シリウス讃歌〉というペア作品も、主星シリウス…大オーケストラ曲…の横に伴星…ピアノ曲が存在している…という構図だったんです。結局、演奏されませんでしたけど。これが順当に評価されて、その後ずっと星の音楽ばかり書き続けていたら、今ごろは〈星の作曲家〉として名を成していたかも知れませんね(笑)。
◇・・・ 天使
♪で、デビューとして最初に姿を現わすのが〈天使〉になんですね。
これは、キリスト教的な天使ではなくて、1にも2にもパウル・クレーの「忘れっぽい天使」というエッチングの影響です。何光年もの彼方の夜空にただ光っていて、交信するのに何年もかかるのが〈星〉なんですが、それに対して〈天使〉は、透明で不完全ながらかすかに形を成しているもの…というイメージです。
最初にこのクレーのエッチングを見た時、その造形に感心する以上に「忘れっぽい」というのは何なんだ?と思ったわけです(笑)。そこで直観的に感じたのは、人間の生と死については〈神〉が司るんですが、その間の人生という細かいところは〈天使〉が司っている…というヴィジョンでした。
つまり、神様が人間ひとりひとりに恋愛させたり才能を与えたり宝くじに当てたり病気にしたりするんじゃ大変だから、そういった雑用は使いっぱしりの天使がやるわけですよ。ところが、それが絶望的に忘れっぽい〈笑)。だから、恋愛させたり才能を与えたりしても、その後のことはすっかり忘れている。そういう可愛くも恐ろしい存在が〈天使〉なんです。
♪それは怖いですね(笑)
私がある日まったく突然音楽に魅せられて作曲家になってしまったのも、キューピッドが恋の矢を放つみたいに、多分どこかの気まぐれな天使が〈音楽の矢〉でも撃ったに違いないんですよ。ところが、人を音楽狂いにしておいて後は奇麗さっぱり忘れてる(笑)。アフターケアもメインテナンスもなしに10年以上ほったらかし、というのが実感(笑)。
そのくせ、「死」だけは神様が司るので、決して忘れられることはない。良い目を見ようが悪い目を見ようが、助けてなんかくれない。それで最後は死ぬしかない、という恐ろしい構図ですね。♪そう言えば、〈悪魔〉って〈天使〉の成れの果てなんじゃなかったでしたっけ。
実は同じなんじゃないですか。白いか黒いかだけで(笑)。ですから、〈天使〉のシリーズにはかすかに〈死〉の影があるんです。
♪これはハーモニカのための〈忘れっぽい天使〉のシリーズですね。
そうです。I , II , IIIの3曲。それから〈天使はまどろみながら…〉という作品にもちょっと顔を出しています(笑)。
◇・・・ 鳥
♪そして〈鳥〉は膨大な〈鳥のシリーズ〉を生みました。
結果的に私の音楽の中で突出して大きなシェアを占めることになりましたが、最初から鳥を重点的にやろうと考えていたわけではありません。透明で浮いているだけの〈天使〉が、生身の実体を持ち、「歌」を手にしたもの…というイメージで、一種の通過点にすぎなかったんです。作家としての「鳥の時代」というのも、作品が演奏されるようになってようやく飛び始めた…という期待される新人的なイメージでしかなかったし(笑)。♪最初はやはり〈朱鷺によせる哀歌〉ですか。
そうですね。でも、もしかしたらこの1曲だけで〈鳥〉は終わってた可能性もあったんです。ところが、この曲を発表した直後にフルート・オーケストラの曲を書かないか?というオファーが来た。これは、なんとピッコロからアルト・フルート、バス・フルートまで、フルート属ばっかり15本によるアンサンブルなんです。それで〈チカプ〉という、鳥のさえずりの音型だけで出来た作品を書くことになり、そこで初めて〈鳥のシリーズ〉を意識しました。これは結構運命の出会いだったかも知れないですね。
そもそも〈鳥〉というのは「現代音楽という不毛な森から飛び立って、調性の空を自由に飛翔する」ということのメタファー(隠喩)だったんですが、この〈チカプ〉をきっかけにして具体的に鳥のさえずりや仕草、あるいは翼の空気力学的な仕様などいろいろなものを音楽に取り込む「音楽語法」に懲り始めて、すっかり深みにはまってしまいました(笑)。そのあたりについては、作曲語法の話のところで詳しく話してます。♪オーケストラによる鳥の連作のほかにも、室内楽でも数多くの鳥のシリーズが生まれました。
最初は〈朱鷺によせる哀歌〉〈チカプ〉〈鳥たちの時代〉という三部作で終わりにしようと思ってたんですが、止まらなくなって(笑)。結局その後、〈カムイチカプ交響曲〉〈鳥と虹によせる雅歌〉〈サイバーバード協奏曲〉〈鳥は静かに〉〈鳥はふたたび〉〈鳥たちの祝祭への前奏曲〉と、鳥づくし(笑)。
室内楽に至っては、〈デジタルバード組曲〉に始まって〈鳥の形をした4つの小品〉〈ランダムバード変奏曲〉〈パラレルバード・エチュード〉〈ファジーバード・ソナタ〉〈鳥ぷりずむ〉〈鳥リズム〉〈ミミックバード・コミック〉〈鳥が月の光を夢見る時に…〉などなど鳥だらけですね(笑)。雅楽〈鳥夢舞(とりゆめのまい)〉なんていうのもあるし。♪デジタルバードに始まる室内楽の〈鳥〉は、またイメージが違うような気がしますが。
オーケストラの〈鳥〉がゆったり飛翔する大型鳥類なのに対して、室内楽の〈鳥〉はちょこまか動く小型鳥類ですからね。白鳥とか朱鷺とか梟とか鷲とかの大型鳥類は、大きく翼を広げて滑空するし鳴き声もロングトーンなんです。でも、スズメとかシジュウカラとかのような小型鳥類は、動きもちゃかちゃかしているし鳴き声も短音の〈さえずり〉が主です。当然、時間の概念が違うだろうし、とするとそこに存在する世界観や音楽観も違うはずなんです。
具体的に言うと、大型鳥類系の〈鳥〉のシリーズはハーモニーとテクスチュア重視のAdagio、小型鳥類系の〈鳥〉はリズムとテンポ重視のAllegroということになるでしょうか。同じ〈鳥〉でありながら「音楽とは何ですか?」と尋ねたら正反対の答えを言いそうな気がしますよね。それで、二方向から攻めていった、というわけです(笑)
♪文字通り「鳥は音楽の師匠である」ですか?
そうです。鳥は、人間が音楽を生み出す遥か前の太古の時代から歌を駆使していた。「歌」に関しては人間よりはるかに先輩であるのは間違いないし、文句なく最上の「音楽の師匠」と言っていいんじゃないでしょうか。私だけではなく、すべての音楽をやる人間にとってのね。
◇・・・ 神話の動物
♪次の神話の〈動物〉というのは?
これは、星が組み合わさって〈星座〉になるように、響きや形や歌が組み合わさって四本足の「形式」が生まれる、そういうヴィジョンです。〈鳥〉よりは進化して、足は4つあるんだけど、まだちゃんと大地には着地しなくて、星の間を駆け巡っている…という、ちょっとモラトリアムしている動物なんですけどね(笑)
このシリーズはいずれもコンチェルト作品で、〈天馬効果(ペガサス・エフェクト)〉〈一角獣回路(ユニコーン・サーキット)〉という2曲。〈オリオン・マシーン〉と〈ケンタウルス・ユニット〉もちょっとかぶっていますね。♪これは〈天馬効果〉が最初の作品になりますか?
そうです。ちなみに、〈天馬効果〉は、ソリストである山下和仁さんのギター(馬)がオーケストラという〈翼〉を得て羽ばたく…というイメージからの発想。次の〈一角獣回路〉は、馬込勇さんがファゴットを吹いている…というのが、まさに馬(馬込)に角(ファゴット)、ということで(笑)。
続く〈オリオン・マシーン〉は、これもソリストの箱山芳樹さん(オリオン)がトロンボーンという金色の楽器(マシン)を持っているイメージ。〈ケンタウルス・ユニット〉は、チェリストであるPeter Dixon氏がチェロを弾いているのを、上半身が人(演奏家)で下半身が馬(チェロ)というユニットに見立てたタイトルです。ほら、チェロというのは胴体が茶色く光っていて馬に似ているでしょ?それに馬のしっぽの毛を張った弓で弾きますし(笑)。♪なんか遊んでません?(笑)
遊んでますよ。もちろん。特にコンチェルトは「遊び」の世界ですから。
でも、この神話の動物シリーズは「パーツを組み合わせる」ということがポイントだったんです。〈馬〉と〈鳥〉をくっつける(ペガサス)、〈人〉と〈馬〉をくっつける(ケンタウルス)…みたいに、異種交配することによって新しい「架空の生物」を創ってゆく。本来ならくっつきようのないものでも、ファンタジーがあればくっつけいてしまうわけです。
同じように、自分の中にあるシリアス・クラシックなモード、ジャズやロック、センチメンタリズム、祝祭的なダンス、そう言った本来くっつきようのない音楽的素材を、冗談めかしてファンタジーで連結させてしまう。それがこのシリーズなんです。
◇・・・ 人間
♪なるほど。すると、それをさらに進化させた〈人間〉というのは?
いや、人間はこの進化の輪でいうと、最底辺なんです(笑)。光らない星であり、堕ちた天使であり、歌えない鳥であり、走れない動物。一応は知性らしきものがあって、そのせいで「私って何なんだ?」と悩むんですけど、回答なんか聞こえてくるわけもなく、存在の考えられない軽さを感じつつ超低空飛行してる(笑)。♪なんだか情けない存在のような気が…(笑)
確かに(笑)。でも、人間が進化の頂点だなんてとても思えないし、99%の人間は社会の中でもみくちゃになって、鳥や動物ほどの自由もないですからね。
要するに「社会」というものを作って「自然」から隔離された場所での安全を図る事で、確かに天敵に食い殺されるとか日々の食べ物に困るとかいう不自由は無くなったけれど、生物としての自由は完全に喪失しているでしょう。自由に殺し自由に殺され、自由に生まれて自由に死ぬ。生物の自由とはこれに尽きますからね。それを失った人間としては、これはもう、愚痴を言い自嘲しながら飲んだくれるしかないんじゃないか、と(笑)♪うーん。なんともひねくれた人間観ですねー(笑)。作品としては?
これは、声楽の丹羽勝海さんとやった〈小市民シリーズ〉ですね。偉そうな人間ではなくて、平々凡々たる庶民の一人というか、ごく普通の中年男としての「人間」なんですよ。〈トラウマ氏の一日〉〈ランダム氏の独白〉〈フラクタル氏の生涯〉〈コンポーザー氏の憂鬱〉〈スプラッター氏の怖い話〉〈ナムウ氏の黙示録〉。これに同じ趣向の舞台作品〈セレスタ〉〈百物語より〉〈KENJI〉を加えると全部で9つあります。
いずれも舞台作品で、台本は自分で書いてます。売れないセールスマン(トラウマ氏)とか、平凡な会社員(フラクタル氏)とか、現代音楽の作曲家(コンポーザー氏)とか、最後の人類を見とる男(ナムウ氏)とかが主人公で。ただしこれは、残念ながら再演も録音ももう不可能ですから、歴史の彼方に消えて行った作品と言うべきです。その点でも情けない存在で(笑)。
◇・・・ 大地(地球)
♪そして、人は〈大地〉あるいは〈地球〉に着地するんですね。
五体を得て大地に着地する。これが今のところ私の考える完成形で、これが〈交響曲〉です。ここには、〈星〉〈天使〉〈鳥〉〈動物〉〈人間〉すべての要素が混交して存在している。さらに加えて〈水〉や〈火〉や〈風〉などもです。実際、大地というのはすべてを含んでいますよね。人間は地表に生まれた動物の小さな一亜種にすぎないけれど、大地そして地球は何もかもすべてを包み込む。と言うより、すべての存在を含んだものを〈地球〉と言うわけですからね。
このあたりは、手塚治虫の「火の鳥」における「地球はひとつの生命体である」というヴィジョンの影響かなあ。人間や鳥や獣や植物を統合した「生命の集合体」が、細胞が集まってひとつの生物になるように、ひとつの「生命」として存在する…というイメージです。音楽においても、歌や旋法やリズムや形式が統合されて、ひとつの生命体になる…というわけですから、これはどう考えても〈交響曲〉ですよね。♪なるほど。でも、最初の交響曲は〈カムイチカプ〉という鳥の名前が付いてますよね?
神の鳥である〈カムイチカプ〉は、ちょうど天空の鳥や神話の世界と、人間や大地の世界との境界にいるポジションなんです。なにしろ最も高い樹のてっぺんから人間を見下ろしている鳥ですから。つまり、「大地への着地」への第一段階として、一番高い木の上へ着地するんです(笑)。
で、その後に本格的に着地するのが交響曲第2番〈地球(テラ)にて〉。分かりやすいでしょ?(笑)。そして、大地に着地したので、以後の交響曲は番号のみで名前を持たない。第3番、第4番、第5番とか。いや、と言うより、〈第3番〉とか〈第5番〉というのがタイトルなんです(笑)。♪でも、一方で「交響曲は人生を描いている」ともおっしゃっていましたよね。
〈大地〉のシリーズとは言っても、大地や地球を描くわけではないんです。あくまでも、音楽的進化のメタファーとして〈すべてが統合された着地点〉を大地になぞらえているだけで。だから、大地に着地したところで何かを物語ったら、それは作曲家という人間が語る以上「人間の物語」すなわち「人生」になる。それだけのことです。
もっとも、逆に言うと、人間が大地の上に立って人生を語った以上、そこから先などあるわけないですから、これでデッドエンドという気がしないでもないんですけど(笑)
◇・・・ 神(ふたたび星)?♪それでは、最後の〈神〉というのは?
実は〈神〉というのは曖昧な言い方で、正しくは〈人間や生命を超越したもの〉ということですね。でも、それは超自然的なものではなく、〈大地(地球)〉を超えたものですから、早い話が…何のことはない…また〈星〉に戻るわけですよ。永劫回帰と言えば格好いいけど、早い話が堂々巡りというか、元の木阿弥というか(笑)。
星は、夜空にポツンと小さく光っている星でも、実は地球や太陽より巨大な恒星だったりするわけでしょう。そういう点では、大地としての地球より巨大ですけど、夜空にぽつんと光っている…という点では、ただの星(笑)。進化した巨大化したと思っても、結局もとの「ポツンと光る存在」に戻る。というわけで、これで見事な進化の〈リング(円環)〉の完成というわけです。♪なるほど。ぐるりと一周するわけですね(笑)
ですから、作曲家当人は「交響曲こそが自分の音楽の最終完成形だ」などと言い張ってますが、聴き手としては「〈星〉や〈鳥〉の方が面白い」と思うかも知れないし、「全然進化してなくて同じじゃないか」と思うかも知れないですね(笑)
大体「作曲家になりたい」という出発点がべートーヴェンの「運命」で、それから延々35年経って到達した〈交響曲第5番〉がそのまんまジャジャジャジャーンで始まってハ長調の協和音で終わる曲なんですから、全然進化してないのは確かです(笑)。到達点がすなわち出発点と言うか、結局最初の最初に戻って来ただけ。お釈迦さまの手のひらの上でもがいていただけという感じですよ(笑)
♪うーん、人生ですねー(笑)。ちなみに、その進化樹に属さない作品はないんですか?
あります。例えば〈夢〉。〈夢色モビール〉〈鳥夢舞〉〈夢あわせ夢たがえ〉〈夢ゆららに〉〈星夢の舞〉〈4つの小さな夢の歌〉とこれは多いです。〈虹〉のシリーズで〈虹色ぷりずむ〉〈虹色機関〉〈鳥と虹によせる雅歌〉なんていうのもありますね。これは透明で実体がないわけだから〈天使〉のシリーズに近い。
〈メモ・フローラ〉は、〈花〉のシリーズと言いたいんですが、まだ1曲しかない(笑)。もうひとつ、邦楽器で古語のシリーズというのもあります。〈もゆらの五ツ〉〈なばりの三ツ〉〈すばるの七ツ〉なんて、ちょっと面白いでしょう?
それから、シリーズと言うわけではないんですがキイワードとして〈舞〉というのもありますね。〈プレイアデス舞曲集〉〈星夢の舞〉〈風夢の舞〉など、舞曲のシリーズというのも結構多いんですよ。
■鳥の歌・自然の響き・北の香り
♪ところで、吉松さんの音楽には〈星〉にしろ〈鳥〉にしろ、独特の「自然」の響きが聴こえますが、その原点はどのあたりですか?
星や鳥をテーマに曲を書いていると、「自然に囲まれて作曲しているのですか?」と聞かれる方が必ずいるんですが、残念ながら、私は生まれた時からずっと都会住まいですし、仕事場に使っているマンションの部屋も、とりたてて静寂に囲まれた環境ではないのですよね。ヨーロッパの作曲家などは、本当に自然にあふれた、日本人の私などから見るとうらやましい限りのような環境で作曲をしていたりするんですが、とても真似できません。♪現実の自然体験と言うより、イメージの中の世界なんでしょうか。
それはこういうことだと思うんです。実際に美しい自然に囲まれていたら、それを自分の目で愛でるのが一番で、敢えて音楽にしようとか自分で描こうなんて考えないと思うんですよ。逆に、自然に囲まれていないからこそ、そして喧騒の都会の中で作曲しているからこそ、見果てぬ「自然の美しさ」に心から憧れる。それで、現実に自然の中で暮らしている人以上に「自然」に関わる音が聴こえてくるんじゃないか、とそう思うんです。負け惜しみかも知れませんけど(笑)。
♪ああ、それは分かるような気がします。
ただ、私の世代は、東京に「自然」が残っていたのを見た最後の世代だというのは確かですね。前にもお話ししたように、東京オリンピック〈1964年〉以前の東京は、まだ舗装されていない道路や、小川や池や空き地や、小さな雑木林や原っぱや鬱蒼とした小さな森なんかが結構ありましたから。
それに、私が育ったのは渋谷と新宿の間で、目の前に代々木公園とか明治神宮の森とか、結構「緑」には恵まれた場所であることは確かです。いや、でも、そんなものは本当の自然の中で育った人から見れば「自然」とはとても言えないでしょうけどね。♪イマジネーションの源泉としては、どんな自然なんでしょうか?
やはり、子供の頃に家の周りにあった自然体験だと思いますよ。東京にもくっきり四季がありましたから。結構、近くの川や池や林や原っぱで遊んだ記憶がありますし、夜は家の二階の窓からは銀河が見えましたし、オリオンやシリウスを飽きずに眺めていましたし、東京もかつてはよく雪が降りましたし。
ただ、面白いのは、別に北国に縁があるわけも何でもないのに、明らかに南方系より北方系の文化に惹かれた点ですね。祖父の系統は遡ると九州とか山陰の方の出身ですし、北に知り合いはいないんですけど、とにかく「北の」「冷たい」風土の方に圧倒的に惹かれていました。♪それはまたどうしてなんでしょう?
それについては最近、西村朗氏と「それはDNAなんじゃないか?」という話になったんです。彼が自分で共鳴する音楽を無作為に並べてみると、日本を起点にして東南アジアからインド、中央アジアを経てようやくヨーロッパへ至ると言うんですね。これは完全に南回りのヨーロッパ便じゃないですか(笑)。一方、私の共鳴する音楽を探って行くと、北海道(アイヌ)からシベリアを回って北欧に出てヨーロッパに至る。まったく北回りのヨーロッパ便なんです。♪つまり、先祖が南回りで日本に来たか、北回りで日本に来たか…という?
まさにその通りなんです(笑)。私の遠い先祖は、アフリカからヨーロッパを北上し、北欧を経てシベリア経由の北回りで日本に来た日本人なんですね、きっと。で、彼(西村氏)の先祖は絶対に中央アジアからインド経由の南回りで日本に来た。いや、証拠はないんですけど、「ああ、そういうことだったのか」と納得してしまいました。
実際、音楽でもアフリカとかアジアとかインドとか中近東と言う方向へは触手が全然動かなくて、もっぱら北海道とか北欧とか、寒い文化圏ばかりにあこがれを持ってましたし。アイヌ文化とか北欧神話とか、ロシア・ソヴィエト音楽とか。車を運転するようになってさんざん通ったのは北海道でしたし、最初に行った海外はフィンランドでしたし。旅をしてどっちへ行こうかと迷うと、必ず北へ行く。それに、昔からあんまり海と言うのは興味がなくて、行くとしたら湖なんですよね。森の中に湖がある。しかも北。それが一番落ち着く風景なんです。これはやっぱりシベリア経由だと(笑)。
♪と言うことは、夏より冬の方がお好きですか?
そうですね。基本的に夏というのは苦手で、冬の方が好きです。そう言えば、以前、雪景色ばかりを描く画家の方の美術館のために〈白い風景〉という「雪の音楽」を書いたことがあったんです。画家の先生は北国生まれ北国育ちで「東京の作曲家に雪の音楽なんか書けるわけがない」と最初おっしゃられていたそうなんですが、曲が出来てみたら「ああ、雪の音がする」と。
その後日談なんですが、イギリスでその曲を録音する機会があって、その時プロデューサー氏がスタジオに入って来て面白いことを言ったんです。「不思議だね。この曲を鳴らすとスタジオの中がひんやりする。温度が何度か下がったみたいにね」って。♪そういった冬の音楽も含めて、吉松さんの音楽には自然回帰と言うかエコロジーの匂いが濃厚のように思われるんですが。
確かに〈朱鷺によせる哀歌〉は、朱鷺を「滅びてゆく日本の美しい自然の象徴」と捉えてるんですが、発表当時、大先輩の世代のある作曲家は「朱鷺なんて、昔は田んぼにいるのを追い払う〈鳥追い歌〉があったほどなのに、それが滅んで可愛そうだなんて曲が出来るとは、時代ですねー!」と言っていたのが印象的でしたね。
そもそも作曲当時はエコロジーなんて言葉はありませんでした。ただ、私が少年時代を過ごした戦後の高度成長期というのは、開発という名の自然破壊が日本中に横行していて、それに悲しい思いをしていたのは確かです。そこから「滅びるものへの共感」というのが頭をもたげてきた。そもその「強者」とか「権力」とか、羽振りのいい力のあるものは嫌いで、弱い者の方が好きでしたし。いわゆる判官びいきと言う奴ですね。自分も、クラシック音楽なんかやっていて、弱くて滅びるものの側だし…という被害者意識があったのかも知れない(笑)。ただ、自然破壊にしてもエコロジーにしても、どちらも人間のエゴの裏表に過ぎないし、共感はできませんけどね。♪エコロジーと言うのもエゴですか?
そうですよ。自然に優しいとか地球に優しいと言うのなら、「排気ガスを何%減らす」とか「割りばしをやめる」とか「冷房の温度を2度あげる」とかいう瑣末なレベルではなく、「自動車を世界から全廃する」とか「人間の数を今の100分の1にする」というレベルの行動こそ急務でしょう?。でも、それは絶対言わない。まあ、現実にやったらホロコーストになってしまうわけですから、当り前ですけどね。
人間にとっての利便さだけを追及するのが自然破壊で、それは確かに憎むべきですが、所詮人間の都合のいい「自然」を手のうちに入れるだけの思考でしかないエコロジーにも、共感は感じません。特に西欧の発想というのは、「自然」をねじ伏せるか「自然」を懐柔するか、どっちにしろ支配しコントロールすることですからね。東洋みたいに「自然に滅びる」とか「自然に死ぬ」というところまで含めた意味での「自然」観はない。
もし地球にとって究極の「自然にやさしい」エコロジーがあるとすれば、それは人間が滅びること。それしかないですからね。♪うーん。と言うことは、吉松さんの考える「自然」には、人間は含まれませんか?
本来は含まれているはずなのに、異常繁殖して完全にバランスを失していますからね。音楽にとっても「自然」の反対語は「人為的」でしょう。人の行為と言うのは、自然に反するんですよ。
でも、音楽は所詮「人間の成すもの」ですから、「自然な音楽」はあり得ないということにもなる。うーん、これは大いなる矛盾ですね(笑)。
♪そうですよね。自然な音楽と言っても実は人為的に作っているわけですし。
私にしても、確かに80年代の〈星〉や〈鳥〉の路線はその「自然回帰」なんですが、90年代の〈交響曲〉シリーズは完全に「人為的」の世界ですしね。そもそもの自然観が違うと自分でも思います。
だって、80年代の〈星〉や〈鳥〉は、別に人間と自然を対峙させているわけではなくて、〈朱鷺〉が滅びたって、「だから人間の自然破壊を糾弾する!」と言うような抗議の視線は全然ない。ただ「滅びてしまった。悲しい」というだけです。言ってみれば、無為の美学ですね(笑)。美しいものは、物言わず生まれて、物言わず滅びるから、美しい。花にしろ鳥にしろ動物にしろ。そこで、滅ぼされた相手に対して抗議するとか、化けて出る…なんて言ったら、そりゃあもうバケモノになっちゃう(笑)。
一方、90年代以降の〈交響曲〉シリーズは、完全に人の迷惑を考えずに肥大化する人間そのものになってますから、これは明らかな退化かも知れないですね。そういう点では、80年代の鳥の作曲家ヨシマツと、90年代の交響曲作家ヨシマツとは、別人格と捉えた方がいいかも知れない。
■宗教と哲学
♪吉松さんのそういった自然観や世界観に、何か宗教的な影響はありますか?
日本人の持ってる宗教というのは、基本的に「精霊」信仰だと思うんですよ。「神」とか「仏」ではなく、自然とか世界の中にある「何だか知らないけど畏怖すべきもの」に対する信仰。表向きは仏教だったりキリスト教だったりするんですけど、そこにある絶対神なんか信じているわけではなくて、何だか知らないけど畏怖すべき天照大神様とかキリスト様とか阿弥陀如来様とかマホメット様を拝む。それと同時に天皇陛下とか自分のご先祖様とか有名な歴史上の人物とか、ちょっと立派なものなら山でも岩でも滝でも樹でも拝んで、信仰の対象にするんですよね。
私も、星とか鳥とか天使とか夢とかいろいろ拝んで信仰してますし、シベリウスとかチャイコフスキーとかプログレッシヴ・ロックとかビル・エヴァンスとかも拝んでます(笑)。すべて畏怖すべき精霊なんですよ。その点、何が一番近いかと言うと、それはずいぶん後になって思い至ったんですが、やっぱり「神道」のような気がします。教会やお寺よりは、神社に惹かれますしね。
♪神社ですか。
生まれ育った場所の地名が「代々木八幡」と言うくらいで(笑)、実家のすぐ近くに八幡神社があって、そこに入り浸っていたせいでしょうかね。彫刻家をやっていた母方の祖父が、その神社のご神体を彫ったりしていたし。作曲の構想を練る時の散歩コースも、もっぱら近所の明治神宮の森。神社の境内って静かで落ち着くんです。大体、どんな街でも神社と言うと商業地の中だろうがこんもり森があって人が少なくて静かですよね。ですから、国内で旅行に出ると必ず現地の神社を訪れますね。別に信仰心からではなく、森があって静かだからというだけの理由ですが。
♪日本人としての仏教への関わりといった点は?
日本では、どんな家でも「うちは浄土宗」とか「うちは法華経」とかありますよね。ちなみに、うちは「真言宗」らしいんですが(笑)。ただ、仏教臭さは子供の頃からいまに至るまで苦手ですね。タバコの煙も線香の煙も同じようにダメなんです。でも、祖父が仏師像も彫ったりしていたので、その影響から、高校の時は奈良興福寺の阿修羅像とか京都広隆寺の弥勒菩薩像とかから結構仏教にも興味持ったことはありました。黛敏郎さんの〈涅槃交響曲〉や〈曼荼羅交響曲〉の影響もありましたし。今でも「弥勒菩薩像」は一番好きな造形のひとつです。
今でももちろん墓参りとか法事で寺を訪れることは必然的にありますけど、念仏を唱えるとか焼香すると言うのは実は凄く抵抗がある。仏教的なものを否定する気はないんですが、自分の中には入ってきて欲しくないんです。イギリスでCDを出すことになった時、〈カムイチカプ交響曲〉の5楽章制を説明するのに、「仏教にも〈地・水・火・風・空〉という五大があるし…」とちらっと書いたら、いきなりCDジャケットのデザインに仏陀の唯我独尊ポーズを持ってきて、「こんなのはどうだ?」と言ってきた(笑)。あわてて「NO!。仏教っぽいイメージは絶対やめてくれ!」と即答しました。あの時は自分でもビックリするくらい拒絶反応がありましたね。何でだろう?(笑)♪天使とか星のシリーズなどは、どちらかと言うとキリスト教的なイメージがありますが?
そうかも知れないですね。母親がキリスト教系の女学校出だったこともあって、賛美歌は日常茶飯事に歌ってましたから。新旧の聖書も子供のころからよく読んでましたし、少なくとも賛美歌は頭に染み込んでますね。一時はYMCAなんかにも通っていたので、牧師さんによる説教なんて言うのもさんざん聞いたし、オルガンとかピアノとか弾き始めた頃は、賛美歌ばっかり弾いていたし。だから、音楽を聴き始めてからも、一番体にすんなり入ってくるのはドーリアとかフリギアとかの教会旋法だったですね。日本的な五音音階とかアジア的な旋法と言うのは、演歌にしても民謡にしてもどこか受け付けないし、一方ヨーロッパ的な機能和声や対位法の音楽も違和感がある。いくぶんドローンっぽい持続音を持った賛美歌的なモードの音楽が一番ストレートに身にしみてくるというか。♪教義でなく、音のイメージからキリスト教に入ったということなんでしょうか。
そうでしょうね。西洋クラシック音楽の基本中の基本ですから。そこから入って〈レクイエム〉とか〈受難曲〉に至れば、それこそ名曲がゴッソリあるわけで、アッという間にキリスト教の宇宙に巻き込まれてしまいますよね。それに、キリストの受難劇というのは、あれはもう完璧かつ見事な構成を持った凄いドラマじゃないですか。様々な人間の思惑や苦悩が絡み合って、神の子イエスが十字架に架けられる。奇跡は起こらず、キリストは死ぬ。でも、そこから2000年を超える信仰が始まる。
そのあたりの物語というのは、大作曲家の伝記と共通してますよね。例えば、ベートーヴェンが耳が聴こえなくなり不遇のうちに死ぬ、でもその音楽は不滅の輝きを持って聴かれ続ける…と言ったような。当のキリストやベートーヴェンがどう考えていたか、ということとは関係なく、物語が作られて信仰が広まって行く。宗教と同じですよね(笑)♪そのあたりの作為が嫌いと言うことですか。
いや、キリストにしろブッダにしろ天使にしろ、宗教が生み出した異界のヴィジョンとかイメージは嫌いではないんですけど、それが「権威」を伴った途端、どうしても受け付けない、ということなんでしょうね。私は、亡くなった父や妹の写真には毎日手を合わせるし、お墓参りもちゃんと行きますけど、じゃあ「霊魂を信じますか?」と言われたら「とんでもない!」と答えます(笑)。
むかし、SF作家の誰か、アシモフだったかな?…が、「あなたは空飛ぶ円盤(の存在)を信じますか?」と訊かれて、「童話作家が、熊がしゃべると信じていると思いますか?」と答えたという(笑)のを聞いて、「おお!」と手を叩きましたね。人は、クマが生物学的に言葉を話せないという事実を理解している。でも、「クマさんが、コンニチワと言いました」というイマジネーションの世界で遊ぶんです。同じように、人は世界や自然の有り様を見て「神」のような存在を感じるけれど、神がいないことは知っている。それなのに、そこで偉そうに「いや、神はいます!」と言い出す人には、うさん臭さしか感じない(笑)。♪それは分かるような気がします。
もっとも、その点は「音楽」にしても「科学」にしても同じです。クラシック音楽は好きだけど、「モーツァルトは天才です。その音楽は完璧で、天才のみにしか作りえない奇跡です」などと繰り返す輩に取り巻かれた〈モーツァルト教〉には、うんざりする。無批判に「信じる」輩が権威付けした途端、美しかったものが汚されて「醜悪な顔」になるということなんでしょうね。
現代音楽だって、最初はその新奇でマイナーなヴィジョンが好きだったんですけど、それが増長して「無調であらずんば音楽ではない」と言い張る〈現代音楽教〉という権威になった途端、大嫌いになったし。結局ひねくれてるだけかも知れないですけど(笑)
♪哲学に関してはいかがですか?
哲学というのは所詮、チェシャ猫の詭弁みたいな…と言うか、信者が少なくて宗派になりそこなった宗教…という感じがしなくはないですけど(笑)。デカンショ(デカルト、カント、ショーペンハウエル)が必読書だった世代ではないですが、高校の時はキルケゴールなんか好きでした。構造主義が流行った頃はレヴィ=ストロースとかフーコーとか読みました。お手上げでしたけどね(笑)。
それより、音楽に絡んで言えば、作曲の勉強を始めた頃、音楽の構造を生み出す根源として「一元論」か「多元論」かというのは、作曲家の仲間同士でかなりの論争になりました。つまり、万物の根源は突き詰めれば「ひとつ」に収斂して行くものなのか、あるいは「複数」の真理が存在するのが自然なのか、というようなことですね。
当時師匠だった松村禎三さんの「管弦楽のための前奏曲」という作品が、いわば一元論による究極の名品だったこともあって、本当の真理の真理…根源的な原理の原理…というような音楽の突き詰め方をしたら、そこには「ひとつ」に収斂してゆく一本の線しかあり得ないんじゃないか?という気になったのも事実です。
♪吉松さんはどう見ても多元論派だと思いますけど。
そうなんですよ。私はどう考えても多元論派なんです。それなのに、師匠の影響で「一元論こそが正しいんじゃないか」という不毛な袋小路に入ってしまった。20歳前後のことですから、まだ若かったし。作曲とはひとつの道を究めてゆく〈道〉である…と信じ、ひとつのものを禁欲的にとことんまで追求し、世界のすべてをひとつに切り詰める昇華させて行く。「一元論」で作曲を突き詰めて行くとそうなるんです。で、私も、ひとつの旋律…ひとつの原理…ひとつの形で音楽を作れないか?という泥沼のような行為にはまってしまったんです。おかげで五〜六年近くを棒に振りました(笑)
考えてみれば、西洋音楽と東洋音楽だって、どっちが唯一無二なんじゃなくて多元的に存在しうるものでしょう。男と女だってそうですし、善と悪だってそうですし、音楽だってスローテンポとアップテンポのものがあって、どっちかひとつを選べば良いってものじゃない。私の中にはその頃既にロックもジャズもワルツも邦楽も入ってましたから、そんなもの一元的に収斂できるわけがなかったんです。で、考えに考えた揚げ句、「考えても無駄だ」という結論に達した。人間の考えなんて、そんなもんです(笑)♪なんだか哲学には恨みがあるような口ぶりですね(笑)
考える…というのは、何かとても高度なことのように思えますが、反面「バカの考え、休むに似たり」と言うように、考えない方がマシだと断言できるほど達の悪いことも少なからずありますね。普通に暮らしていて充分幸せなのに「この幸せはいつか壊れるのでは?」と余計な心配をして自分で世界を暗くする。素直に感性のおもむくまま音楽を書いていればいいものを「音楽は進化して行かなければならないのでは?」などと余計なこと考えて破綻する。
それに、哲学と言うのは所詮「言語」という次元から逃れられないでしょう?。「私とは何だ?」「人間とは何だ?」という問いにしても、それは真の疑問ではなくて、「人間」とか「私」とか「何?」とかいう言語上の概念にしかすぎないものが、文法上あり得ると言うだけの理由で組み合わさって「根源的な問い」みたいな顔をしているとしか思えないんですよ。
♪どういうことですか?
つまり、「人間とは何か?」という質問は文法上ありえるけれど、本当は「人間とは何か?」なんて疑問は存在しない。人間が道具として使っている言語に、「人間・とは・何か?」という組み合わせがありうる。それだけの話なんです(笑)。そもそも根本的に存在していない疑問なんですから、その問いに対する答えも存在するわけがない。
例えば、「なぜブタはゾウなのか?」という問いだって文法上あり得るわけですよね(笑)。でも、ブタはゾウではないんですから、それは問いなどではなく、単に言葉の上に発生した虚像にすぎない。それなのに、その虚像の答えを「言語」上で追い求めようとする。これが哲学の実態です(笑)。♪音楽は、その点、虚像ではない、と?
いや、音楽もまた哲学に輪をかけた虚像なんです(笑)。交響曲で例えば〈ト短調のアンダンテ・ペザンテ〉で「人生とは何か?」なんて語り始めますよね。で、アダージョやスケルツォを経て、最後に主題回帰させてそれが〈ト長調のアレグロ・ジョコーソ〉なんかでコーダを迎える。すると、何だか知らないけど「人生ってこうなのだ」という肯定的で解決した結末になる。でも、これはすべて虚構ですよね。何の解決にもなっていないのに、音楽の上だけで「なんか解決して終わった感じ」が作れる。
哲学は、ロジック(論理)で「AはBであるからCである」という文法を作る。そこになにがしかの整合性がなければ解決にならないですよね。でも、音楽は「ドミナントを経てトニカに至る」というのが、初めから〈解決法〉として存在している。ですから、ロジックとしては何にも解決していなくても、「何だか分からないけどまとまった」みたいな解決を感じさせることが出来る。
つまり、哲学や思想は「言語」という怪しい鏡に映った知性の虚像であり、音楽は「聴覚」という怪しい鏡に映った感性の虚像なんです。双方共に、人間の知性および感性のプログラムとしてのバグ(欠陥)にまみれている。それを虚構と知ったうえで使って遊ぶのが人間なんです。そのどこかに真理があるなんて思ったら大間違いです。♪では、音楽に「哲学的な命題」というのは必要ありませんか?
哲学も思想も、言語による「文法」の世界から一歩も出られない。これは誰かが証明したんじゃなかったかな。一方、音楽は、聴覚による「情緒」的反応から疑似的な文法を引き出す。当然ながら「言語」の解決を「情緒」では行なえない。ですから、哲学的な命題を、音楽に投影することは、これは不可能です。♪明快ですね。と言うより「切り捨て御免」という気もしますが(笑)。
いや、そもそも言葉で語れることなら、言葉で語ればいい。音楽になんかする必要ないじゃないですか。「言語」という思考の領域では不可能な、というより全く異なった領域で「感じる」のが音楽なんですから。
■思想と科学
♪思想と哲学…という話が出たついでに、思想についてもちょっと(笑)。ちなみに、吉松さんは学生運動の世代ではないんですよね?
学生運動は、いわゆる団塊の世代ですから、私より数歳年上という感じですね。大学紛争が華やかなりし頃、こちらは中学生とか高校生くらいで。でも、高校に上がった時に同じ学年で「全学連(全日本学生自治会連合)」とか「民青(民主青年同盟)」に入ってた同級生はいましたよ。何かと言うとすぐ「ナンセンス!」と叫ぶだけだったけど(笑)。「それって、ギャグ?」と聴くと本気で怒るし(笑)。私は、音楽をやっているくらいで、完全に軟派でノンポリでした。
*軟派:腕力やマッチョを誇り激しい政治的主張や活動をする「硬派」に対して、詩や文学や男女交際などを好む一派のこと。ノンポリ:non-politicalの略。政治問題に無関心な学生。♪右翼か左翼か?と言われたら?
創作する人間というのは、革新でリベラルな左翼っぽく思われがちですけど、実は基本的に保守的で国粋主義な右翼のような気がするんですよね。創作というのは個人的な行為で、いわゆる社会一般の常識とは違ったところで制作をしているから、そもそも完全な個人主義でしょう。でも、創作の原点は自己のアイデンティティですから、当然、自分という「個」を生み出した風土とか歴史とか宗教とか民族とかに固執せざるを得ない。しかも、ものを創るという事は自己確認と自己保存を伴いますから、最初は「革新」と言い張るものの、すぐに自分の作った作品や様式を安定化させるため「保守」にすり替わる。
ところが、大体芸術家というのは社会的不適応者ですし、芸術行為というのは政治とも経済とも対立する事が多い。だから、当然の結果として社会的な安定を掴みそこなって、保守かつ国粋主義でありながら孤立し、社会や政治を嫌悪する皮肉屋かアナキストになる。私も基本的にはそんな路線じゃないでしょうか(笑)。
♪いわゆるニュー・アカデミズムは?
それは逆に私より数歳年下の世代ですよね。浅田彰の「構造と力」(1983)とか、読みましたけど、私はどちらかと言うとそのころ登場してきたニュー・サイエンス系の方が興味ありましたね。アーサー・ケストラーとかイアン・プリゴジンとかライアル・ワトソンとか。「ホロン」とか「複雑系」とか「フラクタル」とかいう概念が面白かった。全体と部分と、その間を繋げるシステムのイメージが、かなり音楽的にも有効な感じがして。地球を生命体として捉える「ガイア仮説」とか。
要するに、ニュートン以来の還元主義的な「科学」に対して、もう少し人間ぽかったり適当だったりフレキシブルな「遊び」を組み込んだ、まあ、言ってみれば「反動」的な科学なんですけどね。でも、それって要するに、シェーンベルク以来の前衛まっしぐら的な「現代音楽」に対する「反動」に似ていて面白かったんですよ。「12音主義」とか「セリー・インテグラル」とか、チャチな数学を持ち出して知的創作ぶる連中を、感情論や生理的感覚でなく、論理的に論破したかったこともありますし。ですから、最初に出した本「魚座の音楽論」(1987)では、相当それにかぶれてます(笑)。♪それは「思想」ではなく「科学」なんですか?
いや、「科学」に名を借りてはいるけど、かなり非科学的なところもあったりして(笑)、結局のところ「世界をどう捉えるか?」という怪しげな思想ですよね。量子力学あり、生物学あり、天文学あり、数学あり、と色々なジャンルに渡って、今までの既成概念を壊して一歩先に進もうという「パラダイム・シフト」の思想。一歩間違うと、後のオウム真理教みたいな怪しい科学もどき宗教になる。
でも、「哲学」というのが、結局のところ単なる言葉ゲームに過ぎないのに対して、一応は科学的な現象や法則をベースにしているので、現実に音楽の構造とか響きの構成などにも応用が利くことは確かなんです。その路線で「魚座の音楽論」では、人間が持つ調性の感覚を量子力学になぞらえた「音量子論」なんかを提唱しましたし(笑)♪私のような文科系の人間の頭ではぜんぜん理解できませんでしたけど(笑)
いや、発想は単純なんですよ。ある和音がある和音に変化する時、例えばドミナントがトニカに変化する時、人間の心に中に「おっ、いいな」という感覚が飛来しますよね。あれは、電子がエネルギー準位を変えて軌道上を移動する時にある種のスペクトルを発するのに似ているんです。それを量子力学に見立てて説明したんですけど……完全に無視されましたね(笑)。♪いや、そのエネルギー準位だの量子力学だのがサッパリ(笑)
確かに、あまりに画期的な理論すぎて50年早かったかとは思います。発表したのが20年ほど前だから、あと30年くらいしたら誰かが「おお、これは!」とビックリして研究を始めるんじゃないか……と勝手に想像してほくそ笑んでおりますが、無理か…(笑)♪音楽のように人間の感覚や情緒に関わる「感動」みたいなものも、ある種の「科学」で解明できる…とお思いですか?
「すべて解明できる」とは思いませんが、「解明できるわけがない」と思うのも傲慢だと思います。むかし「機能和声」を勉強した時、「なんでこれが数学的な方程式にならないんだろう?」と不思議でたまりませんでした。少なくとも和声法と対位法は完全に「数学」ですからね。ドミナントがトニカに解決する時それぞれの音の間に発生するテンション(張力)の変化を数値化すればいいだけの話ですから、少なくとも数式化はできるはずです。♪数式化に成功したら、音楽に感動する度合いをコンピュータで分析したり出来ますか?
私の「音量子論(仮説)」では、楽曲ごとにテンションの変化をスペクトル解析した「音量子モデル」というのを作るのが最終目標なんです。ちょうど音の波形がオシロスコープで図形になるように、音楽そのものが色と形を伴った図形になってコンピュータの画面に浮かび上がる。そんな未来が来ないかなあ……と(笑)。♪やっぱり考えることが理工系ですねー(笑)
面倒くさい話はここまでにしましょう(笑)。