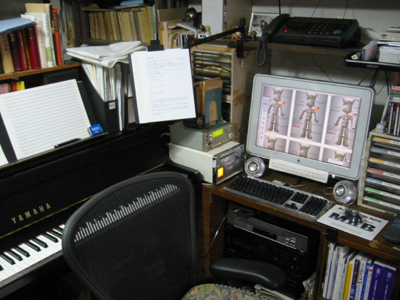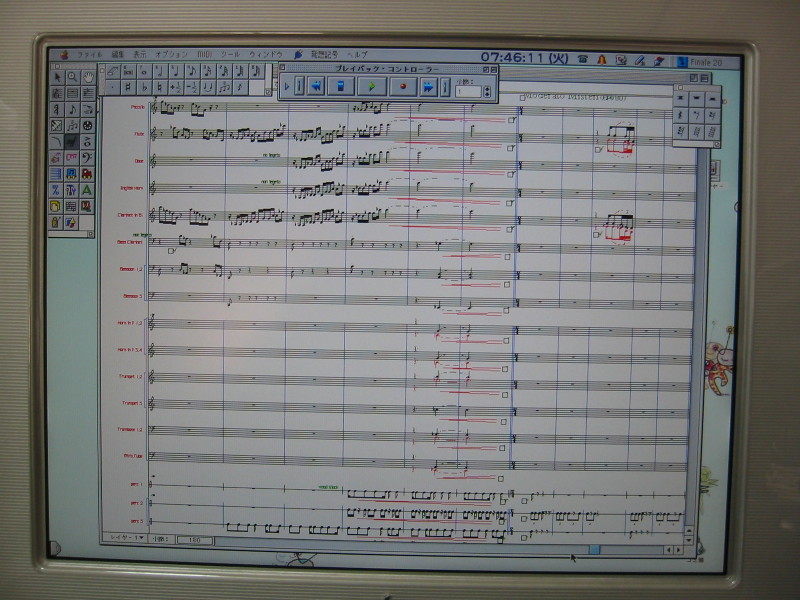★作曲の道具たち...1★
作曲の作業の第一は、まずピアノの前に座ることから始まる。
そして、日々、とにかく頭に浮かんだ楽想、指先からこぼれ落ちる断片を、
ひたすら(とりとめなく)五線紙に書き留めてゆく。
それは、どこか畑にタネをまくのに似ている。
ピアノは、作曲を始めた十代の頃からもっぱら電子ピアノ。
狭い仕事部屋でも入れられるということと、
夜中でもヘッドホンで作業ができる...というのが理由。
(というより、グランドピアノを持てる居住環境になかった、
…というのが正しいかも知れないが)
現在は、YAMAHAのグランタッチ(GDP-1)という機種を使っている。
これは、1997年にピアノ協奏曲(メモ・フローラ)を作曲するに当たって
さすがに電気ピアノじゃコンチェルトは書けないのでは?と思い
なけなしの金をはたいて購入したもの。
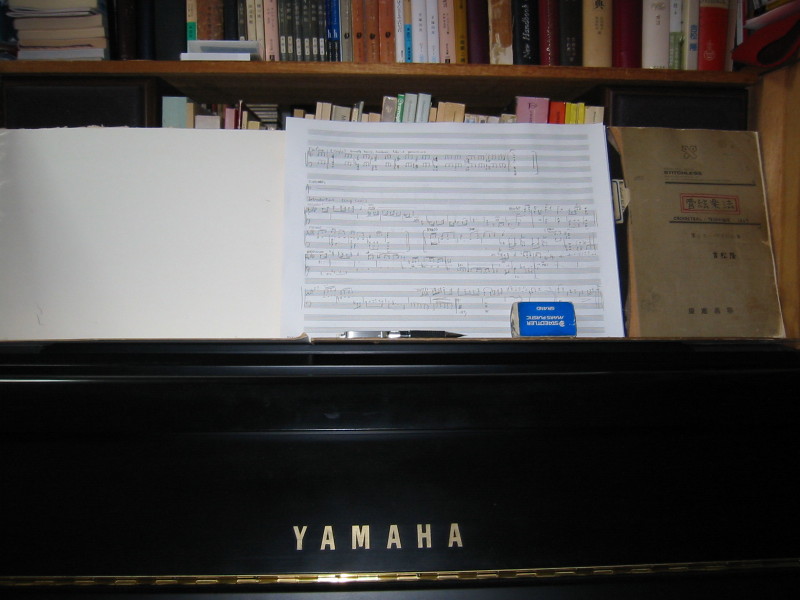
▼作曲の第一段階としてピアノに向かって最初に書いているものは、こんな感じ(写真下)。
スケッチ用の五線紙に、メロディ・ラインやコード進行、リズム
あるいは楽器(時にはイメージとしての言葉や図形)などのイメージや断片を
メモのように書き込んでゆく。
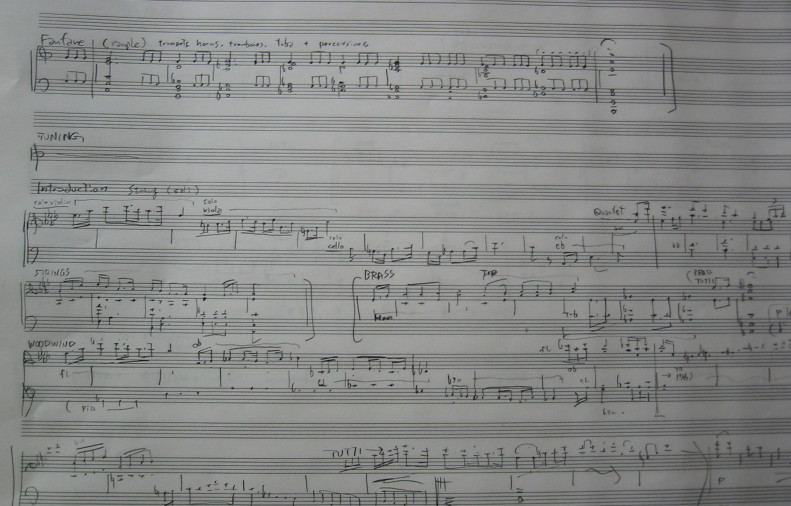
ちなみに、使用している五線紙は、
ECHO TB-18 という、はぎ取り式のB4横組み五線紙。
 ←こうしてスケッチした楽譜は、
←こうしてスケッチした楽譜は、
楽想別に楽譜棚にためておく。
(これは高校生の時に作った手作りのもの
B4サイズの五線紙を収納できる
)
仕分けは・・・
「ピアノ曲」
「室内楽曲」
「アンサンブル」
「コンチェルト」
「オーケストラ」
「そのほか未定」
「使用済み」・・・ という7段である。
そして、スケッチした楽想がある程度まとまると、
それがどういう編成か(オーケストラ曲かピアノ曲か
アンサンブル曲か)....どんなイメージの音楽か....
なんというタイトルか....全体はどういう構成か.... などを決定し、
具体的な作品として構想し始める。
*
かつて(1990年代まで)は、
ここから手書きスコアへの奮闘が始まったわけだが、
現在では、素材が集まったところで、コンピュータ(Mac)に入力してゆく作業が始まる。
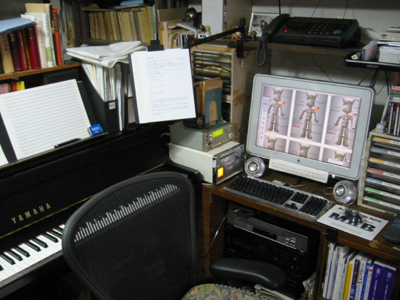
「コンピュータ」というと大げさだが、同じキイボード入力だからピアノと同じ。
作家にとってのワープロ(昔ならタイプライター)のようなものである。
写真上(2003年)のシステム構成は、
Mac G4cube 500Hz(OS 9用)と22インチ液晶ディスプレイ。
これに、デジタル音源(YAMAHA MU2000)がUSB で接続してある。
最大64パート(同時発音数128音)鳴らせるので、3管編成フル・オーケストラの曲でも
作曲のために試しに鳴らしてみるだけならこれ一台でほぼOKである。
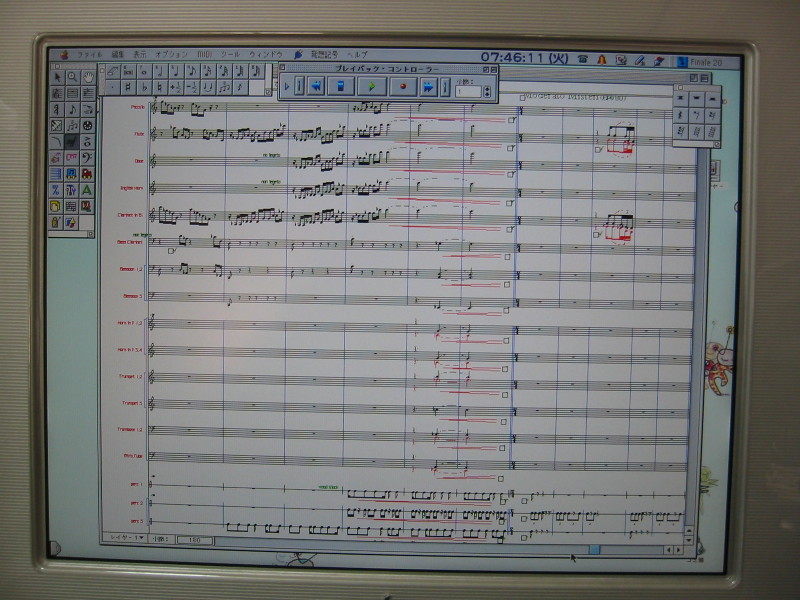
▲作曲している時の画面(写真上)。
使っているのは「フィナーレ(Finale)」という楽譜作成ソフト。
このソフト、楽譜を作成し浄書するのが専門の仕様ながら、
入力した音を即(しかも指定した楽器の音色で)鳴らしてくれるのがなんとも有り難い。
これはもう「楽譜書きを手伝ってくれる助手」と「お抱えのオーケストラ」がいるようなもの。
仕事は早いし文句は言わないし給料もいらないし(笑)、 便利このうえない。
ただし、時々フリーズしたりするのがちょっと難点(意外と気分屋だったりする)なのだが...。
Top
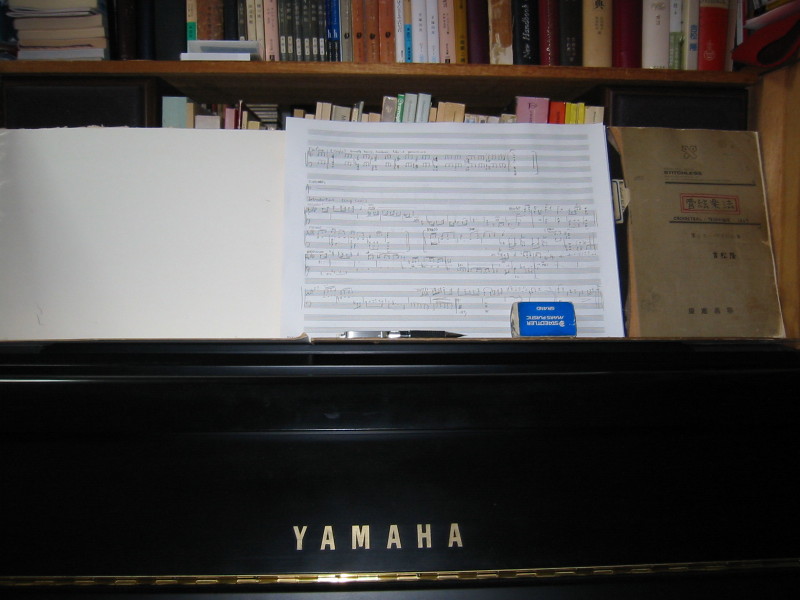
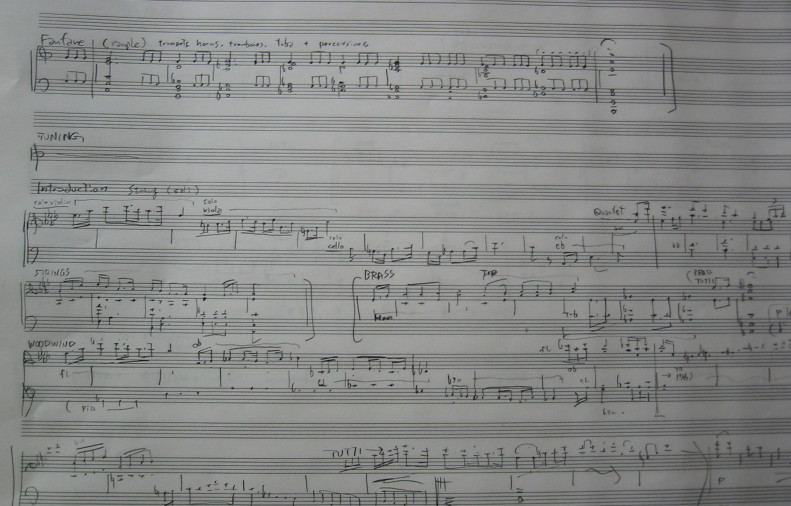
 ←こうしてスケッチした楽譜は、
←こうしてスケッチした楽譜は、