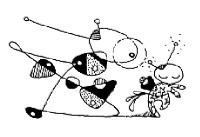 復刻!新世紀末CDノート
復刻!新世紀末CDノート
(2000年版)
★これは音楽現代誌に2000年1月より連載された
「新世紀末CDノート」のオリジナル復刻版です。
2000 / 2001 / 2002 / 2003
第1回「気がつけばアトムの時代」
第2回:クラシック第4世代宣言
第3回:右脳・左脳・電脳。トリオ・ザ・脳の時代
第4回「怪しい日本の私」
第5回:オーケストラ外形標準変形法構想
第6回「回想のニューヨーク1981」
第7回:絶対音感日記てけてんてん
第8回:ヒトゲノム解読は21世紀を救うか?
第9回「夏が来ればグチり出す...」
第10回「絶対安全夏日記」
第11回「鳥について」
第12回:絶対安全音感グルメ日記
第1回「気がつけばアトムの時代」
とうとう2000年である。数えではまだ20世紀だが、新しいミレニアム(千年紀)を迎えて「世紀末」というのも何なので、この連載のタイトルも「新世紀」CDノートとなって新装開店(それにしては、中身は何にも変わっていないが)。お見知り置きを。
*
それにしても新しい世紀を迎えるというのは、単なる数字の上こととは言え感慨深いものがある。昭和30年代のまだ戦後の貧乏臭さが街にたっぷり残っていた東京で少年時代を過ごした私としては、「21世紀」といったらすなわち鉄腕アトムが空を飛んでいる「SF的未来」のことだったのだから。
あのころ想像していた2000年と言ったら、電車は全部モノレールになっていて、自動車は高速チューブの中を走るか空を飛んでいて、ロボットが家庭や町にあふれ、ロケットで月や火星に簡単に旅行できるようになっていて、世界は戦争のない統一国家「地球連邦」になっている、そんな世界だった。
しかし現実には、月旅行ロケットは存在せず、自動車が空中に浮かぶ気配はなく、地球連邦など夢の夢、ロボットもまだ実用には時間がかかりそうだ。
ちなみに、鉄腕アトムの世界では1974年に原子力超小型電子計算機が発明され、1982年にはC・ワークッチャー博士と猿間根博士(しかし、なんちゅう名前だ!)により人間型ロボットが誕生することになっている。アトム誕生は2003年4月7日だ。
それにしても、50年前の人間がタイムマシンで現在の東京に来たら、まず何に驚くのだろう?
確かに新宿高層ビルあたりは未来都市の風景ではある。首都高速道路のトンネルをオレンジのライトを浴びながら疾走(ただし渋滞がなければの話だが)すれば、気分は「未来」と言えなくもない。
あるいは、コンピュータがここまで小さくなって世界中の情報にアクセス出来るようになった状況に驚くべきだろうか。それより妙チクリンなファンションに身をまとった若者たちが携帯電話で空中の仲間としゃべっている異様な風景の方に驚くべきかも?
いや、テレビや映画に氾濫しているコンピュータ・グラフィックスの映像。あれこそが一番目に見えて「未来的」か。コンピュータ・ゲームやテレビのCMなどで「どうやって撮ったのか分からない映像」が次々と乱舞するのは、かなり刺激的な光景だし。
転じて「音楽」はどうだろう?
少なくとも一番耳にショックなのは、これもコンピュータから弾き出されるデジタル・ビートなんじゃないだろうか。エレキ・バンドのバックで叩き出されるドラム・セットの8ビートが最も刺激的だったビートルズの時代の耳からすると、現代のポップスで当たり前のように使われているドラム・マシンによる16ビートのリズムは、薬物のように直接的。まさに足に電極をつながれたカエルのように下半身を直撃する。
それに比べると、かつての「前衛音楽」はあまり未来の音楽として有効な子孫を残していないなあ。昔のSF映画で「未来の音楽」と言ったら必ず登場していたピュイーンとかブオーンとか言う不可思議なアナログ的電子トリップ音楽は、最初はピコピコ鳴いているだけの鬼っ子にすぎなかったデジタル・ビートに駆逐されて絶滅してしまった感があるし、トリップ音楽はむしろアコースティックなサウンドによる「ヒーリング・ミュージック」に変異してしまったし。
無調音楽こそが音楽の未来だと確信していた50年前には、「見ていたまえ。今に新聞配達の小僧も12音で口笛を吹くようになるから!」などと豪語する作曲家もいたのだが、その予言は残念ながら外れてしまった。同じころ「今にゾンビからインド人までデジタル・ビートでダンスを踊るようになる!」などと予言したらそれこそ大笑いだったろうが、こっちの予言は成就している(信じられない人は、マイケル・ジャクソンの「スリラー」とインド映画「ムトゥ/踊るマハラジャ」を並べて見て、大笑いしながら納得すべし)
つまるところ、道具や機材は十年単位で進化するが、人間本体は千年単位でも全く進化しないということなのらしい。
100年前に比べれば、人間は空を飛ぶようになったし、世界各地の映像を自由に見ることが出来るようにもなったし、何千キロ離れた人間と話が出来るようになった。しかし、それは道具に「乗っかっている」だけで、人間本体は一万年ほど前からずっと「毛のないサル」のままなのだ。その辺を誤解しちゃあいけない。
かくして、音楽のどこに「未来」があり、どこに「不変」があるのか。それを探る長い長い旅は、まだまだ当分は続くわけなのだ。
*
 ◆向山佳絵子「白い風景」(ソニー・クラシカル)
◆向山佳絵子「白い風景」(ソニー・クラシカル)それにしてもほんの10年ほど前までだったら、クラシック系の演奏家が生きている作曲家たちに新しい作品を委嘱して新しいアルバムを作ると言ったら、「新しい・でも分からない・売れない」の3拍子揃った現代音楽ものとまず決まっていたものだ。
ところが、向山佳絵子さんのこのアルバムを聞くと全然違う。わたくし吉松隆を筆頭に、三枝成彰、小六禮次郎、岩代太郎、上野耕路、大島ミチルという「現代の日本に生きている現役の作曲家」に新作を委嘱して仕上げた1枚ながら、いわゆる現代音楽臭はゼロ。
だからといってポップス系というわけでもなく、編成は色々ながらテイストはとことんクラシック。それでありながら「新しい・でも聴かせる・売れる」を意識した作り(実際にCDが沢山売れるかどうかは別にして)なのだから面白い。時代は変わったものだなあとしみじみ感じてしまう。
◆シマノフスキ歌劇「ロジェ王」ラトル(東芝EMI)
ただクラシックの場合は、未来が未来だけの中にあるのではなく、過去の中にこそ未来があることも常に思い知らされる。マーラーがリバイバルを果たし、ピアソラが発見されたように、レパートリーは「新しく生まれる」だけではなく「過去から見つかる」ことが多いからだ。
近代ポーランドの作曲家シマノフスキのこの作品も、蔵から古ぼけたスコアを引っ張り出してみたら、意外な名品。まさしく「お宝発見」である。「アトムの時代」の新しい音楽ではないが、アトムの時代にも聴かれる「クラシック」がひとつ増えたと言っていいだろう。発掘者に拍手。
第2回:クラシック第4世代宣言
日本における「クラシック音楽」の発展史は、「進化の歴史」というより、むしろ「享受の歴史」と言うべきだろう。
正式な西洋音楽伝来は、それこそ信長や秀吉の時代にさかのぼるが、現存している日本の「クラシック音楽人」たちを、その享受法や取り込み方から俯瞰してみると、ほぼ4世代ほどが浮かび上がってくる。
*
第1世代は、西洋の異文化としてクラシック音楽を発見・吸収した最初の世代。西洋に対する無知と祖国日本に対する自賛も手伝って、「毛唐(これは今でも差別用語として機能しているんだろうか?)による不思議な音楽」と珍しがり過小評価したり、逆に、光り輝く西洋文明の象徴として過大評価したりと、色々なパターンがあったように思われる。
中には「こんなもん、おれにも出来る!」と西洋文化制覇を夢を見てヨーロッパに立ち向かった先人たちもいたが、残念ながらその夢は孤立か孤高に終わり、後の世代による再発見と再評価を待って眠っている。
続く第2世代は、西欧信奉の一環としてクラシック音楽を崇拝した世代。「西洋クラシック教」という宗教の日本における伝道者であることを最高の幸せとして、教祖(巨匠たち)が差し出す芸術を平身低頭して押し頂き拝聴する、徹底的に受動的な信者たちとでも言えるだろうか。
しかし、そこに妙な特権意識と優越感を感じていて、日本人の西洋クラシック音楽へのアプローチ(演奏)には徹底的に懐疑的か否定的。そのくせ、自身が西洋クラシック音楽を聴いている日本人であるということの矛盾には全く気がつかないか目をつぶっている。
続く第3世代は、「聴いているだけじゃなくてボクも(アタシも)やってみたい」と、自分から行動を始めた能動的世代。国際コンクールに入賞して「世界のXXX」(笑)と呼ばれるようになり、復興とげた戦後日本のジャパン・マネーをバックに海外で活躍し、「経済大国日本」の先兵となった栄誉ある世代である。
しかし、所詮「日本人にしてはよくやるじゃないの」と言われる「被征服民」の立場でしかないと気付いた時、「なぜ日本人である私が西洋音楽をやるのか?」という「答えのない問い」に責め立てられる悩みを持つ。
*
そしていよいよ第4世代。これは、とりたてて西欧信奉もなく、ただ好きだから音楽をやっていて、それが偶然クラシック音楽だったというだけの、思考が透明な新世代。
なにしろニューヨークだろうとロンドンだろうとパリだろうと若者がヒョイと小遣い銭で出かけられる時代だから、清水の舞台から飛び降りるような(例えが古いな)気持ちでヨーロッパに向かった旧世代のハングリー精神など想像しようもなく、ヨーロッパ文化に対してのディープな思い入れも希薄。
ゆえに、西洋音楽だろうとロックだろうと日本の伝統音楽だろうと、そこに根本的な違いは見いださず、やる理由は「好きだから」意外に存在しない。それは聴く側も同じで、日本人の音楽家によるクラシックが本場ヨーロッパものでないのは当たり前と承知しているので、隣のお兄ちゃんやお姉ちゃんみたいな音楽家がベートーヴェンやドビュッシーを弾いていても別に気にならない。
ただ、ロックでも伝統音楽でもコンピュータ音楽でもいい時代に、敢えて「クラシック音楽」をやる、という志向が、どのくらい説得力を持つか、そして創造としてどれほど機能しうるか、ということは大問題。
*
以上は、日本における「音楽家たち」の4世代であると同時に、「聴衆たち」の4世代であり、「作曲家たち」の4世代でもある。
単に年代で区分すれば「祖父の世代」「父の世代」「息子の世代」「孫の世代」と言えなくもないが、問題は年齢でなく「意識」にあるので単純に年代で割り切れないし、特に1234と進化しているとも思えない。
しかし、時代が確実に第四世代へと移行していることだけは確かだ。そして、この世代が「ハングリー精神」や「上昇志向」あるいは「前衛意識」や「愛国心」などで音楽をやっているのではないことは自明の理。
つまり、前の3世代には存在しなかった(そして、前の世代には理解不可能な)新しい「衝動」が彼らを突き動かしていると言うべきなのだろう。
私自身、自分がこの世代の先兵であると言う自覚とともに、この世代に期待している。文明開化の推進者だった第1世代、戦後民主主義の落とし子と言うべき第2世代、バブルの時代の申し子である第3世代に続いて、ようやく自分たちの等身大の言葉としての「クラシック音楽」に気づいた世代だからだ。
*
 ◆デューク・エリントンの時代から/トルヴェール・カルテット(東芝EMI)
◆デューク・エリントンの時代から/トルヴェール・カルテット(東芝EMI)そんな第4世代を代表するグループのひとつが、このトルヴェール・カルテット。サックスのカルテットと言ったら、クラシックなんだかジャズなんだかロックなんだか吹奏楽なんだか不明というまさに未開拓の新分野である。しかし、これを逆手に取れば、クラシックでもジャズでもロックでも吹奏楽でも何でも出来るということに気付く。これぞクラシック第4世代の思考である。
20世紀の俯瞰と称してクラシカルなラヴェルの弦楽四重奏曲からデューク・エリントンのジャズ・ナンバー、そしてわたくし吉松のロックもどきカルテットまでを吹きまくるその意気やよし。しかし、たぶん第2世代の評論家などには、どこをどう評価していいのやらまったく理解できない世界だろうなあ。
◆ジャポニズム〜世界の作曲家の目に映った日本/小川典子(BIS)
続いては、近代ヨーロッパの作曲家たちが「異国ニッポン」への想像力をふくらませて書いたピアノ曲を集めた不思議な1枚。
プッチーニの「蝶々夫人」を筆頭に、映画「将軍(ショーグン)」や「007は二度死ぬ」などなど、外国製のジャポニズム作品は、当の日本人から見ると「何これ?」と言うしかない怪しげな世界なのが多いのだが、ついに日本人女性ピアニストが「吉原帰り」だの「お茶屋」だの「日光の哀しみ」だの「芸者の踊り」だのというタイトルのピアノ曲をぬけぬけと海外でCD録音する時代になったので御座候。
一昔前なら国辱もの(?)の企画だが、意外と美しいサウンドにすらすらと聴けてしまうのが楽しい。ついでに、浴衣姿で微笑んでいる小川典子嬢のジャケットが可愛い。
第4世代万歳!
第3回:右脳・左脳・電脳。トリオ・ザ・脳の時代
コンピュータというのは「人間の脳の外に出来た新しい大脳皮質」であると言った人がいたが、うまいことを言うものだ。
人間はその進化の過程で、スペアとして存在していた二つの脳をそれぞれ感性と知性とに分担させた。それが、直感をつかさどると言われる「右脳」と理屈をつかさどると言われる「左脳」ということになっている。
おかげで「感性」と「知性」とか、「ホンネ」と「タテマエ」とか、「善(天使)」と「悪(悪魔)」などなど二重人格を頭の中に植え込んだことになるのだが、処理能力を分担させることで、地球上の生物中屈指の高度で複雑で多面的「思考(演算)能力」を手に入れたことは確かだ。
だから、そろそろもうひとつ外部に新しいスペアの演算脳を作って、これに違った処理を分担させるというのは、進化として正当かつ必然的な方向と言えなくもない。
つまり、20世紀後半以降の人類は「右脳」「左脳」に加えて、コンピュータという「電脳」を手にし、この新しい3番目の脳を加えた〈3つの脳〉で思考する新種に進化を遂げつつあるということなのだ。
*
確かに、作曲などという行為をやっていると、右と左の脳の間を演算が行き来している様子を実際に体感できるような気がする。
例えば、曲の最初のイメージが「透明な悲しみ」とか「苦い怒り」などいう漠然としたとらえどころのない「感じ」として芽生えると、この感覚的すぎて言葉では説明不可能な素材に対して「感性」が右脳の中でグルングルンと演算している状態になる。
一方、それを「交響曲」とか「アンサンブル」などの作品として具体化するには、音の素材やシステム、楽曲の構造などに対する客観的かつ具体的な構想が必要。すると、言語(タイトル)や形式を思考する「知性」がギュンギュンと左の脳の中で演算を始める。
しかし、この過程でどちらか一方に偏った演算を続けてはいけない。直感的なイメージだけでは「実際に演奏される楽曲」を構成できないし、逆に主知的な構造だけでは「演奏され・聴かれ・心を動かす」という音楽本来の形を失ってしまうからだ。
と言うわけで、この2つの演算脳の間をスイッチを切り替えるように交互に動くことで、作曲は進められる。感性で発想し・それを知性で具体化し・ふたたび感性でイメージとして構成し・もう一度知性に戻して構造として構築する…というように。
そして、これに最近「電脳」が加わった。
この電脳、具体的にはスコアを「紙」ではなく「モニター画面」上の楽譜に書き込み、仮作成の音を「ピアノ」でなく「デジタル音源」でプレイバックしながら校正してゆく、という作業の中で登場する。
別に彼に音を選んでもらうわけではないので、作曲内容にまで関わる本質的な変化はないが、「紙の上にペンで音譜を並べ」「自分でピアノを弾いて楽曲をチェックする」という旧来の方法では為しえなかった幾つかの利点がある。なにしろ、今まで五線紙にもペンにもピアノにもなかった「演算脳」という奴がくっついているのだから。
例えば、手書きのスコアでは「初稿」「改訂稿」「修正稿」などと作ってゆくと、そのたびに全部スコアを書き直すか、修正部分をペンで塗りつぶして訂正を書き込むしかなかった。しかし、電脳五線紙上ではカット&ペーストでいくらでも修正・改訂が可能。けっこう膨大に書き直しを繰り返す私などにとっては、これは極めてありがたい。
そして、書いた楽譜を即座にプレイバックして鳴らしてみることが出来るのも最大の利点。生身の演奏家ではないので、夜中に「ちょっと、この2小節だけ鳴らしてみて!」という無理難題も可能。音が違ってたり#♭が落ちてたりする凡ミスも一発で耳で分かる。
しかも、特定のフレーズを書き出したりスコアをまるまる書き写したりというルーティン・ワークはノー・ミスで瞬時にこなすし、「転調」とか「移調」などという機械的な作業にはすこぶる強い(当たり前だ。機械なんだから)。気に入るまで何度でも何度でもやり直しが出来るし、文句一つ言わない。
おかげで最近は、2つの脳だけが入った自分の脳髄だけでは仕事ができなくなって、電脳と自分とが入った「仕事部屋」が脳髄と化してきている。つまり、電脳込みで「作曲家ヨシマツ」なのであって、外に出てしまったら脳が一ヶないに等しい状態なわけだ。そもそも生身のヨシマツくんじゃ、転調ひとつできないしね(笑)。うーん、これは、ちょっとアブナイ…か。
でも、「機械」と「人間性」とを相容れない対立する項目と見る感覚はもう過去のもの。色々な軋轢はあるのだろうが、今まで2つの脳で2面からだけだった人間の思考が、これからは3面になる。その方がずっと楽しみだ。
さて、3つの脳を得た新種の人類はさらなるどんな未来を持つのだろう?
*
◆七人の侍/早坂文雄の芸術・管弦楽作品集(キング)
それにしても、20世紀を迎えた時は王侯貴族や帝国主義やロマン主義が「19世紀的で古い!」と言われたものだが、もうすぐ21世紀。今度はモダニズムや科学万能主義や前衛主義なんかが「20世紀的で古い!」と言われるようになるのだろうなあ。楽しみだなあ。
そんな時代をひかえて、わが国作曲界の大先輩である早坂文雄の「古さ」は古典(クラシック)へと超然と昇華し始める。いつまでも「ゴジラの伊福部昭」と並んで「七人の侍の早坂文雄」という枕詞付きなのは心外かも知れないが、誰もが「ああ、あの曲の…」と言える一曲があるのは強力。皇紀二千六百年記念の「序曲ニ長調」や大作「管弦楽のための変容」に、あの時代の日本が聴こえる。
◆スクリャービン/ネムティン補筆「神秘劇序幕」(ユニバーサル)
そして、こちらはスクリャービンがスケッチだけを残した遺作「神秘劇」を、その死後ロシアの作曲家ネムティンが26年をかけて補完完成させた超然たる大作。
ピアノとソプラノと合唱付オーケストラによる誇大妄想狂的でエロティックな実にスクリャービンらしい神秘サウンド(形態模写ならぬ作風模写と言えなくもないが)が、CD3枚組でたっぷり3時間鳴り渡る。しかも、「宇宙」「人間」「変容」というこの3章も、全12章からなる「神秘劇」全体のほんの序幕にしか過ぎないと言うのだからものすごい。
「右脳」「左脳」「電脳」の3脳も、全12脳のほんの序幕なのかしらん?
第4回「怪しい日本の私」
日本人が「クラシック音楽」をやることについては、時々考え込んでしまうことがある。
いつだったか海外に住む某日本人エリート氏とクラシック音楽の話になり、日本のオーケストラや若い音楽家たちの海外紹介を頼んだところ、「伝統音楽や現代作品のような日本固有のテイストが出せるものならともかく、日本人がただベートーヴェンやモーツァルトなどのヨーロッパの音楽をやることについては、何の興味も持たれないと思う」と言われたことがひっかかっているせいだろうか。
くだんの彼は「ナショナル(民族的)であることこそがインターナショナル(国際的)である」という誰だかの言葉をあげ、「日本人的な臭いをなくすことを国際化だと思ってるのはとんでもない間違い。洋服(つまり西洋風の服)を着て流ちょうな英語しゃべって外国に溶け込んでも、それは〈国際的〉になったとは言わない。〈国籍不明〉になっただけ」と力説する。
でも、そう言う当の彼自身が、洋服を着て流ちょうな英語をしゃべっているし、日本的でありたくないと思って海外に出て仕事しているわけだから、そのあたりの矛盾についてはどう考えるべきなのだろう? 「クレタ人はみんなウソつきだ」と言うクレタ人に出会った時に似た、「ん?」という感じが頭をよぎる。
そもそも日本は、明治時代に「近代化イコール西欧化」という大原則のもと、この国籍不明の道を邁進し始めたわけだが、その時点の「西欧化による強国化」という図式と、その勢いに乗った「アジア統一(侵略)」という力技は、敗戦という鉄槌によって完膚無きまでに叩き潰されたのはご存知の通り。
続く「経済による富国化」という路線も、膨らむだけ膨らんだ後であえなく崩壊し、今さら「日本的」と言われても、「そもそも日本というのは何なんだっけ?」と首を傾げざるをえなくなっているというのが実情だ。
海外で「日本」をアピールするのは、いまだに怪しげな、そして日本ではとうに絶滅してしまっている過去の亡霊としての「おみやげジャポニズム」だし、前衛をうたった現代音楽も、海外公演では書道で大書された「日本」とか「無」あるいは「ワビ・サビ」や「日の丸」などのイメージをバックに、かなり怪しげなインチキ・ジャポニズムをまき散らしていたのは記憶に新しいし。
そう言う私も昔、ニューヨークのオフ・ブロードウエイで怪しげなジャパニーズ・ミュージカルを上演するのに加担したことがある。現代ロックに尺八や和太鼓を組み込み、サムライや禅や茶道をちりばめた奇妙な(かなりインチキ臭い)舞台だったのだが、アメリカ人には受けた。
しかし、日本が理解されたわけでもなく、日本の若者としての我々がやりたいことでもないものが賛辞を受けて、いったいどんな意味があるのだろう?と、かなり悩んでしまったことは事実だ。
それでも、どんなに努力しても欧米人に比べると背が低く胴長短足の我が日本人俳優たちは、手足が長いアメリカの俳優たちに舞台栄えという点でかなうことはなく、黒髪で切れ長の目をした日本人女優は金髪で白い肌の女性が持つ強烈な女神性を(もちろん外見だけの意味でだが)発散することは出来なかった。そんな中では「日本人だろうと黒人だろうと同じ人間だ」とか「人種は関係ない」という言葉には何の意味もない。
しかし、コンプレックスでしかないはずのそんな「日本人的風体」も、例えば着物姿とか甲冑姿になると、俄然ピッタリ来るのだから不思議なものだ。洋服姿では単なる貧相な東洋系チンピラにしか見えない青年たちが、和服になるとなぜかサマになる。剣道や空手の手もまた、実際の上手下手に全く関係なくヨーロッパ系俳優よりアジア系俳優の方がはるかに強そうに見えるのである。
さて、ここからどんな結論を導き出すべきなのか、はっきり言ってよく分からない。
近代日本は「エセ西欧人」になるべく邁進してきたエセ文明なのだと非難してみても、もはや日本は「インチキ日本人」を作ることしか出来ないまでに日本を喪失してしまっているのだから。
まあ、確かに登録商標としての一人前のアーティストになってしまえば、「自分は日本人である前に一人の人間である」と言い張ることは出来る。しかし、「個人」がただ一人民族から遊離できるわけもなく、足の長さや鼻の低さひとつを取ってみても民族や歴史という背景を背負った「人間」にはかなわないことも事実なのだ。
21世紀に、日本はどこへ行く?
エセ西欧人として海外文化の中に卑屈に紛れ込み続けるか、それともインチキ日本人としてオミヤゲを売り続けるか? どっちも相手にされそうにないような気がするが…
*
 ◆すばるの七ツ/吉村七重プレイズ吉松隆(カメラータ・トウキョウ)
◆すばるの七ツ/吉村七重プレイズ吉松隆(カメラータ・トウキョウ)その点からすると、邦楽というのは一見もっとも「純日本的」で、そういう悩みからは無縁のように見える。しかし、実は「現代日本的」でないことが大問題でもある。
だからと言うわけではないが、私と二十絃の吉村七重さんとの共同制作で生まれたこの一枚で、箏はハープともピアノともつかず、また和楽器とも民族楽器ともつかない不思議なサウンド宇宙の中を浮遊しつつ、現代の日本人にしか出来ない音楽を広げてゆく。
別に「邦楽」だとは思わず、現代の東京が生み落とした一つの「民族音楽」と思えばいい、というわけなのだが、それにしても、作曲家はこうやって「日本」や「現代」や「西欧」の間を揺れられるから面白い。彼女の美しい音を伴って、私の4曲は日本から遊離し、日本上空を夢のように漂う。
◆ベートーヴェン交響曲第6番「田園」ほか/沼尻竜典指揮トウキョウ・モーツァルト・プレイヤーズ(エクストン)
一方、日本のオーケストラによるベートーヴェンやモーツァルトというのも、同じように現代の日本人にしか出来ない音楽ではある。今回スタンダードな名曲でCDデビューした沼尻竜典指揮トウキョウ・モーツァルト・プレイヤーズのこの一枚にも、若い世代の技量の確かさと共に日本的な真摯な姿勢とが聞こえるからだ。
そこで、東京(正確には三鷹)から生まれた彼らの未来に期待しつつ、冒頭の問いにはこう答えよう。
「指揮者もオーケストラも全員日本人でいながら西欧クラシック音楽を究めるということこそ究極の日本的文化だ」と。
なぜなら、日本人以外にはそんなこと絶対出来っこないのだから。
第5回:オーケストラ外形標準変形法構想
先日、お酒で少し酔っぱらった某オーケストラ関係者から「オーケストラって、果たして21世紀の日本で生き残れるんでしょうか?」と暗い顔をして尋ねられた。「いえ、それより何より、クラシック音楽って21世紀の日本で存在できるんでしょうか。センセ、どう思います?」
うーん、確かに、東京だけで十ものオーケストラがあって、それなりの活動をしている。それは、凄い。でも、今のままのあり方で21世紀にオーケストラが生き残れるとはちょっと思えない。そもそも百年以上も前の、それも外国で書かれた音楽ばかりを、楽譜見ながら演奏する、という形態のコンサートに、現代人が興味を持ち続けると思う方がおかしいのだから。
と、そう言うと、「じゃあ、どうしたらいいんですかあ?」とからまれたので、仕方なく酒の勢いで思い付くままのアイデアをまくし立てた。ただし、ほとんどSFの世界なので念のため。
*
まず、生き残りをかけた最初の一歩は、強力な企画プロデュース・セクションの開設から。それも、単なる企画制作部ではなく、トップにはそれこそハリウッドのプロデューサー・レベルの人材を投入し、その下に様々なジャンルに渡る専門家たちによる〈頭脳(アイデア・企画の発案)集団〉と〈手足(実際に公演を具体化させる実動部隊)集団〉セクションを置く。
そして次に、専属の作・編曲家たちによる〈制作工房〉を置く。百年以上も前に書かれた曲をそのまま演奏する遺産の食いつぶしに未来はないが、20世紀の作曲の惨状を顧みるとき、作曲家という社会不適応者が書く新作に未来を託すのもまずい。で、アレンジ・セクションを強化し、さまざまな音楽をコンサート・ホールで上演できるように変形させる〈工房〉を作るわけだ。
なにしろどんなジャンルでも一番動くのは「新作」であるというのが鉄則。つまりオーケストラが生き残る道は、ホールでしか聴けない新しいレパートリーの開発しかない。この〈工房セクション〉の成否こそが最大のポイントだ。
ただしこれも、作曲家のちゃちな想像力だけに任せるなら、やるだけ無駄。まずプロデューサーが企画をたて、頭脳集団と一緒に徹底的な討論と検討を行ったうえで細かい注文書を作成し、作編曲家に発注する。要は、聴き手や演奏家が真に聴きたいと望み、かつ未来のコンサートのメイン・ディッシュとなる新作を本気で作ること。発想を転換さえすれば、クラシック音楽の世界は西欧数百年の歴史が生み落としたネタの宝庫なのだから。
一方、オーケストラにはスタイリストを付け、オーケストラ団員の服装を刷新する。そもそもオーケストラは舞台上に座って演奏するだけなのに、その姿を最低限「見せる」ということを考えなさすぎる。とは言っても、キンピカの服を着ろというのではない。作曲家の経験から言わせてもらえば、オーケストラというのは全員が私服で演奏しているリハーサル風景こそが、一番個性的にして一番チャーミングなのだ。そのことに気付き、目覚めたまえ、オーケストラの諸君!
そして、その中から、コンサート・マスターの黒サングラス氏や第2ヴァイオリンのミニ・スカート女史、3番ホルンのパンクのお兄ちゃんなどにそれぞれファン・クラブができ、彼女(彼)を見る特別席にプレミアが付いたりすればしめたものだ。
それより何より、東京に十もオーケストラがあって、それぞれが中途半端に古典をやったりポピュラーものをやったり現代ものをやったりするのは効率が悪すぎる。オペラ専門のオーケストラと古楽専門のオーケストラ、そしてポップス・オーケストラと現代もの専門のオーケストラなどに分化すべきなのだ。
そのためには、オーケストラ相互の団員のトレードから、レパートリーの開発や著作権処理の調整、および企画やスケジュールについてを統合的に情報整理する〈プラット・ホーム〉的な機関も是非欲しい。海外との折衝や著作権など法律上の処理も含むので、できれば国営がベストなのだが、現在の日本のお役所レベルでは絶望的だろうなあ。
そうそう、ついでにもっと絶望的な夢を言うなら、皇居近くの現在国立劇場のあるあたりを潰してアート・センターとし、フィルハーモニック・ホール、国立オペラ劇場、古楽と現代もの専門の中ホール、およびリサイタル・ホールを林立させ、さらに古典芸能専門劇場、能楽堂、寄席などの劇場を含む大江戸会館(笑)をその周辺に、さらに美術館や演劇用の大小劇場、芸術センターをその並びに建設してしまおう。
フィルハーモニック・ホールでは常時オーケストラが、国立オペラ劇場では常時オペラが上演されているので、東京の夜はこのセンター周辺に来るだけで、オペラやシンフォニーから現代音楽やリサイタル、さらにミュージカルや芝居から落語まで、自在に鑑賞することが出来る。とにかく現在のように、ホールが東京のあちこちに散らばっている現状だけは、何とかしなくてはダメだ。もちろん、それ相応の交通機関の整備をしなければならないだろうけど…。
しかし、これは、ゴジラの襲来か何かで東京が一度壊滅しないかぎり不可能な構想だなあ…。もし実現したら、アート・センターのド真ん中に等身大の救世主ゴジラ像を建ててあげるから、ゴジラくん、来なさい。
いじめられるから、やだって?
あ、そう。
*
◆シマノフスキ:ヴァイオリン協奏曲集/ダンチョフスカ(デジタル・メディア・ラボ)
などとゴジラ的(?)大改革を行わなくとも、自国の音楽家たちが自国の作品を真に誇りを持ちつつ演奏すれば、それは音楽になるものだ。この一枚、シマノフスキの作品をポーランドの演奏家とオーケストラが、都会的でなく、オシャレでもなく、それでいて滋味あふれる心のこもった音楽に編み上げている。感慨深いと共に羨ましい出来だ。
◆ハルトマン交響曲全集/メッツマッハー(東芝EMI)
もう一組、現代ドイツの作曲家カール・アマデウス・ハルトマンの交響曲を集めたこの全集も、別な意味でちょっと感慨深い。前衛までは行かないそこそこの現代音楽で編まれた彼のこの8つの交響曲に、第二次世界大戦前後の苦く狂おしい時代への思いが渦巻いているからだろうか。でも、五十八年の生涯で書いた8つの交響曲が、たったCD三枚に入ってしまうなんて、ちょっとショック!
第6回「回想のニューヨーク1981」
東京キッド・ブラザースを主宰していた劇作家・演出家の東由多加(ひがし・ゆたか)さんが、この四月二十日に亡くなった。
ある年代の人には強烈な印象を残しているこの「東京キッド・ブラザース」、寺山修司らと結成したアングラ劇団「天井桟敷」を経て、一九六八年に東さんが創設したミュージカル劇団である。「黄金バット」という舞台で若者たちに衝撃を与え、七○年には日本のミュージカル劇団で初めてニューヨークのオフ・ブロード・ウェイでロング・ラン公演を行うという快挙を成し遂げた。
そんな彼らと私の交点は、私が「朱鷺によせる哀歌」を初演して作曲家としてなんとか認知され始めた一九八一年(当時二十八歳)にさかのぼる。その前年に初演した「ドーリアン」というオーケストラ曲のテープを東さん(と、当時プロデューサーをやっていた梶容子さん)がどこかで聴いて、いきなり「ミュージカルの作曲をやらないか?」と打診してきたのだ。
その時はじめて会ったヒトラーみたいなヒゲの男(当時三十六歳)が東さん。優しいんだか危ないんだかわからない不思議な人で「秋にニューヨークのオフ・ブロードウェイでサムライ・ミュージカルを上演するんだ。ニューヨークっ子をアッと言わせないか?」と熱っぽく語りかけてくる。
しかし、わずか半年後にNY公演が決まっているというのに、島原の乱と天草四郎を素材にしたミュージカルというだけで、台本どころか話の筋も決まっていないというから驚いた。しかも、ニューヨークに行ける、というだけでお金は一円も出ない、というのだからムチャクチャな話だ。でも、当時はヒマだけは腐るほどあったし、面白そうなのでやってみることにした。
音楽については「あくまでもロック。でも、邦楽のテイストも入れたい」と言う。私としてはそれまでにアマチュア・ロック・バンドでピンク・フロイド風プログレッシヴ・ロックで遊んでいたし、尺八と琵琶にピアノとベースという奇妙なグループも経ていたので、「それなら四人編成のロックバンド(ギター、キイボード、ベース、ドラムス)に尺八と和太鼓!」と即決、音楽サンプルを作り出した。
しかし、この制作過程もメチャクチャで、なにやら葉隠の言葉が入ったラブ・ソングのようなものの歌詞が届いて「今晩中に作曲してくれ」と言われたかと思うと、「なにか戦闘シーンのような激しい曲が欲しい」とか「花笠をもって踊るみたいな軽い踊りの音楽を」とか断片的な注文が突然来る。
そんな中で、バンドに口伝で曲を教え込み(彼らはほとんど楽譜が読めないのである)、スタジオで仮録音してはそのテープを送る、という日々が続いた。その曲を聴いて東さんは場面をイメージし、話を作り上げているようだ。
おかげでストレスのため十二指腸潰瘍になったほどひどい目にあったが、劇団員の方もなにやら日舞だの剣道だののレッスンから始まっているようで、公演日が近づいてきても全然全貌が見えない。聞けば、東さんの作り方はいつもそんなものらしい。
稽古というのも、若い団員に熱気とやる気だけを叩き込むという旧日本陸軍のような精神主義的やり方で、汗だくの全身全霊をぶつけた芝居だけを要求する。しかも、酒を飲みながら竹刀を振り回し、怒鳴りまくるというメチャクチャさ。それでも、怒号と猫なで声の使い分けで彼らを掌握してゆく。
そして、ニューヨークへと劇団員とスタッフ一同あわただしく飛び立ったのが十一月。しかし、その時点でもまだ筋書きが決定していないという凄まじい状況だった。着いて早々、観光する間もなく怪しげな古いビルの稽古場で4日ほど集中特訓をしただろうか。劇場も華々しいブロードウェイからは離れた汚い路地にあるラ・ママ劇場(とは言え、オフ・ブロードウェイ界では有名な場所)。かくして、本番初日の幕が上がったのである。
ミュージカル「SHIRO」。柴田恭兵が扮する現代の若者が、江戸時代の島原で起こった天草四郎の乱の真っ只中にタイムスリップし、様々な人に会ってサムライ(そして日本人)としての心を目覚めさせてゆく。…という筋なのだと、初日を見て初めて知った。
怪しげな英語と奇妙な日本語が乱舞し、ロックのビートの中に和太鼓や尺八や笛が浮遊し、甲冑を付けたサムライが走り回り、桜吹雪の中でラブ・シーンが展開し、花笠を持って全員がダンスを踊り、派手な戦闘シーンがあり、最後は歌舞伎の大見得の衣装でアッと言わせる。その舞台は結構ニューヨークっ子にも好評で、ひと月を予定していた公演は半月ほど伸び、その後もワシントンを始めアメリカ各地で上演を重ね、日本でも凱旋公演をしたほど。
今思えば、主演の柴田恭兵さんを始め、振付の謝珠栄さん、舞台装置の内田繁さん、照明の海藤春樹さん、尺八の中村明一さんと今でも第一線で活躍している凄いメンツが揃っていた(と言っても二十年前。みんな若かった)のだから無理もない。
ただ残念なことに、以上のような次第で出来上がった舞台ゆえ、台本もなければ楽譜もなく録音も残っていない(アメリカでTV放送したというから、もしかしたら映像は残っているのかも知れない)。東さんが亡くなった今となっては再演は不可能だろうから、永遠に幻の作品となるわけだ。
とは言え、私としてはここで邦楽とロック(そしてポップスとクラシック)と舞台の融合などというバカなことを圧倒的にやってしまったので、このジャンルに対する妙な夢も欲求不満もサッパリなくなってしまい、その後はもっぱら純音楽の作曲に専念できたと言えなくもないから、その点では感謝すべきなのかも知れない。
今は昔の物語である。
*
◆マーラー交響曲第10番/ラトル指揮ベルリン・フィル(東芝EMI)
◆マーラー交響曲第9番/高関健指揮群馬交響楽団(ALM)
そう言えば、マーラーはそのちょうど七十年前(一九一一年)にニューヨークにいたのだった。そんなこともあって、彼が最後に仕上げた第9番と、もしかしたら幻の作品として永遠に封印されていたかも知れない第10番を聴いていると、いつも不思議な感慨に襲われる。
まあ、確かに色々あった。でも、特にこの第10番のフィナーレの世にも美しいメロディなどを聴いていると、屈折したさまざまな思いが透明な青空に消えてゆき、すべてが許せるような気がするのだ。
第7回:絶対音感日記てけてんてん
某月某日。浅草の三社祭に行く。どうも昔からテケテンテンと祭り太鼓の音がすると、ジッとしていられない。今回も何やら〆切があったはずなのだが仕事はほったらかして、日曜日の浅草まで一人でノコノコと出かけてしまった。てけてんてん。
とは言え、別に一緒になって騒ぎたいわけではなく、静かに「おお、やってるねえ」と傍観するのが好み。雷門から仲見世を抜けて浅草寺まで凄まじい人の群にもまれていると、そこにまたお神輿がムリヤリ割って入る。そのメチャクチャさがまた楽しいし、最近はキリッと鉢巻きを締めた女性が多くて、これもなかなか凛としていて美しい。
今回は特に「今世紀最後の三社祭!」と言うコピーに釣られて出かけたのだが、考えてみると来年は「21世紀最初の三社祭!」か。祭りの喧騒からはちょっとはずれた路地裏の蕎麦屋で、昼日中から冷酒を一杯すする。く〜、しみる。
*
某月某日。交響曲第3番、舞台初演。こちらも、どこかテケテンテンのノリ。最後の和音が鳴り響いた後でブラヴォとスタンディング・オベーションの中、ノコノコとステージに上がってお辞儀するのは、作曲家(しかも、生きている!)だけが体験できる不思議で奇妙な儀式だ。
でも、書き上げてから二年ほどたっているので、いくぶん時差ボケがある。書いている時は「これを聴いたら驚くぞ!」とニヤニヤしていたはずなのだが、それは二年前の話。今は第4番を書きながら「これを聴いたら笑っちゃうぞ!」(笑)と思っているわけで、その反応は数年先と言うわけだ。(で、第4番が鳴っているころは第5番を書いていて「これを聴いたら…以下同文」と思っているのだろうな、きっと)
それにつけても、オーケストラの定期演奏会のトリで新作交響曲を鳴らしてしまうという快挙を成し遂げてくれた日本フィルと、颯爽とロックンロールしてくれたマエストロ・フジオカに感謝。
*
某月某日。このところ入り浸っている中野のアーケード街で、コミックスを漁る。
最近のマイ・ヒットは松本次郎の「ウエンディ」(太田出版)。ベースはピーターパン物語なのだが、現代日本に住む悩める女子高生ウエンディの寝室にパンクなピーターが現れてネバーランドに連れて行ってしまう、というお伽話なんだか精神病院行きなんだか分からないストーリー展開が凄い。AKIRA的なシュールさをたたえた悪夢の世界のようなネバーランドで、フック船長やティンカーベルや時計を飲み込んだワニが登場し、それを圧倒的なパースペクティヴと妙な粗雑さを同時に持った絵で映像化してしまう筆致(大友克洋プラス宮崎駿か)にも感心。
それにしても、このところ島田荘司とか京極夏彦あるいは北村薫あたりのミステリーを読みふけったかと思うと鶴田謙二とか寺田克也とか駕籠真太郎などの妙にマニアックな異世界コミックスにはまり、一方でなぜかゲーテのファウストや古典落語大全なんかを読み直してみたり、織田信長ものとかキリストものとかに凝ったりと、どうも読書に一貫性がなくなっている気がする。
しかも、これをまた、中野界隈の居酒屋で夕方5時くらいから一人カウンターで酒すすりながら横に何冊も本を積んで読んでゆくのだから、変な客だと思われてるだろうなあ。
まあいいけど。
*
某月某日。なぜか某雑誌で坂本龍一とインタビュー対談をしなければならないことになって、彼のCDをゴッソリ聴き、資料をドッサリ見る。
なにしろ世界のサカモトである。大変である。あれだけ有名になってしまうと、ぶらぶらとコミックス漁ったり、居酒屋で一人静かに酒飲んだり出来ないのである。
ああ、売れない作曲家でよかった。別に、一人で好きな時に酒が飲める程度にかせげれば、それでいいじゃん。(…って、感想はそれだけかい!)
*
某月某日。今回演奏した交響曲のパート譜点検のためジャパン・アーツへ行く。イギリスでスコアをコンピュータ打ち込みして仕上げたパート譜だから万全だったはずなのに、演奏してみたらミスだらけだったことが判明。もしかしたら遅い2000年問題か?
ドッサリとパート譜を持ち帰ってこれからチェックだ。さあ殺せ!
*
某月某日。新たな割烹料理屋を開発。きれいな店構えで悪くないのだが、鯛の刺身を食べているすぐ横で、巨大な水槽から当の鯛が見ている。しかも、時々目が合うと「おい、あんた何を食ってるんだ?」という非難がましい顔をする(ような気がする)。
で、もし突然「魚にも人権がある!」などと魚が主張する世界になったら、まな板の上で生きたまま惨殺してその死体を客に食べさせる割烹料理屋などと言うのは、アウシュビッツ並みの残忍・鬼畜・地獄の施設ということになるのだろうなあ。…などと考えながら、鯛を食う。(おいおい)
*
某月某日。CDを聴く。
◆ショスタコーヴィチ弦楽四重奏曲全集/エマーソン弦楽四重奏団(グラモフォン)
ショスタコーヴィチの十五曲の弦楽四重奏曲を、番号順にきれいに並べたCD5枚組の全集。ライヴ演奏の熱気と勢いも手伝ってか、特にグロテスクなアレグロが飛び回る中期の作品などは凄い名曲に聞こえる。タコ・カル(ショスタコーヴィチのストリング・カルテットです。念のため)って傑作の森だったのだ、と再確認。結構ハマって、雑読にふけりながら繰り返し聴いてしまう。
◆横山幸雄/ベートーヴェン十二会(ソニークラシカル)
こちらはベートーヴェンの全ピアノ作品を、十二回のコンサートによるCD十二枚のライヴ録音で並べた大全集。CDはそれぞれ各夜の曲目をそのまま収録していて、それで「十二会」なのだが、ソナタはやっぱり番号順に並べて欲しかったなあ。でも、関脇の横幸山(?)がぶり寄りで寄り切って金星と言ったところ。拍手。
*
某月某日。音楽現代の連載の原稿を忘れていたことに気付く。そうだ、ここ数日の日記をそのまま載せちゃえ、と思い付き、ワープロに向かう。
…最初に戻る…
第8回:ヒトゲノム解読は21世紀を救うか?
人間の遺伝子情報ヒトゲノムの解読が完了したらしい。
ご存知のように、生物というのは細胞から出来ていて、その細胞は、二匹のミミズが背中合わせに張り付いたような形の染色体というシロモノが持つ遺伝情報によって作られている。で、その対になった染色体(人間なら23対)に仕込まれている情報によって細胞が分裂増殖してゆくと、ヒトはヒトに、カエルはカエルになる仕掛けだ。
そして、その遺伝情報は、染色体の中のDNA(ディオキシ・リボ核酸)というヒモ状のモノに保存されている。そのヒモ(DNA)は、よく見ると二重ラセン構造(つまり2本のヒモがねじりからんでいる状態)をしていて、G(グアシン)・A(アドニン)・C(シトシン)・T(チミン)という4つの塩基でつながっている。
…って難しい話で始まってしまったが、音楽的に発想してみると、要するに、ソ(G)・ラ(A)・ド(C)・シ(T)という4つの音だけで出来た2音の和音が、延々と三十億個ほど続くのが二重ラセンDNAの姿だと思えば間違いない。
この三十億個ほど和音が並んでいる「楽譜」が、人間という生物のスコア。この人間の設計図がDNAという楽譜であることに気付いたのが1953年、以来その音符の並びを世界中の学者達が必死になって解読を続け、ここ十五年ほどは「ヒトゲノム計画」というプロジェクトになってコンピュータで解読し続けてきた。
その完了は当初2005年とも言われていたが、どうやらギリギリ20世紀中のこの6月、ようやく完了した…らしいのだ。
(この「ヒトゲノム」、英語では「HUMAN・GENOME」と言う。人間(ヒト)の・遺伝情報(ゲノム)・という意味だが、私はずっと、英語でも「HITO・GENOME」というのかと信じていたのだが、違うらしい。残念)
さて、と言うわけで、今まで「音楽」として聴いていたとりとめのない音の連なりが、実は「楽譜」というもので綿密に書かれているのだ、と分かったわけで、これは人類にとって結構ショックなのである。
私も実は、作曲家になったきっかけというのが、LPから流れてくるベートーヴェンの何やら難しそうで複雑な、しかし心躍らせる「交響曲」という音響の塊が、実は「スコア」という音符だらけの設計図によって組み立てられた人工的構築物だと分かったことのショックからだった。
つまり、例えて言えば、交響曲が「スコア」という「膨大な音符の組み合わせによる設計図」で出来ている、ということに人類が気付いたのが、つまり「DNA」の発見である。
で、それが4楽章だったりソナタ形式だったりで出来ていて、モチーフをどう組みあわせ、構造や対位法がどうなっているのか…を全部の音符にわたって読み取り、アナリーゼ(解析)を完了したのが「ヒトゲノム解読完了」ということになるだろうか。
今までも、もちろん全部の音符についてアナリーゼ完了していなくとも、テンポを早めると熱っぽくなるとか、リピートを指定通りやると冗長になるとか、フェルマータを効かせると重々しくなるとかくらいは体験で分かっていたわけだが、それは何を食べると高血圧予防になるとか、何かの物質を投与するとガンが治るとかいうのに似ている。
で、長調の所を短調にしてみると曲が暗くなるとか、4拍子のところを3拍子にするとワルツになるとか、リズムをスウィングさせるとジャズっぽくなるとか、色々な「いじくり方」が音楽にはあったわけなのだが、さてこのゲノム・スコアはどうなのだろう?
もちろん、「何番目の遺伝子の塩基配列が壊れている場合に遺伝病が起こる」と解明できれば、それを修復することで無用な疾病に苦しむことはなくなる。また、先天性の病気や、薬が効きやすかったり効きにくかったりする体質、あるいは副作用などについての個人差の理由が解明できれば、その治療法は格段の進歩を遂げるはずだ。
でも、「何千何百何番目の塩基配列をいじくると目が三ツになる」とか、「何千コおきの塩基の繰り返しパターンを何万コにすると翼が生える」とか、「何番目と何番目の配列を入れ替えればヒットラーになる」とか、な〜んかありそうだ。
そのうち、三十億個の塩基をランダムに並べて「無調人間」を作る「三十億音主義」なんてのを言い出す輩が出なければいいけど。
いや、それどころか数十年後には、どんな子供でもコンピュータ上で遺伝子組み替えて恐竜でも怪獣でも妖精でもどんな生物でも作れちゃう、という「バイオ・フリー」の時代が来るかも。
*
◆坂本龍一ピアノ・ワークス/岡城千歳(プロピアノ)
そんな時代になったら、激動の20世紀もまた「古き懐かしい時代」となるのかも知れない。と言うわけで、サカモト教授のピアノ曲十五曲を岡城千歳が弾いたこのアルバムを聴きながら、20世紀を回顧してみる。
YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)で一世を風靡した世界のサカモトは、実は芸大作曲科出身のバリバリの「現代音楽作曲家」。しかし、ピアニストが哲学的な言葉をささやく芸大時代の前衛的ピアノ曲「分散・境界・砂」に始まり、YMO時代のヒット曲「東風(トン・プー)のポップな疾走感から、まるっきりメシアンまるっきりサティまるっきりラヴェル…という曲たちが並ぶ様を聴いていると、「坂本龍一」は作曲家ではなくメディアになっていることを実感する。これは彼の作品集にあらず、「20世紀ピアノ音楽の総俯瞰サンプル集」なのだ。
◆テリエ・リピダル/ダブル・コンチェルト&5thシンフォニー(ECM)
この坂本龍一の例を挙げるまでもなく、いわゆるクラシック界に属さない音楽家も結構クラシカルな作品を書いている。ポール・マッカートニーしかり、キース・ジャレットしかり、ピアソラしかり。ノルウェイのジャズ(ロック)・ギタリストであるテリエ・リピダルもその一人で、ECMで発表されたエレキ・ギター協奏曲「WHENEVER I SEEM TO BE FARAWAY」と名盤「オデッセイ」にショックを受けて以来、この人には注目している。
今回のアルバムでは、エレキ・ギター2本の「ダブル・コンチェルト」でハード・ロックの味も加味したドラマチックな世界を、全4楽章三十五分の大作「交響曲5番」ではシベリウス風の冷たさをたたえた叙情的かつ壮大な世界を聴かせている。拍手。
第9回「夏が来ればグチり出す...」
相変わらず夏は苦手である。
にもかかわらず、なぜか毎年夏というのは大きな仕事を抱えてジタバタしていることが多く、一昨年は交響曲第3番にかかりきりだったし、今年は第4番で潰れそうだ。
昔から、夏はどこか涼しい山の中の別荘でこもりきりになって作曲にふけるというのが理想だったのだが、貧乏作曲家の身でそんなものに縁があるわけもない。結局、今年の夏もまた、古いマンションの狭い仕事部屋で、いつ壊れるか分からないボロ・クーラーを全開にして、ボソボソとペンを(最近はマウスを)走らせているという次第。
それでも、今回の第4番は「田園プラスおもちゃの交響曲」というコンセプトの軽い交響曲で(ただし全4楽章三十分はたっぷりあるのだが)、〆切も今年いっぱい(録音初演がたぶん来年3月ころ)に延びたので、まだ気が楽と言えば楽。
最近はコンピュータにマウス入力してゆく作業にもすっかり慣れ、書き上げた部分をデジタル音源で鳴らして耳で確かめながら、ワープロと同じ感覚でスコアをモニター画面の中に仕上げてゆく。ただ、鉛筆でスコアを書いていたころのペンだこに代わって、一日中マウスをクリックしているために右手の親指と人差し指周辺の筋肉痛がひどい。ヘンな職業病だ。
それに、ピアノを弾きながら手書きのスケッチ稿を何回も書き、コンピュータ入力した楽譜も何度も何度もプリント・アウトして赤で修正を入れたりするので、相変わらず〈スケッチ版初稿〉とか〈デッサン第2改訂稿〉とか〈7月4日修正稿〉とかいう出来損ないのスコアがわさわさと積み重なってゆく。おかげで、一応は世間並みにIT(情報技術)革命を果たしたはずなのに、なぜか紙の消費量は増えるばかりである。やれやれ。
そう言えば、先日、心理学者の河合隼雄氏と対談した時、「交響曲の作曲家というのは意外と、夏に湖の前の小屋かなんかで書く人が多いですね…」という話になった。ブラームスしかりマーラーしかり。シベリウスやチャイコフスキーもそれに近い。完全に都市型なのは、アパート引きこもり独身組のベートーヴェンやシューベルトあるいはブルックナーくらいか。
もっとも、作曲家というのは多くの場合シーズン中は音楽教師とか指揮者とかをやっているので、オフの夏休みくらいしか大作を書くためのまとまった時間がとれないという理由もあるのだろう。
それでも、「夏」に、目の前に「湖」があって背後に「林」がある、という環境が一致しているのは、作曲家の心理を読むうえで興味深い。水は音を吸うので、基本的に湖畔が一番静か(川や海ではザアザアとやかましいのだ!)ということもあるのだろうが、この布陣は音に鋭敏な知性を引きつける究極の「陣形」なのかも知れない。
以前、シベリウスの家(アイノラ)と宮澤賢治の家(羅須地人協会)を訪れて、両者がそっくりの風景の中に建っているのに驚いたことがある。共に、街からちょっと離れた小高い丘の上の一軒家で、眼下に湖か川、背後に林という配置なので、一瞬デジャ・ヴ(既視感)かと思ったほどだ。同じ感性は同じ住環境を求めるのらしい。
聞けば、心理学では「箱庭療法」なるものがあるそうで、小さな箱に土を入れ、そこに模型の家や人や木や柵や川などを置かせて「住み処」を作らせる。すると、その配置で作者の隠された欲求や潜在意識などが分かるのだそうだ。(でも、潜在的な心理を具現化するような理想的住まいに住んで創作している作家が一体どれほどいるのだろう?)
やっぱり作家としては、湖のほとりや林の中を一人静かに散歩中、天から霊感が降りてきたりするのが理想なんだろうなあ。窓からは湖や川が見え、水が音を吸ってくれるのであたりは静けさに包まれていて、遠くかすかに鳥の声が聞こえるくらい…とかね。
でも現実は、本やCDや楽譜が天井まで積まれた狭い仕事部屋で半袖シャツ一枚になって汗をかきかきピアノ弾いたりワープロ打ったりしてるのだ。あたりを取り巻くのは車の音にクーラーのノイズ、それに試聴しなければならない雑多なCDの音楽。
それでも、車の騒音は風の音、クーラーのノイズは波の音、テレビやCDから聞こえてくる音楽は鳥の声だと思えばいい。そもそも日本の湖は多くの場合、観光船だのボートだのが浮遊していて興ざめな所が多くて、特に夏休み中などは絶望的。以前行った某湖ではパンダやドラエモンの形をしたボートが群れ成していたし…。
…などと言っていると、「隣のブドウは酸っぱい」という故事を思い出すけれど、まあ、夏来たりなば、秋近し。せいぜい頑張ってこの夏も乗りきりましょうか。
*
◆フィリップ・グラス:交響曲第3番(ノンサッチ)
それにしてもグラスのような現代音楽の作曲家が番号付きの交響曲を書くなんて、ちょっと前だったら信じられないことだったのに、時代は変わったものだ。もしかしたら「隣のブドウは甘い」とでも思ったのだろうか、彼としてはとうに前衛音楽という脈絡を捨ててフランス近代音楽の延長線上に自分のポジションを決めたかのようにさえ見える。
弦楽オーケストラのために書かれたこの全4楽章二十五分ほどの第3交響曲も、前衛臭ゼロでオネゲルやストラヴィンスキーあたりの交響曲の延長線上にそよそよと鳴り響いているのだから面白い。最近合唱付きの巨大な第5番を発表したのは記憶に新しいが、やはりこの人、怪しげながら才人である。
◆芥川也寸志forever(フォンテック)
才人といえば、戦後日本の音楽界で「社会主義リアリズム」(?)の理想形を目指した芥川也寸志も、その名にふさわしい。
一九六○年代になって前衛音楽に引きずられてしまう以前に書いた若いころの「交響三章(トリニタ・シンフォニカ)」や「交響管弦楽のための音楽」などは(そのまんまプロコフィエフと言えなくもないが)なかなかの名曲で、共にフィナーレの一度聴いたら忘れられないテーマによる健康的な疾走感は魅力的。このまま伸び伸びとこの明るさで作品を連ねてくれていたら…と嘆くのは、見果てぬ「歴史のもしも」か。
交響曲第1番やエローラ交響曲という力作も含めて交響作品をカウントしてゆくと、こちらも5曲ほどの交響曲が並ぶのだが、さて、彼らの交響曲は21世紀にどういうポジションにいるのだろう?
第10回「絶対安全夏日記」
某月某日。クラシックCD界のブロック・バスター(価格破壊王)ナクソスが、日本の作曲家シリーズを始めるとかで、池袋の東京芸術劇場へCD録音の立ち会いに出向く。
今回は、近衛秀麿・伊福部昭・芥川也寸志・小山清茂・外山雄三・そして私の作品を一枚にするという「お徳用盤」第一弾というべき企画で、拙作は「朱鷺によせる哀歌」。演奏は沼尻竜典指揮の東京都交響楽団。
いわゆる前衛音楽があまりお好きでないナクソスの意向と、それに便乗して趣味に走った(笑)片山杜秀氏の選曲が見事に合致したのか、録音予定曲のリスト(予定では六十枚以上の大全集とか)には戦前戦後の聴いたことのない交響曲や協奏曲や管弦楽曲が並び、なかなか壮観(でも、どこから録音費用を捻出するんだろ?)。乞うご期待。
某月某日。ピアニストの舘野泉さんが主催するフィンランドのオウルンサロ音楽祭(七月二十九日から八月六日まで開催)で個展をするべく、成田からヘルシンキへ。直行便が週2便しかないこともあって、同じくフィンランドへ向かう間宮芳生さんと乗りあわせる。ヘルシンキのヴァンター空港で乗り換えて、約一時間のフライトの後オウルへ到着。
翌日、リハーサル。日本で言うなら仙台あるいは盛岡の郊外の小さな町…と言った位置にあるオウルンサロだが、昨今のモバイル業界の隆盛(フィンランドは最近、携帯電話やインターネットの技術でヨーロッパの最先端を走っていて、けっこう景気がいいらしい)もあるのか、お店も何もない田舎そのものの町ながら、高級別荘地みたいな清々しい風景。妙に小奇麗で美しい。
某月某日。その町にポツンと建つオウルンサロ・ホール…なる所で個展。多目的ホール…と言うのだが、もしかして体育館?。演奏しているオーケストラの頭の上にあるのはバスケットのゴールのような気が…。
前半は室内楽編成で、プレイアデス舞曲集、夢色モビール、アトムハーツ・クラブ・カルテット。後半は曽我大介指揮の弦楽アンサンブルが加わって、鳥は静かに、鳥はふたたび(音楽祭委嘱作品)、アトム・ハーツ・クラブ組曲第2番…というプログラム。夜の8時開演で終演は10時半を過ぎるのに、外は白夜で明るいのが不思議。
翌日、オウルからヘルシンキへ出て、しばらく運河沿いのホテルに滞在。インターネットの回線も確保し、翌日シベリウスの墓を訪ねてヤルヴェンパーへ。
20年ぶりのアイノラは、青い空と白い雲の下で静かに佇んでいる。持っていったCDプレイヤーで、田部京子さんがシャンドスから出した最新の「シベリウス・ピアノ・アルバム」(国内盤は東京エムプラスから十月下旬発売予定)を聴く。「樹の組曲」や「花の組曲」などを聴いていると、まさにこの景色の中の樹や花なのだなあ、としばし感激してしまう。近くの湖のほとりで、湖面に浮かぶカルガモを眺めながら一日を潰す。
翌日はトゥルクを回る。シベリウスゆかりの地めぐり…のはずだったのだが、結局、日がな一日青空の下でビールなんか飲んでいるのが一番似合うので困ってしまう。夜は夜で、あやしげなキャビアもどきを肴にフィンランド・ウォッカを飲む。美味なり。
某月某日。ヘルシンキで北欧の大気を堪能した後、帰国。最高気温24度のヘルシンキから38度の東京へ。天国から地獄へ、というのを実感し、さすがにくたびれる。それにしても、東京は暑い!
翌日、「題名のない音楽会」の打ち合わせのため、神谷町のテレビ朝日へ。「現代音楽はなぜつまらない?」というタイトル(私が付けたんじゃありません。念のため)で、ヨシマツ特集の一夜(日曜日の朝に放送の番組だから、一朝…か)なんだとか。
そのまま渋谷のジャパン・アーツに寄って、交響曲第3番のスコアとパート譜のミス・チェックと校正。CD録音も舞台初演も済ませたのに、まだスコアにもパート譜にも膨大なミスがある…という恐ろしい状況を解除すべく、頭抱えつつチェック。
某月某日。真夏の夜の怪異譚と題した「百物語より」上演のため津田ホールへ。日本音楽集団による邦楽アンサンブルをバックに、ナマズや座頭や生首やネコや食人鬼が登場する怖〜い話を十編ほど語る一夜。語りはネオ・カブキの女形スター篠井英介氏。どこか艶っぽい語り口がなかなか怖い。
怪談で人を怖がらせるコツは、シーンとする一瞬の間を作ること。「何かが出るぞ…」と思わせる一瞬の静けさが、想像力を喚起して怖い。突然「ワッ」とか「ギャッ」とか大声を出して怖がらせるのは、極めて安直にして効果大の方法だが、これは邪道と言うべきだろう。
某月某日。「題名のない音楽会」収録のため渋谷公会堂へ。羽田健太郎氏と高橋真紀子嬢の司会で、今世紀のクラシック作曲界を汚染した「現代音楽」を斬る一夜。現代音楽教の教祖ウェーベルン尊師の「交響曲」を肴に、20世紀最大の悪夢のひとつ「無調病」の罪と罰を暴く。(おいおい)
一九二十年代以降のクラシック創作界が不毛なのは、本来2つでいい目を十二個くっつけるような無意味な領域に作曲家が足を踏み込んだせい。おかげで才能あるメロディ・メイカーたちはすべて現代音楽を見捨ててポップスやロックや映画音楽の世界に亡命してしまい、クラシック現代音楽界にはメロディ一つ書けない頭デッカチのカスたちだけが残った。これはメロディ作家の虐殺と言える愚挙であり、ホロコーストと言うに等しい。
…というような過激なお話。たぶん十月下旬ころ放送。
*
◆ストラヴィンスキー:春の祭典(ピアノ版)ファジル・サイ(テルデック)
とは言え、現代音楽だってビートとスピード感さえあればポピュラリティを得られたはずなのだ。そのいい証拠がこの「春の祭典」。才人サイが多重録音を駆使してデッチあげたこのピアノ版を聴いても、スゴさはヒシヒシと伝わってくる。でも、サンプリング・プラス・打ち込みで出来ることを、生身のピアノでやる空しさも少々。
◆カルーソー2000〜ザ・デジタル・レコーディング(BMG)
一方こちらは、往年の名歌手カルーソーの古いSP録音から歌の部分だけを取り出して、バックを最新デジタル録音のオーケストラにすげ替えてしまうという「この手があったか」的な試み。でも、ほとんど手作業のこの裏技、けっこう手間がかかっていそう。トスカニーニやフルトヴェングラーのモノラル盤をデジタル録音のクオリティで蘇らせるなんていうのは、まだまだ無理か…。
第11回「鳥について」
鳥は私の音楽の〈師匠〉である。
とは言っても、別に子供のころから鳥に親しんでいたというわけでも、バード・ウォッチングに勤しんでいたわけでもなく、今でも別に鳥類の研究や鳴き声の分類に励んでるわけでもない。ただ、ある時ふと、彼らを〈音楽家〉として尊敬するようになった、というだけのことではあるのだが…。
なにしろ鳥たちは、(たぶん)地球上に人類など影も形もなかった頃から、歌を歌っていた大先輩。人間よりはるかに古くから〈音楽〉を駆使してきた畏敬すべき音楽家たちにして、地上最高のメロディ・メイカーなのである。
まず、メロディ・メイカーとしての彼らは、ホーホケキョとかカッコーとかいうシンプルな唄歌いから、ピピピとかピュルルピイイとかチチピイチュクピイ…などという技巧派まで、極めて多彩にして記号的な美しい旋律の文化を持っている。
人間が、地上に貼り付けられた二足歩行の哺乳類としての歌を発達させてきたとすれば、鳥たちは空を飛翔し木々の上に住まう有翼類としての歌を発達させてきたのだ。
それは、生殖に関わる本能と、生を謳歌する遊びとに基づき、数億年ほどかけて完成されていった高度な音楽語法なのである。これを〈鳥メロディ〉とでも名付けよう。
しかも、鳥の音楽文化は単にその歌だけにとどまらず、動きそのものの内にも高度な音楽性を秘めている。例えば、飛翔する際のフワリ…あるいはヒラリ…という翼や羽根の動きは、空気力学・動体力学的に完璧であるとともに、優美かつ音楽的きわまりない。
空と一体化することから生まれるその間合いは、時に大気を切り裂き、時に大気と融和し、直線的ではなく〈鳥ゆらぎ〉とでも言うべき不思議な曲線を描いて揺らぐのである。
一方、枝にとまり地面に下り立った時は、また別のテンポ感が鳥を支配する。首を回し、あたりを見回し、クチバシを羽根に突っ込んで身繕いをし、地上に飛び降り、走り回り、立ち止まる。
そのリズム感は、飛翔している時の〈アンダンテ・ソステヌート〉に対して〈アレグロ・コン・スピリート〉。これらを総称して〈鳥リズム〉と名付けたい。
さらに、大地から高く飛び上がり自在に空をゆくその思考も、きわめて音楽的だ。寒く不毛になった森からヒラリと舞い上がり、新しい森を求めて大陸から大陸へと地球を移動するその生命力。
それは、ひとつのモード(旋法)から、もうひとつの新しいモードへ移ることで生命を生み出すという、大地と空との調和の中に生きる〈鳥の思想〉と言える。これはもう〈鳥モード〉と呼ぶしかない。
師匠からのこれらの3つの教え、〈鳥メロディ〉〈鳥リズム〉〈鳥モード〉こそが、わが音楽語法の原点なのである。
つまり、まず〈鳥メロディ〉が「点と線」として音符数コの単位で音楽の旋律細胞を生み出し、それを〈鳥リズム〉が数小節という単位で「線と面」として支配し、それを〈鳥モード〉が統括して「立体」としての楽曲の構造を形作る。これが〈鳥の音楽形式〉というわけなのだ。
実際、私の〈鳥シリーズ〉の最初の作品である「朱鷺によせる哀歌」では、鳥の形に配置された弦楽オーケストラが〈鳥ゆらぎ〉によるアンサンブルを形成し、続く「チカプ」ではフルートで点描形の〈鳥メロディ〉あるいは〈鳥パッセージ〉がちりばめられる。
さらに、「デジタルバード組曲」に始まる〈小鳥のシリーズ〉ではアレグロによる疾走する〈鳥リズム〉あるいは〈鳥ビート〉がジャズとミニマル・ミュージックのイディオムと共に組み込まれ、「鳥たちの時代」では〈鳥モード〉とその拡大形である〈鳥コンセプト〉を全面採用してそれらの統合を図っている…という具合。(本当かいな?)
もちろん、鳥ばかりに取りつかれて、鳥の素材ばかりを取り込むことに終始していたわけではなく、「星のシリーズ」「天使のシリーズ」「神話の動物シリーズ」「小市民シリーズ」などなどで、色々な語法への怪しげなアプローチもやっていたわけなのだが、それはまた別の機会にお話しすることにしよう。
*
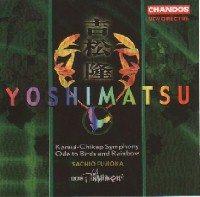 ◆吉松隆:作品集4/カムイチカプ交響曲ほか(シャンドス/東京エムプラス)
◆吉松隆:作品集4/カムイチカプ交響曲ほか(シャンドス/東京エムプラス)そんな〈鳥〉へのオードとでも言えるのが、シャンドスにおける私の4枚目のこの作品集。最初の交響曲(第1番)である「カムイチカプ交響曲」と「鳥と虹によせる雅歌」という、鳥にちなんだ純オーケストラ作品2曲のカップリングである。
ただ、「鳥の王によせる5楽章の交響曲」(カムイ・チカプはアイヌ語で神の鳥という意味)として前者を書いていたころは、3番4番などという番号付き交響曲にまで歩を進められるとは夢にも思っていなかったから、今聴くと感慨深い。なにしろ、そのころは現代音楽界につくづく絶望していて、「もうこれでやめっちまおう」と決心して(崖からでも飛び降りるつもりで)書いた開き直り聖戦派というべき作なのだ。
そして後者の「雅歌」の方も、それから数年後に、妹の死に会って世をはかなみ、やはり「もうこれでやめっちまおう」と思って書いた虚脱から飛翔派というべき一品。
結局生き残ったからこうやって冗談めかして話せるものの、一歩間違えば結構あぶなかった。(誰ですか、間違ったほうがよかったのに…と言ってるのは?)。まあ、人間、四十七年も生きていると、色々ヤバいことがある、ということか。
◆田部京子/シベリウス・ピアノ・アルバム(シャンドス/東京エムプラス)
もう一枚は、鳥ではなく「樹」や「花」にちなむシベリウスのピアノ作品を集めた、田部京子さんのシャンドスにおけるデビュー・アルバム。2年前に私の書いたピアノ協奏曲「メモ・フローラ」を一緒にイギリスで録音した時、プロデューサーのラルフ氏が彼女のピアノに惚れ込んで、「ぜひシベリウスで一枚!」と言った一言が見事に結晶した、こちらは掛け値なしの逸品である。
なにしろシベリウスは〈鳥〉と並ぶ(?)私の心の師匠でもあるので、こうして彼のピアノ作品が最高のクオリティで仕上げられたことはまさに感謝至極。
田部京子さんは北国生まれのせいもあってかシベリウスの音楽と相性も良く(それを瞬時に見抜いたラルフ氏の慧眼おそるべし)、「冷たさの中のほのかな温もり」を感じさせる高純度の詩情がきらめき、希有の名盤の誕生となった。
第12回:絶対安全音感グルメ日記
某月某日。渋谷某所にてマエストロ・フジオカと一緒にトーク&サイン会。シャンドスでの作品集アルバム発売記念なのだが、これで作品集も4枚め。おかげさまで、いずれも好評。日頃のご愛顧に感謝。
某月某日。夏に収録した「題名のない音楽会」がテレビ放映される。この番組の20世紀名曲シリーズの一環ということらしく「武満徹特集」「三人の会(團伊玖磨・芥川也寸志・黛敏郎)特集」に続いての「ヨシマツ特集」。…なのだが、「現代音楽はなぜつまらない?」と題した現代音楽糾弾番組だったような気も…。
番組中では、ウェーベルン大先生の「交響曲」を例に出して「ホラ、現代音楽ってこんなにヘン」…と解説したのだが、逆にヤブヘビとなってしばらくウェーベルンにハマる。ホラー小説なんか読みながら聴くとたまらないのだなあ。「逆ヒーリング(神経逆ナデ)音楽」としてヒットする可能性もゼロではないような気がするのだけど、どこかでやらないだろうか?
某月某日。某音楽誌に特集記事が載る。昔話に添えるためいくつか昔の写真も登場。クラシックを聴き始めた中学三年ころの写真とか、実家の前のワシントン・ハイツ(アメリカ進駐軍の駐留キャンプ。現在は代々木公園になっているところ)の昭和二十年代の写真なんかは、それこそお宝映像かも。
死んだ妹の話も出てくるので何枚か写真が並ぶ羽目になったが、みんなに必ず言われるのが「妹さん、きれいだったんですね〜」という一言。今ごろきっと「生きている時は、そんなこと言われたことなかったのにィ」と、天国で笑っているに違いない。
某月某日。FMのN響定期解説のためNHKへ行く。曲目はショスタコーヴィチの交響曲第13番「バビ・ヤール」。この曲、けっこう怖い曲で、現代の日本で言うなら朝鮮問題とか南京虐殺とかをテーマにした独唱と合唱付き交響曲といったところか。それをまたイスラエルとパレスチナがもめている時期に演奏(指揮:アシュケナージ)するのだから、解説も迂闊なこと言えなくてもう大変。
歌詞の対訳字幕スーパー付きで演奏を聴いていると、若いちんぴら詩人(エフトゥシェンコ)の青臭い熱血詩に、中年の人の悪い作曲家(ショスタコーヴィチ)が全然別の思惑で音楽を付けていることがよく分かるが、「私の中にユダヤの血はないが、私は反ユダヤ主義者どもから、まるでユダヤ人のように憎まれる。でも、だからこそ私は真のロシア人なのだ!」などという歌詞の〈ユダヤ〉とか〈ロシア〉とか言う部分を、例えば〈日本〉や〈アジア〉あるいは〈朝鮮〉や〈中国〉という単語に置き換えてみれば、この曲がどんなに危ないことを歌っているか実感できるはず。おかげで、その後しばらく南京虐殺の「あった本」と「なかった本」などに読みふけったりしてしまった。あぶない、あぶない。
某月某日。知り合いの美術展を見に、一年ぶりに京都へ行く。夕方着いて新京極や木屋町通りをぶらぶら。やけに外人さんが多いと思ったら、時代祭の当日だった。しかも、夜は鞍馬で火祭りをやっているのだとか。一瞬これから行こうかとも思ったが、どうやって帰るのか考えて中止。根性ないなあ。高瀬川のほとりの居酒屋で生湯葉をつつきながら独り玉の光を飲む。美味。
翌日は金沢へ。小雨の降る中、室生犀星ゆかりの犀川のほとりを歩き、さらに茶屋街を散策。いい風情。兼六園と金沢城を横目で見た後、加賀料理のお店へ。ゴリの唐揚げを肴に独り菊姫を飲む。美味。
某月某日。北陸路をぐるりと回って新潟へ。ここの〈りゅーとぴあ〉の音楽ホールで今年の大晦日から新年にかけて行われるジルベスター・コンサートで演奏するファンファーレを委嘱されたので、その下見。丸い卵型で全面ガラス張りという不思議な建物で、中に劇場や能楽堂もあるなかなか立派な施設。
新潟というと、三十年ほど前に朱鷺を見に佐渡に渡った時のことを思い出す(その頃すでに朱鷺は全島で十二羽くらいの幻の鳥。もちろん実物は見られなかった)。駅に着いたら嵐の真っ只中で、雨の中、一人でトボトボ歩いて佐渡汽船の船着き場まで行ったっけ。暗くて真っ黒な日本海しか見えなかった。
あれから何度も佐渡には行き、弥彦とか月岡とか六日町には行ったが、新潟市内に逗留するのはひさしぶり。古町通りや東堀通りを散策し、夜は駅近くの料理屋でノドグロとノッペを肴に独り八海山を飲む。美味。
某月某日。帰宅。月末にしばらく仕事場を留守にすると、送られてくる本やサンプル盤の山(月刊誌やCDの発売日は毎月二十日頃が一番多い)と〆切原稿の処理で大変なことを改めて実感。
ドッサリ積まれたサンプルCDと頼まれ原稿の山を数日がかりでようやく処理し、夜はひさしぶりに近所の居酒屋に行き、サンマの塩焼きをつつきながら独り麒麟山を飲む。美味。(こんなんばっかりや!)
*
◆鏡の国のアリス/ヴィクトリア・ムローヴァ(フィリップス)
◆アンネ=ゾフィー・ムター/リサイタル2000(グラモフォン)
というわけで、20世紀もそろそろ大晦日。だからというわけでもないのだろうが、二人の女性ヴァイオリニストによる20世紀の音楽を俯瞰する(というほど大袈裟なものではないが)アルバムがそろったので、ここにご紹介。
ムローヴァの方はデューク・エリントン、マイルス・デイヴィス、ビージーズ、ユッスー・ンドゥールなどなどジャズ・ロック・ポップ・エスノ界の名品を並べた現代ポップ音楽史観によるアルバム。
ヴァイオリンとパーカッションを軸にピアノやチェロそしてギターが加わる編成で、20世紀のビート音楽と民族音楽とクラシックと現代音楽が軽やかに融合されてゆく。その距離感とアレンジのセンスに拍手。
対するムターの方は、プロコフィエフとレスピーギにウェーベルンとクラムを配した現代クラシック音楽史観によるアルバム。ヴァイオリンとピアノという素材だけで四人四様の20世紀音楽をひとつの軌跡の中で聴かせる手腕はさすが。
*
それにしても、20世紀というのは変な時代だった。変な発明が続々登場するわ、世界中で戦争が起こるわ、人間が世界中で異常繁殖するわ、調性壊す輩が出て来るわ。
でも…たぶん21世紀も変な時代になるのだろうなあ。なんせ、人間がやることと言ったら、いつだって変なのだから。