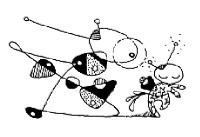 �����I�V���I���b�c�m�[�g
�����I�V���I���b�c�m�[�g
�@�@�i2003�N�Łj
������͉��y���㎏��2000�N�P�����A�ڂ��ꂽ
�u�V���I���b�c�m�[�g�v�̃I���W�i�������łł��B
2000 / 2001 / 2002 / 2003
��37��u���Ă܂����A���Ă܂��A���Ă������܂��v
��38��u��Ԃɂ�ݒ��쌠�l�i���㉹�y�ҁj�v
��39��u�t�@�E�X�g�̖�A���t�B�X�g�̒��v
��40��u���̂��Ɓv
��41��u�l�ԂȂ�āv
��42��u�䂪���͑�T�v
��43��u�Z���ƃ`�F���v
��44��u�˔\�̗͑͂��c�H�v
��45��u�ċx�ݓ��L�v
��46��u�a���҂����̉́v
��47��u�N���m��Ȃ��A�N�������Ȃ��v
�ŏI��u�Ƃ肠�����ŏI��Ƃ������ƂŁv
��37��u���Ă܂����A���Ă܂��A���Ă������܂��v
�@���y�����t�Ő������鎞�A�N�ł��u���X�̂悤�ȁc�v�Ƃ��u���X�Ɏ����c�v�ƌ����Ă��܂����Ƃ������B
�@�����l�����āu���~�̂悤�ȁv�ƌ����Ă��܂����炢�����A��ɕ����ԉ_�����āu���݂����v�Ƃ��u�\���݂����v�Ƃ��������肾����A�܂����y�Ȃǂ͎d���Ȃ��̂��낤�B���̌����ȂȂǂ��u�V�x���E�X�݂����Ń`���C�R�t�X�L�[�݂����Ń^�P�~�c�݂����ŃC�t�N�x�݂����ŁA���b�N��W���Y��|�b�v�X�▯�����y���y�Ȃ̉e���������āA�K�[�V���C���Ƃ��o�[���X�^�C���Ƃ��y���g�Ƃ����C�q�Ƃ��z���@�l�X�Ƃ��}�C�P���E�i�C�}���ɂ����ĂāA���{���ۂ��Ėk�����ۂ��ăA�W�A���ۂ��Ď��X�A���r�A���ۂ��āc�v�ƌ�������B�����Ă��铖�l�����Ă��܂��قǐF�X�Ȃ��̂Ɂu���Ă���v�炵���B
�@�����A��i�̃C���[�W�R�Ɓu���X�݂����ȁc�v�ƌ����Ă��邤���͂����̂����A�u���X�̉��Ƃ����ȂɎ��Ă���v�Ƃ����悤�ȋ�̓I�Ȏw�E�ɂȂ�ƃI���W�i���e�B�⒘�쌠�̖����͂��ł��邩��A��ȉƂɂƂ��Ă͏��Ă����Ȃ��Ȃ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�ŋ߁A�e���r�ԑg�Ŏg���u�e�[�}�ȁv�Ƃ����悤�Ȃ��̂������@��������̂����A���̃T���v���̂ЂƂ����v���f���[�T�[������A�r���ŏo�Ă���t���[�Y���u�Ȃ�Ƃ������O���̃q�b�g�Ȃ̃T�r�݂����ł��ˁv�ƌ����A������Ƌ��������Ƃ�����B
�@���͂��̋Ȃ�������̂��Ă���O���[�v�����������Ƃ��Ȃ������̂ŁA�ǂ̒��x���Ă���̂��͕�����Ȃ��̂����A���͂��̃t���[�Y�́i��������N�ł�������j����L���ȃe�[�}�̃M�~�b�N�Ƃ��ċ����肾�����̂��B�ŁA�����^�l������������ƁA�u���A�Ȃ�قǁB����������c�v�ƌ����B�i���Ȃ݂ɁA���ʂ���̂̓I�N�^�[����ɉ�����ԂQ�������B�r���ŃI�N�^�[�����o�Ă��郁���f�B���S���u����v�ɂȂ�����A�|�s�����[���y�E�͉�ł����I�j�����l������ł��܂����B
�@���ꂾ����A�|�b�v�X�n�̍�ȉƂɂȂǕ|���ĂƂĂ��Ȃ�Ȃ��c�ƁA���߂Ďv���B�Ȃɂ���A�I�[�P�X�g���ȂȂ�ϔ��q���R�A�R�[�h�i�s���\�������R�A���[�h���y��Ґ������R�A�ቹ���獂���܂ʼn���͍L��c�Ȃ̂ɁA�|�b�v�X�Ɨ�����S���q�̒��ł��������f�B���������Ȃ������ɁA�̂���̉���̓I�N�^�[��������Ƃ����A�C���g���������ăT�r�������ĉ̎��̌J��Ԃ��������āc�Ƃ����\�����ς��悤���Ȃ��B����ł́A���`���g�̒��Łu������Ǝ��Ă邯�ǂ�����ƐV�����v�Ȃ��Ђ��߂�����ł͂Ȃ����I
�@���������A��T���A�c�u�c�Ŕ����Ă����^�f������Ă�����A���̔w�i���y�̒��Ɏ��̃s�A�m�Ȃƃ\�b�N�������t���[�Y�������ăM���b�Ƃ������Ƃ������������B���̌��Ȃ͈�㎵�\�N��A�f��͔��\�N��̂��̂�����A��Ȃ����͎̂��̕�����Ȃ̂����A�t�ɂb�c��y���̓o��͌�B�܂�A���삵���̂ł����ꂽ�̂ł��Ȃ����S�Ɂu���R�v�i�P���ȃ����c���������j�Ƃ����킯�Ȃ̂����A���`��A�|���|���B
�@�̃o���h������Ă��������A�Ƃ���I���W�i���Ȃ����t���邽�тɃh�����̔ނ��u�����A���Ԃ��C���`�i�c�͂��Ă����̎q���j���ĕ���������ǁv�ƌ����B�ق��̃o���h���Ԃ��u�ǂ������H�@�S�R���ĂȂ������v�ƌ����Ă��A�ނ́u���Ă鎗�Ă�B�ق�A���Ԃ��C���`�v�ƌ�������B�ŁA�L�C�{�[�h�������ʂ��q�ׂɔ�ׂĂ݂�ƁA�Ȃ̓r���ɂ���h���~�t�@�\�Ƃ����}�C�i�[�R�[�h�̉��K���m���Ɂu�Ԃ��C�v�Ɠ����ł��邱�Ƃ͔����������A���ꂾ���B�Z���̋ȂŃh���~�t�@�\���������Ă���S���u�Ԃ��C�v�ɕ�������Ƃ����Ȃ�A�����f�B�Ȃ��₵�Ȃ��B�ŁA������̃h���}�[���A�u�ǂ����������Ă�A���܂��́H�v�ƃo���h�S�������q���V���N�����ƂɂȂ����B
�@���Ȃ݂ɁA���̍��u���̃e�[�}���āA�^���^�����ʂ��c�Ɏ��Ă��ȁv�ƌ��������T�C�h�M�^�[���́A���̌�u���ʂ����v�ƌ����ď����̂ɂȂ����c�̂����A������Ă����������玗�Ă�H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@����Ȑl�Ԃ̎��̕s�m�����̂����Łu�q�b�g�Ȃ̓�����v�Ƃ����̂����X�j���[�X�ɂȂ邪�A�u���Ă���v�Ǝv���̂͐l���ꂼ�ꂾ����A���������͂悭������Ȃ��B�����f�B�̍\�������܂�����蓯���ł��Ȓ����Ⴄ�����Łu���Ĕ�Ȃ���́v�ɂȂ邱�Ƃ�����A�������Q�����R�������������Łu�ǂ����璮���Ă��\�b�N���v�ɂȂ邱�Ƃ����邩�炾�B
�@�������������Ɍ����Ă��܂��A�u���b�N�v���u�W���Y�v���u���㉹�y�v���u���́v���A�����鉹�y�W�������͂��ׂē���̘A���łȂ肽���Ă���킯�ŁA�ꉹ�̖͕���Ȃ����S�ȁu�n��v�Ȃǂ��肦�Ȃ��B�����ŁA�N�����m���Ă���L���Ȃ��p�N��u�M�~�b�N�v�́i���h�ȓ���Ȃ���j���ċ�����邱�ƂɂȂ��Ă��āA�x�[�g�[���F�������R�Ɛ^�������u���[���X���}�[���[�����V�}�c���A���Ɂu����v�ƌ��w������邱�Ƃ͂Ȃ��i�c�ł���ˁH�j�B
�@�����A���Ȃ����������ėL���ɂȂ�����b�c������Ėׂ������肷��ƁA�N���[�����t�����Ƃ�����̂ŁA�v���ӁB�܂�A���́u���삷��Ƃ����s�ׁv���̂��̂̑P���ł͂Ȃ��A���삳�ꂽ���ƂŐ�ɍ������҂Ɂu��Q�z�v���o���Ǝv����ꍇ�Ɍ����āA�@�������Ⴕ���o�Ă���c�Ƃ������ƂȂ̂��B���ꂾ����A�|�b�v�X�n�̍�ȉƂɂȂǕ|���ĂƂĂ��c�ȉ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�������N�F���B�V���k�̉��g�^�����A�L�i�J�����[�^�E�g�E�L���E�j
�@�c�ȂǂƂ��������̂�����݂��������ꂽ�����F�����N�ɂ��S�U�͔��\���ɂ���Ԓ����s�A�m�Ȃ́A�q���h�D�[���̐_���B�V���k�ɂ悹���lj�B������̍\�z����͒N�ł����V�A����z�N����ɈႢ�Ȃ��̂�����ǁA����Ȃ��Ƃ͕S�����m�̗͋Z�ŁA�s�A�m�Ƃ����y��ւ̐V��������ƂƂ��ɁA��l�����ւ̃I�[�h�i��́j�����ݍ����삪�d�オ�����B��������ĉ��y�j�͉ߋ����疢���ւƌq�����Ă䂭�킯���B
�����L�I�E�v���C�Y�E���R���}�i�\�j�[�j
�@����A�s�A�j�X�g���R�K�Y���A���̖��G�̃e�N�j�b�N����g���ăs�A�m�Ȃ̎��쎩���ɒ���B���t�}�j�m�t�A�V���p���A�h�r���b�V�[�A�o�b�n�A���V�A����h�������ȉƂ����ւ̎]�̂荞�݂A�ޓƎ��̗͊����ӂ��L���L�������s�A�j�Y��������B���̐����ŃR���`�F���g�܂Ŏ��L���A�V���I�̋��͂ȃR���|�[�U�[�E�s�A�j�X�g�a����������Ȃ��i�����j�I
��38��u��Ԃɂ�ݒ��쌠�l�i���㉹�y�ҁj�v
�@�O��A�����f�B�̒��쌠���ɂ��ď������Ƃ���u�\���y�ɂ͒��쌠���Ă����ł����ˁH�v�Ƃ����Ƃڂ������₪�����B
�@����Ⴀ�A�������u����v�낤�B���̑g�ݍ��킹�ł���ȏ�A���앨�Ƃ��ėL���ȁu�����f�B�v�����݂���킯�����A�͂�����Ɛ��l���ł��鉹��ŏo���Ă������o�^���������B������A�Ⴆ�u1-9-5-11-3-7-2-4-10-8-12-6�v�Ƃ�������ŏ����ꂽ�ׂׂ��̃I�[�P�X�g���Ȃɑ��āA�S����������ŏ������|�|�|���̃s�A�m�Ȃ��������Ƃ�����A����͖��炩�Ɂu���쌠�N�Q�v�̂͂��B
�@���łɁA���̉���ƈꃖ���������Ȃ��u1-9-5-11-3-2-7-4-10-8-12-6�v�Ȃ�ĉ���ŏ����ꂽ�S�S�S���̌��y�l�d�t�Ȃ��������Ƃ��āA����͍ٔ��N�����ꂽ���u����v�ɂȂ�B�Ȃɂ���A�o�^����Ă��郁���f�B�͂������萔���ɂȂ��Ă��邩���r���ȒP�B�P���ɉ����E�����͔�r����A���w�����x���̎Z���ł�12����11�i91.6���j�̐��x�œ���ƌ����邱�ƂɂȂ�̂�����A��������͏o���Ȃ��B��́u�̈Ӂv���u���R�v���ŁA�������z���ς�邭�炢���낤���B
�@����ł́u�����v�Ƃ����̂͂ǂ��Ȃ̂��낤�H�@
�@�Ⴆ�`�Ƃ��������f�B�Ƃa�Ƃ��������f�B�������u�N�������Ă��܂����������ɕ�������v�Ƃ�����A����͓���ł��蒘�쌠�N�Q�ł���c�͂��B�����āA�����̃����f�B�Ƃ����̂͂܂������u�N�������Ă��܂����������ɕ�������v�㕨�i�����Ƃ��u���ׂē����v�ƌ����Ό����邪�A�u���ׂĈႤ�v�ƌ����Ό����Ȃ����Ȃ����j�B�Ƃ������Ƃ́u�����f�B�Ƃ��Ă͂܂������L���ł��Ȃ����̗���v�Ƃ����R���Z�v�g�́u�����v�̉��y�́A���ׂāu�����v�Ƃ����������f�B�́u���앨�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃɂ���i���ǂ��悤�����j�u�N�������Ă��܂����������ɕ�������v�̂��B�V�����u���앨�v�Ƃ͔F�߂������ł͂Ȃ����B�������A�ŏ��ɖ����ʼn��y����������ȉƁi�N���낤�H�j�́A��������ł����Ղ�50�N�ȏ�͗����Ă��邾�낤����A���쌠�͊�����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����B
�@���������A�O�X��A�W�����E�P�[�W�́u�S���R�R�b�v�i�S���R�R�b�Ԓ��ق��鉹�y�j�ɒ��쌠������Ƃ���������|�̋L�����Љ�����A�u�O���O�O�b�v�i�Ȏ��̂��O���O�O�b�̉��y�j�ɂ�����낤���H�@���쌠�g�p���͂T���܂ł���1000�~�A�P�O���܂ł���1500�~�Ƃ����悤�ɉ��t���Ԃŋ��z�����܂�̂����ʂ�����A����ōs���ƂO���O�O�b�ł͒��쌠�͂����Ă��g�p���̓[���Ƃ������ƁH�@���邢�́u�O�h���O�Z���g�v�̏��؎�i�j�ŕ����낤���H�@
�@�܂��A�����△���͂Ƃ������Ƃ��āA�u�s���a���v�Ƃ��u�g�[���E�N���X�^�[�v�͂ǂ��Ȃ̂��낤�B�Ⴆ�Δ������V�R�d�˂��s���a���Ƃ��A���y��Œቹ�̂b����ō����g�܂Ŕ����łт�����ł߂��N���X�^�[�A�Ȃ�Ă����̂ɂ����쌠�͂���낤���H�@������u�N�������Ă��S�������ɕ�������v�Ƃ��������������N���A���Ă��邩��A��������ŕs���a����N���X�^�[��炵���痧�h�Ȓ��쌠�N�Q�ɂȂ肻�������A�����f�B�Ƃ͌����Ȃ�����A�A�����W�̗ގ��i�ҋȌ��̐N�Q�j�Ƃ������Ƃɂł��Ȃ�̂��낤���B���邢�́A�����b������a�܂ł̃N���X�^�[��������n�j�ɂȂ�낤���B�������́A��������ł��NJy��̃N���X�^�[�Ȃ�n�j�Ƃ��H�@
�@������Ȃɂ��A���㉹�y�ł́u�Ґ��v�ɂ��I���W�i�����앨�Ƃ��Ă̌�����^����ׂ��Ȃ̂����m��Ȃ��B�Ⴆ�A�s���̃X�R�A����W���߂܂�܂铐�ނ��A�ڔ��Ɣ��i�ƃI�[�P�X�g���c�Ȃ�ĕҐ��ŋȂ����������u����v�ƌ��w�����ꂻ�������A�N�����l�b�g�A���@�C�I�����A�`�F���A�s�A�m�Ƃ����Ґ��ŃJ���e�b�g�������čٔ����ɌĂ�A�u�l���̋Ȃ͒m��܂���ł����v�ƌ����Ă��ʂ�܂��B
�@�c�ȂǂȂǁA���㉹�y�E�ɂ͍l����Ɩ������Ȃ��Ȃ肻���ȕs�v�c�i�H�j�����悤�悵�Ă���B�����ɒN���i�N�����Č��Ȃ����m���B�ٔ������ǂ�Ȕ������o���̂���������ł͂Ȃ����B�i���������쌠���́A������҂��u�����N�Q����đ��Q�����������v�Ƃ����i�ׂ��N�����Ȃ���Ζ��ɂȂ�Ȃ��炵���̂ŁA���삳��Ă��N�Q����Ă��u��Q�z�v�ƌ����̂�����Ȃ��[���ɋ߂����㉹�y�E�ł́A�܂��A�o�J�炵���ĒN���i�ׂ��N�������Ȃ�Ďv��Ȃ��̂��낤�Ȃ��j
�@����ɂ��Ă��A�����l���Ă݂�ƃV�F�[���x���N���̊v���Ƃ����̂́u�����f�B����̂��邱�Ƃɂ���āA���쌠�Ƃ����l�������ꎩ�̂�����̂���v�z�v���������Ƃɉ��߂ċC�t���B���`��A�[���B���y�̍�����h�邪���g���f���Ȃ��A�i�[�L�[�㕨�������̂ł���B�i�����A��̂���Ă����E���т��Ƃ����Ȃ��̂��߂�������ǁj�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�����I�E�I�[���X�^�C���F��s�@�ɏ���Ď��E�`�s�A�m��i�W�i�n�C�y���I���j
�@�ƌ����킯�ŁA�A�i�[�L�[�Ȍ��㉹�y�����������Ȃ����Ƃ���ɁA�ʔ����b�c���]���荞��ł����B�I�[���X�^�C���̓��V�A�ɐ��܂ꂽ��A�����J�ɖS���A��\��ɂ��ēV�˃s�A�j�X�g���O�q���y��ȉƂƂ��Ĉꐢ���r���Ȃ���ˑR���ނ��A���炭�����s���̂܂܂������̂��A��N�i2002�N�j109�ŖS���Ȃ����Ƃ����s�v�c�Ȍo���̐l�B�u��s�@�ɏ���Ď��E�iSuicide in an Airplane�j�v�ȂǂƂ����^�C�g���Ńs�A�m�Ȃ���������炵�āA���̍앗�͑�̑z���ł���Ǝv�����A�S�҃A���O���E�o���o���B�v�����X���[���O�����h�s�A�m����Ɋi���Z�C���v�����B�[�C�V������������炱��Ȋ����c���B�u1917�N�̎��v��Q�ȁu��]�̎���܂��l�v�Ƃ��A�A���x�X�N��X�ԁu���K���r�ꋶ�����v�A�s�A�m�E�\�i�^��W�ԑ�Q�y�́u�����������ւ̗��`�i���Ɏ���ꂽ�q��������v���ė܂����H�v�ȂǂƂ�����ȃ^�C�g�����ʔ����B
���t�H�X�^�[�F�s�A�m�ȑS�W���ҋȏW�i�v���E�s�A�m�j
�@�c�ƁA�A�i�[�L�[�ȃs�A�m������A�m�X�^���W�b�N�ȃs�A�m�����������Ȃ����B�ƌ����킯�ŁA�Ō�̓t�H�X�^�[�B�����̃W�F�j�[�A������l�A�l���[�E�u���C�A�P���^�b�L�[�̂킪�Ɓc�ǂ��������������������ŋ��D��U���B����́A�ǂ��܂ł��u�����f�B�v�̉��y�B�ł��A�S���Ȃ��ĕS�O�\���N�قǂ����Ă���̂Œ��쌠�͏��ł��Ă���͂��B�܂��A�m���ɂ��̃��x���ɂȂ�ƍ�Ȏ҂̏��L���Ȃǂł͂Ȃ��A�l�ދ��L�̕����Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�Ȃ��B�����v���Ɓu�����v�Ƃ������z�͂Ȃ�Ƃ����n�����B�����I���ɂ́u���쌠�v�ȂǂƂ����������炯�̎v�z�ɕς�邫����Ƃ����u���y�ی�V�X�e���v���o���邱�Ƃ�ɋF�肽���B
��39��u�t�@�E�X�g�̖�A���t�B�X�g�̒��v
�@���N�������T�ڂ̌����Ȃ��u�t�@�E�X�g�����ȁv�d���Ăɂ��Ă���A���ƂȂ����̊�ȕ���ɂӂ����ю䂩���悤�ɂȂ����B
�@�����Q�[�e�ɂ��u�t�@�E�X�g�v�̋���ȕ���́A���ɐF�X�Ȓf�ʂ������Ă��邯��ǁA�����ĊO�ʓI�Ɍ���A�V�w�҃t�@�E�X�g���m���������t�B�X�g�t�F���X�ƌ_�A��Ԃ��Ď���������܂��܂ȑ̌�������i�S�Q���ɂ���Ԓ���ȁj����Ƃł��������炢�����낤���B
�@�����Ƃ��A�ŏ��ɓǂ��Z���̍��́A�u������x���܂�ς���ĎႳ�����߂������v�Ȃǂƌ����v���́A�Ⴓ�̂������ɂ���g�䂦�Ƃ�ƕ�����Ȃ���������A�u�����Ƃ̌_��v�Ƃ����}����������ۂɎc�����ŁA���قǖ��͓I�ȕ���ɂ͎v���Ȃ������̂����B
�@���������̌�A�Ⴆ�x�����I�[�Y�́u�t�@�E�X�g�̍����v��X�g�́u�t�@�E�X�g�����ȁv���邢�̓I�y���Ƃ��Ắu�t�@�E�X�g�v�i�O�m�[�j��u���t�B�X�g�t�F���X�v�i�{�[�C�g�j��u�t�@�E�X�g���m�v�i�u�]�[�j�j�A�^���t�@�E�X�g����ł���`���C�R�t�X�L�[�́u�}���t���b�h�����ȁv�A�t�@�E�X�g�̎���S�ʂɎg�����}�[���[�́u�����ȑ�W�ԁv�A�t�@�E�X�g�����Ȏd���ẴV���X�^�R�[���B�`�́u�����ȑ�10�ԁv�ȂǂȂǁA���y�j�̒��́u�䂪�i�����j�E�t�@�E�X�g�v�̗����m�邱�ƂɂȂ�A���̈�ۂ͂����Ԃ�ώ����čs�����悤�ȋC������B
�@����ɁA���{�̋ߑ㕶�w�j�̒��ɂ��A�X���O�́u�t�@�E�X�g�i�S��j�v�Ɏn�܂�A�k�����J�́u�H���ȁv�A�����ւ́u���o���E���V�فv�A����ɂ͎�ˎ����́u�l�I�E�t�@�E�X�g�v�Ɏ���u�䂪�t�@�E�X�g�v�̌n�������邱�Ƃɂ��C�t���A���Ȃ�F�������߂邱�ƂɂȂ����B
�@�����A���݂̐l���Ƃ��Ẵt�@�E�X�g�́A��s�Œm��ꂽ�����̘B���p�t�i���\�t�H�j�ŁA���������w�����̖��ɔ���������Ȑl���ȂƂ��B���̓`�����A�Q�[�e�����R�ɖ|�Ă���ɂ������ẮA�d���E���ŏ��Y���ꂽ�ꏗ���ւ̓�������Ȃ�D�荞�肵�Ă��Ă��邩��A�����J�ɗ��z���Ă����t�@�E�X�g�`���Ƃ͂����Ԏ�Ⴄ�B
�@�����������m���Ɍ����ƁA�u�n��ł̉��y���̂ĂĒm�����ɂߑ����A���ɘV�w�҂ƂȂ����v�Ƃ����t�@�E�X�g���m�̏�Ԃ́u���̋��n�v�Ȃ̂�����A���ꂪ���̒��O�Ɉ����Əo����āu����ς�i������x��Ԃ��āj�n��ł̉��y�ɐ������ꂽ���I�v�Ȃǂƌ�����̂́u�ϔY�v�̂���݁B�����J���ē��Œ��O�̘V�m���u����ς菗����������I�v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂ŁA���Ȃ�̔j���V��Ƃ��������悤���Ȃ��B���܂�ɐ��X��������ǁA�܂��A��͂�j�͂����Ȃ̂����m��Ȃ��c�ƁA�Ȃ�ƂȂ��[�������Ă��܂��B
�@�������A���̌��ʁA�Ⴂ�����}���K���[�e�i�O���[�`�F���j�ƍs������̗������������D�P�����A�ޏ��͕������q�����ɂ�����E���ĎE�l�߂ɖ���A�������C���G��Ă��܂��Ƃ����ߌ����ĂԂ̂��Q�[�e�̃t�@�E�X�g村�ꕔ�B���̂����A�Ō�Ɉ����Ƃ̓q���ɕ����Ēn���ɗ����鎞�A���̃O���[�`�F���̍��i�i���ɂ��ď����I�Ȃ���́j�ɂ���ċ~�ς���ēV���ɍs���B���̂�����A�����ǎ҂ɂ͋�����ꂻ���ɂȂ��W�J���B
�@�L���X�g���I�Ȕw�i���Ȃ���i�����Ă��j����s�\�Ȃ��̕���ɁA�䂪���̋ߑ㕶�w�̍�Ƃ�����������ꂽ�̂́A�ǂ���疾���ȍ~�̐������ɂ���ē��{�l�̐S�̒��ɏ��߂āi���m���́j�u����v�Ƃ����T�O���萶�������Ƃ��痈����̂炵���B�Ⴆ�A�����ւ��u�킪���V�L����v�Ƒ肵�č\�z���n�ߖ����ɏI������u���v�̃V���[�Y�ł́A��̒�ɏZ�ޗd���ɉ߂��Ȃ���������A�O���@�t�⑷���⒖�����Əo����āu����v�ɔY�ޕ���ɕώ�����Ă���̂��ʔ����B
�@����Ɏ�ˎ����̐�M�ƂȂ��������́u�l�I�E�t�@�E�X�g�v�ł́A1970�N��̓�����ɘV�w�҃t�@�E�X�g�i��m�֔��m�j�Ǝ�Ԃ����N�t�@�E�X�g���^�C���E�p���h�b�N�X�d���Ăŕ��сA�������t�B�X�g�͏����Ƃ��ēo�ꂵ�A����Ƀz�����N���X杂��N���[���Z�p�̘b�ւƃV�t�g�������肵�Ă��āA����߂Č���I�����͓I�ȃA�����W���������Ă���B
�@�Ȃ�قǁA�ǂ�Ȏ���ł��j�͎��Ȃ̑��݂ɔY�݁A������l���ւƗU���Ă���鈫����Җ]���A��X�������݂̂悤�Ɍ����Ď��͎��ȕۑ��̌������鏗���ɖ|�M����A�o�J�Ȃ��Ƃ��Əd�X�m��Ȃ��猻���̉��y�i�x�E���́E����etc�j��ǂ����߂�c�Ƃ����㕨�Ȃ̂炵���B�i�����j
�@�Ƃ���ƁA������ēW�J����t�@�E�X�g杂̋��傳���A���͂����u�V�l�����̒��O�Ɍ������v�ŁA�߂������ڏ��ȁu�͂��Ȃ����v�Ȃ̂����m��Ȃ��B�m���ɁA�j�́i�Q�[�e���Ō�ɍ����ʼn̂킹���悤�Ɂj�u�i���ɂ��ď����I�Ȃ���́v�ɋ~�ς���邵���~�����Ȃ��⏬�ȑ��݂̂悤�ȋC������B
�@���̓_�A���̕���͗ǂ����������u�j�v��j�̑�����`�������̂�����A���邢�͏����̃t�@�E�X�g��ł���l���ɂ�����A�܂�����������u�t�@�E�X�g����v���o����ɈႢ�Ȃ��B�i���̏ꍇ�́A����������ς菗�����낤�Ȃ��j
�@���Ȃ݂ɁA���y�I�Ƀt�@�E�X�g杂���͂���A���i�t�@�E�X�g�j���A�����i���a�����邢�͕s���a���j�ɖ|�M����Ȃ�����A�i���Ȃ鑶�݁i��a���j�ɓ�����ďI�~�`���}����c�Ƃ����h���}�B�m���ɁA��������s���a�����o�ꂵ�Ȃ���A�l�͋��a���Ɍ������Ď��ʂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B���̕��ꂪ�����̍�ȉƂ𖣗����Ă����̂����̂����Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���n���K���[�̃`�F�����y�`�`�F���̒���^�V�l�P���X�E�f�r���[�i�L���O�E�C���^�[�i�V���i���j
�@�����������i�\���E���B�I���jMy BACH plus ONE�i���C���m�[�c�j
�@�t�@�E�X�g���̎v���ɂ́A�Ƒt�`�F���i���B�I���j���悭�������B�`�F���̃P���X�̃A���o���́A�V���^���P���̉��t�ŗL���ɂȂ����R�_�[�C�́u�����t�`�F���E�\�i�^�v���j�ɁA����n���K���[�̍�ȉƃN���^�[�O����у��F���V���̏a����i��z���āA�Â��X�̒��̍��̉̂�����B����̏��������̃A���o���́A�o�b�n�̖����t�`�F���g�ȂQ��Ƃo.�p�^�[�\���ɂ�錻���i���烔�B�I���Ǝ��́i���ɔ�߂���M�����߂��悤�ȁj���ȓI�ȋ����������o���B�Q�����ׂĒ����ƁA�t�@�E�X�g���m�i�`�F���j�Ə���̃��[�O�i�[�i���B�I���j�Ƃ������������B�@
��40��u���̂��Ɓv
�@����A����S�������B
�@���������������w���̎��A�ŏ��Ɂu�X�R�A�v�Ƃ������̂������Ă��ꂽ�̂�������������A��ȉƂɂȂ��Ă��܂����͕̂��̉e���i�����j�ƌ����Ă����B�������A���C�̐^�ʖڂȋZ�p�n��Ј��ł��镃�́A���q�����y�ȂǂƂ��������ҋƂ�����邱�Ƃɂ��ẮA�����܂ł������Ă����B
�@����ł��A�Ⴂ���A�}�`���A�E�I�[�P�X�g���Ńt���[�g�𐁂��Ă������Ƃ����������́A�y����X�R�A�����\�����Ă����B�����Ŕ������y���̓s�A�m��t���[�g�̊y���ŁA�I�[�P�X�g���̃X�R�A�͑c�����R���N�V�������Ă����r�o�ɕt���Ă������̂����������悤���B�c���̎���̂r�o�͕ЖʂT���قǂ������^�ł��Ȃ���������A�����Ȃ⋦�t�ȂȂǂ͐�������\�����̒��d�ʋ��A���o���ƂȂ�A����ɂ��܂��Ƃ��ăX�R�A���t���Ă����̂ł���B
�@���́A�����p����C�[�Y�̂k�o���̂��D���ŁA�C�������Ƃ悭�h�b�v���[�́u�n���K���[�c�����z�ȁv��r�[�[�́u�A�����̏��v�Ȃǂ𐁂��Ă����B���̍��͉Ƃɂ͂܂������ȑ�ヌ�R�[�h�E�v���C���[�����Ȃ��������A����ł��\�m�V�[�g�i�Ⴂ�l�͒m��Ȃ����낤�Ȃ��j�̃N���V�b�N���ȑS�W�ȂǂŁA�����f���X�]�[����`���C�R�t�X�L�[�����Ă��ꂽ�̂������Ă���B
�@����ȕ����A�������w�Z�ɏオ��������ŏ��ɔ����Ă��ꂽ�k�o���A�v���R�t�B�G�t�́u�s�[�^�[�ƘT�v�ƃu���e���́u���N�̂��߂̊nj��y����v�����\�ɂȂ����ꖇ�������i����������Ǝq�������̃��R�[�h�����肻���Ȃ��̂����c�j�B�i���[�V�����͉p�ꂾ�������A����ł��i�����C�ɓ������̂��j�����Ԃ�J��Ԃ��J��Ԃ������Ă����L��������B
�@���́A���㕨�͂��܂�D���łȂ��c�ƌ������Ă������A���̃v���R�t�B�G�t��u���e���̂ق��A�k�o�̃R���N�V�����ɂ̓h�r���b�V�[�́u�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁv��u��z�ȁv�A�V���X�^�R�[���B�`�́u�����ȑ�T�ԁv�i�m���~�g���p�E���X�̎w������A���Ղ������j�Ȃǂ�����������A���\�q�V�����̍D���r�ƌ����Ȃ����Ȃ��B�i���Ȃ݂ɑc���̂r�o�R���N�V�����ɂ́A�Ȃ�ƃV�F�[���x���N��o���g�[�N�̌��y�l�d�t�Ȃ���߉q�G���̉z�V�y�܂ł����āA������Ƌ��������Ƃ�����B�������A�����͑I��Ŕ��������̂ł͂Ȃ��A�����Еz�̂悤�Ȍ`�ő����Ă������̂炵���B�c�����ǂ�Ȋ�����ăV�F�[���x���N�������A�z������Ƃ��������̂����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���Ԃ́A�c���i���̑]�c���j����҂��������Ƃ������āA�����Ɂu���q���i�o����j��҂Ɂc�v�Ǝv���Ă����悤�ȋC������i���̑]�c���́A�Ȃ�ƓV�c�Ƃ̎��������Ă����l�Ȃ̂ł���j�B�������A���Ɂu������v�ƌ���ꂽ���Ƃ͈�x���Ȃ��B�����g���A�Ƃɂ����C���t���Ɗ��Ɍ������Ė{��ǂ�ł��邩����������Ă���l����������A����������͎̂��R�Ȃ��Ƃ��ƍ��荞�܂�Ă����悤���B
�@�����A�������W�I�ɋ��������Ɠd�C��H��z���}�ɂ��ď����Ă���{��ق��Ď����ė�����A���������ɋ��������Ɖ������~�X�e���[�̖{���A���ɋ��������ƓV���w���̃M���V���_�b�̖{���̂��u�ق�v�ƌ����Ă����c�Ƃ��������́u�㉟���v�͂��Ă����悤�ȋC������B�ʂɁu�ǂ߁v�Ƃ͌���Ȃ��B�u����Ȃ̂�����v�Ǝ�n���Ă���邾���Ȃ̂����B
�@����Ȗ{�̒��Ɂu�����H�w�v��u���㕨���w�v��u���p�͊w�v�̖{����������A�Q�[�e�́u�t�@�E�X�g�v����������A�u���b�h�x���́u�ΐ��N��L�v����������A�N���X�e�B�́u�����ĒN�����Ȃ��Ȃ����v����������A��ˎ����́u�S�r�A�g���v���������肵�A����Ƀx�[�g�[���F���́u�^���v�̃X�R�A���������肵���킯�ł���B
�@���̕��́A������������u�}���K�v���́u�����ԁv���́u�M�^�[�v���́u�����v���́u�r�e�v���́u���q�����w�v���́u���G�v���́u��w�v���̂ƁA���ꂱ������P�ʂł��낱��Ƌ�����ς���q���������̂ŁA�u��ȉƂɂȂ�B��w�͂�߂�I�v�ƌ����o���������A���Ƃ��Ă͍ŏ��u�ǂ����O���邾�낤�v���炢�Ɏv���Ă����悤�������B
�@���ꂪ�A���e�̔����������Ė{���ɑ�w����߁A�����ɖ��E�������́u��ȉƉҋƁv���n�߂Ă��܂����Ƃ����̂́A���v���ň��̐e�s�F�������B������������Ȃ��������A���~�S�݂����ȎO��Ԃ��������o�Ȃ��悤�Ȑ������V�`�W�N������ԁA�u�C���G�ꂽ�s�т̑��q�v�Ƃ��ĕ��̓��̒��ł͎��̑��݂͕���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���ꂪ�A�悤�₭���Ƃ���ȉƂƂ��Đ��ɏo����悤�ɂȂ�A�����u���͑��q�͍�Ȃ�����Ă��܂��āc�v�Ɛl�l�Ɂi�����Łj������悤�ɂȂ�܂łɏ\���N�B�����āA�e�l��V����b�c�Ȃǂ̃��f�B�A�ō�ȉƂƂ��ĔF�m����A�������ʂɁu���q�͍�ȉƂł��v�ƌ�����悤�ɂȂ�܂ł���\���N�B�V��̌����Ȃ������ĕ����j�R�j�R�Ə����ɋ삯�t���Ă����悤�ɂȂ�܂ŁA�Ȃ�ƎO�\�N�߂������������ƂɂȂ�B
�@�����S���Ȃ������A�������̐V�����]�ڂ����B���̕��ʂ̂قƂ�ǂ́u��ȉƂ̋g��������̕��A�g�����������v�Ƃ������̂��������A�����ǂ�ł�����A�u�������B�ڂ��̌������́A��ȉƂ̕��c���v�ƌ����ċ�����镃�̊炪�A�ӂƌ������悤�ȋC�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�������O�^�nj��y��i�W�Q�i�a�h�r�j
�@�߂���������������Ȃ������������Ԃɂ́A�����������̍�i�̑�C�ɕY���G�[�e���̂悤�ȒW�����S�n�悢�B���B�I�����j�ɂ����u�A�E�X�g�����O�E�A���E���h�E�I�[�^���v�A�t���[�g���j�ɂ����u�E�H�[�^�[�E�h���[�~���O�v�A�s�A�m���j�ɂ����u�����@�[�����v�A�ǂ�������ɖ����������̐��E�B���C�����鎞�ɂ́A�Â����邢�コ�ɒ������邱�Ƃ����邪�A������ƌ��C�̂Ȃ����ɂ͂��̗D���������₫�ɖ������B
�@�����|�^���F�[�������ꂽ�C���X�i���@�[�W���E�N���V�b�N�X�j
�@�����ꖇ�A���E�߂̒��|�i�`�F���E�L�K���j�́A���V�A���剺�̐V��������̌��㒆���l��ȉƁB�t���V�A���䂸��̂����ґz�I�ȃA�_�[�W���̐��E�́A�^�P�~�c�E�g�[���ɑ��ʂ���Ƃ��������A�Ђ��Ђ��ƐÂ��ɔ����L����������n�[���j�[�ƁA�����������ɒ��ؕ��̃T�E���h���G�R�[����F�ʊ����ƂĂ����ꂢ�B�^���E�h�D�������菟���̕����Ȃ�A������͒[���ȋZ�I�h�̏����Y�c���B�i�̂��������������H�̂悤�Ȑ��k�ȉ��y�c�B�@
��41��u�l�ԂȂ�āv
�@���������ƂɁu���̒��ɂ́A�ǂ�Ȃɘb���Ă�������Ȃ��l����������v�B2003�N�́A���E�������̂��Ƃ��v���m�����N�Ƃ��ė��j�ɋL������邱�Ƃ��낤�B
�@�������u����Ȃ��Ƃ͕�����������Ƃ���v�Ƃł��������łԂ₭��l�������̂��낤����ǁA��\�ꐢ�I�i����͒������Ƃ�������́u�����v�������̂Ɂj�ɂȂ��Ă܂��R�N���o���Ȃ������ɁA����������ɉ��ƌ��Ƒ����݂ʼn����Ă��܂����̂�����A���̋��s�̘A���ɂ͈��R�Ƃ��邵���Ȃ��B�u�ȂA�l�Ԃɂ͂����K�b�J���ł���v�B�����ꂭ�N���̐��������������ȋC������B
�@�Ԃ������̂������̂��A���傤�Ǎ����̐V���ɃQ���M�G�t�w������V���X�^�R�[���B�`�́u���j���O���[�h�����ȁv�������āA�A�����J�R�̃o�O�_�b�h�Ɏn�܂����C���N�N�U�̃j���[�X�����ڂŌ��Ȃ��璮�����ƂɂȂ��Ă��܂����̂����A���j���O���[�h�ɐi�U���Ă䂭1941�N�̃i�`�X�E�h�C�c�R�ƁA�o�N�_�b�h�ɐi�U���Ă䂭2003�N�̃A�����J�R�́A�Ȃ����܂�ň����̂悤�ɂ������肾�B�Z�\�N�O�̓q�g���[�ƃX�^�[�����A���݂̓u�b�V���ƃt�Z�C���c�ƍ\�}�������B����͉����̏�k�Ȃ̂��낤���H
�@����ɂ��Ă��A���E�ɂ��ꂾ���l�Ԃ����āA���ꂼ�ꂪ�ꉞ�͎v�l�Ƃ������̂����Ă��āA�݂�Ȏ����⎩����������l�����ɂ悩��Ǝv�����Ƃ��l���Ă���B����Ȃ̂Ɂu�b���Ă�������Ȃ��z�v�Ɓu�b���Ă�������Ȃ��z�v���u�b���Ă�������Ȃ����R�v�Ő푈���n�߂Ă�����u�N���~�߂��Ȃ��v�c�Ƃ��������́A�|���c�Ƃ�������R�c�Ƃ������ɋ߂��B
�@�N�����������m��Ȃ����A�푈�ɂ��Ă���ȃW���[�N������B
�@�u���푈�͎^�������A
�@�@������푈�͔����v�@
�@�ł��A�N�������Ȃ��푈�Ȃǂ���͂����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�c�ȂǂƐ��E�I���n�̘b�����Ă����āA�����Ȃ莄���ɂȂ邪�A�ŋߕ���S�����A���j�Ƃ��Ă��̌�̂��낢��ȏ��������Ă��čl���������邱�Ƃ����X�������B
�@�ЂƂ́A�Љ�l����l���Ȃ��Ȃ�i���ʁA���邢�͏��ł���j���ƂŔ�������u�葱���v�̙ˑ傳�ɂ��āB�ːЁA�Z���[�A�N���A�ی��ȂǂȂǂɎn�܂�A���Ƃ��܂��܂ȕ�����ԍ����`�F�b�N���͂��o����ɏ��������˂Ȃ�Ȃ����Ƃ��B�Ŗ����ւ̔[�ŁA�N����ی��̖��`�ύX�A���邢�͌��N�ی��A�Ј��A�^�]�Ƌ��A�p�X�|�[�g�A�g�ѓd�b�ɃC���^�[�l�b�g�̃A�h���X�B�݂�ȉ����ԍ����t���Ă�����ɉ��̘A���Ƃ����̂��S�������A�ق��Ă����Ύ��R�ɐ�ď��ł��Ă��܂����̂����邪�A���Ȃ�̕��͂��ꂼ��͂��o�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�������A���̂��ꂼ��ɉ��������ƌːЁi���Ёj���{�ƏZ���[�ƈ�ӂƈ�ӏؖ��Ǝ��S�f�f�����v��B�i�^�葱���ŁA190�~���������̂ɑ����Łu��������⑰�S���̌ːГ��{�ƏZ���[�ƈ�ӂƈ�ӏؖ����c�v�ƌ���ꂽ���ɂ́A�{�C�ŃL�������ɂȂ����B�u�K���ł�����v�͕����邯��ǁA�����ɂ��u���̒��ɂ́A�ǂ�Ȃɘb���Ă�������Ȃ��l����������v�Ƃ����@���͐����Ă���炵���B�j�āB
�@���Ȃ݂ɁA���S�Ƃ��������Ɓi�l�̍��Y��ی삷��Ƃ������ڂŁj��s�����������ׂĕ������Ă��܂��Ƃ������Ƃ����߂Ēm�����B������100�~���낤��100���~���낤�ƁA���r�[�ɂ����͑������Y�ƂȂ�̂ŁA�Ȃ��낤���q���낤���g���Ȃ��Ȃ�B�g�����߂ɂ́u��������⑰�S���̌ːГ��{�ƏZ���[�ƈ�ӂƈ�ӏؖ��c����Ɉ�Y�������c���ȂǂȂǁv��Y�����͂��o���K�v�ŁA��������Ȃ��Ɠ��l�̂����������o�����Ƃ��o���Ȃ������łȂ��A���܂ŋ�s�U���ŕ����Ă����d�C�E�K�X�E�����E�d�b�̎x�������ׂĂ��~�܂��Ă��܂��B�⑰�ɂ���Ă͍��Y�̊��S�ȁu�����������v�ɓ��������ƂɂȂ�킯���B
�@�܂��A���̏ꍇ�͒��j�i���j���d���̍��Ԃ�D���Ă��̎G�����i�����������邩������Ȃ�����ǁj�R�c�R�c����Ă���킯�Ȃ̂����A���āA�Ƃ�g�Ŏ��ꍇ�͂��������̂͂ǂ��Ȃ�̂��낤�H�@�c�Ȃ����ʂ̂��ʓ|�ɂȂ��Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�c�ȂǂƂ����h�C�L���b�����Ă����āA�����Ȃ艽�Ȃ̂����A2003�N�S���V���̓A�g�������܂ꂽ���ł���B�������̒��ł̘b�����猻���ł͂Ȃ��̂����A�V����j���[�X�Ɂu�w�w���S���Ȃ�܂����v�Ƃ����ߋ��`�̎��S�L���͂����Ă��A�u�w�w�w�����܂�܂��v�Ƃ��������`�̒a���L���Ȃnj������Ƃ��Ȃ��B������A�Ȃ��f�G�ȃ��B�W�������Ȃ��c�ƑO�X����v���Ă����̂��B�ł��A�����������Ă�����ߋ��`�ɂȂ��Ă��܂����B������Ǝ₵���B
�@�v���A�g���̏��o��͈��܈�N�Ɂu���N�v�Ƃ����������ɘA�ڂ��ꂽ�u�A�g����g�v�Ƃ�������B�n���l�ƉF���l�Ƃ̐푈���~�߂���i������ŏ��̘A�ڎ��́u�A�g����g�v�Ƃ����^�C�g���j�������B�F������n���l��������̐l�������ږ��Ƃ��Ă���Ă���̂����A�����傫���ȊO�͒n���l�Ɠ����Ȃ����n���l�ЂƂ肠�����l�̃\�b�N���F���l������B�܂�n���̐l���͂����Ȃ�Q�{�ɂȂ�킯�ŁA���R�H�Ɩ�肪�N����A���̂��߉F���l��r�˂����E���悤�Ƃ���l�Ԃ��o�Ă��āA���ɂ͗��ҊԂł̐푈���n�܂�B
�@���̉F���l���E�̒��S�l�����A�g���̐��݂̐e�ł���V�n���m�i�Ȋw�Ȓ����ɂ��Ĕ閧�x�@�����j�Ƃ����l�ŁA���R�Ȃ���A�g���́i���{�b�g�Ƃ�������Ȃ���j��ʂ̒n���l�����Ɠ��l�ɕ��a�I�ȉ�����]�ނ킯�����A�ƍَ҂Ɖ����Ă���V�n���m�ɂ͂܂�������������Ă��炦�Ȃ��B�����ŁA�ނ̏\���n�͂͏��߂āu�ǂ�Ȃɘb���Ă�������Ȃ��l�����i���������݂̐e�j�v�Ɍ����Ď{�s�����̂��B
 �@�������Ő푈�͉�����ꂽ�̂����A�ރA�g���͈Ȍ�u���̒��ɂ́A�ǂ�Ȃɘb���Ă�������Ȃ��l����������v�Ƃ������]�Ƃ���]�Ƃ��t���Ȃ��߂��݂ɑς��Ȃ���A�l�ԂƐl�ԂłȂ����́i���{�b�g�j�Ƃ̊Ԃɋ��܂�Ȃ���Y�ݑ����邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�A�g��杂Ȃ̂ł���B
�@�������Ő푈�͉�����ꂽ�̂����A�ރA�g���͈Ȍ�u���̒��ɂ́A�ǂ�Ȃɘb���Ă�������Ȃ��l����������v�Ƃ������]�Ƃ���]�Ƃ��t���Ȃ��߂��݂ɑς��Ȃ���A�l�ԂƐl�ԂłȂ����́i���{�b�g�j�Ƃ̊Ԃɋ��܂�Ȃ���Y�ݑ����邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�A�g��杂Ȃ̂ł���B�@�����āA�����́A�A�g�������Ȃ��Đ푈�͂���Ƃ������ȓ�\�ꐢ�I�ɐ����Ă䂭�c�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���V���X�^�R�[���B�`�F�����ȑ�V�ԁu���j���O���[�h�v�^�Q���M�G�t�i�t�B���b�v�X�j
�@���A�X�g���{�[�C�E�S�r�A�g���^�I���W�i���E�T�E���h�E�g���b�N�E�X�R�A�i�\�j�[�j
��42��u�䂪���͑�T�v
�@���せ�N�Ɏn���������̌����Ȃ̃V���[�Y���A�悤�₭�`���̃i���o�[�u��T�ԁv�܂ŕ���i�߂邱�Ƃ��o�����B�����K�v���Ƃa�a�b�t�B���ɂ��V�����h�X�E���[�x���ł̘^���������ɐi�݁A����̑�T�����߂��A���o���łU���ڂƂȂ�B�܂����A�����Ă��邤���Ɏ����̑S�����Ȃ��b�c�Œ�����悤�ɂȂ�Ƃ͎v���Ă����Ȃ������̂ŁA���̍�ȉƖ����ɐs����K�^�ɂ͐S���犴�ӁB
�@���Ȃ݂ɁA����b�c�W���P�b�g�̃f�U�C���́u���Ă̂��y���݁v�Ȃ̂����A�w�i�ɑ傫���u�u�v�i�������u�T�v���j���������ꂽ����̃f�U�C���ɂ͂������ɏ����g���������܂�v���B�����Ă��u�����ȁv�A�����Ă��u��T�v�Ȃ̂��Ȃ��c�Ɩ��ȁi�ƌ������A�ςȁj�������S���悬��B���̂悤�ȁq����҂�V���t�H�j�X�g�r�ɂƂ��Ă��u�T�v�͂�͂�u���Ȃ鐔���v�Ȃ̂ł���B
�@����A�m���ɁA���m���y�j�Ƃ͖����̌��㓌���ɐ����鎄�Ƃ��ẮA���ɂׁ[�g�[���F���搶�Ȍ�̉��y��Y�𑊑����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǂƂ����`���͊����Ă��Ȃ��B�����u�ܐ����i�X�R�A�j�v�Ƃ����\�t�g�E�E�G�A�œ����u�I�[�P�X�g���v�Ƃ��������������W���[����ɂ��āu��i�v������Ă��邾���B�ł��A�u�����ȁv�Ƃ������O���g�p���Ă���ȏ�A�����ɌÍ��̍�ȉƏ���y���̎c���v�O�i���O�H�j���w���̂悤�Ɏ��߂��Ă��邱�Ƃ͔ے�ł������ɂȂ��B
�@�Ȃɂ����T�ԂƂ������ƂŌ���ʂ�u�W���W���W���W���[���v�̉^���̃��`�[�t�Ŏn�܂�A�I�y�͂̓n�����̎�a���ŏI���c�Ƃ����_��������ʏ��ƁB�������A���p�ł��p���f�B�ł��Ȃ��A�}�W�i�{�C�j�Ȃ̂�����|���B�������A����͂������Z���̎��Ɂu�����Ȃ����������b!�v�Ǝv�����u�Ԃ��猈�߂Ă������ƂȂ���d�����Ȃ��B�������F�X�Ȑl����u�E�\�ł���I�v�ƌ���ꑱ�������A�����ł��i���́u��5�v���̂���p���������̂Ɂj����Ȓp���������̓��O��݂����Ȃ��Ƃ��{���ɏo����̂��ǂ����A����߂ċ^��ł͂������̂�����ǁc�B
�@�ł��A����Ă��܂����B���̓_�ɂ��ẮA�w���ɂ��������}�G�X�g���E�t�W�I�J�ɂ��u���V�}�c���`��A����U���ĂĒp���������ł���`�v�ƎU�X����ꂽ�B������O���B�l�Ԃ̂����Ƃ���肽�����ƁA����Ă����Ƃ��C�����ǂ����Ƃ́A�p�����������ƂɌ��܂��Ă���B����ɁA�N���V�b�N�E�̖��Ȃ��v�������ׂČ����܂��B�ǂ��������p�������`���e�[�}�ŏo���Ă���ł͂Ȃ����B���łɁA��T�Ԃƌ����ׁ̂͂[�g�[���F���搶���n�߃`���C�R�t�X�L�[��V�x���E�X��}�[���[��V���X�^�R�[���B�`�Ɏ���܂ŁA�ǂ������������p���������܂ł́u���o�J�v���Ɓu���v�I�ȏ�������Ǝv���̂����@���H
�@�c�ȂǂƂʂ��ʂ��ƃN���V�b�N�̌����ȍ�Ɛ搶�����̖��O������ɋ������肷����̂�����A������Ɩ��f����Ɓu����Ƃ�������Ɍ����Ȃ������Ӗ��́H�v�Ȃǂƒ�����邱�Ƃ�����B�ł��A�ʂɌ���łȂ��Ă��ׁ[�g�[���F���̎���ł��u���[���X�̎���ł��A�����Ȃ������̂ɈӖ�������������ȂǑ��݂��������͂Ȃ��B�l�Ԃ����ē����ŁA�u����ɐ��܂��Ӗ��́H�v�ƒ�����ē��������낤�͂����Ȃ��B����ł����܂��B���܂�Ă��܂��B���ꂪ�l�Ԃł���A�����Č����ȂȂ̂��Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@�����Łu�Ȃ��I�[�P�X�g���ŁA�Ȃ������ȂȂ�ł����H�v�Ƃ����₢�B�����A�`���ƌ���Ɠ��������݂��Ă��铌���Łu�m���v����Ɂu���{���ł͂Ȃ��A���m���[���b�p���̂��ł����v�ƈӎ����Ē��Ă���l�͂��Ȃ��悤�ɁA���͂�I�[�P�X�g�������Ɂu���m���[���b�p���v�ł͂Ȃ��B�ނ���V���Z�T�C�U�[�̉������W���[����b�N�E�o���h�Ɠ����悤�ɁA�u�l�X�Ȋy�z��y�킪���R�ɃI�v�V�����Œ��E�\�ȃx���[���j�̂悤�ȉ��y���j�b�g�v�Ƒ�����������R�ȋC������B
�@����䂦�ɂ����A�����ɗl�X�ȉ��y�̑f�ނ�C���[�W��g�ݍ��ނ��Ƃ��o����B�������A����𐧌䂷��u�ܐ����i�X�R�A�j�v�Ƃ����\�t�g�͖������ʂŁA�S�N�O�ł�����ł��A�����ł��x�������ł��p���ł��i�قځj�����悤�ɋ@�\����B�������A�ߑ�I�[�P�X�g���̋@�\��d�l�Ƃ�����A�u���[���X�搶��`���C�R�t�X�L�[�搶�̎���Ƃ͎��Ĕ�Ȃ鍂���\�Ԃ�Ȃ̂��B���Ɂu���㉹�y�v��u�d�q���y�v�̎�����o�āA���̐F�ʂ̃p���b�g�̑��ʂ��͊i�i�̐i�����ʂ����Ă���B
�@���̂����A�������̎���̓N���V�b�N�̍�ȉƂ������m�肦�Ȃ������l�X�ȁi�����ęˑ�ȁj�^�C�v�̉��y��m���Ă���B�u�������y�v�u�W���Y�v�u���b�N�v�u�������y�v�u�R���s���[�^���y�v�A�����ăo�b�n�ȑO�̗l�X�ȍ��̗l�X�Ԏ���́u�Êy�v�u�@�����y�v�A���邢�͗l�X�Ȏ���́u�q�b�g�ȁv��u���w�v�B�����āA�Y��ĂȂ�Ȃ��͓̂�\���I�ȑO�ɂ͑��݂��Ȃ��������s���́u�m�C�Y�v�B
�@�����́A���W�I��e���r��f�悩��C���^�[�l�b�g��s�s��ԂȂǂȂǁA�l�X�ȃ��f�B�A��X�y�[�X���o�ď���ꐔ�l�����ꕽ�ω�������ى�����m�C�Y�����ꂽ�u���v�Ƃ��Ď������Ɂi�D�ނƍD�܂���ƂɊւ�炸�j���ݍ���ł���B
�@���̖����I�[�P�X�g���Ƃ����������W���[���ɓ��e����B���̖��̃u�����h���@�͌l�̊����ł���A���̔䗦�͌��ł���B�����炱����S�N�O�̌����ȂƓ����f�ނ𗿗����Ă��A�S����������̂ɂȂ�B����A�ނ��댻��̃m�C�Y�����ݍ����ŁA�x�[�g�[���F���搶��u���[���X�搶�Ɠ������̂����ƌ������������B�ˑ�ȃI�v�V������t���ĉ��b�݂����ɂ���̂��\�����A�t�ɃI�[�\�h�b�N�X�ȕҐ��̂܂܁q�y�z�r�������������x���肬��܂ő��w�����Đ��荞�ނ̂��I�V�������B
�@�u���y�͌`���̏��I�[�P�X�g����i�v�ƌ����Ƌɂ߂Č��肳�ꂽ�f�ނɌ����邩���m��Ȃ����A�\���͂��ꂱ���c��ɂ���B
�@���ꂪ�u�����ȁv���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
 �@���g�����F�����ȑ�T�Ԃق��i�V�����h�X�j
�@���g�����F�����ȑ�T�Ԃق��i�V�����h�X�j�@�ƌ����킯�œ���N�ɏ������u��T�v�B�}�[���[�̑�T����S�N�A�V���X�^�R�[���B�`�̑�T������Z�\�N�ȏソ���Ă���킯�ŁA���ꂪ�������łȂ��Ƃ͌����Ă������܂���B
�@���̂T�̌����Ȃ̒��ł́i���Ԃ�j�����Ƃ��v���C�x�[�g�ȓ��e�������Ă��邵�A�����Ƃ�������ꂻ���ȍ�i���낤�Ƃ͎v������ǁA�Ԉ���Ă��u��Y�v����u����v�ցc�Ȃ�ĕςȃ��b�Z�[�W�͒�������ė~�����Ȃ��B�����A�u�I�[�P�X�g������Ȃ��ă��b�N�E�o���h�ʼn��t���ׂ��Ȃł���ˁv�ƌ���ꂽ��f���Ɂu�����ł��ˁv�Ɠ��������B
�@�u�ŁA���̂U�Ԃ́q�c���r�ł����H�v�Ƃ��������܂�̎���ɂ͂����܂�̂��Ԏ����B
�@�u���z���ɂ��C�����܂��v
��43��u�Z���ƃ`�F���v
�@����A���k�ɂӂ��Ɨ��ɏo���B���������̃`�F�����t�Ȃ̃y����������Ƒ����̂ŁA���z�̌��_����{�V�����̃`�F�������ɉԊ��̋{�V�����L�O�قɍs�����Ǝv�������Ă̏����s�ł���i���Ȃ݂ɁA�����̏ꍇ�̓`�F���ł͂Ȃ��u�Z���v���������j�B
�@��������̃Z���D���́u�Z���e���̃S�[�V���v�ŗL���ŁA�L�O�قɂ̓K���X�E�P�[�X�ɐ_��̂悤�ɒ����܂��܂��Ă���B�����Ȃ�ƌ����}�j�A�Ƃ��ẮA�ЂƂ茎�̌��̉��Ńo�b�n�̖����t�Z���t�ȂȂǒe���Ă�p���v�������ׂ����Ȃ�Ƃ��낾���A���ۂɐ搶�ɂ��ďK�����̂͏㋞�������̂R�������A���Ƃ͔��d���̍��ԂɒʐM����̓Ɗw�c�Ƃ����ނ̃`�F���̘r�O�͕s���B�ǂ����u�J���������������ƒe���̂�����Ƃ������v�Ƃ��������肪�^���炵���A�����ߏ��̔_�Ƃ̐l�͌����̏Z�܂�����钆�ɕs�C���ŕςȉ�����������̂ŕ|���ĒN���߂Â��Ȃ������ƌ����B
�@�v����Ɍ����Ƃ��ẮA�Z���̑t�ł�u���y�v�ł͂Ȃ��u���v�ɐZ���Ă����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�Z����e���ďo�鉹���ʂɉ��y�̑̂𐬂��Ă��Ȃ��Ă��A���́u���F�v�������i�����āA���̓�������ĉ��t����Ƃ����p�������j�����ɂƂ��ẴZ���̑��ݗ��R�������̂����m��Ȃ��B���̏؋��Ɂu�Z���e���̃S�[�V���v�ł��A�l�Y�~�̎q�̓Z���̑t�ł�u���y�v�ł͂Ȃ��u�U���v�Ŗ�����Ă���B
�@�����Ƃ��A���̕��ꎩ�̂͂��܂�D���Șb�ł͂Ȃ��B�����ɂ��u������ė��K���āA�Z�������܂��Ȃ�܂����Ƃ��v�I�ȋ��P�������B�ꂷ�邩�炾�낤���B��P�y�́u�l�R�ɂ�郁���f�B�̒v�A��Q�y�́u�J�b�R�E�ɂ��P�����^�̔������K�i���k�G�b�g�j�v�A��R�y�́u�^�k�L�ɂ�郊�Y���̊�{�i�X�P���c�H�j�v�A��S�y�́u�l�Y�~�̎q�ɂ�鉹���o�����X�̃��b�X���v�A�����čŌ�Ɂu��U�����Ȃ̉��t��v�Ƃ����t�B�i�[���������ăA���R�[�����i�i�C���h�̌Պ���j�܂ŕt���Ă���Ƃ����\�����A�Ȃ������Ɋy�ȍ\���I�ŃX�L���Ȃ�������̂��B
�@�����Z���Ȃ�A�������Ŏx���ŗ�Ȃ̂ɕ������F���I�C���[�W�������Ă���u��͓S���̖�v�̒��ɏo�ė���u�Z���̂悤�Ȑ��v�Ƃ����̂��D�����B���ݓǂ߂�ŏI�e�ł͂�������폜����Ă��邯��ǁA���e�ł̓W���o���j����������߂���A���́u�Z���̂悤�Ȑ��v���������Ă��āA���������B
�@�u���܂ւ̂Ƃ��������ǂ����֍s�����̂��炤�B
�@�@���̐l�͂ˁA�ق��ɂ���≓���֍s�����̂��B
�@�@���܂ւ͂����J���p�l�������������Ă��ނ����v
�@���̑傫�ȖX�q�����Ԃ�������̂₹���i�������A�D�������Ă���j��l�́A�u���J�j�����m�Ƃ����̂����A�Ȃ������̌�̉����ł������葶�݂�������Ă��܂��Ă���B����͂ǂ����A���̔��m�̘b��O�ʂɏo���Ɓu��͓S���̖�v�Ƃ������������B�W�������̂��̂��A�Ȋw�҂��q���i�W���o���j�j�ɖ�����܂��Č������u�����̌��o�v�Ƃ��������^���Ă��܂�����Ȃ̂��낤�B
�@�������A���́u�{���ɍ��鉓���֍s�����̂��v�Ƃ����ꌾ�B�Ȃ�Ƃ��Ȃ��B���������A���́u�i���̒��v���A�����n�܂�B
�@
�@�u���ӂ̂�����
�@�@�Ƃق��ւ����Ă��܂�
�@�@�킽�����̂������Ƃ�
�@�@�݂��ꂪ�ӂ���
�@�@�����Ă͂ւ�ɂ����邢�̂��v
�@�������ꂽ���Ȃ��āu�����֍s�����v�ƌ����A���́u�����v�֗�Ԃōs�����Ƃ���A���̎q�����݂����z���߂������ۗ�������B���ہA�����͖��g�V�̎��̌�A�X���犒���܂œS���ł��܂悢�A���̍s���Ă��܂����u�����v��ǂ��B�����āA�V��ւ̘H���������z��l���́u��͓S���v��n������̂��B�����ł̓Z���͖��E����̐��ł���A�V��֓����S���̎ԏ��̐��ł���A���������ӂ�����u�����v�̐����B
�@�Ƃ���ł��̕���A���ׂẮu�P���^�E���Ձv�Ƃ��������̏o�����ł���B����͂�������̑z���̎Y�������A���{�Ō����u���~�v�̃C���[�W���B��c�̗�ƌ�M�ł��鐹�Ȃ���炵���A���̓N���X�}�X�̂悤�ȃC���~�l�[�V�����ɏ����A�X���͂��݂��̎}�ŕ�܂�āA�q�������͐��߂���̉̂����J�Ő����u�P���^�E���X�A�I���ӂ点�v�Ƌ���ő���A�G�Z�̂�������M�����ɗ����B
�@���ہA�Ă̂��傤�ǂ��~�̍����ƁA�����Ƃ��ẴP���^�E���X���͓�̋�̌������ɔ����B��Č�����ʒu�B��������͓S���̏I�_�i�J���p�l�����ƕʂꂽ���j�ɐݒ肵���̂́A���̃P���^�E���X���̉��̓�\�����Ƒ����̐ΒY�܂ƌĂ��Í����_�Ȃ̂����A�����͂܂������V��Łu�����Ƃ������Ƃ���v�ɂȂ�킯������A���̏I���_�Ƃ��Ă͗��ɂ��Ȃ��Ă���B
�@�����łӂƋC�t�����̂́A���l���n�́u�P���^�E���X�v�́A�ǂ����l���`�F����e���Ă���p���Î����Ă���Ƃ������ƁB�ق�A���Ə㔼�g���l�ԁi���t�Ɓj�ŁA�����g�����ߐF�̓��i�`�F���j�ł��傤�B�l�Ɣn�����̂����̂��_�b�̃P���^�E���X�Ȃ�A���t�Ƃƃ`�F�������̂����̂̓P���^�E���X�̃��j�b�g�Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ����킯�ŁA���������̐V�����`�F�����t�Ȃ́u�P���^�E���X�E���j�b�g�v�Ƃ����^�C�g���Ɍ��߂��B
�@���ꂪ�A�����̃`�F�������ċA�����Z�����̐��ʁB���āA�����ɖ߂��đ��������������˂c�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���G�X�g�j�A�̃t���[�g���t�ȏW�i�t�B�������f�B�A�j
�@�D�������䂽�����̂悤�ȃG�X�g�j�A���̃t���[�g���t�Ȃ��S�B��������N���V�J���Ȍy�₩���������A�ǂ��������̔�����コ�̔��w�������Ă����������{�l�D�݂̃g�[���B�A���o���E�^�C�g���ɂ��Ȃ��Ă���^���x���N�́q���W�J�E�g���X�e�r�ȂǁA�܂��������{���ۂ��āi���ۂɃC�t�N�x�E�^�P�~�c�E���V�}�c�̃G�R�[���������邵�j�v�킸���B�܂��A���Ƃ����Ă��܂������Ȃ̂�����ǁA���̊����A��������Ȃ��Ȃ��B
�@���V�F���E�nj��y��i�W�i�i�N�\�X�j
�@���Ă�����̓_�C�i�~�b�N�ŊO���I�Ȓ��T�E���h������m�x�ݏZ�̂a.�V�F���̍�i�W�B�o���g�[�N�́u�����̕s�v�c�Ȗ�l�v��{�Ɩ{���̒����l��ȉƂ����㕗�ɗ�������Ƃ����Ȃ�A�ƌ������Ƃ��납�B�u�q���V�}�I�v�ɑ��āu�i���L���I�v�������o�������i���t�ȂȂǁi���㉹�y���Ă�����̂́j���|�I�ȗ͋Z�ƃp���[�Œ������Ă��܂��B�@
��44��u�˔\�̗͑͂��c�H�v
�@���̂����d���ɕK�v�Ȃ̂́A�˔\��艽���܂��u�̗́v�����m��Ȃ��B
�@�ȑO�A�����Z�Ȗ^�R�~�b�N��Ɓi�����j���A�u�ŋ߁A�����`���Ă��鎞�����������薰���Ȃ����肷��悤�ɂȂ��āA���������N������Ȃ����Ďv���܂��v�Ȃǂƌ����Ă����ƕ����āu�ւ��`�v�Ɗ��S�������Ƃ�����B�܂�A���̐l�́u���܂ŁA�����`���Ă��鎞�͂������������Ƃ������Ȃ邱�Ƃ��Ȃ������v�炵���̂��B
�@���������A���̎�ˎ������A���̎d���Ԃ�ƌ�������A���Ŗ����`�������łȂ��^�N�V�[�̒����Ԃ̒��ł��`���A���s��ł��`���A�Q���ł������ɂȂ��ĕ`���c�Ƃ������܂����������ƕ����B����ł��Ȃ����u�܂��܂��`������Ȃ��B�A�C�f�A�̓o�[�Q���Z�[���ɂ��邭�炢����I�v�Ƌ���ł����Ƃ�������A�܂�Ƃ���˔\�ƌ����̗̂͑́i�Ƃ͌����Ă��A������^���\�͂Ƃ��Ắu�̗́v�ł͂Ȃ��B�O�̂��߁j�������Ďn�߂Ĉ����o������̂Ȃ̂��낤�B
�@�����A�\�ォ��O�\�㏉�߂��炢�܂ł́A�Q�Ă鎞�ԈȊO�͂قƂ�ǂ��ׂĊy���������Ă��邩�ǂ�ł��邩�s�A�m��e���Ă��邩���Ă�������A�S�R�d�����Ȃ������ɂ�������炸�����Z�������i�j�B�����ȂƂɂ�����i�i���i�ł������f�B�����ł��j�������̂����ۂ��������A�nj��y�@�̓ƏK�����a�J�̊y��X�ɃX�R�A�̗����ǂ݂ɒʂ��Ă��āA�d�Ԃ�o�X�̒��ł͉��y�ɊW�̂Ȃ�������Ȋw����r�e��Ȃǂ̎G���Ȗ{��Ђ��[����ǂ�ł������A���܂��ɏ�������������G��`������o���h���������薟���`����������Ă����̂ŁA���ɂ��d�����Ȃ������̂ɐQ��ɂ��Ȃ��قǖZ���������B���l����ƂЂǂ����������B
�@�ŋ߁A�d�����ЂÂ��Ă��āA����Ȏ���i���Ԃ�\��̍��j�ɏ������I�[�P�X�g���Ȃ̌Â��X�R�A���������������̂����A�悭���܂��A�Ƃ������炢�R�c�R�c�˂��˂���������ł����āA�u���`��A�Ⴂ�Ȃ��v�Ɗ��S���Ă��܂����B
�@���̍��͂ƌ����ƁA�y���f���c�L��Q�e�B�猻�㉹�y��Ƃ̃X�R�A���ߓǂ݂��A�������O�A�����O�Ƃ�������y��ȉƂ����́u�Ƃɂ����ׂ��������Ⴒ����Ə�������ł��鐸���@�B�̐v�}�̂悤�ȃX�R�A�v�ɐS�����Ă����̂ŁA���̉e�����傫���B�Ȃɂ���X�g�����O�X�����ׂăf�B���B�W���Ă��ꂼ�ꂪ�`���`���ƕʁX�ȃp�b�Z�[�W�����t���Ă�����A�s�A�m�ƃ`�F���X�^�ƃ��B�u���t�H���ƃO���b�P���V���s�[���ƃA���e�B�N�E�V���o�������������ƌܘA���E���A���ł݂����肫�炫��苿���Ă�����A�Ƃɂ����������������ގ��O�����̐����̂��B
�@�������A�Ⴆ�t���[�g��11�̉��ō\�����ꂽ�p�b�Z�[�W��17���P�ʂŃ��s�[�g���A�I�[�{�G�͂���Ƃ͋t�s����p�b�Z�[�W��21���P�ʂŃ��s�[�g���A����炪�؊NJy��ƌ��y��̑S�p�[�g�ɂ킽���ăY���Ȃ���d�Ȃ��Ă䂭�c�Ȃǂƌ����ʓ|�����������Ŗ��Ӗ��ȑΈʖ@���˂��˂���������ł����A�I�[�P�X�g���̑S�y�킪�������Ƀo���o���ȃt���[�Y�����t���Ȃ���c�����ł͏�ɂЂƂ̃��[�h�i���邢�̓R�[�h�j���`�����Ă䂭�c�ȂǂƂ�����Ԃ����肩�����Ĕ��I�ȏ����ɂ�������Ă����A������l�ɂȂ������Ƃ��Ắi�����^�C���}�V���ł������Ă��̍��ɖ߂��Ȃ�j�u��߂Ȃ����A����Ȃ��ƁI�v�ƒ����������Ȃ�Փ���}�����Ȃ��قǂ̃C�J����ł���B
�@���Ȃ݂ɁA���̍��͂܂��R���s���[�^�ȂǂƂ������̂͂Ȃ������̂ŁA���̏�Ɍv�Z���������āi���邢�͓d��������o���āj�����v�Z���Ȃ���A�N�����l�b�g57���ߖ�5���̗��͕t�_���������̂f���A�`�F���X�^88���ߖڂR���ڂ̂V�A���̂R�ڂ̉��͂c��A�ȂǂƏ�������ł����B���R�A15���قǂ̃I�[�P�X�g���̃X�R�A�������̂ɁA�\�z�R�N�A�f�b�T���Q�N�A�X�R�A�����ɊۂP�N�ȂǂƂ����������ꂵ�����Ԃ�������A�Ȃ��������Ă���Ō�ɐ������邾���ŁA�Ђƌ����قǂ̓O��d���ɂȂ������̂��B�@
�@���͂Ƃ肽�ĂĎ����ɍ˔\������Ƃ��̗͂�����Ƃ��v�������Ƃ͂Ȃ����A���̎���̎��O�����͂������Ȃ��B���ꂾ���͋����Č�����B�i�ł��A�Ȃ�ł���Ȏ��O�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��́A�悭������Ȃ��̂����c�j
�@�ŁA�l�ԒN�ł������ł���悤�ɁA�����ŋߊm���ɔN������đ̗͂͂Ȃ��Ȃ����B�Ⴂ���Ɠ����悤�ɃI�[�P�X�g���̃X�R�A15���������̂�45���̓O��Ȃǂ���Ă������ɂ́A45���̌����Ȃ̃X�R�A�������グ��Ȃǁi�P���v�Z����ƁA�S�������̓O��H�j�ƂĂ��������B������ď����o������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�������A���̒����܂��������̂ŁA�̗͂�������Ɠ�����MAC�i�R���s���[�^�j�ƌ����L�\�ȏ��肪���Ă���āA�{���Ȃ牽�����̓O������Ȃ���Ȃ�Ȃ����[�e�B���E���[�N�̂��Ȃ�̕��������Ȃ��Ă����悤�ɂȂ����B����A�]���ōs����͎d���̂������������s���Ă����킯�Ȃ̂ŁA�u�A�C�f�A�͂���̂����̗͂��Ȃ��ď����グ���Ȃ��v�Ƃ��������͉���ł������ƂɂȂ�B
�@������A�ނ�����������i�̃X�R�A���i�����[�N����K�v�ɂ����āj���������Ă����̂����A���̃p�[�g���f���B�W����Ă��ꂼ�ꂪ16�������̂U�A���ŏo�����p�b�Z�[�W���J��Ԃ��Ȃ���5���A4.5���A4���A3.5���A3���Ƃ����P�ʂ�16���ߊԂɂ킽���ă��s�[�g����c�ȂǂƂ������G�Ȃ��Ƃ��i�������菑���ł��d��Ў�Ȃ�o���Ȃ��͂Ȃ����A���̂�����16���߂ʼn��ӂ��̓O��͔������Ȃ����낤�j�������萔���̍�Ƃł��Ȃ��Ă��ꂽ�̂ɂ͊������Ă��܂����B
�@�����A�Ⴂ�����֗̕��ȏ���ɏ������Ă��܂��Ă�����A�u�����Ȃ�z������i�n���c�ł͂Ȃ��j�̗́v�͂ƂĂ��炽�Ȃ��������낤����A���͂��̍��́i�̗͏����ʼn��y�Ɗi�������A��]�Ɛ�]�ɂ܂݂ꂽ����́j��J�̌o���ɂ͐S���犴�ӂ��Ă���B
�@�������A��x�Ɩ߂肽���͂Ȃ�����ǁc�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�����������^�s�A�m�ƃI�[�P�X�g���̂��߂̎��ƕϑt�i�i�N�\�X�j
�@���c���V�Y�^���i�i�R�W�}�^���j
�@���m�̃I�y����V���t�H�j�[���ƁA�����u�̗͂��i�����ĐH�ו����j�Ⴄ�Ȃ��v�Ƃ��ߑ����o��̂����A���{�̉��y�̏ꍇ�́A�̗͂��u��O�i���邢�͐��_�́j�v�ƌ������悤�Ȃ��̂����y�I�Փ���˂��������Ă���悤�ȋC������B
�@�܂�́A���̓I�ȑ̗͂����Ȃ����A���_�I�ȁu��O�v��u�Z�p�v�B�����Ă����킯�Ȃ̂����A���́u�̗͂ɂ��됸�_�͂ɂ���A���郌�x�����ێ���������̂͂���߂ē���v�Ƃ������ƁB
�@�˔\���܂��̗͂Ȃ̂��B
��45��u�ċx�ݓ��L�v
�@�^���^���B�H�ɏ����\��̃`�F�����t�ȁi�P���^�E���X�E���j�b�g�j�̃X�P�b�`�e�i�s�A�m���t���̂悤�ȕ��j���d�グ�ăC�M���X�̓Ƒt�҂̌��֑���B�I�[�P�X�g�������̋ȂȂ�A���ꂱ��������T�ԑO�ɃX�R�A�����ȂǂƂ������d�X�P�W���[�������蓾�邯��ǁA�R���`�F���g�͓���B�Ȃɂ���A�����������ĉ����^���̓��������܂��ă`���V������o����Ă���̂ɁA�Ȃ����݂��Ȃ��̂��B�ƂȂ�Ɓi�����܂łɂ݂�������K���āA������������Õ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������m��Ȃ��j�\���X�g�Ƃ��Ắu��̂ǂ�ȋȂȂH�v�Ɩ�X�Ƃ��ăX�g���X����̓��X�B�����ŁA�i�{���͊����O�̊y����l�ɂ͌��������Ȃ��̂����j�u���݂܂ł̂Ƃ���A����Ȃӂ��ɐi��ł܂��v�Ƃ����o�ߍe�𑗂邱�Ƃɂ�������B�ł��A�G��Ō����Ƃ܂����G�̒i�K�Ȃ̂ŁA��͒����B
�@�@�@�@�@�@�@��
�@�^���^���B�q�V�x���E�X�Q�r�Ƃ����y������\�t�g�̓��{��ł���ɓ����B���݁A�d���ł́q�t�B�i�[���r�Ƃ����\�t�g���g���Ă��āA���ꂪ�ꉞ���{�����ł͏p�̋ƊE�W���Ȃ̂����A���̑R�n�Ƃ��ă��[���b�p����o�ꂵ���̂����̃\�t�g�B�l�I�Ƀl�[�~���O���C�ɓ����Ă��邱�Ƃ������āA�ȑO����T���v���p�p��ł͎����Ă����̂����A���̂��ѓ��{��Łi���}�n�j����������邱�ƂɂȂ����̂ő��������B�����A���͑傫�ȋȂ̍�Ȓ��Ȃ̂ŁA�����Ȃ�\�t�g�͑ւ���ꂸ�i�}�j���A���Ԃʼn^�]���Ă����̂��I�[�g�}�Ԃɐ芷����悤�Ȃ��̂Ȃ̂Łj�A�`�F�����t�Ȃ������I����Ă���{�`�{�`���炵�^�]���n�߂邱�Ƃɂ���B�Ƃ���Łq�V���X�^�R�[���B�`�T�r�Ƃ����\�t�g�͏o�Ȃ��̂��ȁH
�@�@�@�@�@�@�@��
�@�^���^���B��Ƃ̋{��J���������䎩�g�̃N���V�b�N�b�c�R���N�V�������J�����u�N���V�b�N���̖���1001�v�i�V���Ёj�̃Q����������ēǂށB�����ȁE���t�ȁE�����y�E��y�ȂƃW�������ʂɑS1001�ȁB���ꂼ�ꌴ�e�p���Q�����ł܂Ƃ߂Ă���̂ŁA���v2002���̑咘�ł���B���̍�i�����Ȃ舤�����Ă���Ă��邱�Ƃ������āA�ҏW�����珑�]�̂��w���������ēǂ݂ӂ���B����ɂ��Ă��ŏ��̌����ȕ҂��炵�ăA�[�m���h�A�o���g�b�N�A�x�������h�A�`���h�E�B�b�N�c�ƕ������}�j�A�b�N�ȑI�ȁI�B�������s��ȗ��j�����ӂƂ����Ƃ��������āA���̏N�W�Ȃ���ёI�Ȋ�̓v���̉��y�]�_�ƂɂȂ����@�K�I�ȍ������ƖȖ����B���Ȃ݂ɁA���ɂ��ƃV���X�^�R�[���B�`�́u��T�Ƒ�W���̂����āA���Ƃ��Ƃ��ł�ł��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����h���]���B�ǂ��Ȃ낤�H
�@�@�@�@�@�@�@��
�@�^���^���B�Ƃ����킯�ŁA�V���X�^�R�[���B�`�̑��q�Ɩ����������u�킪���V���X�^�R�[���B�`�v�i���y�V�F�Ёj�Ƃ����{��ǂށB�`�L�ł��������ł��Ȃ��ЂƂ��ƂŌ����Ă��܂��u��������̎v���o�v�B���������̂��̓�l���A�Ắu��ȉƂ̉Ɓv�ŗׂɏZ�ރv���R�t�B�G�t�̂Ƃ���֍�Ȃ̎ז��ɍs�����b�i���̂��тɁu���̈��K�L�ǂ��I�e������Ɍ������邼�I�v�Ɠ{��ꂽ�ƌ����̂��ʔ����j�ȂǂȂǁA�����̒��ł̈�b�̓V���X�^�R�E�t�@���Ƃ��Ă͋����ÁX�����A���F�������q���ɕ��e�̎d���ȂǕ�����͂����Ȃ��̂��Ȃ��A�Ɖ��߂Ďv���m�炳���B�����[���G�s�\�[�h�͑������A�����Ɍ�����̂͂����́u��l�̕��e�v���ł����āA��\���I�Ƀ\���B�G�g�A�M�Ƃ������ŏ\�܂��̌����Ȃ���������ȉƑ��́A�܂��܂������Ȃ��Ȃ�B�܂��A��ȉƂ̓���Ȃ�Ă̂�������Ȃ��c�Ƃ������Ƃ��B
�@�@�@�@�@�@�@��
�@�^���^���B�u�`�J�v�v�Ƃ����Ȃ̃X�R�A���悤�₭�d�グ��B����́A20�N�ȏ�O�Ƀt���[�g����15�{�i�I�j�Ƃ����A���T���u���̂��߂ɏ���������ŁA�u���ɂ悹�鈣�́v�̑��҂Ƃ��āu���̃V���[�Y�v�i�ނ��������ƂȂ����ȁB���̏H�Ƀ`�F�����t�ȂƁu�������̎���v�Ƃ̃J�b�v�����O�łb�c�^������Ȃɂ��đŐf����A�����Ԃ�O���炱�̋Ȃ̃I�[�P�X�g���ł��l���Ă����̂Łu������@��Ɂv�ƌ��S�B�u�q�_�̌ߌ�v���炢�̕Ґ��̒��^�I�[�P�X�g���ɂ��A�����W�ō\�z�����̂����A���Ȃ͂����Ԃ�}�`�y���I�ȁi���̃p�b�Z�[�W�͖�T�b�ʼn��t����c�Ƃ����悤�ȁj���R�x�̂��鏑���ŏ�����Ă��āA���̂܂܂ł̓I�[�P�X�g���ł̃A���T���u���͕s�\�B�Y�g����A�ʏ�̃A���T���u�����@�ʼn��t�\�Ȃ悤�Ɂu�|��v���������邱�Ƃɂ����B��������̂́A��\�N�O�̎�����N�H���Ȃ��悤�Ɂc�Ƃ������ƁB�Ȃɂ����\�N�O�̎����ƍ��̎����Ƃ��ኴ����������\�Ⴄ�̂ŁB
�@�@�@�@�@�@�@��
�@�^���^���B�����Ƃh�r�c�m���������Ƃɂ`�c�r�k�������AWindows�}�V�����q����B�d����͊��ɍ�N����`�c�r�k��Mac���R��q�����Ă���B���P�[�u�����E�߂�ꂽ�̂����A���������҂��Ƃɂ���B����ɂ��Ă��A����摜�≹�y�������܂Ńl�b�g��ŊȒP�Ɍ����ł��R�s�[�o���Ă��܂��悤�ɂȂ�Ƃ́I�B�����������N�������č������i�ƌ����ǂ��A�N���b�N���邾���Ń|�C�Ɓi���̂̐��b�Łj�����ł���̂́A����Ƃ��Ă̓V���b�N�B����́A�l�ނ̕������l���L���痣��Ă܂������l�ޑS���̂��̂ɂȂ������j�I�g���ƌ����ׂ��Ȃ̂��A����Ƃ�����N�̕�������u�ɂ��Ēn���I�K�͂Ɋg�U�����߂Ă��܂������I�����ƌ����ׂ��Ȃ̂��B�ǂ����炩�u�������z�������낤����v�Ƃ����_�̉̐��iby �A�ؓ��j���G�R�[����B
�@�@�@�@�@�@�@��
�@���`�F���o���{���{�T�i�`�k�l�j
�@�ŋ߂Ȃ����C�ɓ����Ē����Ă���̂�����B�`�F���o���Ƙa�y��̓�d�t�O�d�t���W�߂��A���o���ŁA�ڔ��A�O�����AⵁA♂Ȃǂ��`�F���o���Ƃ���ޕs�v�c�Ȑ��E�����ȁB����������̍�ȉƂ��������ꂼ��V����������낵�Ă���̂����A���������`�F���o���͐D�c�M���E�L�b�G�g�̎���ɓ��{�ɓ����Ă��āA�ނ�����̉��y���Ă���̂��Ƃ����j���i�I�j�̋��ɒu���Ȃ���A���j�����ȂǓǂ݂Ȃ��璮���ƉĂ̖钷�ɍœK�c�����B
�@������̋����`�_��̊y��J���e���i�t�B�������f�B�A�j
�@�����āA���̉Ĉ�Ԃ̈����Ղ͂���B�t�B�������h�̖����y��J���e���́A�̔��ɋ����������n�[�v�̂悤�Ȏd�l�����A���̋����͖{���ɗ������ŁA������悤�ȗD�����B���₩�ɂ��炫����鉹���ǂ��������������E�֒������U���B�@
��46��u�a���҂����̉́v
�@�����������A�Ƃ��鋏�����̕Ћ��ŁA�N���V�b�N���y�ɂ͉��̂Ȃ������ȎႢ�j�̌�����u�x�[�g�[�x�����v�Ȃǂƌ����P�ꂪ�o���̂����ɂ��āA�v�킸�����������ĂĂ��܂����B�������A�ނ̌��ɂ��Ɓu�x�[�g�[�x���̉��y���ď��X�����v�̂��������B
�@������ƕ��������Ƃ̂Ȃ����������Ȃ̂ŋ����ÁX�A�u�ق��A����̓��j�[�N�Ȕ�]���ˁB��������ɂЂƂ��R�����Ă���Ȃ����H�v�Ɛ����������̂����A�Ԃ��Ă����̂͂��傤���Ȃ��u���R�v�������B
�@�ނ��킭�A���Z�̂��뉹�y�̎��ƂŁu�x�[�g�[�x���v�Ƃ����̂��̂���ȉƂȂ̂��ƕ��������̂́A���̉��y�͒����������Ȃ��B�����Ńs�A�m���K���Ă���Ƃ����������̏����k�Ɂu�ǂ�ȋȂ��������Ă���Ȃ��H�v�Ƃ��̂Ƃ���A�u�G���[�[�̂��߂ɁA��������v�ƌ����āA���y���̃s�A�m�ł��ǂ��ǂ����e���Ă��ꂽ�̂��Ƃ��B
�@�Ȃ�قǁB����Łu���X�����v���B�u�G���[�[�̂��߂Ɂv���������āi����ł��S�Ȓ����A�ƂĂ��u���X�����v�Ȃ�Ĕ�]���o�ė���킯���Ȃ��̂����j�����Ȃ��\�i�^���������ɂׁ[�g�[���F����_�����Ⴀ�A�]�E�̐K�������G���āu�ւ݂����v�Ƃ����̂Ɠ������B
�@����A�l�̂��Ƃ͌����Ȃ��B�������Z�̂���u�n���K���[���ȏW��T�ԁv�������āA�u�u���[���X�ƌ����̂͑�O���邾���̂��n���ȃ����f�B��������ȉƁv�ƌ��߂��A�����Ȃ��璮���Ȃ��������Ƃ������������B���̌�A�ނ͑S���t�́u��O���Ȃ��a�������f�B���������Ȃ���ȉƁv�ł��邱�ƂɋC�t�����̂́A���������Ă��炾�����B����ۂ���O�ꂾ�����킯���B
�@���̋t�ɁA�V�x���E�X�͍ŏ��ɕ������̂��u�����ȑ�S�ԁv�Ƃ��u�^�s�I���v�Ƃ����Â��a���Ȃ��炾�����̂ŁA�u�����I�ňÂ���������悤�ȉ��y�������Ǎ��̍�ȉƁv�Ƃ�����ۂ������A�u�t�B�������f�B�A�v��u�����ȑ�Q�ԁv�̂悤�ȊO���I����O�I�ȋȂ炭�ǂ����Ă��t���Ȃ������B����Ȃǂ́A�]�E�̖ڂ����̂�������őS�̂̎p�`�����Ă��Ȃ������ނ����m��Ȃ��B
�@���̎̂����ł�����̂��낤���A�ŋߖ^���Łu���V�}�c�̉��y�͂����v�Ƃ����b������R�R�ꕷ���@��������̂����A��l���u�q�[�����O�~���[�W�b�N�݂����œ�ゾ��v�ƌ����A������l�́u���H�t����Ȃ��́H���b�f��̉��y�݂��������v�ƌ����̂ŁA�v�킸���]���Ă��܂����B�N������̃]�E�̂ǂ���G�����̂��ȁH
�@����A�m���ɁA�����̂͊O�ʓI�ȃT�E���h�̒�������������u���}����`�v�Ƃ��u�f�批�y�I�v�Ȃǂƕ]���ꎩ���ł��u�R��y�h�v�Ȃ�Č��������Ă������̂�����ǁA�����ȂȂǂ������悤�ɂȂ��Ă���͗��ɂ��Ȃ蒧��I�ōU���I�ȁu���Ӂv��u�j��Փ��v���߂Ă��邱�Ƃ���āA��������u�J������y�h�v�ɂȂ��Ă��܂����B��ȉƂ̌������ƂȂM�����Ⴂ���Ȃ��B
�@����ɂ��Ă��A���̒��ɂ́u�E�E���Č��ǁE�E���v�Ƃ����ꌾ�f����D�ސl�A�������������B�������\�D���ȕ��ł͂���̂����A�R����������������Łu�t�����X�́E�E�E�v�Ƙ_���A�T�[�U�{�������Łu���C���́E�E�E�v�Ƙ_���A�Q�[�R�Ȓ����������Łu���[�O�i�[�́E�E�E�v�Ƙ_����B���łɁu����i�j�͂����E�E�E�v�Ƃ��u���ǁA�����Ă����̂́E�E�E�v�Ƃ��u���F�A���{�Ȃ�āE�E�E�v�Ƃ��B�m���ɁA�ꌾ�Œf�肷��̂́i��҂̋t�P�Ȃǂƌ������l�����邯��ǁj�C�����ǂ��͎̂������B
�@�Ȃɂ���l�́A�m��Ȃ����Ƃ�m��Ȃ����̂ɂ͕s���������A�u�m��v���Ƃł悤�₭���S����B�������A���E�̂��ׂĂ�I�m�ɒm��ȂǂƂ������Ƃ͐�Εs�\�B�ƂȂ�ƁA�s�����瓦�����@�͓�����Ȃ��B�u��������v���u�m�������Ƃɂ���v���A���B��������i�Ⴆ���ꂪ���\�ł��j���̊Ԃ̈��S����ɓ���B
�@�ƌ����킯�Ő��E�ɂ́A����⍷�ʂ⎹�i��A�]���Ȃ��܂��ɂȂ����Ƃ�悪��ȑ��ȁu����ہv���������ӂ�Ă���킯�Ȃ̂����A����ł��r�M�i�[�Y�E���b�N�Ƃ������炢�ŁA���S�҂䂦�̂���ȁu���z�v���哖����ɂȂ邱�Ƃ���B������A���Ƃł��f�l�̏����i�f�l�����̒����j���ꏊ�����ɕ���������Q�l�ɂ�������l�͏��Ȃ��Ȃ��B
�@�̂́A���������u���̐��v�����邩�ǂ������א��҂ɂ��돤���l�ɂ���\���҂ɂ���d�v�Ȏ����ł������̂����A�����̓C���^�[�l�b�g�Ȃǂɂ��̎�́u�Ƃ茾�v�����Ԃ��Ă���悤�Ȏ���ɂȂ����B
�@�Ȃɂ���A�����{�����{�Ƃ�������E���ɂ�܂���Ă���̂��B���R�ǐ^�ɖ������Ă��������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�u�g�C���̗������v�ɂ����āu�a���҂̌��t�v��������Ă��邱�Ƃ�����悤�ɁE�E�E�B�i�������A�g�C���̕ǂ������J��������̂́A���Ȃ肵��ǂ���������ǁE�E�E�j
�@
�@�l�X�͎���������������l�I���̐_��
�@�@�ʂ������A�F��B
�@�����ăl�I���T�C����
�@�@����ȉ��߂���ׂČ���B
�@�@�@�u�a���҂̌��t�́A�n���S�̕ǂɂ�
�@�@�@�@���h�̘L���ɂ��A������Ă���v�c�ƁB
�@�@���Ƃ͒��ق̋����̒��ł����₭����B
�@�i�T�C�������K�[�t�@���N���u�T�E���h�E�I�u�E�T�C�����X�v�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
���V�x���E�X�F�������u�C�̐��v�ق��i�a�h�r�j
�@���́A�V�x���E�X�Ƃ����̂̓u���b�N�i�[�Ɠ����悤�ȁu�������������Ȃ�a�v�ɜ���Ă����炵���B�������A�P�ɃI�[�P�X�g���C�V�����̕ύX�╔���J�b�g�Ȃǂł͂Ȃ��A�S�R�Ⴄ�Ȃɂ��Ă��܂����Ƃ����X�������Ƃ����̂͂��Ȃ�������B�u���@�C�I�������t�ȁv��u�����ȑ�T�ԁv�ȂǂɎ����ŁA����́u�C�̐��i��m�̏��_�j�v������ۂ������ɕ�����A�u�V�x���E�X�̉��y���āE�E�E�v�̌�ɂȂ����t�ɔY�ݎn�߂Ă��܂��B
���k�l�̂����₫�`�k�����y���i�W�i�t�B�������f�B�A�j
�@����ȃ}�j�A�����P���ɑ��Ă�����͏��S�Ҍ����B���̂P�����s�������Ƃ��Ȃ��Ă��u�k���̉��y���āE�E�E�v�Ƙ_������悤�ȋC������B�ł��A�t�W���}���Q�C�V���ƃA�j�������Łu�j�b�|�����āE�E�E�v�ƌ�����̂͂�����Ƃ����悤�ɁA�����ɖ{���̖k��������Ƃ͌���Ȃ��B�i�Ƃ���ň�l�����C�M���X�̍�ȉƂ��������Ă���̂́A�ԈႢ���ăN�C�Y�H�j�B���F���ׂĂ͌��z�̒��ً̈��̌i�F�Ȃ̂��낤�ȁB�@
��47��u�N���m��Ȃ��A�N�������Ȃ��v
�@�ނ����A�S�R���t����邠�Ă̂Ȃ��Ȃ����������Ə����Ă������A�]���ɂ��т���Ă����|�����B�W�������������B
�@����́A�l������Ԃقǂ̋��������ō�i�����������l�m�ꂸ����ł��܂��A�����ɐςݏグ���c���ꂽ�y���̎R���A�A�p�[�g�̊Ǘ��l���u���݁v�Ƃ��đS���̂Ă���R�����肵�Ă��܂��Ƃ������B�W�������B
�@�������Ȃ��悤�ɂ����Ă������i����A�������Ă��S�R���܂�Ȃ�����ǁj�ʂɁA�㐢�Ɏc�肽���Ƃ��A����ɔF�߂�ꂽ���Ƃ��A�����قɂł��ۑ����Ă��炢�����Ƃ��A�����������Ƃł͂Ȃ��B�����A�����̐��ݗ��Ƃ��������������u�����������ɐ��܂�Ă����̂ɁA��x�����ɂȂ炸�ɏ����Ă䂭�v�Ƃ������A����A�����艽���u���݂����ɂ�������炸�A�S������ɂ��m���Ȃ��v�Ƃ����Ȃ����A�u�����v�̔߂������v�킹�A�S�ɂ����т̂悤�ɐH������ŗ���Ȃ������̂��B
�@�N�ɂ�����ꂸ�ɍ炢���Ԃ́A���݂����ƌ����邩�H
�@�N�ɂ�������Ȃ��������y�́A���݂����ƌ�����̂��H
�@�N�ɂ��m��ꂸ�����������́A���݂����ƌ�����̂��낤���H
�@��������̖₢�́A�l�Ԃ��u�l����v�Ƃ�����ȃv���O������]�ɐ����������䂦�ɋN�������u���Ӗ��������s�\�Ȃ܂ܖ������[�v��������o�O�v�̓T�^���B�Ƃ��낪�A�����ƕ������Ă��Ă��A�o�O�͈����̂悤�ɕa��Ō͂����삯����B
�@�ŁA�Ⴂ���͈ꐶ�����u����A�N�ɂ��m���Ȃ��Ă������͑��݂��A�N�ɂ�������Ȃ��Ă����y�͑��݂���̂��I�v�ƔO���Ă����킯�Ȃ̂����A����́u�_�́A���݂��Ȃ����A���݂���v�Ƃ��A�u���́A���݂��邪�A���݂��Ȃ��v�Ƃ����\���Ɠ����B�ǂ�����A���͂Ƃ��Đ��藧���v�l�Ƃ��Đ��藧���i�����āA����䂦�ɉ������[���Ȗ₢�̂悤�Ɏv���邪�j�A�Ӗ��̓[���B�܂��������Ӗ��Ȍ��t�̌����B
�@�ł��A���������v�l�̖������[�v���v�����߂Ԃ̂��u�m���v�Ƃ������̂����m��Ȃ��B�u�|�p�v�Ƃ��u�N�w�v�Ȃ�Ă��̍ł�����̂��B������u�l�Ԃɂ����ł��Ȃ��v�ƌւ�ׂ����A�u�l�Ԃ������Ȃ��v�ƒp���ׂ��Ȃ̂��B�����ƁA����Ȗ₢���܂����Ӗ��Ȍ��t�̌����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���u���b�N�i�[�����ȑ�X�ԁ^�A�[�m���N�[���iRCA�j
�@������A�A���g���E�u���b�N�i�[��72�ŃE�B�[���̃x���f���F�[���{�a�̊Ǘ��l���������������Z���Ŏ��Ƃ��A�����ɂ͏��������̑�X�����Ȃ̃t�B�i�[���̑��e���U����Ă����A�Ƃ����b�͕|���̂��B��V�����Ȃ̐����̌�u���[���X�ƕ��ԑ��ȉƂƂ��Ēm���Ă����ނ̌��ɂ́A�e�ʂ�m�l�₳�܂��܂Ȑl���K��A�����āu���������̎菑���X�R�A���L�O�ɂƂĂ�łɎ����A�����v�ƌ����B
�@�������ŁA��X�����Ȃ̓t�B�i�[���̑��݂��Ȃ��u�����������ȁv�Ƃ��Ēm���邱�ƂɂȂ����킯�Ȃ̂����A�ŋ߃A�[�m���N�[�����E�B�[���E�t�B���𗦂��Ē������Ă��ꂽ�u��X�ԁv�̖����̃t�B�i�[���̒f�Ў����ɂ�郏�[�N�V���b�v�E�R���T�[�g�̂b�c���ƁA�u�m��Ȃ��v�����Łu���݂��Ȃ��v�킯�ł͂Ȃ��炵�����Ƃɜ��R�Ƃ���B
�@�A�[�m���N�[���́A���y�ƂƂ������͈�̂��i�@��U����@��w�̋����̂悤�ȃA�v���[�`�ŁA��X�����Ȃ̈�̂��J���e�ɏ������߂Ă䂭�̂����A�f�ГI�ɖ炳���f�Ђ́i�E�B�[���E�t�B���̋����̂���������̂��낤���j�܂������^���u���b�N�i�[�̂��̂ŁA���̋������L���ł������قǂ��̑r�����ɒ��������B
�@���j�Ɂu�����v�͖��Ӗ������A�����x�[�g�[���F���̑�X���t�B�i�[���̂Ȃ��u�����������ȁv�������Ƃ��āA��X�͎c���ꂽ���e��������u���́v�t�B�i�[�����ǂ��܂őz���ł��邾�낤���H
�@�����Ȃ��A�����Ȃ��B�܂����Ӗ��Ȗ������[�v�̓D���ɛƂ荞�ނƂ��낾�����B���������u�z���v�̂������ŁA�l�ԂƂ����͎̂��Ɉ���Ȃ��ƂɁA�{���Ȃ瑶�݂��Ȃ����|����∫���������玟�ւƍ��o���ė����̂������B
�@���������b�����́u�H��ꂽ��ǂ����悤�H�v�Ȃǂƍl�������Ă͂��Ȃ����A�������́u������������ǂ����悤�H�v�Ǝv���Ȃ����т₵�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�u�l���Ă��ǂ����悤���Ȃ��v���炾�B��������ȃo�O���b�Ⓓ�����̔]�ɐ��܂ꂽ��A��������āi����A�ꕪ�����āj�����Ă����Ȃ��Ⴂ�Ȃ��B
�@����Ȃ̂ɐl�Ԃ͐�������Ȃ��u�l����v�B�������Łu�u���b�N�i�[�̑�X�̑��e���S���c���Ă���v�Ƃ����z�����R���T�[�g�ވ���A�u�ׂ̍��͕���������Ă��邩���v�Ƃ����z�������ƋK�͂ł̎E�������ށB���������ȊO�̐��E�Ȃnj������Ƃ��Ȃ��͂��̎q���܂ł��u�n�����g���v�ɂ��n���̖�����J���A�s�u��ʂł����������Ƃ̂Ȃ��j���[���[�N��C���N�̎S��Ɂu�l�Ԑ��v��ߊς���B�u�C�}�W���i�z�����Ă����j�v�͈��╽�a�����ނ���ǁA������푈�����ށB
�@�ł��u�S���E�\�Ȃ�v�ƌ���ꂽ��A���̓r�[�ɂ��ׂĂ̓��Z�b�g�����B���E�Ǝv���Ă�����̂́A�]�̕\�w�ɐ��܂ꂽ�_�o�M���̘A���ɂ������A�u�F�v�Ǝv���Ă�����̂͂��Ȃ킿�u��v�B���߉ޗl�������������̂͂������N�ȏ�O�ɂȂ�̂������B���ꂩ��l�Ԃ̐S�͂܂������i�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ炵���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���[�ÓT��`�I���_�j�Y���E�V���[�Yvol.1�^�z�O�E�b�h�iARTE NOVA�j
�@������A�X�C�X�̃o�[�[���ň��l���N�ꌎ��\����ɍs��ꂽ�R���T�[�g�̂��ƂȂǁA���ɂ͒m��悵���Ȃ��A����͂��Ȃ킿�u���݂��Ȃ������v�Ƃ������Ƃ������B�������A������Č��������̂b�c�ɂ���Ēm�邱�ƂɂȂ�A�������Ń}���e�B�k�[�ƃX�g�����B���X�L�[�ƃI�l�Q���́u���݂���v���ƂɂȂ����B�߂ł����B
�@���l�Z�N�Ƃ�����ȔN�����ꂽ�R�Ȃ��Ă���ƁA���̔N���}����܂łɂǂ�قǑ����̉��y��i���A��ŔR�₳��j������U�킵�������A�v�킸�ɂ͂����Ȃ��B�N�ɂ�������Ȃ��܂܁A��������ȉƎ��g�����ɏo���Ȃ��܂܁A���j�̔ޕ��ɏ��������y�����B
�@�ނ�Ɂu����ł��A���Ȃ������͑��݂����̂��v�Ƃ������͕����������낤���H
�@�������A�����������܂��v�l�̃o�O�ł͂���̂�����ǁB�@
�ŏI��u�Ƃ肠�����ŏI��Ƃ������ƂŁv
�@���̘A�ڂ��u���I�����y�m�I�g�v�Ƒ肵�Ďn�߂��̂��A���傤�Ǐ\�N�O�B���̌�A���I���ς���āu�V���I���y�m�I�g�v�ƂȂ����킯�Ȃ̂����A�C�����ƂȂ�Ə\�N�Ԃ��i���邸��Ɓj�����Ȃɂ�炩�ɂ�珑�������Ă������ƂɂȂ�B
�@���Ȃ݂ɁA�L�O���ׂ���1��i����l�N�ꌎ���j�́u��ȉƂ͎E���Ă��璮�����A���������܂ܒ������H�v�Ƒ肵�āA�����n�܂�B
�@�E�E�E�u���āA���悢���\���I���c�菭�Ȃ��Ȃ�A�i�C���₦���݁A���y���S�ɐ��݂���G�߂ɂȂ��Ă����B����A�Ȃ�Ƃ��킭�킭���銦���ł���B
�@�Ȃɂ���]�V�C�ȔM���ɕ�����鉹�y�ł́A�͓̂��������͓����Ȃ��B�₽�����X���������ȋ炱���A�F���ɘA�Ȃ鉹�y����������B�܂�A���y�͉��y�Ƃ��Đ��܂��̂ł͂Ȃ��A���y�ɂȂ�̂��B������A���������y����lj��y�B�Ƃ͌����A�N�V���₷�����y�����������B�����ŁA���������Ȏ���₹�B
�@�Ƃ����킯�ŁA���I��������N�����̂��߂̕K�g�A�C�e���ł���q��F�~�Ձ��b�c�r���Љ�邱�ƂɂȂ����B�Ȃ�Ƃ����m�Ș_�|�ł���v�E�E�E
�@�����A���̖��Ɏɍ\���Ęc�������́A�\�N�o���Ă��ς��Ȃ��炵���B�����Ƃ��Ⴂ���Ɂu�\�N�ԁv�ƌ������炻��͂����ʂĂ��Ȃ��������Ԃ��������A�l���\�N���ЂƂ܂��I�������̔N�ɂȂ�ƁA�\�N�Ȃǂق�̈������炢�̊��������Ȃ��ł��Ȃ�����A�܂��A�d���̂Ȃ��b���B����̖��ł͂Ȃ����A���̖������Ă����̂��A���̖��Ȃ̂��A�ق�̈��Q�Ԃ��ł��Ėڊo�߂Ă݂���\�N�o���Ă����A�Ƃ����̂������Ȋ��z�ƌ����Ȃ����Ȃ��B
�@����ł��A���̊Ԃɍ�i�́i�����ȂƂ����t�ȂƂ��j�ꉞ���������Ă��邵�A�����̂b�c����������c���Ă��邩��A�����Ɛ����Ă����̂͊m���炵���B�ł��u�{���ɂ��܂����������̂��H�v�ƌ�����Ǝ��M���Ȃ��B�������ɂȂ����������Ă���ԂɁA��ȉƂɂȂ����������Ă��钱���������̂����m��Ȃ��B
�@���������A��i�������Ă��鎞�Ƃ����̂́A���̎��_�ł͂Ȃɂ��Ȗ��ɍ\��������\�̂悤�Ȃ��̂��������蓪���삯�����Ă���̂����A�����I���Ă��܂��Ƃ��ꂢ�����ς�L���������Ȃ�B���t�ɎO�\�����l�\���������鐔�\�l������̉��̉�������Ă���̂�����A�������琔�\���̉��̗����\���͊w�I���������w�I�i�����Ȃ��j�ɑg�ݏグ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA�����ɂ͂��Ȃ�Ȗ��Ȍv�Z������ȃo�����X�v������͂��Ȃ̂����A���̕����̎v�l�̃��J�j�Y���ɂ��ẮA�����Ă��铖�̍�ȉƖ{�l�ɂ���͕s�\�ȃu���b�N�{�b�N�X�̊�������B
�@���̓_�ɂ��ẮA�̂���s�v�c�������̂����A�l���Ă݂�Ώ��������āA�q�{�̒��ōזE����`�q���Ȃɂ�炩�ɂ�炵�đَ����o���Ă����ɍ����h��Ɏ���v���Z�X��J�j�Y���ɂ��āA�{�l�����ׂĂ�m���Ă���͂����Ȃ��킯�ŁA�u���ݏo���v�Ƃ����̂͏��F�u�m��v�ȂǂƂ������͈̔͊O�ɂ���Ƃ������ƂȂ̂����m��Ȃ��B
�@����͂Ƃ������A�Ō�ɍ�������A���������Ă��̏\�N�ʼnʂĂ��Ȃ��ӊO�������̂́u�\�N�o���Ă��܂������Ă�v�Ƃ������Ɓi���́u���v�ł���B�O�̂��߁j�B�����̌��㉹�y�ɔ�����|���Ăʂ��ʂ��ƒ����̉��y���������̂��A�������̈╨�ƌ���ꂩ�˂Ȃ��悤�ȁu�����ȁv�ȂǂƂ������̂��킴�킴�T���������̂��A�ςȕ������ł��������ɓG������āu�����Ȃ���ȉƁv�̊m�ł���n�ʂ��̂��A�ʂɁu�Ȃ�Ƃ��Ȃ�v�Ƃ����̎Z���������킯�ł����ł��Ȃ��A����A����ǂ��납�u�ǂ����_���Ɍ��܂��Ă�v�Ǝv�������炱��������킯�Ȃ̂ł����āA�����ɋ��łȈӎu�Ƃ������Ȍv�搫�Ƃ��Ȗ��Ȋ�݂��������킯�ł͂��炳��Ȃ��B�i�����Ƃ��A������������̂��ʔ������A���l�͂��������Ă��邯��ǎ��͌v�Z����Ă����̂��Ɛ[�ǂ݂����̂������Ȃ������m��Ȃ�����ǁj
�@�N�̖��悾�������A������̑��������̉e���҂ɂȂ����j���A����Łu����ł����I�v�ƌ����ă��P�N�\�œG�ɐ荞��u������������v�Ƃ����̂�����������ǁA����Ɏ��Ă���B�i������̂��āu�������L��A�������L��v�Ɗ��j�����̂����̏㐙���M�A�Ƃ����b�͂ǂ����ŏ����������B�Ȃ�Ƃ����������c�Ǝv�����玀�ʂ̂��|���̂ł����āA���������܂��c�Ǝv���ΐ����Ăă��b�L�[�A�Ȃ̂ł���B�c���āA�Ђǂ����߂������������j
�@�����ЂƂӊO�������̂́A�����u���ɂ悹�鈣�́v�Ńf�r���[�������u���Ƃ킸�����N�Ő�Łv���Ă��܂��͂����������n�̎��i�L���j���A�Ȃ�ƎO�\�Z�̒����čŋ߁i���O�N�\���j�g��������ƁB
�@���݂ł͍��n�Ŏ��炳��Ă��钆���Y�̎����O�\�H�߂��ɑ����Ă���ƌ������A���Y���̂c�m�`�͗Ⓚ�ۑ�����Ă���Ƃ�������A�߂������ӂ����і쐶�ɕ�����鎞������邩���m��Ȃ��B������A����������A���ꂪ����H�����H�ɂ������ăJ���X�ƈꏏ�ɐ��S�~�ł�����悤�ɂȂ�����A���̉��y�Ȃǁu�ǂ������̂�˂�I�v�ƌ��w������鎞������邩���m��Ȃ��B�����A����I
�@�������āA�Ȃ�Ƃ������I�����тĂ��܂�����ȉƂƂ��Ă͂����v���̂��B�u�����Ƃ́A�i�_������j�m����̂ɂ��炸�B�����̂ł���v�ƁB
�@�����B�m���ɁA�ߋ��͍����B
�@�������A�����͍��̂��B��҂�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@���R�c�k⩁^�����ȁu�����ǂ��ƕ��a�v�ق��i�i�N�\�X�j
�@���{�l���̃I�[�P�X�g���ȁu���ȓ��v�ƁA���{�l���̌����ȁu�����ǂ��ƕ��a�v�����߂����{���y�j�̋��ȏ��I�ꖇ�B���ׂĂ͂�������n�܂����B�Ƃ���ŁA���{�u�Ō�v�̌����ȂƃI�[�P�X�g���Ȃ������̂́A�ʂ����ĒN�H
�@���V�x���E�X�F�����ȑ�U�ԁ���V�ԁA�^�s�I���^�T�J���E�I�����i���[�i�[�j
�@�v���N�����ΎO�\�N�O�B�u��ȉƂɂȂ낤�v�u�����Ȃ��������v�ȂǂƎv�����̂́A���̎O�Ȃ����̂����������B�ƌ����킯�ŁA�Ō�̃��t���C���́u���ׂĂ͂�������n�܂����v�B������Ăӂ����э�ȉƂւ̓��ɓ]������i�H�j���̂悤�Ȏ�҂��o�Ȃ����Ƃ�S����F��B
�i�������A�������Ĉ����͂����₭�̂��B���������j
�@�ł́B