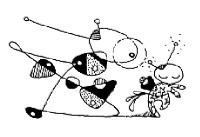 復刻!新世紀末CDノート
復刻!新世紀末CDノート
(2001年版)
★これは音楽現代誌に2000年1月より連載された
「新世紀末CDノート」のオリジナル復刻版です。
2000 / 2001 / 2002 / 2003
第13回:2001年と言えども平成では13年
第14回「進化の真価は深化と心火」
第15回:急性〈音楽ぎらい〉病の症例
第16回:雑学でいこう
第17回「突然引越日記」
第18回:ド#もドーナツのド?
第19回:「独学」とは何だ?
第20回:異種交配は純音楽を構造改革するか?
第21回:夏休み「第5」日記
第22回:ファウストの夏
第23回:3センチの虫にも1.5センチの魂
第24回:ある交響曲作家の私信
第13回:2001年と言えども平成では13年
ずいぶんと先の未来のような気がしていた「二十一世紀」が遂にやって来た。一九九九年の七の月に世界は滅びなかったし、第三次世界大戦や核戦争の危機も乗り越えて、一応まだ人類は生きている。ここはひとまず「めでたい」と言っておこう。
仕事場の窓から見える新宿副都心の景色などは高層建築が立ち並んで確かにそれなりにSF世界っぽくないことはないし、私のような零細音楽家の仕事もほとんど鉛筆やペンからコンピュータになって一応オンラインで世界と繋がっている。そこだけ見ると確かに二十一世紀的だ。もっとも、だからと言ってあんまり未来世界に住んでる気はしないが…。
ただ、手紙から電話と進化してきた個人的コミュニケイションの手段に、FAXと電子メールそして携帯電話が加わったことは確かに未来的かも知れない。おかげで表向きは「だれでも、どこででも、いつでも」連絡が可能になったのだから。
しかし、にもかかわらず、現代人がますます「コミュニケイションの飢餓」に陥ってゆくという構図は皮肉だ。湯水のごとくあふれる情報は、知識を薄め、心を冷やしてゆく。かくして、人口が増え、情報は増えたのに、断絶と孤独だけが増殖してゆく。
*
さて、音楽に目を(正しくは耳を…か)向けてみると、SF的未来音楽としてはもう少しわけの分からない電子的音響が跳梁跋扈するかと思っていたのに、さほどではない。このあたりは意外だ。
最新のダンス・ミュージックは確かに未来的なスピード感をもってデジタル・ビートを刻んでいるが、いまだに四拍子から一歩も抜け出ないし、無調的な音楽は誕生からすでに八十年近くたっているのにまったく一般的になる気配がない。
それでも、録音メディアの方は、SP、LP、CD、DVDと進化して小さく高機能になり、ハイクオリティな音質でしかも映像付きの一晩分のコンサートを、たった直径十二センチの円盤一枚に封じ込めることが出来るようになった。これはけっこう画期的と言ってよさそうだ。
ただ、CDがDVDになろうがインターネット配信になろうが、「音楽を一パックいくらの商品にして売る」…という構造は動かないから、音楽が聖なる地位から堕して、「束の間の気持ちよさを売る、大量生産可能で副作用のない一過性のドラッグ」としての繁栄を築いている現状は変わりそうにない。
後は、コンピュータやネットの中に、架空の神殿を建てるように幻の音楽を組み立てることが出来るようになったこと。これが吉と出るか凶と出るか…だろうか。
例えば、一万人に一人しか聴かないようなマイナーな音楽を人口一万人の町でやっていたら、聴衆ゼロ。でも、一億人が繋がったネットの中なら単純計算で一万人の聴衆を得る可能性があることになる。そこにはちょっと不思議な未来がなくもないような気がする。
*
一方、クラシック系音楽が二十一世紀にどうなるかについては、まったく予想も付かない。それこそ七十年代あたりにロックの台頭と共に絶滅してしまっていても別に不思議ではなかったのだが、意外にも音楽メディアのデジタル化などの波にもまれつつまだ生き残っている。これは、少なくとも大健闘と言うべきだろう。
そもそもカラヤン〜バーンスタイン以降圧倒的なカリスマ・アーティストがいなくなり、今やポップス界とのCD売り上げの枚数の格差は優に三桁に及ぶのだ。それなのに、いまだにCDショップにクラシック・コーナーがあり、毎月百枚近い新譜や再発盤が登場するということ自体(自分もその業界にいながら、こんなことを言うのはなんなのだが)大いなる謎としか言い様がない。
日本国内の現状を見ても、バブル経済が弾けて以降かなり状況は厳しくなっているはずなのに、オーケストラやオペラの公演にしろリサイタルなどにしろそこそこお客が入っているし、〈音楽G〉とか〈音楽のT〉とかいう老舗のクラシック系音楽雑誌がいまだに潰れそうで潰れないまま生き残っているし(失礼!)、私のような怪しげな作曲家が新しい交響曲を発表したりもしている。不思議だ。
それでも確かに最近は、クラシック系音楽をやっているからと言って「なにも百年も二百年も前のヨーロッパの伝統音楽を日本人がやらなくったって…」などという的外れの忠告をする人は少なくなった。ポップス系ヒット曲を聴いているからと言って「なにも日本の今の若いモンが毛唐の(古いな!)ダンス・ビートで踊らなくったって…」などと言わないように…。
そう。今や、十九世紀ヨーロッパの音楽も、一九六十年代のロックンロールのリズムも、千年前の雅楽の響きも、同じ近くにあり同じ遠くにあるのが「現代」なのだ。
もしかしたら現代には、もはや音楽はないのかも知れない。あるのは音楽の記憶だけ。その記憶の亡霊を二十一世紀が呼ぶ。
*
 ◆あのころ…日本のマエストロたち/といぼっくす(BMG)
◆あのころ…日本のマエストロたち/といぼっくす(BMG)と言うわけで、クラシック系音楽の楽器の名手たちが集まって「二十一世紀の都市型サロン・ミュージック」を紡ぐというこんな試みも、新しさと同時に不思議なノスタルジーを持つことになる。
素材は、わたくし吉松隆をはじめ、細野晴臣、武満徹、坂本龍一、渡辺貞夫、清水靖晃といった、現代音楽ではない〈現代の作曲家〉たちのメロディたち。しかも、合成や編集なしの生演奏にこだわったジャンル不明のコンピレーション・アルバム。
「新しい」とか「前衛的」とか気負わない二十一世紀の音楽への指標のひとつがここにある(…のかも知れない)。
◆冨田勲/源氏物語幻想交響絵巻(デンオン)
一方、現代日本最高のオーケストラ作家の一人である冨田勲は、源氏物語をテーマにして、オーケストラ(作曲家自身の指揮によるロンドン・フィル)と、琵琶・箏・笛・篳篥を合体させた全十六曲七十分の壮大華麗なる「交響絵巻」を編み上げた。言ってみれば西洋のオーケストラと東洋の音楽との邂逅なのだが、この見事なサウンドの前では、「西洋と東洋の合体」などという言い方すら陳腐。素直に音楽の生み出すファンタジーの宇宙に酔いしれよう。
そう言えば、源氏物語からちょうど千年。西暦では二○○一年と切りがいいが、平成は十二年が十三年になるだけ。さて、二十一世紀に音楽はどこへ行くのだろう?
第14回「進化の真価は深化と心火」
音楽そのものが果たして進化しているのかどうかは不明だが、確実に進化しているものがある。演奏技術だ。
むかし、中学校の音楽室で先輩が弾くチゴイネルワイゼンを初めて聞いた時、それはもう本当にびっくりしたものだが、彼は「このくらい弾ける程度でプロになろうなんて思わないよ。こんな曲は音楽学生なら誰でも弾くしね」と笑っていたのを思い出す。
かつてパガニーニやサラサーテが「悪魔に魂を売って」身に付けた超絶技巧の難曲も、現代では「別にプロになろうとも思わない」彼のような学生が手慰みに弾いていて、どこかの音楽コンクール予選会に行けば、そんなレベルの名手たちが「演奏家のタマゴ」として十把一からげで並んでいる。
そして、初演当時は「演奏不可能」などと言われていた幾多の協奏曲も、現代では学生でも弾く当たり前のレパートリーになり果てている。それが現代だ。
と言うことは、パガニーニやリストが現代に生まれてきて、どこかの音楽コンクールを受けたら、どのくらいのレベルまで行くのだろう? もしかしたら予選で落ちたりして…などという嫌な予感が頭をよぎる。
もちろん音楽史上に伝説として残っている程のヴィルティオーゾなのだから、かなりのテクニックだろうとは思うが、録音も映像も残っていない過去の天才たちと、現代の音楽家たちとを比べる手だてはない。
今なら小学生でも弾くようなレベルの演奏を「悪魔のテクニックだ!」と騒いだだけだったのかも知れないし、逆に、現代の我々には想像を絶するような(本当に悪魔的な)超人的かつ驚異的演奏を聴かせていたのかも知れない。それは、タイムマシンでも出来ないかぎり確かめようがない永遠の謎だ。
などと考えていた時、チェコのザトペック選手の訃報記事を見つけた。それによると、彼が一九五二年のヘルシンキ五輪のマラソンで優勝した時の記録が二時間二十三分三秒。ところが、昨年のシドニー五輪で(例の)高橋尚子選手が優勝した時のタイムが二時間二十三分十四秒。わずか十一秒差で、ザトペックの勝ちではあるのだが、あの「人間機関車」と異名をとった驚異の鉄人の記録も、現代では女子マラソンのタイムなのである。(ちなみに現在の男子マラソンの世界記録は二時間六分台とか)
だからと言うわけではないが、数字では表せない格闘技や各種競技はともかく、こうやって記録が数字で残るタイプの競技の記録については、どうやら人間は確実に進化(と言うより単なる「技術向上」と言うべきかも知れないが)しているように見える。
確かに、クラシック音楽について考えてみても、たぶんアルトゥール・ニキシュ指揮するベルリン・フィルより、現代の日本のオーケストラの方が格段に技術は上だと思う。ポップス界でも、ビートルズの頃のどんな上手いバンドより、今の高校生素人グループの方がテクニックは上だろう。
この点については、素晴らしいのひとことである。初演当時は凄まじい変拍子ゆえに演奏不可能の超難曲だったストラヴィンスキーの「春の祭典」も、現代ではどんなオーケストラでも余裕で弾いてしまうし、一昔前は「こんな難しい曲を弾けるのは世界で一人か二人」などと言われた難易度の高い現代作品も、音楽大学を出たばかりの若手がバリバリ弾いてしまうのだから。
ただ、昔「きわめて難しい」ことが今「余裕で当たり前」になったことが、ことごとく良いことづくめというわけではない。
例えば、小さなバイクで山道を時速百キロで飛ばせば、それこそ体がバラバラになるようなスリルと、轟音にまみれて風を切る豪快で刺激的な気分が味わえる。しかし、最新型のリムジンで高速道路を走れば、時速百キロなんて眠気を誘うごく普通の巡航速度でしかない。つまり、人は運転の安全を得た代償として、運転の快感を失うわけだ。同じように音楽も、何かを得た代わりに、確実に何かを失った。
かくして、五十年前なら二時間二十三分で走って世界的「鉄人」と賞されたものが、今ではオリンピックどころか国内大会の予選すら通過できないレベルとなり、十九世紀に生まれていれば明らかに天才と賞されていたであろう才能も、現代では「別にプロになんかなろうとも思わない」とつぶやく。巨匠などいなくなるはずである。
つまるところ人間は、「機能」の追究に関しては確実に進化してきたとは言えそうなのだが、しかしそれは、人間が本来持っている原初的な感覚を鈍らせることと引き換えであり、そしてそのことが、機能を喪失させるあやうい次元へ人間を向かわせているということらしいのだ。なかなか皮肉な構造だと言うしかない。
だから時々、ヴァイオリンの音を初めて聞いて震撼したあの時の耳を、そして小さなレコード・プレイヤーで初めて聴いた交響曲に心底感動したあの時の心を、もう一度取り戻したいと思うことがある。
でも、たぶん大切なものほど、決して取り戻せないものなのだろう。そして、決して取り戻せないからこそ、大切なのものなのだ。
*
◆福田進一&E・フェルナンデス/タンゴ・ミレニアム(デンオン)
それにしても、演奏技術の向上という点では、昨今のクラシック・ギター界はなかなか凄い。かつてセゴビアが新天地を築いた土壌に、今みっしりと名手が集っている。
このアルバムで福田進一とエドゥアルド・フェルナンデス両氏が聴かせるデュオの世界も、今でこそ当たり前のように聞き流してしまいそうになるが、一昔前なら超絶技巧の乱舞。タンゴをキイワードに、2本のギターが奏でる自由な音楽宇宙が広がる。
◆ドヴォルザーク&サン=サーンス:チェロ協奏曲/デュ・プレ(テルデック)
一方、若くして伝説になってしまったチェリスト、ジャクリーヌ・デユ・プレの場合は、こうして録音が残っているので、今でもその凄さを実感できる。そして、この演奏を聴いていると、テクニックがどうこうというより、音楽に向かう深さや熱気のようなものが圧倒的であることに気付く。
でも、何と引き換えにデュ・プレがその深さや熱気を得たかということを考えると、音楽の怖さに背筋が寒くなることも事実だ。
音楽の「深さ」を得るということは、すなわち「深み」にはまるということだし、心の炎を得るということは、同時にその火に焼かれることを意味するからだ。
代償のない進化はない…ということか。
第15回:急性〈音楽ぎらい〉病の症例
年に何度か、どんな音楽も受け付けなくなるという時がある。
私はこれを「急性〈音楽ぎらい〉病」、正確には「突発性音楽嫌悪症候群」と呼んでいる。要するに、あまりにも音楽を聴きすぎて耳が一時的に音楽を受け付けなくなる状態とでも言ったらいいだろうか。
確かに、仕事がら毎日毎日膨大な音楽を聴いているので、耳が「もう満杯で、これ以上一音たりとも入りません」と悲鳴をあげるのも仕方ないことなのかも知れない。どんな酒呑みだって、あんまり飲みすぎたら「もうこれ以上一滴だって入りません」という状態になるだろうし。
なにしろ起きている間はほとんど「音楽びたし」。作曲というのは日々何時間も自分の出す音楽に浸る仕事だし、そもそも音楽が好きだから音楽家をやっているので、どんな音楽でも片っ端から聴く。そのうえCD評の仕事で聴かなければならないクラシックの新譜は月に百枚近くあり、オーケストラなどの演奏会の解説のためプログラムの曲目のCDにも耳を通さなければならない。もし耳の許容量というのがあれば、とっくに限度を越しているに違いない。
生のコンサートは滅多に行かないが、作曲している間や原稿を書いている間も、部屋には何らかの音楽がCDで流れている。そうしないと都会では生活騒音が気になって仕事など出来やしないからだが、時には作曲中のコンピュータ音楽モジュールとCDとFMとテレビからそれぞれ出る音楽が混合され、二重・三重になって聴いていることさえある。
そんなわけだから、仕事場にはCDを再生できるデッキやコンポのたぐいが複数台あるのだが、これがまたよく壊れる。一日中取っ換え引っ換えCDを投げ込んで酷使しているのだから仕方ないのかも知れないが、最近もとうとうまた一台、トレーが出てこなくなって昇天されてしまった。
でも、機械ですら壊れるほどなのだから、それを全部聴いている耳の方こそおかしくならない方が不思議なのかも知れない。そう思うと、ちょっと怖い。
ただ、昔から音楽に関する間口は広い方だから、クラシック系の音楽に聞き飽きても、なじみのロックで耳をリセットしたり、ヘビー・メタルやハード・ロックをガンガン鳴らしたり、逆にモダン・ジャズにしっとり浸ればまず社会復帰できる。時には六十年代フォークや懐かしのメロディから最新のJポップやテクノにまで飛ぶこともあるが、雅楽とかコーランなどに浸るところまで行くと相当ディープだ。
それでもどうしてもダメなこともある。そんな時はどうするかと言えば、応えは簡単。どうしようもない。しばらく音楽のないところに行って静養するしかない。
この「突発性音楽嫌悪症候群」に、最近また襲われた。と言うより、今この原稿を書いている現在が、その真っ只中である。
実は、4つ目の交響曲を書き上げた後、仕事場のマンションの上の階で改装工事が始まった。このあたりはもう天災としか言い様がないので、その工事騒音を避けるため普段以上の音楽びたし(密閉型ヘッドホンで普通より大音量で聴く)をやっていたのだが、さすがにそのせいで耳の許容限度を超えたのだろう、突然「ああ〜、いやだいやだ、音楽なんてもう聴くのもいやだ!」と言う状態になってしまったのである。
しかも、今回ばかりはオラショを聴いても前衛音楽を聴いてもダメ。で、仕方ないので仕事はスッパリやめてブラリ旅に出た。昼間は知らない町を歩いて、古本屋や神社や蕎麦屋をのぞき、夕暮れになると居酒屋を見つけてカウンターで一人酒を飲む。音楽はなし。そして、人もなし。治療はこれしかない。
ただ、この「急性〈音楽家なのに音楽ぎらい〉病」は確かに困った状態ではあるのだが、一過性なので、一週間もすれば治る。ところが、昔から発症している「慢性〈人間なのに人間ぎらい〉病」は、どうも治癒しそうにない。こちらは最近むしろ一段とひどくなった気がする。
それでも、長年作曲家をやっていると「音楽ぎらい」には見えないように振る舞うくらいのことは出来るし、もっと長年人間をやっているので「人間ぎらい」には見えないように振る舞うくらい出来るようになった。
おかげで一応は社会人のような顔をして生活できるわけなのだが、いつまでこの仮面が持つか、ちょっと不安ではある。
でも、例えばバスや電車の運転手諸氏だって「あ〜、もう運転なんかいやだ!」と突然思うことがあるのだろうし、黙々と朝のラッシュアワーで揉まれているサラリーマン諸氏も3日に一度くらい(あるいは毎日)は「あ〜、もう会社なんかうんざりだあ〜」と思っているのだろうなあ。みんな仮面の奥で、自我の崩壊をじっと耐え忍んでいるわけだ。
と言うわけで、旅に出ると、人に会わない代わりによくネコに会う。今回は京都の先斗町あたりで何匹かと出会ったのだが、彼(彼女)らも「あ〜、ネコなんかいやだあ〜」と思うことがあるのだろうか。
そう思って「いいなあネコは。音楽聴かなくてもいいし、会社行かなくてもいいし、運転しなくてもいいし…」と話しかけると、公園で日なたぼっこしていた黒ネコが「そう思うんだったら一度ネコやってみればぁ?」とニヤリと笑って言った(ような気がした)。
あ、危ない危ない。公園でノラネコなんかと話すようになったら、それは別のビョーキなんだっけ。そろそろ東京に帰らなくちゃ。
*
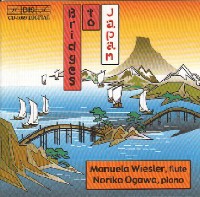 ◆日本のフルート/ヴィースラー、小川典子(BIS)
◆日本のフルート/ヴィースラー、小川典子(BIS)東京に帰ったらCDがゴッソり届いていた。その中の一枚は、私の作品(デジタルバード組曲)が入っているので輸入盤の状態で以前もらったアルバム。フルートのヴィースラーさんとピアノの小川典子さんによるジャポニズム味の一枚で、その浮世絵風のジャケットを見ていたら、新京極の土産物屋さんを思い出した。それに、山田耕筰・江文也・菅原明朗・金井喜久子……というラインナップは、寺町通りの古本屋さんでものぞいているみたいで、なんだか楽しい。
◆ショスタコーヴィチ:交響曲第2・3番/ヤルヴィ(グラモフォン)
一方、ショスタコーヴィチ先生は、作曲家としてつらい時があっても「でも先生よりはマシ」と思えば心の支え(?)になるという魂の人。二十歳そこそこで書いた初期のこの2つの交響曲など聴いていると、確かにノラネコに話しかけたくなる。あ、危ない危ない。そろそろ我に返らなくちゃ。
第16回:雑学でいこう
とある若い人から「作曲家になるのに必要なことって何ですか?」という質問を受けて、ちょっと考え込んでしまった。
私の中での答えは簡単明瞭「雑学」なのだが、人に(特にこれから音楽を勉強しようという若い人に)は、あまりうかつなことも言えない。
なにしろ作曲家としての勉強というのは、中学高校の音楽の授業さえちゃんと聴いていれば、おおむねOK。そこで習った楽譜の書き方の基本さえ知っていれば、国家試験も調理師免許も保健所の許可もいらない。
で、スコアを書いているうちに、「ええと、総譜は楽器をどういう順番で書くんだっけ」と思えば楽器屋に行ってスコアを立ち読みして調べればいいし、「へえ、クラリネットとかホルンは移調楽器なんだ」と知れば図書室へ行って「管弦楽法」などという本を借りてみればよろしい。
あとは、どれだけ音楽以外のムダなことを吸収しているかで作曲家の資質は決まる(と私は思っている)。
*
なにしろ私はと言えば、作曲家を志して大学をやめてからも、小説やラジオ・ドラマを書いて雑誌に応募したり、ロック・バンドに入ってキイボードを弾いたり、ペン画やマンガをせっせと書いていたりしていて、自慢じゃないが本格的に音楽大学で勉強しようとか先生に付こうとか海外留学しようとか微塵も考えたことがない。
一方、〈おたく〉なんて言葉が存在するはるか昔からアニメやSFの類をかなりマニアックに見ていたし、ホラー映画なんていう言葉が存在するはるか以前からB級映画には目がなかったし(というのは、あんまり自慢できないかも知れないが)。ゴジラなどの東宝怪獣映画ものなどはビデオをゴッソリ集めていたし、今を時めく宮崎駿の作品などもかなり初期からすべてチェックしていたっけ。レンタル・ビデオ屋という代物が出来た時は店にあったB級SFやC級ホラー映画を片っ端から借りて見てたから、連続殺人なんかあったら警察からリストアップされてたかも知れない。
それから、昔はプラモデルをめちゃくちゃ作っていた。私の世代だと主に第2次世界大戦モノで、日本海軍とアメリカ空軍の飛行機が部屋に入り乱れていた。潜水艦とか戦艦や空母も何十隻とあって、引出しには「まるで貝塚ね」と母に言われたほど壊れた破片が散乱していた。最近、リハーサルで航空自衛隊の楽団がある基地に入ったとき古い戦闘機が展示してあるのを見て「あ、F86Fですねえ」と言ったら、「なんでそんな専門的なことを知ってるんですか!」と言われたけれど、私の世代のプラモ・マニアでは珍しいことではない。
そうそう、モデル・ガンも集めていて、ワルサーとかルガーとかベレッタとかスミス&ウエッソンなどから、ウィンチェスターのライフルとか照準スコープ付きのマグナム44とかもゴロゴロしていた。その頃の知りあいに車のダッシュ・ボードにまでモデル・ガンを置いてる男がいて、本物のヤーさんから声をかけられたことがあるそうな。
そう言えば、子供の頃は石弓(今で言うボウ・ガン)とか手裏剣(忍者が投げるやつ)とかペンシル・ロケット(花火の加薬を入れて飛ばす)とか、危険なものを秘密の工房で手作りしていたなあ。近所の女の子に空き缶のフタを集めてもらい、それを星形に切って磨いた手裏剣は結構すぐれ物だった。でも、オモチャだと笑ってみていた大人が、手製の石弓13号がブリキ板3枚をブチ抜くのを見て仰天。みんな壊されたうえ、製造禁止を言い渡されてしまったっけ。
そんなだからコンピュータも、モノクロ画面(正確にはグリーン)に英字と半角カタカナしか打てなかったPC8001なんてころからいじくっていた。なんの役にもたたなくて高価なだけで、日本語も使えなければ漢字の表示も出来なかったけれど、音源につないでピアノ曲やアンサンブル曲をせっせと打ち込んで鳴らしたりしていた。まだMIDIなどという規格が出来る前の話である。
とは言え、それらも別に「音楽に役に立つから」と思ってやっていたわけでも、「雑学でいこう」というポリシーがあってやっていたわけでもない。とにかく止まらないのだ。
でも、それらすべてが確実に今の自分の音楽に重要不可欠の要素になっていると断言できる(ゴジラも手裏剣もコンピュータもね)。
つまり、何と言うのかな、自分が心から面白いと思うものを雑多に追及してゆくうちに、そのベクトルが指し示す道というのが見えてくる。まさに「遊びをせんとや、生まれけむ」というわけなのだ。
だから結論としては、つまるところ作曲家に限らず「何かになる」というのは、自分という迷宮の中央にいる〈魂の主〉をしっかり見据える行為なのだ、ということかな。
*
◆鳥のシシリアーノ〜新実徳英ヴァイオリン・ソング・ブック(カメラータ)
そう言えば、敬愛すべき友人である新実徳英氏も、東京大学工学部を卒業したのに作曲家になってしまったという怪しげで不思議な人物なのだった。確かに音楽家には理工科系出身が多い。それも「理知的なことを追及したいから」ではなく、数学や科学では割り切れない「人間的な美を追及したいから」というのが理由。逆に、作曲家のくせに理知的ぶる人には意外と数学オンチの文科系が多いような気がする。
この一枚は、彼がゲンダイオンガクを離れて「歌える歌」を目指したヴァイオリンとピアノのための小品集。1巻6曲の曲集が3つ、計十八曲が収められている。可愛いメロデイが浮遊するきれいな貝の破片…のよう。
◆どですかでん〜武満徹/鈴木大介(フォンテック)
そうそう、雑学といえばタケミツさんも相当なものだった。ゲンダイオンガクの巨匠なのに、最初に会ったときはなんと阪神タイガースの野球帽をかぶっていたし(ただし夏の避暑地での音楽祭でのこと。念のため)、ジャズの話を実に楽しそうにする。彼の映画好きは有名だし、面白いことや変なことに対する触覚が鋭敏で、いい意味で芸術家ばなれした人だった。
そのタケミツさんが遺した愛すべきメロディを、鈴木大介と渡辺香津美の両氏がギターで紡いだのがこの一枚。「作曲家の根源はなんといってもメロディなのだなあ」と心から実感できる美しいアルバムだ。
そう、最初の問いの答えは「メロディを書くこと」。これにしよう。
第17回「突然引越日記」
某月某日。突然、引越しを決意する。
別に引越マニアというわけではないのだが、このところ5年に一回ほどのペースで引越している。原因はいつも「音」。確かに普通の人よりは神経質だとは思うが、どうも人の出す音が苦手なのらしい。以前から頭の上の部屋の音が気になっていたのだが、それにプラスして改装工事の騒音が発生し始めたため、意を決しての首都移転となった次第。
そんなわけで、今回は「絶対頭の上に人が住んでいない部屋」をテーマに、新宿から中野界隈を探し、5階建てマンションの4階で上にも隣にも部屋がないという一室を発見。不動産屋さんに飛び込んで即決。引越決意からわずか2日目のことである。
*
某月某日。田部京子さんによる「続プレイアデス舞曲集(仮題)」の録音立会いのため、横須賀のベイサイド・ポケットという小ホールへ。
前回の第1集から第5集までに続いて、今回は第6集から第9集までとピアノ小品集という組み合わせ。いずれも田部さんのピアノの音に出会ってから以後に書いた作品ということになるが、特に作風を変えたわけでもなく、「作曲家はとっくに死んでいて存在しないと思って自由に弾いてください」とリハーサルもせず注文も出さず、解釈も彼女に全面的に御任せというのは前回と同じ。
それにしても、田部さんの美しい繊細な音で紡がれてゆく音楽を聴いていると「ああ、自分が書いた作品で良かった」とつくづく思う。これが人の作品だったら、嫉妬で胃をやられるに違いない。夏ごろ発売予定。
*
某月某日。引越屋さんが引越しの見積もりに来る。しかし、仕事場の部屋を見るなりCDと本の山を見て「ひえ〜!」と叫ぶ。確かに8畳の洋間は全部ギッシリCDだし、6畳の和室は全部ギッシリ本だらけ。「こりゃあ4tトラックでもあぶない」と脅かされて、あわてて本やらLPやら資料やらを整理し、半分を目標に捨てることにする。結局ダンボール五十箱分ほどを処分。
*
某月某日。ビオラのバシュメット氏のご指名でコンサートの後、錦糸町で飲む。
バシュメット氏は私と同い年で、若いころはロックに惹かれてエレキ・ギターなどを弾いていた人。黙っていると哲学的な風貌だが、実はけっこう明るくて女性好き。ジャパンアーツの関田社長が橋渡しをしてくれて、コンチェルトかなにかを書く話になりそう。
日本の作曲家の研究のため来日中のロシアの音楽学者ヤクーボフ氏も一緒で、どこかで私の書いたイラストを見たらしい彼は「カリカチュア(戯画)の本は出さないのか?」としきりに言う。出したらそのまんまマンガ家になりそうで怖いのです、ヤクーボフさん。
*
某月某日。いよいよ引越当日。今回は住み慣れた渋谷区初台近辺を離れて、4キロほど山手通りを北上。新宿区の最西端で、道を一歩隔てると中野区というところ。
そんなに騒音が気になるなら、静かな田舎に引っ越せばいいじゃないかと言う人もいそうだが、実は田舎の方が周りが静かなだけ遠くの音が聞こえるし、こちらの出す音もはるか彼方まで聞こえる理屈。難しいのである。
というわけで、ひとまずは落ち着き場所が決まったわけだが、ここもまた5年以内の運命に違いない。さて、放浪の作曲家の安住の地はいずこ?
*
某月某日。引越荷物もそのままに、交響曲第1番(カムイチカプ交響曲)の関西初演のため、名古屋へ。
指揮:藤岡幸夫、ピアノ:横山幸雄による名古屋フィルの現代日本音楽特集コンサートで、外山雄三「ラプソディ」、伊福部昭「リトミカ・オスティナータ」との組み合わせ。
3曲ともビート全開、メロディ噴出、ハーモニー濃厚の作品ばかりで、熱い音楽がホールに満ち、満員(なんとこのプログラムでチケット完売だったそうだ!)の聴衆に祝福された素敵なコンサートとなる。
*
某月某日。シャンドスでのCD録音のためイギリス、マンチェスターに飛ぶ。
5枚目のアルバムになる今回は、新作書き下ろしの「交響曲第4番」の録音初演を中心に、トロンボーン協奏曲「オリオン・マシーン」(独奏は、最近ウィーン・フィルの首席に抜擢されたというイアン・ブースフィールド氏)、弦楽アンサンブル版の「アトム・ハーツ・クラブ組曲」の組み合わせ。
第4番はそもそも第3番と第5番という巨人に挟まれた北国の乙女…じゃなかった「トイ(おもちゃ)&パストラル(田園)・シンフォニー」として書かれたもの。オリオン・マシーンもアトムもどこか玩具の肌触りだし、ロックのリズムとオモチャの仕掛けが合体した不思議なアルバムに仕上がりそう。
*
某月某日。朝イギリスから戻って成田着。その夜、日本フィルによる「二十世紀シリーズ」のコンサートへ。
私の「朱鷺によせる哀歌」と、ラウタバーラの「鳥とオーケストラのための協奏曲」およびデュリュフレの「レクイエム」という、二十世紀に書かれたのにハーモニーもメロディもある作品3つの演奏会で、コンサート前には指揮の井上道義氏とプレ・トーク。
二十世紀音楽という視点が、徐々にだが確実に変わりつつある。そんな手ごたえを感じる。
*
◆ラッセル・ワトソン/ザ・ヴォイス(デッカ)
というわけで、今回はイギリスで大ベスト・セラーのヴォーカル・アルバムをご紹介。プッチーニやヴェルディのアリアから「明日に架ける橋」や「フニクリ・フニクラ」までを歌ってしまう節操のなさながら、その黄金の声で聞き手を魅了するのが、彼ラッセル・ワトソン。これだけ声が出たら気持ちいいだろうなあと思わせるような、いい声だ。
◆ファジル・サイ自作自演「シルクロード」(トリトーン)
もう一枚は、「春の祭典」の一人多重録音で話題になったトルコのピアニスト、ファジル・サイの自作自演アルバム。「シルクロード」と題された不思議なコンチェルトからジャズ風のソロまでが並ぶ力作で、ストラヴィンスキー的モダニズムを核に、民族音楽を思わせるプリペアド・ピアノのサウンドやフリー・ジャズからベタベタの泣き節まで、その語彙も豊富。なかなかの才人である。
第18回:ド#もドーナツのド?
数学を学校で習っていて「こんなこと勉強して一体社会に出て何の役に立つんだ?」と一度でも思わなかった人はいないはず。
確かに、普通の社会生活を営んでいる限り、せいぜい小学校高学年くらいまでの算数の知識さえあれば事足りる。そこで、工学部出身の私ですらもはや因数分解も確率も微分積分も、すっかり記憶の彼方に消えているわけなのだが、「二二んが四」「二三が六」という九九だけは頭の底にこびりついている。
つまり、さしあたり足し算・引き算・九九くらいまでを憶えれば、なんとなく「数」を使える気になるということらしい。と言うわけで、この九九というのは、数の性質とも数学の本質ともまったく無縁の単なる「呪文」ながら、数学の入口としては有効というわけだ。
音楽における「ドレミ」というのも、これに似ている。
「音楽とは何か?」という問いはあまりに難問だが、さまざまな楽曲をドレミで読んだり書いたりすることを憶えると、さしあたりなんとなく「音楽」を使える気になる。と言うわけで、このドレミというのは、音の性質とも音楽の本質ともまったく無縁の単なる「呪文」ながら、音楽の入口としては有効というわけ……
……なのだろうか?
私の世代だと、例えば「チョウチョ・チョウチョ…」という歌は「ソミミ・ファレレ…」と習ったと記憶しているのだが、最近若い世代の人と話していたら、「ぼくの時は、ドララ・シソソ…でした」と言う。
なるほど、ハ長調なら「ソミミ」だが、楽譜がヘ長調で書いてあれば「ドララ」だ。
つまり、これが一時論争になった「固定ド」と「移動ド」の差なのだが(最近はどうなっているのだろう?)、「でも、ヘ長調なら正しくは、ドララ・シ♭ソソ…だよね。シふらっと・ソソ…って歌ってたの?」と聞くと、「シソソ…のままでしたよ」と言うから面白い。
まあ確かに、普通の小学校の音楽の授業で「それはシじゃなくて、♭が付くからシふらっと(あるいは、シふら…とか?)と歌いなさい」とまで言うのはいささか専門的にすぎるか。でも子供の音楽教室などでは、#♭の付く音はしっかりドイツ音名で読むそうな。つまり、先ほどの部分は「ドララ・ベーソソ」、ニ長調なら「ラフィスフィス、ソミミ」となる。(先生、そうでしたよね?)
どうせなら、和音名で「ハイイ・変ロトト」とか「イ嬰ヘ嬰ヘ・トホホ」と教えればいいのに、それはないらしい。(え、トホホ…はイヤ?)。でも、そもそも、このために明治の初期に苦労して和音名を開発したんじゃなかったのかしらん?
まあ、これは九九と同じことで、要するに「嬰ヘ」「ファ・しゃーぷ」「フィス」「エフ・しゃーぷ」という四種類の読み方のうち、どれが並べて読むのに語呂がいいかといういうことなのだろう。
しかし、そのどれもが唯一にして絶対のものでない証拠に、いまだに音楽の現場ではこの四種類(さすがに海外ではハニホヘト…はないが、国内ではハ短調・ヘ長調などで健在だ)の音名が飛び交っている。
例えばドイツ音名の「E」と英語音名の「A」は同じ発音「エー」だから、そんなときは「ミ・なちゅらる」という言い方がないと収拾が付かないし、「B♭」は即座に「ベー。ビーふらっと。シふらっと」とまくし立てないと必ず「え?」と聞き直される。
ロックやジャズではすべて英語読みで「ビーふらっと・メジャーせぶん」とか「エフしゃーぷ・マイナーないん」ですむのに、クラシックは国際的になったがゆえに逆にこの点については不便になってしまったような気がしないでもない。
個人的には、九九と同じで初等音楽教育には「ハニホヘトイロ」「嬰ハ」「変ロ」を使えばいいのにと思う。ただし、嬰(えい)と変(へん)は2音になるので改良が必要。例えば#が濁音で、♭が半濁音…というくらいだと話が早い。「バビボベド」とか「パピポペトゥ」とかね(でも、イとロが駄目か…)。
問題は、専門家になってしまった音楽家に、「ハニホヘト」の読み方で絶対音感を憶えた人がいそうにないということ。なにしろ、トホホ…だもんなあ。でも、十二音音楽なんか、この新和音名で歌ったら面白そうだ。「ハボペロトゥニベドポイトホ……」とかね。(お、これは意外と合うかも…)
ただし、音楽は「ドレミファ」にあるのでも「ハニホヘ」や「CDEF」にあるのでもない。音が次の音に移る瞬間に発するエネルギーをある種の感情のスペクトルと感じる「人間の心」の中にある、ということだけは覚えておきたい。
例えば「F(フ)」と「A(ア)」の発音をいくらつなげても「Fa(ファ)」にはならない。「F」の口の形が「A」の形に移る瞬間に「ファ」という音が生れるのだ。音楽はそれに似ている。
だから、九九を覚えて数字をいくら書き連ねてもお金は貯まらない(当たり前だ!)ように、ドレミファを憶えていくら並べても音楽にはならないのだ。
九九とドレミを教わる前に、良い子はしっかりそのこと、覚えておこう。
*
◆モーツァルト、シェーンベルク/アルノルト・シェーンベルク・トリオ(カンパネラ・ムジカ)
ところで、絶対音感を持つ某知人は、テレビなどから「音名がわからないフレーズ」が聞こえてくると気持ち悪くなるらしい。でも「ミ・フィス・ギス・ベー」などと音名が分かれば、不協和音でも安心できるのだとか。
なるほど。と言うことは、このCDみたいに、モーツァルトのもっとも優美な弦楽トリオ(変ホ長調のディベルティメント)と、シェーンベルクのもっとも不協和音炸裂の弦楽トリオ(弦楽三重奏曲)を並べても、彼はもしかしたら「同じに聞こえる」と言うのかも知れない。
でも、「フツーの耳」にとっては、同じ楽器の組み合わせでこれだけ異質な音楽が生れるのはショック。それは、「いちめんのなのはな」と「バベゴゴドギベビビ」は同じ9つの音で出来ているにもかかわらず、まったく異質なイメージを持つのに似ている。
◆ブルックナー交響曲第9番ニ短調/スクロヴァチェフスキ指揮ザールブリュッケン放送交響楽団(アルテノヴァ)
ちなみに、人間が知性と技術を総動員してドレミファを駆使すると、こういう「交響曲」が出来上がる。
第19回:「独学」とは何だ?
「独学なんですよね」と、よく言われる。
確かにそうなのだけれど、最近、若い人から念を押されるようにそう言われると、「じゃボク(わたし)も独学で音楽をやろうっと…」という決心の共犯にされるような気がしてちょっと怖い気もする。
でも、確かに「音楽は独学に限る」と私は思いますよ。自分の音楽は自分でしか掴めないんですからね。中でも特に自分度の高い「作曲」なんていうのは、これはもう絶対教わりようがなければ教えようもない。
言い方は悪いけれど、芸は「習う」物ではなく「盗む」もの。それに、作曲をやろうなんて言うひねくれた(?)人間が、「先生に習う」なんて殊勝なことに耐えられるはずもないし、そもそもそんな悠長な(?)ことをやっている暇はないですからね。…と言うわけで、今回は「独学」のお話。
*
私がクラシック音楽なるものをまともに聴き始めたのは、実を言うと高校生になってからだから、ちょっと遅い。中学での最後の音楽の授業で「運命・未完成・新世界より・悲愴・合唱(だったかな?)の5曲を5大交響曲と言います」というような先生の話を聞いた記憶があるが、その時点ではその中の1曲たりともまともに聴いたことがなかったのだから推して知るべし。
しかし、高校に上がるやいなや、なぜか知らないが「シンフォニーを書くッ!」と決心して、いきなり書き始めた。まあ、この時点では、油絵を描く、とか小説を書いてみる、とかいうのと同じような次元だったような気がするのだけれど。
一応、小学生の頃しばらくの間ピアノを習って(習わされて?)いたことがあるので、多少は五線譜を読めたものの、さしあたりの音楽的素養は義務教育レベルの楽典プラスそれだけ。後は、ギターかき鳴らして覚えた「コード・ネーム」くらいだろうか。
で、まずはピアノのフタを何年ぶりかで開けて、家にある楽譜を片っ端からとにかく弾き始めた。と同時に、家や学校にあるクラシックのレコードを片っ端から聴き始め、毎日とにかく最低でも1曲(1メロディ)というペースで曲を作り始めた。
そして、例えばチャイコフスキーの「悲愴」のLPを聴いて、その解説に「三大交響曲が…」などと書いてあれば、翌日には第4番と第5番を聴きに学校の試聴室に飛んで行き、聴いたら今度はスコアを探しに楽譜店に行き、スコアを読んでいると今度は楽器法についての疑問が出てきて、図書室でオーケストレイションの本をひも解き、ひも解くと今度はそこに「XXという曲にこの楽器法の一例がある」という一行のせいで、またその曲をレコード屋にすっ飛んでいって確かめる……というような〈止まらない尻取りゲーム〉をずーっと十年ほどやっていたような気がする。
とは言え、実を言えば同じくらいのペースで小説を読みまくり書きまくり、絵を見まくり描きまくっていたから、「作曲家になる勉強」をやっていたわけではない。ただ、とにかく朝から晩まで四六時中、スコアか小説か科学書か画集か、何か本を読んでいた。
しかも、正統なる名作とか文芸作品とかよりも、二流とかB級とか異端とか言われているものの方にひかれるので、どんどん雑多でディープな世界にのめり込む始末。おかげで現代音楽に関しては、FMで放送されるものほとんどすべてをエア・チェックするマニアとなり、一方でアニメやB級映画(特にホラーやSFもの)のマニアもやっていた。そうそう、それにマンガも描いていて、せっせと専門書店に入り浸っていたし。今なら立派な「オタク」である。
おかげで、時間がいくらあっても足りやしない。だから、誰かに何かを習いに行くなんて思い付きもしなかった。なにしろ一日単位で、現代音楽〜量子物理学〜プログレッシヴ・ロック〜古代史〜シュール・リアリズム〜ホラー小説〜モダン・ジャズ〜古典邦楽〜アニメ〜幻想文学などなど、集中しているものが変わるのだから。
と言うわけで、音楽に目覚めた十五の春から、なんとか作曲家としてデビューする二十八の春までの十三年間は、何にも仕事がないくせに独りでず〜っと忙しかった。大学に行くなんて暇もなかったから中退してしまったほどだし。
これを「独学」と言うなら確かに独学。今となってみれば、どれが欠けても今の自分の音楽はなかったと思うし、まるでジグソウ・パズルのすべてのピースがぴたりと合うように、すべての雑学が交響曲の中でピタリと重なっている気がする。これ以外に作曲家への道はなかったとしか言い様がない。
しかし、こんな奇妙な独学法を人に勧めるわけにはとてもいかないだろうなあ。横でハラハラしながら見ていた両親の感想はたぶんこうに違いない。
「何とかなったからいいようなものの…」
*
◆ヤルグレップ:がらくた交響曲/カルニンシュ:ロック交響曲(BIS)
しかし、世の中には独学でなくとも奇妙な作曲家は育つものらしい。このCDで「ロック交響曲」という怪しげな曲を披露しているラトヴィアのカリスマ作曲家カルニンシュもその一人。一応ちゃんと音楽院を出て、国会議員を務めながら(!)作曲家をやっている人らしいのだが、この全4楽章四十分以上の大作交響曲は、本当にアマチュア・ロック・バンドのレベルのロックを大オーケストラで鳴らしてしまった壮大な問題作。このチープさ、このシンプルさ、そしてこの熱っぽさ。しかも、プログレありバラードありロックンロールありと、お客を楽しませる(そして、ちょっと恥ずかしがらせる)術も心得ている。どこまで本気なのかな?とも思うが、その問いは私にも向けられそうなので、パス。
◆ヴァレーズ:アメリカほか/ブーレーズ指揮シカゴ交響楽団(グラモフォン)
一方、二十世紀の現代音楽界における巨人のひとりエドガー・ヴァレーズは、もちろん独学なんかではなくちゃんとパリ音楽院で学んだ人。アメリカに亡命してからは作曲の先生としても活動していたが、このCDに収められている「アメリカ」「アルカナ」「砂漠」というようなオーケストラ曲を聴いていると、なんだか「〈春の祭典〉を盗もうとして盗みそこなった」独学の士の作品という感じだ。でも、咆哮する金管楽器、わめき散らす弦楽器、叩きまくる打楽器は、ヴァレーズの本領発揮。結局、音楽は独りでジタバタしながら掴んでゆくしかないのだろうな。
第20回:異種交配は純音楽を構造改革するか?
先日、ロック・ギターの雄イングウェイ・マルムスティーンと新日本フィルの共演(というより異種格闘技)によるコンサートを聴く機会があった。
演奏(舞台初演)された彼自作のコンチェルト「ミレニアム(新世紀)」は、ハード・ロック系ギターの大音響と電気増幅したオーケストラとが協奏する全十一章四十分ほどの大作組曲。ただし、以前彼にインタビューした時スコアを見せてもらったことがあるが、書式自体はストコフスキーのバッハ・トランスクリプションを思わせるクラシカルなもの。エレキ・ギターでなくヴァイオリンで弾いたら、そのままバロック風コンチェルトになりそうな曲である。
しかし、バンドやドラムス(リズム・セクション)のバックなしに、ソロ・ギターたった一人でオーケストラと1対1の協奏を試みる姿はきわめて潔い。最初は、なんとなくオーケストラと(音量の点でも音色の点でも)しっくりいかない感じがしたが、フィナーレやアンコール曲あたりになると、すっかり客席はスタンディング・オベーション状態。このあたりはさすがである。
彼自身は「(正しく現代にクラシック音楽を継承しているのは)カール・オルフ以降オレだけ」と豪語するのだが、いわゆる現代音楽には全く興味はないようだし、クラシック・オーケストラのコンサートで披露される新作にしては(言ってみれば、タケミツさんがニューヨーク・フィルの前に尺八と琵琶をサウンドさせたのと同じ次元の試みなのに)、どう見ても「現代曲」の範疇ではまったくない。たぶん現代音楽どころかクラシックの関係者の姿すらなかったのではなかろうか(大音響で帰ってしまったのかも?)
そう言えば、私の作品も、最近では普通のオーケストラの定期コンサートでチャイコフスキーなんかと当たり前のように初演されたり演奏されてしまうので、現代ものの関係者など見かけたことがない(もっと招待状すら出してないのだから当然といえば当然なのだが)「クラシック系の作曲家」ではあっても、もはや「現代音楽の作曲家」では完全になくなっているのである。
しばらく前まではそれでも、オーケストラで演奏されるような新作はすべて「現代音楽」という枠で括ったうえで、様々な様式の折衷主義なら「ポスト・モダン」あるいは「多様式主義」、調性やメロディに回帰する傾向があるなら「新ロマン主義」などと無理やりこじつけていたのだが、さすがに「ヒーリング系」や「ロック系」が登場するに至って「現代音楽の中でポピュラー寄りの作風」などという括り方すら出来なくなってきたようだ。
そこで、最近では、逆に「こんなのはクラシックではない!」とか「こんなのは現代音楽ではない!」と言い張る保護貿易主義が蔓延し始めたのか、あるいは雑多なジャンルに目を光らせる目利きの人材がいなくなったのか(もっとも、これだけ現代の音楽シーンが雑多になってしまっては、全ジャンルに一応目を光らせるというだけでも人間業ではないのだろうな)、ますます視野を狭めているクラシック系創作界は、あたら優れた才能を他のジャンルに流出させ、自らの首を絞めている感がある。ま、いいけど。
そのあたりのきっかけはピアソラ・ブームからだろうか。ペルトやグレツキは、ポピュラリティを持ってもまだ「現代もの」だったし、クロノス・カルテットなども領界ギリギリながらクラシック〜現代音楽のセンを崩してはいなかった。しかし、元がタンゴのピアソラはそうは行かない。以後、マイケル・ナイマンを始め坂本龍一や吉松隆なんかも、クラシック系を匂わせながらも、完全に現代音楽界からは遊離しているし。
などと思っていたら、最近イギリスから究極の破戒カルテットが登場。「ボンド」というこの女性4人のストリング・カルテット、エレキ・ヴァイオリンを手にしてダンス・ビートをバックにセクシー・ポーズで演奏するというあたり、どこから見ても完全にポップ・グループ。でも、アルバムは「クラシック・チャートで一位!」なのだそうだ。これは果たして、クラシックの新しい夜明けなのか、単なる価格破壊なのか?
で、「ちょっと待てよ」なのだが、確かに「クラシック系音楽」を構造改革して「民営化」するのはある程度可能には違いないのだ。ただ、純正現代音楽にはどう転んでももはや大衆性も自主更生能力もないことは八十年の歴史で明々白々だから、このテのロック系やヒーリング系新音楽に真っ向からぶつかられては、小錦にがぶり寄られた幼稚園児位のレベル差で消し飛んでしまうのは必至。
となると、確かに枠でかこって保護するしかないのかも知れない。無調の現代音楽なんて、もはや国際保護鳥のレベルだし。わがもの顔で飛び回って害鳥してたころはバンバン撃ち落としていても、さすがに絶滅が近くなると可哀想になるしなあ。(おいおい)
確かに、純粋種ほど生命力が弱い、というのは自然界の掟。クラシック系音楽だって、実は様々かつ雑多な音楽と異種交配することでここまで生き残ってきたのだが、その機能はジャズやロックに取って代わられ、かつては「前衛」で鳴らした現代音楽界すら今では妙に純粋種づいてしまっている。
というわけで、二十一世紀を生き延びるキイワードは「異種交配」かな。(異種格闘技…という話もあるけれど)
*
 ◆吉松隆:プレイアデス舞曲集2/田部京子(デンオン)
◆吉松隆:プレイアデス舞曲集2/田部京子(デンオン)でも、「ピアノ」というハード(楽器)があって、それを走らせる「五線譜」というソフトがある、ということだけで現代に音楽を編んでゆくことはまだまだ可能。その証拠が、この〈プレイアデス舞曲集〉のシリーズ。クラシック系の響きだがクラシックではなく、メロディはあるけどポップスではなく、ここまでシンプルで美しくても「ヒーリング系」ではない。もちろん、新しい作品だけれどどこから聴いても現代音楽では「ない」。
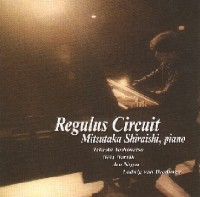 ◆109/白石光隆(音楽の友)
◆109/白石光隆(音楽の友)それに、「ずっと昔に書かれた楽譜」というソフトを「今のピアノ」というハードで走らせて、現代を刻印することもまた可能。その証拠がこの「109」というアルバム。ベートーヴェンのソナタ第三十番op.109を核に、そのソナタの影響下に書かれた矢代秋雄のソナタを対置させ、ラヴェルとショパンの小品を挟むという不思議な構成から、ギターの一人語りのような現代の詩情が立ち現れる。全然クラシカルではないが、クラシック系の現在を語ってやまない。何より、すこんと「109」と言い切ったタイトルがいい。
第21回:夏休み「第5」日記
某月某日。この秋の個展で初演する〈交響曲第5番〉のスコアを本格的に書き始める。猛暑の中、これから丸二ヶ月ほど狭い仕事場にこもりっきりのカンヅメ状態による作業が続くわけである。で、ちょっと部屋を片付け、軽く禊(みそぎ)の儀式。
ただ、前作の交響曲第4番あたりからスコアを書く作業すべてをコンピュータ化したので、ピアノや机に向かうのでなく、ひたすら22インチの液晶画面に向かってマウス入力してゆく毎日。なんだかペンの持ち方と日本語の話し方を忘れてしまいそうになる。
それにしても、昔はクーラーもなく助手のコンピュータ〈Mac〉くんもいなかったはずなのだが、その頃は一体どうやっていたのだろう。思い出せない。
*
某月某日。ピアノ&手書きの〈スケッチ稿〉を元に、まずはMacの画面上に〈デッサン稿〉を作る。一年ほど前からコツコツと書いてきた〈スケッチ稿〉は、ピアノで音を探りながらB4十八段の五線紙に曲のイメージを書き込んだ第一段階の譜面。モチーフや主題、リズム音形やコード進行、全体の構造やオーケストレイションのアイデアなどなどを思い付くまま並べたアナログ思考の草稿で、映画で言うなら「絵コンテ」みたいなもの。
一方〈デッサン稿〉作りは、それをスコアというデジタル言語に変換してゆく作業。FINALEというソフト上に作った(管楽器・打楽器・弦楽器というくらいの大まかな譜割りによる)十二段ほどの簡略スコア上に、スケッチ稿の素材を具体的に書き込んでゆく。
ここからはMac助手と二人三脚。最近G4にグレードアップした彼は、楽譜の書き写しや切り貼りから移調・転調、拍子や拍の計算などを文句も言わずテキパキとこなし、きれいにレイアウトしたうえ、音にして聴かせてくれる。助手というより魔法使いの弟子という感じである。
*
某月某日。録音の立会いのためひさしぶりに外へ出て、都内の某ホールへ。
実はこれ、まだ映画になるかTVになるか未定の、とあるSFもの(いわゆる劇伴)音楽の収録。基本的にこの種の仕事はまずやらないのだが、子供の頃からのB級SFマニアの血が騒ぎ、フル・オーケストラにオンド・マルトノ、二十絃、笙、篳篥、ソロ・パーカッションが加わる結構大掛かりなスコアを書くことになってしまった。
それにしても、こんな豪華な編成を丸2日(リハーサルも混ぜれば3日)ホールを借り切って収録すること自体SFしてる。おまけにその録音セッション中、メイキング・ビデオも作るとかでオーケストラの周りではカメラが回りっぱなし。クラシック界の仕事ではあり得ない不思議な景色である。
ついでに、映画になるのかTVになるのか、あるいはボツになるのかも未定というあたりも、う〜ん、SF!
*
某月某日。連日の猛暑の中、ようやく「第5」の〈デッサン稿〉が仕上がり、全4楽章、演奏時間四十分強、スコアにして百三十ページ超の全体像が見えてくる。
ここで一旦デジタル音源の疑似オーケストラ・サウンドで全曲を鳴らしてみる。何度か通して聴いてみて、曲のバランスやテンポ設定などと共に、音楽として「客観的に」面白いかどうか(聴いていて飽きないかどうか)を厳しくチェックするわけである。
*
某月某日。宅急便で秋のコンサートのチラシが送られてくる。しかし、マンガ風の朱鷺がペタリと貼り付けられたデザインにヘナヘナと腰砕けになり、ショックでMac助手と一緒にしばしフリーズ。夜はヤケ酒。
*
某月某日。猛暑をかいくぐって久しぶりに銀座へ。指揮の藤岡幸夫氏の後援会の会合に、サクソフォンの須川展也氏と共に出席、ミニ・ライヴ(ただし作曲家は横に立っているだけなのだが)をやる。
*
某月某日。CD「プレイアデス舞曲集2」発売。優しく夢見るようなピアノに、しばし癒される。銀座の山野楽器と渋谷のタワーレコードで、田部京子さんとこちらもミニライヴ(ただしこれも作曲家は横に立っているだけなのだが)&サイン会。
*
某月某日。気を取り直して「第5」の〈スコア稿〉に着手。これはデッサン稿をさらにフル・スコアに仕上げてゆく工程。
手書きだと、この段階でもう一度音符をすべて書き写さねばならなかったのだが(それだけで下手をすると数週間かかるのである)、今回はMac助手の〈コピー&ペースト〉という技のおかげでほんの一日作業。究極の裏技、おそるべし。
そして、ここからが本格的なスコア書きの作業。オーケストレイションを施し、細かいダイナミクスやアーティキュレイションなどを書き込みつつ、常に全体を把握しながら部分を描いてゆく。そのあたりは壁画を描くのに似ている。スコアは「絵を描くように」書くべし…なのである。
この後、さらに丸ひと月ほどこういう作業が続いて、最終工程に至る。そして、この原稿が世に出るころには我が〈第5交響曲〉は無事仕上がり、夏は終わっているはず…なのだが、さて?
ちなみに、初演は十月六日の「サントリー音楽財団コンサート・作曲家の個展2001・吉松隆」にて。
*
◆ノーノ「愛に満ちた偉大なる太陽のもとで」(テルデック)
ところで、真夏に突然コテコテの前衛音楽が聴きたくなるのはなぜだろう。暑すぎてどこかが壊れるのだろうか。というわけで前衛音楽界の巨匠ノーノのCD2枚からなる巨大な舞台作品を聴く。真夏の夜に怪談が似合うように、無調サウンドにまみれてソプラノが(まさに「ニワトリが首を絞められたみたいな」声で)絶叫する世界は、まさに暑気払いに最適。サザンとかチューブとか聴いてる場合じゃないぞ。
◆春の祭典&法悦の詩/ゲルギエフ(フィリップス)
…などという冗談が通じない方には、こちら。暴走する恐竜の群れのようなプレストから、巨大断層のような変拍子の連打、太古の霧のようなアンダンテ、心臓に悪い最後の一打のショック…に至るまで、下手なお化け屋敷を凌駕する「春の祭典」ひさびさの名盤である。拍手。
第22回:ファウストの夏
ようやく交響曲第5番を書き上げて、長い夏が終わった。
さて、これから愛車ベンツを飛ばして軽井沢の別荘に行ってしばし遅い夏休みを過ごし、その後は去年ハワイに数億円で購入した白亜の豪邸にこもり、日がな一日青い海と白い雲を愛でながら読書三昧…
…だったらいいなあ。
しかし現実は、2ヶ月こもりきりだった仕事部屋の掃除と、たまった洗濯物と、山積みのCDと郵便物の整理と、燃えるゴミと燃えないゴミ出し…という「戦後処理」。やれやれ。そこで一句。
夏交響曲や、〆切すぎの夢のあと
*
それにしても、交響曲を9つ書くと死んでしまうというジンクスは、なんとなく分かる気がする。それほど正攻法の交響曲は心底くたびれる。
それに、何の役にも立たないし、何の期待もされていないし、何の未来も秘めていない。そのあたりは人間と同じなのだが、書くたびに「何でこんなモノ書いているのだろう」と思う。それなのに懲りない。
なんだか悪魔に魅入られているような気がする…と思うせいか、今度の交響曲を書くに当たっては、実を言うとちょっぴり「ファウスト」を意識していた。文学で言うところの「モン(我が)・ファウスト」である。
と言うのも、主人公ファウスト博士の冒頭の悩み、すなわち「自分は学ぶことに追われて老いてしまったが、結局なにも真理を知ることは出来なかった」という心理状態を、なんとなく実感出来る歳になったということなのらしい。
この物語を最初に読んだ若い頃は、これがまったく分からなかった。もちろん、「時よ止まれ、美しい!」と心底言える瞬間のために魂を賭ける、という悪魔メフィストフェレスとの契約については、物語として面白いと思うのだが、「若返る」ということが悪魔に魂を売ってまでも手に入れたいものだという実感は、「若さ」のただ中にある人間にあるわけもない。
それが最近、何となく分かるようになった。しかし、それは「大人になった」というよりは「老いてきた」ということなのであって、逆に言えば、かなりヤバいぞ…という気もしないでもないのだが。
もう一点、ファウストと悪魔メフィストフェレスのほかにゲーテの「ファウスト」の核になるもう一人の人物グレーチェンの存在も、実を言えば若いころ読んだ時点ではまったく理解不能だった。若返ったファウストが気まぐれに抱いて子供をはらませ、あげく父なし子を生んでそれを殺してしまい、最後は気が触れて死んでしまう「ただ若いというだけの薄幸の女性」である。
この恋人でもなく母性の象徴でもない女性が、「永遠にして女性的なるもの」として最後の最後にファウストの魂を救済する。それが理屈の上でも感覚的にも分からなかった。
その後、この三者のドラマについて何となく思うところが出来たのは、ショスタコーヴィチの交響曲第10番(これが実はリストの「ファウスト交響曲」の構造をトレースした「我がファウスト」交響曲であることは、あちこちで書いてきた)と、手塚治虫の絶筆「ネオ・ファウスト」(朝日文庫。ファウスト譚を高度成長期の現代日本に置き換えたSF風大河ドラマ)のせいだろうか。
そして、森鴎外訳の「ファウスト」を再読しつつ、本屋で見つけた「ファウストと嬰児殺し」(大澤武男著・新潮選書。ゲーテのグレーチェン像のモデルとなった嬰児殺し事件裁判の詳細を描いている)を併読して、何かをズーンと感じた。「よく分からないが、よっく分かった」(?)と言ったところか。
結局このファウストというドラマは、老いた善と若き悪とが二重構造になった「男」と、その人生に関わる「悪魔的存在」、そして恋愛とも母性とも遊離した「女性性」が織りなす交響曲だったわけだ。
なにしろ人間ならだれでも「我がファウスト」とともに、「我がメフィスト」と「我がグレーチェン」を持っている。それが人生というものであり、二百年前から変わらぬ不変の「人間の力学」なのである。
と言うわけで、実はそれが今度の交響曲の影のテーマになっているわけなのだが、「我がグレーチェン」はともかく、私にとっての「我がメフィスト」はやっぱり「音楽」だろうなあ。なにしろ、ある日突然現われて人を奈落へ引きずり込み、苦しみと楽しみを交錯させて人の心を翻弄し、しかも「時よ止まれ、美しい!」と言ったら最後、魂を取られてしまうのだから。
*
◆シベリウス:クレルヴォ交響曲/ヴァンスカ(BIS)
そう言えば、シベリウスの出世作となった「クレルヴォ交響曲」もどことなくファウスト交響曲的な匂いがする。クレルヴォはフィンランドの民族叙事詩カレワラに登場する英雄の名前だが、この人、実の妹を知らずに陵辱してしまい、その事実に悩んで最後には自殺してしまう悲劇の人。
その物語を全5楽章一時間半の声楽付き交響曲にして、弱冠二十七歳のシベリウスは楽壇に衝撃のデビューを果たすのだが、当時彼は婚約中。後に愛妻となるアイノというフィアンセがいるのに、どうしてこんな題材で曲を書いたのだろう?(そう言えば、ショスタコーヴィチも婚約中の二十六歳に、新妻が浮気して旦那を殺すオペラ「カテリーナ・イズマイロワ」を書いているのだっけ)
◆ベートーヴェン:交響曲第5番/ラトル指揮ウィーン・フィル(東芝EMI)
ところで、百九十三年ほど前に書かれた元祖「第5」も、ひさしぶりにまともに聴いてみた。やっぱり凄い曲だ。
そもそも三十余年前、このトンでもない音楽の熱気と妄想と勢いに押されて「ボクも交響曲を書こう!」と思ってしまったのだっけ。この悪魔との出会いこそが、現在に至る転落と破滅の道への第一歩。まさか自分も「第5」を書くハメになってしまうとは。後悔だけが人生である。
交響曲なんか書いて幸せになった奴はいないのに!
*
蛇足ながら、手塚治虫の「ネオ・ファウスト」は悪魔メフィストが女性である。男の悪魔は〈牡フィスト〉で、女が〈牝フィスト〉なんだそうだ。あんまり面白いのでオペラに出来ないかと思ったこともあったが、第二部冒頭で作者死去により未完成に終わっている。残念。
第23回:3センチの虫にも1.5センチの魂
命を賭けて何かを「創造」しようとするのが人間なら、それを命を賭けて「破壊」しようとするのも人間、…か。
あの日、TVで何度も何度も映し出されるニューヨーク貿易センタービル崩壊の「嫌な映像」を見ながら、そこに「真っ白な沈黙」が漂っているのを感じたのは、世界中で数億人にも及ぶのに違いない。そして、あの映像を見た人たちの頭の中に繰り返し繰り返し刷り込まれたのは、人間に対する白濁した失望感だったような気がする。
むかし、SFのショートショートにこんなのがあった。
頭が雲の上にあるような巨大な宇宙人が突然地球にやってきて、しばらく上からしみじみ人間を見ていたのだが、そのうち何やら霧のようなものを降らし始めるのだ。
「何をやってるんだろう?」と不思議がる男の横で、「さあね」と言いながら庭の花壇に霧吹きをかけている男がいる。そこで「おまえは何をやっているんだ?」と尋ねるとその男が答える。
「害虫がビッシリ繁殖してるのを見つけてね。殺虫剤で皆殺しにしてるのさ」
まあ、確かに、葉っぱをめくってそこにビッシリ虫が繁殖しているのを見たら、人は普通「ああ、虫くんたち、元気に生きてるね」などとにこやかに笑顔を浮かべたりはしない。まず「ひゃあああ」と悲鳴を上げて葉っぱを振り払い、殺虫剤を持ってきて噴霧しまくるに違いない。
そこで虫たちが「ボクたち何も悪いことしていないのに…」とか「どうして虫だからというだけで殺すの?」と抗議したら、少しは殺虫剤を噴霧する手が緩むだろうか?
人から見れば「害虫駆除」。しかし、それは虫から見れば「大量殺戮」。これは、被害者側から見た「テロ」が、加害者側から言わせれば「聖戦」になる構図とまったく同じである。
この構図の前では、「戦争反対」とか「暴力反対」という言葉はなんとも空しく響く。人は、相手が「同じ仲間」だと思えば殺せないが、「同じ仲間ではない」と思えれば殺戮も絶滅も征服も自由自在だからだ。
そもそも異種族の排斥や淘汰は戦争でも暴力でもなく、単なる力学でしかない。「なんじ殺すなかれ」は同族社会の中で同族間にのみ機能する(限定付きの)規律であって、種族が変われば何の機能もしない。
その証拠に、ほんの半世紀前には我らが日本人も「鬼畜米英」と叫んでアメリカ兵イギリス兵を殺し、大陸に攻め込んで中国人を殺せたわけだし、アメリカはアメリカで「黄色い猿」が住む大都会に焼夷弾と爆弾を降らせて数十万という規模の「駆除」を行うことが出来たわけだ。
いずれも、今となっては想像を絶する非人間的蛮行だが、当時の世界の力学の中では至極当たり前に行われ、特に異常なことをやっているという意識はなかったに違いない。
だから時々思うのだ。今我々がやっている至極日常的なことも、時代が変わったらとてつもない非人道的蛮行になる可能性もあるんじゃなかろうか…と。
例えば「人間も動物もすべて平等に生きる権利を持つ」という新しい理想社会が生まれたとすると、今我々が日常的にやっていることは恐怖の非人道的行為のオンパレードだ。
ペットを飼うというのは動物を「不当に束縛」し「奴隷」にし「虐待」する行為だし、牛や豚や鶏に対しては「大量殺戮」したうえ「食用」にするという残虐行為を行っている。魚釣りだって魚を「拉致」したうえ「なぶり殺し」「串刺し」にして果ては「焼き殺す」超残虐行為だし、蚊取り線香とか殺虫剤なども神をも恐れぬ「大量殺戮兵器」ということになる。
さらに話を脱線させて「ロボットも人間も平等の生きる権利を持つ」という社会になれば、人工知能の付いたコンピュータのスイッチを切るというのは、彼を「殺す」ことだから絶対許されないわけだし、古くなったコンピュータを捨てるなんていうのも言語道断。ちゃんと最後の回路が焼き切れるまで責任持って添い遂げるのが常識、ということになる。(確かに私も先日、古いコンピュータを処分したのだが、もし彼が「やだ〜」とか言うアラーム音か何かで泣き叫んだら、一生うなされたかも知れない)。
さらにさらに話を脱線させて、「音階の十二の音がすべて平等に鳴る権利を持つ」なんて音楽が出来ようものなら、それこそ地獄のような…。あ、これはもうやったか。
でも、今の我々は言うわけだ。「動物と人間を一緒にするな」「ロボットと人間は同じじゃない」。
まさにその通り。だからこそ我々は、相手を「虫ケラ」だと思えば人を殺せるし、「テロリスト」と「その仲間」だと思えば兵器をもって殺戮ができるわけだ。嗚呼。
そして、音楽史の中でもそんな戦争の周辺に幾つかの作品(チャイコフスキーの「1812年」やショスタコーヴィチの「レニングラード交響曲」あるいはアウシュビッツやヒロシマを題材にした現代作品などなど)が生れているわけだが、その描き方は「勝った。ばんざい!」と喜ぶ超楽観的視点か、「なんという悲劇だ!」と嘆く超悲観的視点かに二極分化し限定されているような気がする。
しかし、二十一世紀型(とやら)の「勝利も敗北もない」「ただひたすら分極化されて不毛な」戦争には、もはや音楽はあり得ないのだろうなあ。ただ「白濁した沈黙」が広がるばかりだ。
*
◆シネマ・イタリアーノ(デッカ)
◆ハートランド〜アパラチアン・アンソロジー(ソニー)
と、人類に対するノスタルジックな気分になっているところに、なんとななくスルリと入ってきたのがこの2枚。
前者はスティング、フィリッパ・ジョルダーノ、パバロッティらが、イタリア映画の名作メロディを歌ったオムニバス・アルバム。後者はヨー・ヨー・マ、エドガー・メイヤーらによるヒット・シリーズ「アパラチアン・ワルツ」から編纂したアメリカのフォーク・ミュージック集。
どちらも、「むかしは良かったなあ」と夕日に向かって回想するような、郷愁の世界がじんわりと広がってゆく。
ぼんやり聞いていたら、むかし書いたこんな(ちょっと怖い)子守歌の一節を思い出した。
おやすみパパ
おやすみママ
明日の朝も世界があるといいね。
第24回:ある交響曲作家の私信
夏以来ご無沙汰していますが、お元気でしょうか。
こちらは、この秋に交響曲第5番の初演をなんとか終えて、ちょっと一息ついているところです。春にイギリス録音を終えていた第4番の方も、この手紙が着くころにはCDが出来上がっているはずですので、そのうちお送り致します。
それにしても、一九九○年に最初の交響曲を書いた時は、その先に未来があるなんてまったく想像もしてなかったのですが、結局あれから十二年間で5つ書いたことになります。さすがに、ちょっとくたびれましたが、聴く人すべてが顔を赤らめてしまうような第5番の派手な(?)コーダを聴きながら、長い長い道のりを歩んできた事を実感して、結構感慨深いものがありました。
もっとも、ここまで来ると「シンフォニスト(交響曲作家)」というより、立派な「シンフォマニア(交響曲狂)」ですね。現代において番号付きの交響曲などというものをぬけぬけと書き続けるのはアナクロニズム(時代錯誤)だと言う声があちこちから聞こえてきそうですが、なあに、交響曲が時代錯誤でなかった時代なんて人類史の中で一度もありませんでしたし、これからも絶対ないでしょうから、別に構いはしませんや。
なにしろ、私にとっての交響曲は、別に西洋音楽の伝統を継承しようなんて殊勝な心がけでやっているのでは毛頭なく、まあ、言ってみれば、寄席みたいなもの。まず最初に第1楽章がテケテンテンと始まってテーマをぶち上げる。続いて、スケルツォがちょっと軽い笑いでくすぐって、ご機嫌を伺う。それからアダージョが人情ばなしでホロリとさせて、最後は陽気かつ派手にスチャラカチャンとフィナーレで盛り上げて拍手を頂く…というわけです。
この「お決まり」があってこそ、聴き手は「さて、次はどう笑わしてくれるかな」「どう泣かせてくれて、どう締めてくれるかな」と期待し、作り手はそれを煽ったり逆に裏切ったりすることで巨大な表現の振幅が可能になる。これは、オーケストラという音響合成システムを使った「音楽ソフト」の構造として、古いどころか普遍的な理想形のひとつのように思えるのです。
*
などと書くと、けっこう楽しそうにやってると思われるでしょうか。でも、作曲家をやっていると、色々あります。ミューズの女神のほんのかすかな微笑につられて交響曲を書いてしまうこともあれば、トイレの落書きのような心ない評に作曲家をやめてしまいたくなることだってありますしね。
でも、例えば、ベートーヴェン先生の第5が鳴ったとしますよね。一人は「西洋音楽の歴史に燦然と輝く不滅の傑作だ!」と叫び、一人はただ「なんてデカイ音だ。天井が落ちてきそうだ!」とわめき、もう一人は「高度な作曲技法と精神性の見事な融合だ!」と唸り、一人は「恥ずかしくてとても聴いていられない!」と悲鳴を上げる。一体どれが正当な「反応」であり「批評」なのでしょうね?。なんだか、どれも分かるような気がするので困ったものです。
なにしろ、分かりやすさは「恥ずかしさ」と紙一重ですし、高尚・難解は「退屈」と紙一重。もはや「新しさ」を売り物にしたものほど古くなるのが早いことは歴史の常識ですが、「マンネリ」も徹すれば「普遍」となり「時代錯誤」も度を越せば「不滅」となる…というのは、さて定理となりますやら。
*
それでも結局のところ、私としては「恥ずかしげもなく」「ぬけぬけと」、一番正攻法かつ一番「音楽的」と自分で信じるフォームを追い続けてきたわけですが、思えばそれは本当に無人の荒野を一人行く…といった感じでした。孤高と言うと格好良すぎる。絶望と紙一重の「孤立」ですね。
だから、無理解とか孤独には結構慣れているつもりです。ただ、誉められたりするのはなんとなく居心地が悪いですね。私はそもそも音楽的戦災孤児のような育ち方をしているので、音楽的両親に愛された記憶がない。ずーっと親に愛されないで育った人間が、もうヒゲも生えて白髪まじりになったころ「愛してますよ」なんて誰かに言われたって手遅れでしょ?
それに、「私の音楽」は「私」ではない。それは「あなたの言葉」が「あなた」ではないのと同じです。そりゃあ初演で拍手貰えれば、貰えないのよりは嬉しいですけど、それだけです。「醒めていますね」と言われればそうなのかも知れませんが、それもまた歪んだ育ち方のせいかも知れません。
まあ、個人的には、ある瞬間私の音楽を聴いて、心震えてくれて(あるいは不覚にも涙してくれて)、最後に「ああ、面白かった」とつぶやいてくれれば、それがベストでしょうか。そうでなかった場合はすべて「失敗」であり、「残念でした」としか言いようがありません。
*
そんなわけですので、これからも交響曲を書き続けるのかどうかという点については、よく分からない、というのが正直なところです。なんだか5つも書いてきた割には交響曲というものをちっとも信じていないな、と自分でも今ちょっと呆れているところですし。
それに、曲の数だけ喜びはありますが、同じ数だけ失望もありますからね。だから「なんでこんなものを書くのだろう?」という問いには、いまだ答えが出ません。
そう、「シンフォマニア」は「ニンフォマニア(色情狂)」と同じで、職業ではありません。たぶんビョーキなのです。
*
◆迦楼羅〜西村朗管弦楽作品集(カメラータ・トウキョウ)
ところで、こんなCDが最近出ましたので、お時間がありましたら聴いてみてください。いずれも日本の作曲家によるオーケストラ作品ですが、さて、「わが国が生んだ素晴らしき音楽的成果!」と賛辞を連ねましょうか、それとも「同病相哀れむ」と逃げましょうか。なにはともあれ日本という国の文化土壌にまっすぐ向かい合いながら、それでも西洋伝来のオーケストラに固執する不思議なご同輩たちの夢の軌跡が忍ばれます。
…などと書いてきたところで、そろそろ枚数も付きました。では、お風邪とテロにはお気を付けて、ご自愛ください。来年も、世界があることを祈りつつ。お元気で。
二○○一年晩秋 吉松 隆