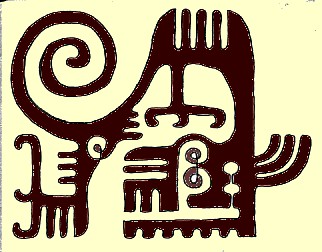 復刻!世紀末CDノート(1994年版)
復刻!世紀末CDノート(1994年版)
★これは音楽現代誌に1994年1月より連載された「世紀末CDノート」のオリジナル復刻版です。
1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999
第1回:作曲家は殺してから聴くか、生かしたまま聴くか?
第2回:死んだ作曲家に口なし、生きている作曲家に金なし
第3回:死せる魂は深き淵より永遠の安息へ
第4回:犬も歩けばオリジナル版に当たる
第5回:嬉し恥ずかしシンフォニック・ロックの世界
第6回:今は昔、懐かしのクラシックとジャズの融合
第7回:京都〜東京「バビ・ヤール」紀行
第8回:奥の細道ひとり旅〜天と地と新日本紀行
第9回:猛暑の夏、鍾乳洞を抜けたらそこはカンテレ
第10回:我田引水!CD「風色ベクトル」録音顛末記
第11回:緊急特報、20世紀にロマン派を見た!
第12回:古きをたずねれば新しきを知るかも知れない
第1回:作曲家は殺してから聴くか、生かしたまま聴くか?
さて、いよいよ二十世紀も残り少なくなり、景気も冷え込み、音楽が心に染みいる季節になってきた。いや、なんともわくわくする寒さである。
なにしろ脳天気な熱さに浮かれる音楽では、体は動くが頭は動かない。冷たく寒々した透明な空からこそ、宇宙に連なる音楽が聴こえる。つまり、音楽は音楽として生まれるのではなく、音楽になるのだ。だから、たかが音楽されど音楽。とは言え、青年老いやすく音楽聴きがたし。そこで、おせん泣かすな耳肥やせ。
というわけで、世紀末を生きる青少年たちのための必携アイテムである〈銀色円盤=CD〉を紹介することになった。なんとも明確な論旨である。
しかし、まあ、どうせまともなCD紹介じゃないんでしょうけどね、としっかり期待されている(?)ようなので、早速の第1回目は拙作が収録されているCDの制作裏話でお茶を濁してしまおう。昨年(1993年)発売された須川展也「ノスタルジア」(東芝EMI)、中川昌巳「クロス・ウィンド〜デジタルバード」(ビクター)、「現代日本の音楽/京都をテーマにした作品集第4集」(デンオン)、「白い風景」(アトリエ・ダンシュ)の4枚である。
*
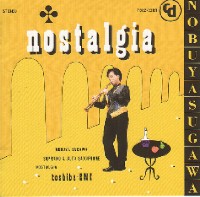 まず須川展也「ノスタルジア」。若手ながら日本を代表するサキソフォンの名手である須川氏とは、前作のアルバム「ファジイバード」(アポロン)に続く2枚目の仕事で、この原稿が活字になるころには次作のサキソフォン協奏曲とやらのデッサンが終わっていなければならないのだが(うーん。こんな原稿書いてる場合じゃないぞ)、これは酒乱のプロデューサーにのせられて新曲を書くハメになってしまった不思議なCD。
まず須川展也「ノスタルジア」。若手ながら日本を代表するサキソフォンの名手である須川氏とは、前作のアルバム「ファジイバード」(アポロン)に続く2枚目の仕事で、この原稿が活字になるころには次作のサキソフォン協奏曲とやらのデッサンが終わっていなければならないのだが(うーん。こんな原稿書いてる場合じゃないぞ)、これは酒乱のプロデューサーにのせられて新曲を書くハメになってしまった不思議なCD。
なにしろ、別の大仕事で毎日楽譜書きに追いまくられていて夜もオチオチ寝られない状況になっているところに、「そろそろメ切ですが、書けましたか?」という電話。うわわわわ!とばかりパニックになって仕上げた作が、この中に収録されている「夢色モビール」という曲なのである。ちなみに、同時収録されているのはドビュッシーやサティを始めとする近代キレイ派音楽の編曲もので、もう一曲収録されている拙作「プレイアデス舞曲集より」は、ピアノ曲をファゴットと弦楽四重奏版にアレンジした旧作。こっちがあるので、すっかり済んだものとばっかり思い込んでいたわけだ。
しかし、自慢ではないが今回の新曲、その割にはきわめて穏やかできれいぶった響きを持っている。これだから作曲家は信用ならない。きれいな音楽を心きれいな人が心穏やかな時に書くと思ったら大間違いなのだ。
そこで一句。
作曲は、心ならずも詐欺に似る。
*
続く中川昌巳「クロス・ウィンド〜デジタルバード」は、フルートとピアノのために書いた拙作「デジタルバード組曲」の通算して4枚目の録音(ちなみにコジマ録音の野口龍(LP)盤、カメラータの甲斐道雄盤、外盤のC.Thorspecken盤がある)。録音の話は聞いていたらしいのだが、すっかり失念していて、これも突然「来週録音しますが、よろしく」と連絡があって、「き、聞いてないよ!」と思わず叫んでしまった不思議なCD。
ジャズ・シーンと現代音楽シーンを飛翔する名フルーティスト中川氏らしく、今回は「クロス・ウィンド」という共通タイトルで、ジャズをクラシック風の木管五重奏で演奏した「イン・ア・センチメンタル・ムード」と、クラシック曲だがジャズ風でオシャレなボリングの組曲を中心に据えた「デジタルバード」との同時発売という企画。
中川氏には何回も私の曲を演奏していただいているので、慢性健忘症の作曲家はほとんど死んだふりをして、録音にも立ち会わずおまかせでやってもらった。中川昌三の名でジャズ・フルーティストとして大活躍しているだけあって、リズム感や疾走感は文句なしだし、ピアノの野平一郎氏も作曲家とピアニストをこなす名手で言う事なし。もはや完全に作曲家の手を遠く離れてしまったなあ、と孫を見る年老いた父親のような感慨に浸った一枚である。ああ渋いお茶がおいしい。
*
続いて京都市交響楽団による「京都をテーマにした作品集第4集」。ここに収録されている拙作は、日本初のファゴット協奏曲にトライした作品(珍品?)だが、これもなぜか通算2枚目の録音(カメラータの円光寺雅彦指揮、仙台フィル盤がある。独奏者は共に馬込勇氏)である。
この曲は、毎年年末の第九の演奏会の際にドサクサに紛れて現代作家の新曲を聞かせてしまおうという京都市の謀略(?)による委嘱シリーズの第16作。5年たって5曲たまったところでCD(昔はLP)にするというシリーズの第4集だが、これもいきなり「来月京都で録音します。作曲家をお呼びする予算はありませんが、よろしく」という連絡で始まった不思議なCD(こればっかりだな)。
小泉和裕指揮の京都市交響楽団により4日で現代曲5曲をリハーサルと同時に録音してしまうという強行軍だったが、5人の作曲家(一柳慧氏、北爪道夫氏ら)はアタフタと京都に集い、私も、ちょうど桜が満開の季節だったので、花見がてら出かけた。ただ、花見シーズン真盛りの日曜日の京都とあって、ホテルはどこも満員。知り合いの家(ちなみに新婚さん)に転がり込み、あげくの果てに録音の後で八坂神社にて夜桜見物としゃれ込み、馬込さんと新婚夫妻と日本画の先生とで祇園の料亭(!)で食事。目一杯の大赤字である。ガッデム!
*
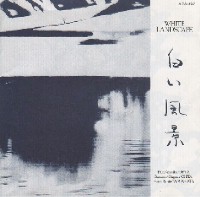 最後の「白い風景」は、新潟県六日町にあるトミオカ・ホワイト美術館というところで録音された不思議なCD。これも、突然「録音しちゃいましたあ」と極寒の新潟から連絡があったような気がする。呼ばれたのかも知れないが、寒そうだったので行かなかった。出不精作曲家ここにきわまれりである。
最後の「白い風景」は、新潟県六日町にあるトミオカ・ホワイト美術館というところで録音された不思議なCD。これも、突然「録音しちゃいましたあ」と極寒の新潟から連絡があったような気がする。呼ばれたのかも知れないが、寒そうだったので行かなかった。出不精作曲家ここにきわまれりである。
この美術館には富岡惣一郎氏という雪景色を追及されている日本画家の作品が常時展示してあり、トミオカ・ホワイトというのは、彼が雪を描くために独自に開発した白い絵の具。このCDに収録された「3つの白い風景」という曲は、フルートの太田嘉子さんとファゴットの太田茂さん夫妻が企画しているその美術館でのコンサートのために作曲したもの。フルートとハープとファゴットによる雪を主題にした(これも、きれいぶった)3曲からなる作品である。
「六日町の美術館で初演する、雪をテーマにした曲を書いてください」と頼まれた時はピンと来なかったが、「八海山っていう酒で有名な山の麓にあるんですが」と言われた途端、「おお!八海山!」と思わず銘酒につられて引き受けてしまった。「あなたの芸術意識や創作意欲は酒でつられるわけね」と皮肉を言われつつの作曲。録音は厳冬1月の雪に埋もれた美術館。おかげでこのCDからは、しんしんと降り積もる雪の静寂が聞こえる(ような気がしないでもない)。
第2回:死んだ作曲家に口なし、生きている作曲家に金なし
作曲家としては、新しい作品を書いている途中というのは概ねわくわくしているものだが、このまま未完で止まってしまったらどうなるのだろう?という奇妙な感慨がよぎる事もないではない。
私も今現在、この春初演予定のサキソフォン協奏曲を抱えているものの、ある事情でスケッチ稿の段階で筆が止まっているので、そんな不安とお友達だ。一応ピアノ・スコアらしき段階には至っているから、寸法はほぼ決定しているのだが、肝心なところには「この辺適当にグリグリと盛り上がる」とか「アドリブっぽくコテコテと色々あって次へ」などとしか書いてないので、これは第三者が見ても何がなにやら分からないに違いない。
そこで、というわけでもないが、新作を作曲途中で亡くなってしまった先輩たちの例が気になりだした。
*
◆モーツァルト「レクイエム」(モーンダー版)ホグウッド盤:ポリドール
モーツァルト先生の場合は、ご存じのように頼まれものの「レクイエム」を書いている途中で亡くなっている。仕上げないと作曲料をもらえないという事情からコンスタンツェ未亡人は、弟子のアイブラーとたまたま死の直前に見舞いに来た作曲家ジュスマイヤーにスケッチを託して補筆完成を依頼。ジュスマイヤーの方がこれを仕上げている。
そこで現在に至るまでジュスマイヤーが補筆して完成させた版が演奏されているが、全曲の名曲ぶりはともかく、補筆部分の評判はあんまりよろしくない。真性モーツァルト作は冒頭の「入祭唱」と「キリエ」だけで、「サンクトゥス」と「ベネディクトゥス」は完全にジュスマイヤー作だからだ。
そこで、最近ホグウッドが取り上げたモーンダー版のように、ジュスマイヤーの手による部分をバッサリ切り捨て、新たな編作を施して純正モーツァルトに迫る試みも出てきたりする。しかし、モーツァルト自身のスケッチはジュスマイヤーが補作完成した際に破棄してしまったらしく、彼に託した部分は残っていないとか。うーん、胸が痛む。
*
◆マーラー交響曲第十番(D・クック復元版)インバル盤:デンオン
マーラー先生の場合も、亡くなってみたら10番目の交響曲のスケッチが出てきた。第1楽章のアダージョのフル・スコアと、第3楽章プルガトリオおよび第5楽章フィナーレのショート・スコア(五線譜4段に書かれたデッサン稿)である。
早速、作曲家クシェネックらの補筆によって冒頭のアダージョ楽章が初演され、アルマ未亡人はシェーンベルクやショスタコーヴィチに全曲の補作完成を依頼しているのだが、その困難さに誰も快諾せず、長いこと遺稿は埋もれたままだった。
しかし、1960年のマーラー生誕百年祭にイギリスBBC放送がこの未完の交響曲の復元を企画し、音楽学者デリック・クックが指揮者やマーラー学者との共同作業で「マーラーの未完の草稿を試しに音にするための補筆版」を完成させた。これがD・クック版である。
この復元版、最初はいくらかキワモノ的な扱いだったが、近年ラトル盤、シャイー盤などの秀演に恵まれ、最新のインバル盤ではマーラー交響曲全集に組み込まれての登場。現在ではすっかり市民権を得てしまった感がある。
*
◆ブルックナー交響曲第9番(終楽章付き)アイヒホルン盤:カメラータ・トウキョウ
もうひとりの巨大交響曲作家ブルックナー先生も、最後の交響曲第9番を未完のまま亡くなっている。一応の完成を見ていた前半の三楽章はレーヴェの補筆により初演を果たしたが、独り身のブルックナー先生には遺稿を整理する未亡人はおらず、フィナーレの草稿は散逸し、長いこと存在しないものとして扱われてきた。なんだか身につまされる話である。
未完で終わった場合はフィナーレの代わりに「テ・デウム」を演奏して欲しいというのがブルックナー先生の遺志とされてきたが、終楽章は壮大な純器楽フィナーレとしての構想がかなり固まっていて、フィナーレ前半部分の完全スコア、後半部分のスケッチ、および「フィナーレの終結部にはアレルヤを力強く持ってくる」という言葉などが素材として残されている。
かくして音楽学者や作曲家、指揮者らの共同作業により補筆完成版の作成が試みられ、作曲者の死後ほぼ百年を経て復元フィナーレ付きの第9番がその全貌を現わした。サマーレ、フィリップス、マッツーカらによる復元版を演奏した最新のアイヒホルン盤では、30分に及ぶ巨大なフィナーレを持つ全4楽章一時間半の堂々たる交響曲がその偉容を見せ、ブルックナー・ファン垂涎の名盤となっている。
*
◆ベルク歌劇「ルル」(3幕版全曲)テイト盤:東芝EMI
現代音楽の祖ベルク先生も未完のオペラ「ルル」を残して亡くなっている。生前完成させたのは第2幕までと、第3幕最後の幕切れ部分。これも初演が決まっていたのでヘレーネ未亡人が慌ててシェーンベルクに補作完成を依頼したが出来ず、2幕までの未完成版で初演。しかし、それはそれでまとまっていたので初演は大成功。以来この未完成版で上演が続けられ、未亡人も補作完成するに及ばずと遺言までしてしまった。
しかし、ピアノ・スコアまで存在するこの第3幕、聴いてみたくなるのは人の情。そこで作曲家ツェルハに補筆が依頼され、オーケストレイションを施された第3幕を加えての全3幕版が、作曲者の死後実に半世紀を経てブーレーズ指揮パリ・オペラ座で初演された。
このオペラ、転落し娼婦にまで落ちぶれた主人公ルルが切り裂きジャックに殺される第3幕なくしては全貌が見えないし、この完成版は期待に見事に答えた出来。最近では、お昼の連続ドラマ風に展開するテイト盤も登場してすっかり定着した。
*
とは言え、自作が未完で後世に残って他人にいじくられるくらいなら燃してしまいたいと思う作曲家もいるようで、シベリウス先生などは未完の交響曲第8番をしっかり自宅の庭で焼いてしまっている。
その一方で、後世では紙クズにしかならないような作品を大量に残される作家先生も多々いるわけで(あ、私もか....)、まあ、なんというか、死人に口なしというか、ラーメンにシナチクというか、浮世のことは夢の夢である。
第3回:死せる魂は深き淵より永遠の安息へ
正月早々の1月6日に妹をガンで亡くした。昨年秋から三ケ月ほどの入院闘病生活に付き合ったので、年末年始は病院通いで潰れ、最後の一ケ月は徹夜の看病になった。
クリスマスから大晦日そして正月と真白な時が空しく流れ、人工呼吸器を付けられたまま臨終の床に眠る妹のベッドの横のテレビが希薄でにぎやかな音楽を吐き出し続けるのを、ただ呆然と見ていた。
それは不思議な体験だった。人間たちは浮かれ、神は沈黙し、ただ時だけが無表情に流れていた。あらがうことの出来ない巨大な流れの前で、音楽は本当に無力なのだと今更ながらつくづく思い知った。
そして、すべてが終わり、幾つかの「レクイエム」を聴くことになった。
*
なぜか人は死者に花を手向ける。人類の黎明期の原人の住んだ洞窟にも、死んだ子供に花を手向けて埋葬した跡があるそうだから、これはかなり原初的で本能的な何かに根ざす行為らしい。
そして、なぜか作曲家は「レクイエム」を書く。これも、死者によせる花束のようなものかも知れない。悲しみを包み込むように歌が歌われ、墓に花を手向けるように音楽が紡がれる。
思い付く名作としてはモーツァルト、ヴェルディ、フォーレ、ケルビーニ、ベルリオーズ、ブラームス、ドヴォルザーク。意外なところではシューマン、リスト、ブルックナー。あるいはグノーにサン・サーンス。
送り主の名前を大書した花輪のような作品もあれば、ひそやかに一輪おかれた手向け花のような清楚な作品もあり、重厚な儀式向けに並べられた花束のような作品もあり、と多彩な献花が並ぶ。
中でもモーツァルトとヴェルディそしてフォーレが逸品だが、前二者は、ちょっと油断すると盛り上がってしまうので、落ち込んでいる耳には結構疲れる。どれか一曲だけ、と言われたら私は文句なくフォーレだ。
◆フォーレ「レクイエム」。コルボ盤:エラート
近代フランス音楽の父ガブリエル・フォーレ(1845-1924)によるこの作品は、優しい極みのような独特のハーモニーが、きわめて抑制されたオーケストレイションによって紡がれて行く奇跡のような作品だ。ヴァイオリン群が上空を浮遊する薄雲のようなオブリガートに徹し、壮麗さを排したオルガンが天国の夢のように優しくすべてを抱擁する。
この名作の演奏で気に入っているのは、少年合唱を使ったコルボ盤。これはもう天国の花園を漂っているかのように美しい。絶品なのははなんといってもオルガンの高音で繰り返されるオブリガートが印象的な最後の「イン・パラディスム(天国にて)」。いつ聴いても涙が止まらない。どうしてこんなに美しい音楽が書けるのだろう?
このフォーレ以降の近代・現代では、ポスト・フォーレとでもいうべきスタイルのモーリス・デュリュフレ(1902-1986)のものが美しい。一九四七年の作というから時代からすれば現代音楽に属するのだが、フォーレを踏襲した優しいハーモニー感覚にいくらかのルネッサンス音楽臭も漂わせているなかなか清楚な作品である。
*
....と、ここで、ペダンチックな間奏曲「蘊蓄(うんちく)」を少々。
現存する最古のポリフォニー・レクイエムは、1482年頃に書かれたヨハンネス・オケゲム(1425頃-1497)の「レクイエム」なのだそうだ。さらに数十年遡ってギヨーム・デュファイ(1400頃-1474)も書いたとされているが、楽譜は現存していないらしい。また、レクイエムではないがジョスカン・デ・プレ
(1440頃-1521)も「オケゲムの死を悼む挽歌」という作品を書いている。この時期では、スペイン宗教楽派の巨匠トマス・ルイス・ヴィクトリア(1548-1611)のレクイエムが美しい清冽な叙情性をたたえた傑作。
バロック期のレクイエムでは、フランスのジャン・ジル(1668-1705)とアンドレ・カンプラ(1660-1744)の両作品が当時の人気曲だったらしく、特にジルのレクイエムはこれが演奏されない葬式は稀、と言われるほどの人気だったらしい。しかし現在では共にCDを捜すのに苦労する。
次いで古典期になると、モーツァルトのレクイエムに影響を与えたとされるミヒャエル・ハイドン(1737-1806)の「死者のためのミサ曲」ハ短調、ドメニコ・チマローザ(1749
- 1801)の「レクイエム」ト短調、ルイジ・ケルビーニ(1760-1842)のハ短調とニ短調の二つのレクイエムなどが登場する。
しかし、「レクイエム」が作曲家一世一代の神聖な作品になったのは、もちろん白鳥の歌としてレクイムを書いたモーツァルトのせい。おかげでレクイエム史は「モーツァルト以前」と「モーツァルト以後」に区分けされるのだが、聴き手として「モーツァルト以前」のレクイエムの名盤を一枚と言ったら、これ。
◆ピエール・ド・ラリュー「レクイエム」。ラヴィエ盤:フィリップス
ピエール・ド・ラリュー(1460頃-1518)はジョスカン・デ・プレやオケゲムと同時代の作曲家。その作品を現代に再現したこのCDは、近代フランス風の柔らかい響きを付加され独特の美しさを放っている。特に合唱をフルートやハープで縁取りした絶妙の音感覚が素晴らしく、古さと新しさを優しく包み込んだ不思議な空間を産み出している。
*
第二次世界大戦後の現代ではレクイエムという発想自体に、死という不条理に対する抗議の意味合いが込められてきているようだ。ブリテンの名作「戦争レクイエム」を始めとして、クルト・ワイルの「ベルリン・レクイエム」やペンデレツキの「ポーランド・レクイエム」、あるいは武満徹の「弦楽レクイエム」に三善晃の「レクイエム」から細川俊夫の「ヒロシマ・レクイエム」まで、死者の安息というよりは死をもたらす歴史的・社会的不条理を音に託している感がある。
◆A・ロイド・ウェッバー「レクイエム」マゼール盤:東芝EMI
ミュージカル作曲家アンドリュー・ロイド・ウェッバー(1948-)による現代のレクイエムも、そんな作品のひとつ。当初は「北アイルランド・レクイエム」とでも言うべき政治的内容を持って構想されたらしいが、さらにカンボジア内戦のエピソードも交え、現代の不条理に対するレクイエムに昇華させた。
この作品の聴きどころはボーイ・ソプラノとソプラノによって歌われる「ピエ・イエズス」。この気絶しそうに美しい四分間のメロディを聴いていると、涙も痛みも透明になって本当に天国いる気分になる。
第4回:犬も歩けばオリジナル版に当たる
作曲家の中には、いつまでもジタバタと自作に手を加える「あきらめの悪いタイプ」と、一度書いてしまったら二度と旧作を振り返らない「割り切りのいいタイプ」とがいる。
前者の横綱は何と言ってもベートーヴェン先生で、悩んで悩んで作品を創るその姿勢は、なんだか息苦しくなるほど。ブルックナー先生もこのタイプの張り出し大関。あれだけ巨大な交響曲を9つも書いた人の割には、まるで自作の出来や自分の才能に対する自信がなく、人に批判されるとすぐ書き直してしまう。
一方の後者の横綱はモーツァルト先生。こちらはもうヒョイヒョイと軽やかに音符を書き飛ばし、後を振り向いたりなどしない。多作系の作家は概ねこのタイプ。前者のジタバタ・タイプは悩むのに時間がかかるので当然ながら一作品あたりの作曲時間は膨大になり、寡作になってしまうのである。
このタイプの差は、才能の差というより性格の差らしく、ショスタコーヴィチのように「旧作をいじくってる暇があったら新しい作品を書いた方がいい」と断言する人もいれば、旧作の改訂補筆に死ぬまでかかりきりだったブルックナーのような人もいるし、ストラヴィンスキーのように経済的な理由から再演や新しい出版の機会を増やすためにせっせと異稿を書き残す人もいれば、ムソルグスキーのように書いたまま整理も改訂もせずにうっちゃっておく人もいる。色々なのである。
私も、どちらかと言うと悩むタイプ(おまえのは才能がなくて悩むタイプだろうって?ほっといて下さい!)なので、決定稿以前の未熟な初稿を見られるのは恥ずかしい。だから、オリジナル版など聴かれたくないという作家の気持ちはよーく分かるつもりである。
よーく分かるつもりなのだが、やはり他人の未熟な初稿は見てみたい。のぞき見趣味というわけでも、うわ、こりゃあ確かに恥ずかしい!などと言って人の若書きを聴いてみたいわけでもない。あくまでも、そう、あくまでも純粋な研究心からである。(本当ですってば!)。そこで一句。
自分の不幸は嫌だけど、
他人の不幸は蜜の味。
(こらこら!)
*
◆シベリウス「ヴァイオリン協奏曲ニ短調(オリジナル版)」(ヴァンスカ/カヴァコス盤:BIS)
シベリウスは、敬愛する作家にベートーヴェンを挙げているように悩んで悩んで改訂するタイプ。37歳の頃に書かれ、当時の盟友R・シュトラウスの指揮によってベルリンで初演されたこのヴァイオリン協奏曲も、2年後に大幅改訂している。
この時の改訂がどの程度のものだったのか最近まで分からなかったのだが、このヴァンスカ盤の登場で、その全貌が明らかになった。これはもう新しい未聴の作品を聴くような新鮮さがあり、価値の点でも質の上でもファン待望マニア垂涎の名盤である。
しかもこのオリジナル版、埋めてしまうにはもったいない瞬間が幾つもある。特にバッハのシャコンヌを思わせる第一楽章の美しいカデンツァは白眉。どうしてこんな素晴らしい部分まで削ってしまったんだア!と思わず作者に抗議したくなるほどの美しさである。
このシベリウス先生にはもうひとつ交響曲第5番という、作者自身が「全く違う作品になってしまった」と言うほどの大幅改訂が施されている作品があるのだが、こちらはまだ遺族のOKが出ず、当分聴くことが出来ないとか。うーん、聴いてみたい!
◆グリーク「ピアノ協奏曲イ短調(オリジナル版)」(デルヴィンエル/広上淳一盤:BIS)
続いて、北欧のもう一人の雄グリーク先生の最も有名な作品であるイ短調のピアノ協奏曲。これも現在聴かれるのは後の改訂稿であって、作曲時のオリジナル稿とは違うのだそうだ。
作曲は24歳の時(1868年)。グリークはその二年後にリストに会った時この曲のスコアを見せているのだが、その時リストが初見で全曲を弾いてしまったのは有名な話。この時のリストのアドヴァイスに発奮してグリークは改訂版を作成し、晩年に至るまで何回かの改訂を試みている。おかげで全部で7つほどの異稿があるという。
この曲も、オリジナル版が最近CDで登場して聴けるようになった。とは言っても、改訂の大部分はピアノの技巧性を効果的にするための補筆と、オーケストレイションのヤボったさの修正がほとんどで、聴けて得した!というほどの耳新しい異稿ではない。
*
◆ムソルグスキー歌劇「ボリス・ゴドノフ(原典版)」(フェドセーエフ盤:フィリップス)
ブルックナーと並ぶ優柔不断の天才モデスト・ムソルグスキー先生の場合は、当人が改訂を諦めてしまっている点でちょっと異例。
先駆性のある天才的な音楽を書きながら、売り込み下手で不遇の道を歩む彼の作品は、他の作曲家によって補筆改訂され生命を得たものが多い。ラヴェル編曲の「展覧会の絵」はその筆頭だし、R・コルサコフ編曲の「禿山の一夜」に同改訂の歌劇「ボリス・ゴドノフ」...と、考えてみるとムソルグスキーの書いたそのままで流布している作品はないに等しい。
最近いずれもオリジナル版が聴けるようにはなってきたが、作曲者自身がオーケストレイションした原典版の「禿山の一夜」やこの「ボリス・ゴドノフ」を聴くと、いかにモデスト先生ファンの私でも、原典の方がいいとは言い張れない。モーくん、ごめん!
◆ショスタコーヴィチ歌劇「ムツェンスクのマクベス夫人」(ミュンフン盤:グラモフォン)
ムソルグスキー・ファンにして前述のように旧作は書き直さない主義のショスタコーヴィチだが、二十代に書いて政府ににらまれた(いわくつきの)歌劇「ムツェンスクのマクベス夫人」だけは書き直している。改題したうえに作品番号も付け直して30年後に再発表した「カテリーナ・イズマイロワ」がそれである。
前作の歌劇「鼻」ではアクビからヒゲ剃りまで音楽化したショスタコ先生、次作のこの「マクベス夫人」ではベッド・シーンを克明に音楽化していて、これがもうXXXがXXXでXXX(検閲済)。これを当時の婚約者に献呈したというのだから凄い。ところが後年の「カテリーナ」ではこのポルノフォニーとまで呼ばれた第1幕第3場のシーンは自主規制してしまっている。別に改訂はここだけではないが、文句なしに改訂前の方が面白い。必聴。ただし、変な期待はしないこと。(へ、変な期待って、な、何だろ?)
第5回:嬉し恥ずかしシンフォニック・ロックの世界
むかし、私がロッカーだったころ(駅のロッカーではない。念のため)、友人はジャンキーだった。今はその息子がハッカーで(くどいようだが、なめるハッカではない)、娘がヤンキーなのだが、わかるかな?わかんないだろうなあ。(そもそも古すぎるギャクで、わかんないか....)。
などと言い出したのは、最近「シンフォニック・イエス」に「シンフォニック・ピンクフロイド」などというアルバムが出てしまったからで、「ロックとクラシック・オーケストラの融合!」などと言われると、うさんくさいと分かっていても身体の中のシンフォニック・ロッカーの血(なんじゃ、それは?)が騒いでしまうのである。
*
今を去ること四半世紀前、1970年代にロックはクラシックへの接近と融合をを試み、全人類的な統合へと向かった。解散したビートルズの後を受けて、その種の試みへ疾走を始めた「プログレッシヴ・ロック」と呼ばれるこの種の音楽は、頭カラッポのハード・ロックやヘビー・メタルとは一線を画した知的音楽を試行していたのである。
このプログレ(プロの愚連隊ではない。念のため)の代表的バンドが、変拍子を多用した精密なアンサンブルが絶妙の「イエス」と、スロウ・テンポでカリスマ的陶酔を音楽で産み出す「ピンク・フロイド」なのである。
他にも、キイボートとベースとドラムスというたった3人のユニットで超絶的な力技の音楽を聴かせたエマーソン・レイク・アンド・パーマー(略してELPと言います)。プログレ・ロックの名を高らしめた前衛集団キング・クリムゾン、叙情的で幻想的なムーディ・ブルース、ジャズ風先鋭のソフト・マシーン、キャラヴァン、キャメル、ルネッサンスと百花繚乱、そうそうフォーカスなんてのもいたし、PFM、サード・イヤー・バンド、カーヴド・エア、ヴァンダー・グラーフ・ジェネレーター、....うーん。と、止まらない!
*
オーケストラをロックに導入した試みは、もちろんビートルズを抜きには語れない。弦楽四重奏をバックにした「エリノア・リグビー」や「イエスタデイ」もエポック・メイキングだったが、なんといっても名作「サージェント・ペパーズ」(1968)の最後の曲「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」でオーケストラのクラスターを使った斬新さはショックだった。
同じころにムーディー・ブルースが試みた「デイズ・オブ・フューチャー・パスト」(1967)でのオーケストラは、対照的にソフトで印象派風の上品な響きで、いい雰囲気。これは名作だった。続いてディープ・パープルが試みた「ロック・バンドとオーケストラのためのコンチェルト」(1969)も悪くなかったが、ブルースっぽいロックと近現代風な響きのオーケストラとを折衷的に組み合わせていて、今聴くと少々恥ずかしい。
この種の試みでビートルズ以降最大のショックは、プログレッシヴ・ロックの誕生を決定付けたピンク・フロイドの名作「原子心母」(1970)。これは不協和音炸裂のブラス群と不思議な唱法のコーラスまでを混入させた傑作で、70年代の現代音楽というなら、ドイツやフランスに巣食う頭デッカチ作曲家たちの雑音の寄せ集めではなく、こういう音楽のことを言うべきだろう。必聴。
少し遅れて、キャラヴァンがオーケストラとコーラス付きのライヴ・コンサートを収めた「キャラヴァン・アンド・ニュー・シンフォニア」(1973)というアルバムを発表。きれいなストリングスが付いた佳曲もあるが、音楽性の高さという点で今いち。続いてキャメルが、ポール・ギャリコの小説を音楽化した「スノー・グース」(1975)を発表。オーケストラというより室内楽的なアンサンブルによる叙情的な音楽を作り上げた。これは美しくも切ないメロディが全編にあふれていて、お薦め。
このころの作品で個人的に好きなのは「原子心母」でエンジニア助手を勤めたアラン・パーソンズによる「エドガー・アラン・ポーの世界」(1976)という逸品。基本的にはロック・ユニットのアルバムであってシンフォニックが売り物ではないが、これにかぶさる現代的なオーケストラのサウンド(現代作曲家でもあるアンドリュー・パウエルが担当)が見事。これもお薦め。
*
◆シンフォニック・イエス(BMGビクター)
で、シンフォニック・ロックものの新譜なのだが、このアルバム、当のイエスのヴォーカルであるジョン・アンダーソンから、ギターのスティーヴ・ハウ、ドラムスのビル・ブラッフォードまで参加しているので、純正の「オーケストラ化されたロック」ではない。
プロデュースとアレンジはジェスロ・タルのキーボード・プレイヤーだったデヴィッド・パーマーが担当しているが、ハッキリ言ってオーケストラの処理は「エグい!」。例えば、ほぼ単音で歌われるヴォーカルのメロディ・ラインをオーケストラがいかにも「楽譜に書いてありますので」とばかりにトレースして演奏するあたりは、キャー!と叫びたくなるほど恥ずかしい。(キャー!)。
....とは言いながら、イエスのメンバーが三人も参加しているので、イエス・ファンとしては実は隠れてウフフと愛聴していたりする。(ウフフ)
◆シンフォニック・ピンク・フロイド(BMGビクター)
もう一枚は同じシリーズとして最近再発売されたもので、プロデュースもアレンジも同じ。ただし、こちらはピンク・フロイドのメンバーは不参加。マニアとしては嬉しい音の仕掛けは色々あるものの、オーケストラのアレンジは二流ナイト・クラブ並み。恥ずかしいけど嬉しい。けど、恥ずかしい。
まあ、要するに、イエスならマーラー先生、フロイドならブルックナー先生クラスの、ロックの強靭なサウンドに拮抗できるだけの力量と才能をもったアレンジャーが担当しなければダメということなのですよね。しかし、そんな才能があるアレンジャーが、こんな企画に乗るとは思えないしなあ....。
ちなみにこのシリーズ、他にも「シンフォニック・ジェネシス」、「シンフォニック・ジェスロ・タル」、「シンフォニック・ローリング・ストーンズ」というアルバムが並ぶそうだが、私は「シンフォニック・ELP」で「恐怖の頭脳改革」全曲を聞いてみたい。(うーん。今回はどうもマニアックな話になってしまった。これ、クラシック音楽誌でしたっけね)
第6回:今は昔、懐かしのクラシックとジャズの融合
最近、サクソフォン協奏曲を書いた。
なにしろジャズからフランス近代まで何でもありのサクソフォンが素材で、ソリストはクラシックから現代まで何でもありのテクニックを誇る超名手の須川展也氏。こうなると、クラシック・現代音楽・ロック・民族音楽そしてジャズなどなどが頭の中でオモチャ箱を作っている私としては、どうしてもそのすべてに巻き込まれてしまう。
そこで、クラシック・オーケストラの前にサクソフォンとピアノとパーカッションの三人がジャズのトリオのように並び、ロックのビートを叩き出しながら民族音楽風のパッセージも吹き、同時にフリー・ジャズ風の即興演奏も混じえるという世にも奇妙な協奏曲が出来上がった。
言ってみれば異種音楽の融合だが、改めてクラシックとジャズを融合しようとか、ロックの影響をとどめようとか、民族音楽の要素を組み込もうとか、あえてそんなことを考えるまでもなく、「現代人」として音楽を書くとそれら全部が混じってしまって、分離できないような気がする。
しかし、むかしは色々苦労してクラシックを、ジャズを、ロックを一歩一歩融合していったのだ。そう思うと、脳天気に全部を融合して喜んでいるのは申し訳ない、というような敬虔な気持ちにかられる(などと殊勝なことも言ったりする)。
*
◆ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」(プレヴィン盤:フィリップス)
ところが、クラシックとジャズを融合する試みの最初の大成功作として燦然と輝くこの名作、なんと「ジャズとクラシックの融合を果たす実験的コンサート!」とブチ挙げた演奏会のわずか一ケ月ほど前に正式に発注された即席作品というから驚く。
最初は冗談と思っていたのに急に正式発注されたガーシュイン先生、本腰を入れて書き始めたものの七転八倒。独奏部分は自分が弾くからスケッチ程度だし、バンドの部分もそもそもオーケストレイションの勉強などしたことがないのでスケッチ以上にならない。業をにやした企画者であるポール・ホワイトマン氏はそのスケッチを彼からひったくり、その構成と仕上げとオーケストレイションをグローフェに依頼したのが一週間前(!)という。修羅場が目に見えるようだ。
初披露は1924年というから今からちょうど70年前。ただし、その時のピアノ(ガーシュイン本人)のバックはジャズ・バンドであるポール・ホワイトマン楽団。後にやはりグローフェが、さらに正規のオーケストラ用に編曲し直しているから、この曲における「クラシックとジャズの融合」は、ホワイトマンとガーシュインとグローフェの三重融合による相乗効果というべきだろう。
このいまさら改めて紹介するのも恥ずかしくなるようなド名曲、ここ数年でもラトルによるオリジナル版とか、ラベック姉妹による2台ピアノ版とか、ガーシュイン本人がロール・ピアノに残した演奏の復元盤とか、色々な話題盤が出ているが、ここでは自身もジャズとクラシックの両刀使いだったアンドレ・プレヴィンの定盤を挙げておこう。
*
◆ショスタコーヴィチ「ピアノ協奏曲第1番」(ヤブロンスキー/アシュケナージ指揮ロイヤル・フィル:ロンドン)
この時期、ヨーロッパのクラシックの作曲家がジャズに影響を受けて音楽を書くという「逆輸入」も多々見かけられるが、脳天気さで群を抜いているのが、ガーシュインに遅れることわずか10年後の1933年に書かれたソヴィエト製のこの曲。特に、無声映画で悪漢と探偵が凄まじい追いかけっこをしているような暴走し疾走するフィナーレが凄い。
このころのショスタコーヴィチは「ジャズ普及委員会」なるものに入っていて、ジャズ・バンドとも親交があり、しかもガーシュインのラプソディが26歳の作品で、ショスタコーヴィチのこの曲が27歳の時の作品。世が世なら、ショスタコーヴィチはロシアのガーシュインになっていた(?)のかも。
CDは、そのガーシュインのピアノ協奏曲でデビューした若きハンサム坊やペーテル・ヤブロンスキー盤を挙げよう。この人も、わずか6歳でまずジャズ・ドラマーとしてデビューしたという両刀使いの才人。若々しい駿馬のようなリズム感が素晴らしい。
*
一方、ジャズ・サイドからクラシックへの融合の試みは、1950年代のジャズ黄金期に多くの名盤を生んだ。有名なのは作曲家ガンサー・シュラーとモダン・ジャズ・カルテットのコンビによる「サード・ストリーム・ミュージック」(1960)あたりだが、そう言えばバーンスタインの「ウエストサイド物語」(1957)もこのころ。
◆ビル・エヴァンス・トリオ「ウィズ・シンフォニー・オーケストラ」(ポリドール)
しかし、この時期最高の名盤は誰がなんと言ってもこれ。オーケストラをバックにしたジャズのピアノ・トリオという編成で、基本的にはフォーレやバッハなどのクラシックの名曲をアレンジしたものだが、エヴァンスのピアノは全編を宝石のように静かにきらめく音楽に変質させ、その後ろに淡い絹のベールのようなオーケストラが絶妙な繊細さで揺らめく。究極の逸品。
*
そして、続く70年代最大の成果は、マンフレート・アイヒャーによってヨーロッパから発信された「現代の音楽としてのジャズ」と言うコンセプトに基づくECMレーベルの一群のアルバム。
特にクラシックとジャズとの融合を掲げたわけではないが、クラシックの繊細な美しささとジャズの自由さを融合させた音楽作りが見事で、現代音楽とジャズという二つの音楽の死骸を透過した天空に、孤峰のようにそそり立っていた。
70年代のいわゆる「現代音楽」は人間の音楽史にいらない。このレーベルの音楽だけあればいい。そう言いたくなるほど現代的でかつ美しいアルバムが並んでいる。
◆キース・ジャレット「ブルー・モーメント」(ECM)
その中でも、上品なクラシックの素養で一頭地を抜いていたのがピアノのキース・ジャレット。特にこのアルバムは、弦楽オーケストラをバックに北欧のサックスの名手ヤン・ガルバレクと、知る人ぞ知る名ベーシストのチャーリー・ヘイデンを配して、静かで透明で北の叙情そのもののような音楽を創りだしていて、それはもう実に美しい。
なぜかクラシックはジャズを導入すると下品で動的になり、ジャズはクラシックを導入すると上品で静的になるようだ。
第7回:京都〜東京「バビ・ヤール」紀行
5月20日。昼、井上道義さんから突然、「京都でバビ・ヤールをやるから聴きに来ない?」という電話。当方、超出不精で最近は死んだふり(死んだという噂さえある)までしている登校拒否作曲家だが、5月の京都にご招待と聞いてはたまらない。
しかし、聞けば演奏日はなんとわずか3日先。作曲のメ切2曲と原稿のメ切3つと本の出版とサクソフォン協奏曲の再演とギター曲集のCD録音とNHKの番組録画があるという、暇な作曲家には珍しい十年に一度のパニック週間の真只中。絶対行けるわけがない。
....はずだったのだが、「バビ・ヤールですヨ。京都ですヨ。天気いいですし、経費は出ますし、グリーンでどうぞ」という悪魔のささやきに誘われて、毒食わば皿までというか飛んで火にいる夏の虫というか無理矢理24時間こじ開けることにする。
5月21日。昼、NHKに電話。時間を少し動かしてもらって、収録が終わってから新幹線に飛び乗ればコンサートの時間に間に合うことになる。そのむね京都の井上さんに電話。折り返し「アイ・アム・ベリー・ハッピーよ」のFAX。
夜、春から月イチで出演しているそのNHK教育テレビの謎の番組を見る。これがまた、国立競技場の聖火台の下でハンス・ロットの交響曲のCDを紹介するという信じられない映像。何を考えているんだ?(こらこら、やっているのはアンタだろうが!)
5月22日。午後、朝日新聞日曜版に連載している原稿をFAXで出す。こちらも月イチ(第2日曜)の連載で、今回は難解なリズム論を分かりやすく噛み砕いて論じる....はずだったのだが、噛み砕きすぎてほとんど漫才になってしまった。(もっとも、毎回漫才じゃないか!という説もあるが)
5月23日。昼、渋谷のNHK放送センタ1110スタジオに行く。教育テレビの深夜バラエティ番組の中で、クラシックの新譜を紹介する2分ほどのコーナーの担当。....なのだが、早くも3ケ月めで番組打ち切りが決定。プロデューサー氏が頭を抱えている中、ホルストのパートソング集という輸入盤新譜を紹介し、収録後、NHKからもらったタクシー券を葵の紋章よろしくふりかざして放送センターの門前から東京駅へ。3時56分の「のぞみ」に飛び乗って京都へ行く。
6時12分京都駅着。そのまま京都会館に直行し、7時開演の京都市交響楽団定期演奏会にすべり込む。一曲目がヴォーン=ウィリアムスの「あげひばり」。ヴァイオリン独奏がきれいな作品だが、解説に「あげひばり、とは決してフライド・チキンのことではない」と解説してあって、のけ反る。
続いてショスタコーヴィチ先生の交響曲第13番「バビ・ヤール」。ユダヤ人、思想家、女性、詩人、科学者、と権力から弾圧された人々についてバス独唱と男性合唱と大オーケストラとで歌う怖い音楽。現代の日本で言えば、南京大虐殺、朝鮮人問題、アイヌ問題、部落問題などに関する詩を合唱付きで歌いあげるようなもので、これをあの時代のソヴィエトで演奏してしまったのだから怖すぎる。しかし、学生が中心らしい若々しい男性合唱も熱演し、コンサートは大成功。
終演後、楽屋へ。井上道義さんは祇園へ繰り出すと言う。こちらはホテルにチェック・インしてから、先斗町をしばし散策し、木屋町通りで飲む。
翌5月24日。朝、井上道義さんと朝食。「バビ・ヤール」の中の「恐怖」という楽章で、「妻と語ることの恐怖....」っていうのがあって、そこでバス独唱のセルゲイ・アレクサーシキンが妙なクスグリをかけるのがおかしくてネ、と昨夜の話。また、全曲で鐘が62回鳴ることについてしばし論争。ちなみに作曲年が1962年なのだ。
井上さんと別れてホテルをチェック・アウトした後、天気もいいので鈴虫寺へ行く。最近有名になった幸福祈願の寺なのだが、修学旅行生であふれ返っている。続いて酒の神様のいるという松尾大社へ。酒飲みのお札というのを見つける。それからブラブラと嵐山まで行くが、ここも渡月橋を中心に修学旅行生が五月の蝿のようにたかっている。
昼、京都に住んでいるギタリストの山下和仁くん宅へ。「忙しいはずじゃなかったんですか?」と呆れられる。午後、近くを散歩。本阿弥光悦ゆかりの静かな光悦寺と、天井に血の手形足形がある源光庵へ。夜、すぐ近くにあるのに行ったことはないという懐石料理の松山閣というところに山下夫妻と愛娘のKちゃん一歳とで出かけ、京都の奥山に夕陽が沈むのを見ながら夕食。9時すぎ最終の「のぞみ」で東京に戻る。
5月25日。午後、新日本フィル定期演奏会プログラムの曲目解説の原稿を書き上げてFAXする。バルトークの「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」とドヴォルザークの「交響曲第7番ニ短調」。
5月26日。昼、サクソフォン協奏曲のリハーサルのため王子の北とぴあへ。サクソフォン須川展也、指揮増井信貴、オーケストラ新日本フィル。夜から雨になる。今ごろヨーロッパ演奏旅行中の群馬交響楽団がウィーンで拙作「朱鷺によせる哀歌」を演奏しているころだなあ、と思いつつ酒を飲む。
5月27日。昼、音楽現代のCD立体評の原稿をFAX。午後、ゲネプロへ。大雨という予報にもかかわらず、晴れる。夜、一晩サクソフォン協奏曲だらけという凄い企画の須川くんのリサイタルで、トリに「サイバーバード協奏曲」の再演。大成功。打ち上げでは東芝EMIの担当者も交えて全国制覇だ!ロンドン録音だ!と盛り上がった後、須川くん宅でネコ(ニャーという名前)にからまれながら朝五時まで飲む。
5月28日。しっかり二日酔。夜、サントリー・ホールの東京交響楽団定期演奏会で「バビ・ヤール」の東京公演。てっきり七時開演だと思っていたら、六時に井上道義さんから「吉松サン。6時からヨ。6時!」と電話。あわてて飛んで行く。おかげで前半のヴァイオリン協奏曲の第一楽章を聞きそびれるが、「バビ・ヤール」には間に合う。
帰り道、うちの近くで新しい酒処を見つけ、菊姫、久保田、天狗舞と飲む。
5月29日。この原稿を書く。6月出版の「世紀末音楽ノオト」(音楽之友社)がそろそろ刷り上がる。表紙からイラストまで結局描くことになってしまったのだが、「マンガの本みたい」と言われ、傷つく。音楽之友社から出す本にもかかわらず、音楽現代の編集者氏との会話が延々あったりするのだが、大丈夫だろうか?
5月30日。無謀にも私のギター作品ばかりを集めたCDを出すという山下和仁くんとリハーサル。明後日から某ホールに3日間こもりきりで、全5楽章20分以上というソナタも含む三部作ほかを一挙録音する。BMGビクターから9月に発売予定。乞うご期待。
5月31日。9月25日初演予定の岡山シンフォニーホール委嘱作品のメ切日。ピアノの上に「鳥と虹の雅歌」と題するそのスコアが確かにあるが、さて、問題です。私は一体いつこの曲を書いたのでしょう?
*
◆ショスタコーヴィチ交響曲第13番「バビ・ヤール」(インバル盤:デンオン)
第8回:奥の細道ひとり旅〜天と地と新日本紀行
邦楽の団体から委嘱されていた語りと邦楽器のための怪談オムニバス「百物語より」という作品を仕上げ、ようやく半年近く続いた暗いトンネルから抜けたので、ひさしぶりにぶらりと旅に出た。
いつも、出かける当日までどこに行くか決めていない旅である。適当に数日分の荷物を旅行用バッグに詰め、郵便局に行ってスコアを郵送し、銀行に行って少し貯金をおろし、東京駅まで出てから、しばし駅の本屋で旅行情報誌など眺めながら行き先を物色。まだ行ったことのない出羽三山というのにちょっと心惹かれ、結局まだ乗ったことのない山形新幹線に乗ることにした。
当然着いたところはサクランボの山形。新幹線(といっても福島から先はほとんどローカル線の風情)の中で読んだガイドブックによると、芭蕉の「閑けさや、岩にしみ入る蝉の声」句で有名な山寺がすぐ近くらしいので、着いた日の夕方まず寄ってみた。
翌日から、目が飛び出るほど高いサクランボを横目で見ながら湯殿山〜月山〜羽黒山といういわゆる出羽三山を回る。羽黒山ではおりから暗く重い梅雨空の下、人影全くなしの深い森の中を延々二千四百段続く石段をうっかり登ってしまい、なんとか頂上の神社に辿り着くと土砂降りの大雨。人がいないはずである。
しかし一人旅の最大の御馳走は「人のいないこと」。大体がシーズンオフの平日に名所でも旧跡でもないところを歩く旅なので、その希望は満たされることが多いが、たまに名所旧跡に寄って団体さんなどと出くわすと舌打ちして脇道に入ってしまう。そして気がつくといつの間にかポツンと一人で歩いているわけで、この孤立感がたまらないのである。
そんなわけで最近の仕事を離れての旅は、ほとんど国内の神社巡りの旅か地酒巡りの旅になっている。神社があるところにはどんな町でも必ず深い森があり、うまい酒があるところには必ずいい水がある。つまり、神社と酒こそが日本の風土を守る二本柱なのである。決して酒が飲みたい一心の旅ではない。ポリシーがあるのである。(え?説得力に欠けるって?)。
そして、田舎のローカル線などに乗ってコトコトと田園の中を走っていると、いつも頭の中で鳴り始める音楽がある。それが、昔NHKでやっていた「新日本紀行」という番組のテーマ音楽である。
*
◆新日本紀行「富田勲の音楽」(BMGビクター)
というわけで、今回の旅行から帰るとすぐCD店に飛んで行って買ったのがこれ。発売日をワクワク待ちながらCD新譜を買うなんて滅多にないことなのだが、これはそんな一枚である。
富田勲というと、シンセサイザーで世界的に有名になってしまったが、この人、人ぞ知る日本随一のオーケストレイションの魔術師。NHKの大河ドラマ全盛期の音楽(「花の生涯」「天と地と」「新平家物語」「勝海舟」「徳川家康」)を始め、いまだに語り草になっているテーマ音楽の超傑作「新日本紀行」から杉良太郎のデビュー作「文吾捕物絵図」、そして手塚アニメの名作「ジャングル大帝」や「リボンの騎士」と名作・傑作は数知れない。
いわゆる純音楽のシーンには登場していないものの、「音楽」を書く作曲家としては伊福部昭と並んで戦後日本の音楽を代表する両巨頭。戦後の純音楽のジャンルで現代音楽という「非音楽」が荒れ狂っていた時代に、伊福部昭氏がゴジラなどの特撮映画を始めとする「映画」のジャンルで、富田勲氏がNHK大河ドラマを始めとする「テレビ」のジャンルで「音楽」を追及していたことは、日本の音楽史に特記すべき事項なのである。
かくいう私も、テレビの前にマイクを置いてオープン・リール・テープで録音する(!)という前近代的な時代からのファン。
そもそもは、そう、確かに「新日本紀行」(1963〜)の音楽である。クラヴェスの絶妙な合いの手に乗って歌われるテーマ・メロディは、気が遠くなるほど美しく日本人の郷愁を直撃する。西欧オーケストラで日本情緒を表わす試みは、外山雄三氏の成功例を除けばこの曲がトドメの一曲。この方向でうっかりオーケストラを鳴らすと、いまだに「あ、新日本紀行みたい」と指摘されるという、作・編曲家には畏怖すべき伝説の「聖典」でもある。(ここだけの話だが、私も交響曲第2番で「あ、新日本紀行みたい」と言われる箇所を書いている。)
また、中学生の時テレビから「文吾捕物絵図」(1967)のテーマ音楽が流れてきた時のショックも忘れられない。わずか一分そこそこのタイトルの間に、三味線風のギターやシロフォンやチェレスタやホルンがまるで万華鏡のようにオーケストラの中から飛び出してくるのだ。これがオーケストレイションというものか!と感嘆したのを覚えている。ませた中学生である。
そして、高校生の時に聴いた「天と地と」(1969)の音楽。これは上杉謙信の生涯を石坂浩二が演じたNHK大河ドラマだったのだが、フル・オーケストラの中に琵琶が毅然と鳴り渡る見事なテーマ音楽に始まり、全編まるでオペラのような綿密な音楽が付けられていて本当に凄かった。武満さんの「ノヴェンバー・ステップス」(1967)もほぼ同時期だったが、私にとっては「天と地と」の方がショックだった。LP二枚組の名場面集というのも買って(当時はまだビデオで簡単に録画できる時代ではなかったので)テーマ曲を何度も何度も聴き、弦楽器の不思議な効果やブラスの見事な書法に感嘆し、これはどういう魔術なのだろう?という驚きから「管弦楽法」の勉強を始めることになったのだから、富田さんは私の師のひとりと言っていいのかも知れない。
そんなわけで今回のCDは、私にとっては狂喜の一枚。「おお!天と地と!」「うわ!文吾捕物絵図!」「ああ!新日本紀行!」で、数日つぶれてしまった。
放送当時の録音そのままではなく、大友直人指揮東京交響楽団による新録音であるというのは、まあCDの音質を考慮すれば許せる処理。ただ、マニアとしてどうしても許せない点が三つ。その一。「勝海舟」オープニング・テーマ三十一小節目でブラスの短二度をぶつけたアレンジャーの耳。その二。「天と地と」のオープニング・テーマ冒頭の琵琶パートをつなぎそこなったミキサーの編集技術。その三。「青い地球は誰のもの」という稀代の名曲に脳天気なスタカン・リズムを付けたアレンジャーのセンス。
それでも超推薦盤。これは現代日本の音楽が達成した最高峰のひとつである。必聴!
第9回:猛暑の夏、鍾乳洞を抜けたらそこはカンテレ
7月半ばの猛暑の中、秋に初演する作品の打ち合わせのため岡山に行った。
なにぶん今年の夏は東京でも何年ぶりかの記録的な猛暑。7月早々からカンカン照りの昼間と熱帯夜が連続して、いささかウンザリぎみ。ところが、岡山はもっと暑い(前日電話で聞いたら最高気温が39度とか)そうで、おまけに水不足気味だという。
なんだか直接行くのはしんどそうだな、と思った途端に生来の気まぐれ旅趣味がムクムクと頭をもたげ始め、結局大阪で途中下車して、宝塚にこの春に完成した「手塚治虫記念館」に寄り道することにした。
例の宝塚歌劇場のすぐ横にあり、手塚マンガが生んだ数々の主人公たちのレリーフに囲まれたきれいな建物。自筆の原稿はもちろん、昔の全集本や様々なキャラクター・グッズが展示してあり、あまりの懐かしさに半日入り浸りになったあげく、鉄腕アトムのキイホルダーまで買ってしまった。
翌日、岡山着。汗を拭き拭き吉備路も回ったのだが、あまりのピーカン天気に人影はほとんどない。春や秋のシーズンにはサイクリングの旅などが気持ちよさそうな所だが、こんな猛暑の下では自転車ごととろけるチーズになりそうだ。
暑い中ようやく打ち合わせも終わり、担当者氏に「この近くでどこか涼しい観光地はありませんかね?」と聞くと、「うーん。鍾乳洞なら涼しいんじゃないですか?」とのこと。「おお、それそれ!」と、観光案内所で調べると、ローカル線で一時間半ほど北に行ったところに井倉洞という大きな鍾乳洞がある。早速行ってみた。
岡山駅から電車に乗って高梁川という川に沿ってコトコトと進んで行くと、やがてあたりは緑深き山と溪谷ばかりの景色になり、雰囲気は悪くない。これは涼しいかも....と思って駅を降り立つと、これが....あ、暑い。
ぜいぜい言いながら、駅から歩いて十数分のところにある鍾乳洞に辿り着く。川沿いの切りたった断崖の奥がその鍾乳洞らしく、結構大きそう。川を横断するように橋がかかっていてそれを渡るのだが、人影はまったくなく、しかもこれがまた太陽の光を遮るものが全然ないので暑い。
ようやく洞窟の入り口に近づくと中からヒンヤリとした冷気が漂ってくる。お、これは涼しい!と、閉所恐怖症であることも忘れて中に飛び込むと、これが....さ、寒い!
半袖シャツしか着ていないので冷気がダイレクトに身にしみる。しかも汗をかきまくっているので、汗が冷たい湿気となって余計にこたえる。そう言えば、缶ビールをすぐ冷やすには、湿らせた布で包んで冷凍庫に入れるといい、と聞いていたが、ああ、こりゃ確かに冷えるわい....と妙な感心をしながら奥へ。
しかし、寒いし人は誰もいないし狭いし暗いので、生来の閉所恐怖症がムクムクと頭をもたげ始め、鍾乳洞を観賞するどころでなく結局あたふたと出口に急ぐと、外に飛び出した。すると、これが....あ、暑い!
ひャー....と鍾乳洞の出口に戻り、中に入ると、これが....さ、寒い!
それからしばらく鍾乳洞の出口で、出たり入ったりしながら、....あ、暑い、....さ、寒い、とやっているうち、暑い外気と寒い冷気が交じり合う出口手前数メートルの所に快適空間があることに気が付いた。
イスでもあれば座り込んで涼むのがベストなのだが、残念ながら石段の途中で、座る所も寄りかかる所もない宙ブラリンの一角。しかし、快適温度の涼しいスペースはここしかない。おかげでかれこれ小一時間くらい鍾乳洞出口手前の石段の途中でボケーッとしていた。
そのうち、背後から人の気配。どうやらこのクソ暑い中わざわざ鍾乳洞を見に来た物好きな観光客らしい(こらこら、人のことが言えるか?)。彼らは「あ、出口だァ」という歓声をあげた後で、出口付近に職業不詳年齢不明の妙な男が意味不明にボケッ立っているのに気付き、不審げに横目で見ながらも目をあわさないように横を通り抜ける。
そして、ある臨界点を一歩越えたところで「あ、暑い!」と叫び、数歩後戻りして私の立っている当たりをチラと見て、ようやく「なるほど」と私がこの場所にボケッと立っている意味を理解するわけである。
その後、数組の観光客が出てきたが、行動パターンは判で押したように同じだった。まず、「あ、出口だ!」と言って出てくる。しかし出口横の不審な男に気付いてしばし沈黙、そして通り過ぎて外に出て「あ、暑い!」と叫び、それから私をチラと横目で見て「なるほど」という顔をするのである。
そこで教訓である。つまり、妙な人が妙なところに意味なくいるように見えても、それは実は裏に深い深い意味が隠されているものなのである。だからシャーリプトラよ、妙な人が妙なところで無意味なことを言っているといって嘲笑してはならない。(こらこら、シャーリプトラって一体誰なんだ?)
一見無意味で奇妙な形をしているものが真理でないとは誰にも言いきれない。真理は洞察することで真理となるのである。
色、すなわちこれ空。
空、すなわちこれ色。
合唱。もとい、合掌。
*
◆「カンテレに寄す」カンテレの世界Vol.1、「カレリアの丘にて」同Vol.2(フィンランディア)
そんな猛暑の夏に聴くには、ブラームスやマーラーではいかにも暑苦しい。何かこう鍾乳洞の天然クーラーのような涼しい音楽はないだろうか、と捜しているうちにこんなCDを見つけた。
カンテレは北欧フィンランドの民族楽器で、木製の胴に金属の弦を張った琴のような形をしているのだが、オルゴールのようなハープのような実に涼しげな音を出す。
その音楽には、ヨーロッパ系の品のよさとアジア系の(フィンランド人の先祖はハンガリー人と同じでアジア系らしい)独特なペーソスがあって、遥か北欧の昔の音楽ながら現代日本人の私たちにとっても、どこか懐かしい気持ちにさせられる。
そしてこのカンテレ、冬に聴くと、暖炉の前でぼんやり火を眺めているような温かい懐かしさがあり、夏に聴くと、キラキラときらめく渓流の水の飛沫でも見ているような、涼しい懐かしさを感じる、実に不思議な音楽なのである。
今回紹介したこの2枚は伝承曲や民謡などを中心に弾いた古典的なカンテレの音楽だが、現代の北欧の作曲家たちが現代音楽の中にカンテレを使った作品を集めた1枚「新時代のカンテレ」も出ていて、こちらもなかなか面白い。
第10回 我田引水!CD「風色ベクトル」録音顛末記
最近、山下和仁氏の演奏で、私のギター作品ばかりを集めたCDを作った。
収録曲は、1991年から年一作のペースで山下くんのために書いた「風・水・空」にちなむ「三部作」と、旧作の「リトマス・ディスタンス」および「2つの小品」。
「三部作」は、中篇サイズの「風色ベクトル」(1991)と、疑似ルネサンス風の舞曲集「水色スカラー」、そしてギター版交響曲のギター・ソナタ「空色テンソル」(1992)からなる。一方の「リトマス」は、山下くんに書いた最初の作品で、私がまだ27歳、山下くん19歳の時の曲である。
現代のしかも一作曲家だけのギター曲を集めた一枚ということで、すんなり企画が通ったわけではないが、ギター協奏曲「天馬効果」(1984)を出している因縁(?)からかBMGビクターからのリリースが決まったのが昨年。収録予定曲は全曲とも初演はしているものの、録音するとあっては決定稿を作らねばならず、早速改訂に着手する。
この間、山下くんは結婚したり京都に引っ越したり娘が生まれたりと忙しい最中で、私の方も妹がガンで死んだり作曲のメ切が幾つも重なったり本を出したりと慌ただしい最中。しかし、何度も改訂部分を相談し、リハーサルを重ね、気は熟し始める。
そして、今年の春、録音場所は東京郊外の秋川きららホール、日程は6月1日から三日間、CDの発売は9月の彼のリサイタルに合わせて、9月下旬発売と決定。
*
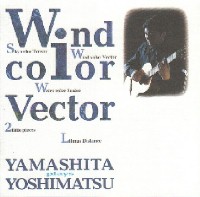 ◆「山下和仁/風色ベクトル〜吉松隆ギター作品集」BMGビクター。
◆「山下和仁/風色ベクトル〜吉松隆ギター作品集」BMGビクター。
5月31日。新宿で待ち合わせて山下くんと今回のレコーディングのプロデューサー荒生昌彦氏と三人でまず福生へ。新宿から急行で立川に出て、それから青梅線に乗り換えて7つめ。夕方ホテルに到着し、技術の及川・杉本・北村三氏と計六人で夕食。この日はホテル泊である。
翌6月1日。朝十時、三人して車で十五分ほどの秋川きららホールへ。レンガ仕立てのまだ新しい中型ホールで、駅の近くだが回りにはほとんど家もなく、東京らしからぬ静かな環境の中に建っている。
午前中は技術スタッフのチーフ及川公生氏を中心にして録音のセッティング。舞台中央にピアノ用のイスを置いて、ギタリストの位置を決定。その位置を狙って中央にメイン・マイクのAKGの414が2本、少し後ろにホール・エコーを録るマイクが1本。
この舞台から黒いヘビのようなラインが何本も地ベタを這って楽屋まで続いていて、ここがミキシング・ルーム。壁から鏡まで黒い吸音シートが一面に張り付けられていて、その中央にデンとミキシング・コンソールが鎮座し、モニター・スピーカーが並べられている。ちなみにコンソールはステューダーの可搬型962、モニター・スピーカーはフィンランド製のS30BNF。この部屋にミキサー、プロデューサー、作曲家が待機する。
録音機材は隣の部屋にあり、録音スタッフ二名が操作する。今回は20ビット録音と言うことなので、ソニー製の二十ビット光磁気ディスク式録音機PCM9000と、K2と書かれたJVC製20ビット・コンバーターが並ぶ。これが今回の録音の目玉。
この間、山下くんはマイペースで爪の手入れや弦の張り替え。一方の作曲家は何もやることがなくて手持ちぶさた。精神集中している演奏家や忙しそうに動いている技術さんたちの横でボーッとしているだけ。
そして午後からようやく録音が始まる。まず一番弾きなれた中篇「風色ベクトル」から。全3曲で10分くらいの曲だが、音をチェックしながら何度もプレイバックし、ミスした箇所を部分録りしたりするので、録音にはたっぷり数時間かかる。
続いて、一応一番やさしい作品(という触込みの)「水色スカラー」全5曲。しかし、山下氏いわく「やさしく見えるけど、続けて弾くと指をネンザしそうになるんですよね」とのこと。反省。結局、この録音も数時間かかり、終わったのは夜もふけてから。
翌6月2日。午前中は再び音の調整。舞台後方のヒナ段を上下させて残響の調節をし、音が決まったところで昼ころから全5楽章の大曲ギター・ソナタ「空色テンソル」の録音を始める。「ハードな曲なので、一日にそう何回も弾けない」そうなので、一パツ録音を目指すが、午後、通り雨で録音中断。
それにしても、雨が屋根にあたるパラパラいう音はもちろん、空調のファンのキュルキュルと回る音、演奏中イスがきしむ音、通風孔から風がもれる音などなど、静かなはずのホールも完全無雑音が理想のデジタル録音にとっては恐怖のノイズに満ちている。
途中、録音現場の取材に評論家氏や記者氏が来訪してインタビュー。レコード会社からも何人か様子を見に来る。そして夕方、「聖歌」および「ノエル」と題された小品を録音。終わってから、明日録音する「リトマス・ディスタンス」で使う鈴の仕込み。マイク台に日本製の風鈴やインド製の鈴、中国製の風鈴などを吊るし、2日め終了。
翌6月3日。今日はなんとか早目に終えようということで、午前中から「リトマス・ディスタンス」を録音。しかし、ギターは民族音楽風の妙なチューニングだし、傍らに鈴を幾つも吊るし、胴を叩いて太鼓のリズムまで作るので、なかなか奇妙な景色。
そして最後に、初日に録音した「風色ベクトル」を、もう一度ザッと再録音する。ただ、「一応、録っときましょう」と録音するのはいいが、プロデューサー氏はこの複数のテイクからOKの部分をつなぎ合わせて編集しなければならないわけで、後が大変。しかし、なにはともあれ丸3日間の録音キャンプは無事終了し、後片付けをし、シャンシャンシャンと手締めをして、スタッフ全員で打ち上げ。
*
そして、編集が終わって音のサンプルが仕上がったのが七月末ころ。作曲家はこの間に作品についてのノートを書き、その一方でジャケットのデザインと内パンフレットのレイアウトが進む。解説は濱田滋郎さん。
8月になるとなんとなく形が見えてきて、宣伝やプロモートが展開し始め、8月下旬発売の各音楽誌9月号には(まだジャケットも出来ていないうちに)予告広告も掲載され始めた。たぶん本号にも何か関連記事や広告が載っているはず。捜してみてください。
ちなみに、9月26日には、この時CD録音された曲のうち三曲が、「山下和仁の現在」というコンサート(東京文化会館小ホール)で藤家渓子さんの作品と共に披露される。彼は今後も現代のアジアの作曲家に焦点を当てて、委嘱・初演を試みてゆくとのこと。乞うご期待!
第11回 緊急特報、20世紀にロマン派を見た!
音楽が好きで音楽を始めた。
ところが、同時代の音楽として「現代の作曲家たち」とやらが創っているグチャグチャ・キイキイ・ゲチョゲチョ・ゲボゲボ....の、あれは一体なんなんだ!と、長いこと私は怒っていた。
作曲家などという外道の職に身を落としたのも、「私はこんな音楽を聴きたいんだ!」という切なる希望の噴出であって、音楽らしい音楽を「現代の作曲家たち」が作ってくれていたら、なにもこんな馬鹿げた商売など自分で始めたくはなかったのだ。....と今回は愚痴で始まる。(編集者注:すみません。くれぐれも穏便に願います。)
巨大な伝統音楽に対するオイデプス・コンプレックスに始まった非音楽を、「これが新しい音楽だ!」と言われて信じ、「あんまり耳に心地よくないなあ」と思いながら黙認し、挙げ句はこの非音楽をヨーロッパ中に蔓延させ、まともな音楽を書いている作家を「時代遅れ」呼ばわりした。この構図は、まさにナチスの台頭や日本の軍国主義の生成に実によく似ている。
確かに、ハーモニー・システムにがんじがらめに縛られた音楽の封建主義体制を一掃することを目的として生まれた「十二音主義」も、出現当初は新しく理想的な「未来音楽」を指向するように見えた。それは、第一次大戦後の戦後処理にがんじがらめに縛られたドイツが、その体制を一挙につき崩すために選択した「国家社会主義(ナチズム)」が、出現当初は新しく理想的な「第三帝国」を指向するように見え、同じくアメリカやヨーロッパ諸国からアジア侵略について非難を受けていた日本がその状況をつき崩すために掲げた軍国主義が、出現当初は理想的なアジアの在り方である「大東亜共栄圏」を指向するように見えたのによく似ている。
しかし、民衆の同意なく感性の承認を得ない「進出」は「侵略」でしかなく、「勢力の拡大」は「広域の荒廃」と同義になり、ナチスと日本軍国主義は崩壊した。そして彼らは、ヨーロッパを瓦解させアジアを侵略し、その結果として多くの人命と財産を奪ったゆえに糾弾され、裁かれたわけだ。
それなら、ヨーロッパ音楽を瓦解させ、調性やメロディやリズムを侵食し、その結果として多くの作曲家・演奏家・聴衆から音楽の悦びと感動と楽しみを奪った連中は、糾弾され、戦犯として裁かれなければならないはずではないか!
「...って、盛り上がってるとこ申し訳ないんですけど...。」
ちょ、ちょっと。あんた誰なの?。人の原稿に勝手に入ってこないでくださいよ。
「いやね。黙って聞いてるとね、なんかブーレーズ先生とかシュトックハウゼン先生あたりを絞首刑にでもしたいみたいで。」
そう。実を言うとね。ウェーベルン先生を誤認で射殺したアメリカ兵って、実はタイムマシンで過去に遡って前衛音楽の根を断とうとした二十一世紀の作曲家だったりして。
「んな、アホな。」
シェーンベルク先生はタイムトラベルしてきたその暗殺者から逃れるためにアメリカに亡命したのかも。あ、これ、SFにしたら面白そうだな。ベルク先生を間接的に殺した歯医者も一味だったりして。
「何を考えてるんでしょね。この人。」
いや、ま、オトギ話はともかく、結果的に音楽の荒廃と不毛を生んだこのオトシマエはきちんと付けてもらわないと、ということなんですよ。正論でしょ?
「どこが正論ですか?」
それと、自分ではちっとも好んで聴かないくせに尻馬にのってこの種の音楽を容認してきた評論家や研究家も執行猶予なしの懲役刑にしなくちゃね。
「でも、そもそも音楽で誰も死んだわけじゃないですし、逃げようのない戦争と違って、音楽はホラ、耳ふさげばいいことでしょ。」
いや、そんな単純なもんじゃなくてね。こういうタイプの音楽が二十世紀の主流として喧伝されたことで、ちゃんとメロディを歌って感動させるタイプの音楽を書きたかった作曲家たちを絶望させてしまったこと、これが最大の罪悪なわけですよ。こんな音楽が今世紀の音楽だっていうなら、俺はもう音楽なんか書かない!って筆を折った作曲家が一体どのくらいいたか想像できます?
「でも、ヌケヌケとメロディ書いてる人は書いてたんじゃないですかね?。実際、あなただってそうでしょ?」
そう、ヌケヌケ。いや、でもね。きれいなメロディを書きたいなんて、時代に遅れてるんじゃないだろうか?とか、人を音楽で感動させたいなんて古いんじゃないだろうか?なんて、地下豪に隠れて息をひそめているユダヤ人みたいな境遇にあったのは事実ですからね。これは、問題ですよ。
「でも、いまさら悪しきを糾弾しても、なくなってしまったものは帰ってこないんじゃないですか?」
知識人ヅラした凡人がよく言う月並みな反句みたいなこと言いますね。でも、その通りですよ。だから、これから我々がなすべきは、悪者にさらわれて隠れていた赤頭巾ちゃんを捜し出すこと。地震で潰れてしまったビルの瓦礫の山から生き残っている赤ん坊を発掘すること。これが、音楽関係者が二十一世紀に向かってなすべき最大の努力目標であり、われわれが不毛にしてしまった二十世紀の音楽に対するせめてもの謝罪と言えるんじゃないですか。
「ふうん、それでこんなCDを聴いてるわけですか。どれどれ。」
*
◆バーバー&コルンゴルド「ヴァイオリン協奏曲」グラモフォン
◆ラーション「ヴァイオリン協奏曲ほか」CBSソニー
この三曲、ともに二十世紀中盤に書かれたヴァイオリン協奏曲。バーバーのが1940年、コルンゴルトのが1945年、ラーションのは1952年の作。
この時代、ヨーロッパでは全面セリーによる作曲法が蔓延し始め、アメリカではケージがチャンス・オペレーションによる作曲法で音楽界にショックを与え、ミュージック・コンクレートや電子音楽の習作が話題になっている。
しかし、この三曲にはそんな未来主義は微塵もなく、ひたすら古風にして普遍的な「音楽」が鳴り渡る。温和で甘美なバーバー、優美で端正なコルンゴルド、シベリウス風の冷たい美しさのラーション。いずれもひと昔前だったら、時代錯誤と嘲笑されていたタイプの音楽だが、さて、二十世紀の新たなる名作としてよみがえるか?
それは聴いているあなた次第。
第12回 古きをたずねれば新しきを知るかも知れない
商売がら、現代音楽のCDはよく聴く。最近もXXXとかXXXXというのを聴かされた。XXXXのXXXというのもあった。凄かった。(編集者注:この伏せ字は私どもが付けたのではありません。念のため。)
多少は期待もしながら、大体は「だまされたと思って」聴くのだが、聴くといつも本当に「だまされた!」と思う。新しいとか古いとか、知性とか感性とか言う問題ではない。「楽譜」に依存して「耳」に依存しない音の連結が「吐き気をもよおす」のである。
しかし、同じく「楽譜」に依存して「耳」に依存しない音を連結させながら、バッハの音楽は美しいのだ。なぜだろう?
「ようするにアナタは、不協和音にたいして耐性がないんじゃないですか?」
「うーん。鋭い指摘ですね。ただ、調性を使うのが旧悪の〈感性〉で、無調を駆使するのが新しい〈知性〉だと思い込むスカタンな理屈は、そろそろ国連か何かで禁止してもらいたいですね」
「相変わらずムチャクチャ言いますね。でも、知性っていうのは基本的にスカタンなような気もしますけど。」
「いやいや、あれは知性じゃないですよ。カラオケで〈音痴〉な歌をわめいておいて、今のは〈無調〉だ、と言い張るのが知性ですか?。ハッハッハの大洗海水浴場ですよ。」
「な、なんですか、今の唐突なギャグは?」
ハッキリ言って、ヨーロッパの音楽は1920年代にシェーンベルク先生が解体して死んでしまったのである。(しかも、ベルク先生とウェーベルン先生による三人がかりの父親殺し。一本では折れる矢も、三本重ねればこのとおり!)
そして、その後の「前衛音楽」は、第二次世界大戦後の十年ほど「前衛」を務めた後、アッという間に時代に追い越されてしまった。以後「現代音楽」と呼ばれるものが大衆に理解されないのは、「先鋭的」だからではなくて「時代遅れ」だからだ。ここに「現代音楽」の決定的な事実誤認がある。
では「音楽」はどうなったか?
簡単である。臨死の「ヨーロッパ音楽」は白い移民たちの記憶となって新大陸アメリカにわたり、そこで奴隷として連れてこられた黒い移民たちの記憶「アフリカ音楽」と邂逅し、「ジャズ」という肥沃な音楽的大地を生んだのだ。
このジャズは、白人世界のみの音楽言語だったクラシックを駆逐して、二十世紀前半における世界的な音楽言語になった。単純なビートと単純なハーモニーを基盤にした新しい音楽言語は世界各国に普及し、新しい形態の民族音楽である「ポップス」に昇華・堕落したのである。
そして、さらに二十世紀後半。世界に伝播したこのヨーロッパ音楽とアフリカ音楽の融合体は、電気増幅と録音複製技術が産み出した新しいメディアを得て、より全世界的な音楽言語「ロック」になる。
かくして、ヨーロッパの知性からアフリカのリズム感そして各国の民族的感性にいたる人類の音楽的記憶の集合体に、さらに現代の科学技術とメディアを付加したこの「ロック」という音楽語法こそが、二十世紀後半における人類の音楽の正統なる王位継承者になるのである。(ここでいう「ロック」は音楽の「スタイル」ではなくて、「語法」のことである。念のため。)
「あ、私もそう思いますよ。歌謡曲も演歌もエスニックもアシッド・ジャズもヒップ・ホップも基本的にはロックなんだし。」
「そう。広義に見れば、現在のクラシック音楽だって、ヨーロッパの古典音楽の複製をコンサートやCDというメディアで汎世界的に広めている点で〈ロック〉ですしね。」
「それはしかし、もの凄い強引な理屈ですね。」
この、ジャズ=二次元的な音楽の混合、ロック=三次元的な音楽の融合....という公式は、近代が現代になる変遷期に世界中のすべての国の文化交流史上で展開され、二十世紀末の現状を作った。
日本もその例外ではない。まず、明治以前の伝統的音楽の中に、黒船で来訪した西欧クラシック音楽(断片の輸入はもちろんもっと以前だが)が軍事的優位を伴って入ってきて、それを明治新政府が軍楽隊の音楽や幼児教育の中に組み込んだ。これが日本におけるジャズ的な二次元音楽混合である。
続いて第二次世界大戦後、アメリカの進駐軍によってジャズが入ってきて戦後復興期をトレースし、さらにビートルズらによるロックンロールが入ってきて高度成長期をトレースした。これが日本におけるロック的な三次元音楽融合、というわけである。
「だから、真の現代の音楽というのは、その国の伝統音楽の死(第一次)と、その後の他の音楽文化との混合(第二次)、そしてそれに近代科学文明が溶け合ったロックとの融合(第三次)という、三段階の展開をはたした音楽語法なんですよ。明快でしょ?」
「ふんふん。一、二、三、と。こりゃ分かりやすいですね。」
「そういう議論をしてるんじゃないですけどね。ま、ともかく、この三次元的融合は世界のどの国でもその文化的背景の中で行われたわけで、ゆえに民族固有の個性を持ち、同時に万国共通の普遍性を持った〈第四次〉の語法になりえる可能性を秘めているわけですよ。」
「はあ。それで今回はこんなCDを聴いているわけですか。どれどれ。」
*
◆ヒリヤード・アンサンブル&ヤン・ガルバレク「オフィチウム」(ECM)
一枚目は、ヒリヤード・アンサンブルが歌うヨーロッパ中世の聖歌をバックに、ヨーロピアン・ジャズの雄ヤン・ガルバレクが自由な旋律をサックスで歌う見事なまでに美しい音楽の「融合」。
◆エムパイヤ・ブラス「パッセージ」(テラーク)
続く二枚目は、同じく中世ヨーロッパの聖歌や舞曲を、自由にブラス・アンサンブルや現代の楽器にアレンジしたもの。ヴォーカルやエレキ・ベースからシンセサイザーまで登場し、リズムを付加する編曲ながら、どこまでも静かで水平な叙情に徹していて、これがまた実に美しい。
*
この両CDが「ジャンル不明」と遇されている現状こそがまさに現代音楽の不幸と言うべきだろう。真の「現代の」音楽とは、かくも美しく同時代的かつ普遍的たりえるのだから。「現代」を騙る偽物などは、みんな燃えるゴミの日に出してしまおう。
(え?燃えないって?)